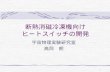日射量の急変に対応可能な太陽光発電システムの開発 ~第 2 報~ (米子高専電気情報工学科) ○小西沙季・山本賢人・宮田仁志・石倉規雄・権田英功 キーワード:太陽光発電,MPPT,部分影,SOM 1.緒言 現在,日本の発電方式は火力発電をはじめと する非再生可能エネルギーが年間発電電力量 の約 9 割を占めている.このような状況の中, 再生可能エネルギーが注目を集めている.中で も,資源が無限で住宅にも設置可能な太陽光発 電に期待が集まり,多くの研究がなされている. 本研究では再生可能エネルギー発電の中でも 太陽光発電に着目し,その高性能化について検 討した. 2.日射量の急変に対応した MPPT (Maximum Power Point Tracking) <2.1>SOM(Self- Organizing Maps)を用 いた MPPT 太陽光発電に用いられる太陽電池はエネル ギー変換効率が低いため,最大電力点追従制御 MPPT によって,まず出力を最大に保つ必要 がある.MPPT の 1 つに山登り法がある.山 登り法とは最大電力が得られるまで,動作電圧 と電流を調整し続けるというものである.例え ば,動作電圧を高めると出力が増加する場合は, 出力が低下し始めるまで動作電圧を高める.そ して,出力の低下を検知したら,出力が最大値 に戻るまで,動作電圧を引き下げるというもの である. 本研究では,まず山登り法について評価した. そして SOM を用いて最大電力点を探索し,そ れを用いて,山登り法の欠点である部分影が生 じたときなど,日射量の急激な変化に対応でき る太陽光発電システムの開発を目指す. <2.2>動作試験 図 1 にシミュレーション回路を示す.実線内 は太陽光パネル,点線内は降圧チョッパ回路に なっており,破線内の回路によって MPPT 制 御を行っている.日射量の選定には,NEDO (New Energy and Industrial technology Development Organization)日射量データベ ース閲覧システムを利用し,日射量 600[W/m 2 ] と 1000[W/m 2 ]時について太陽光パネルの P-V 特性をシミュレーションした. その結果,発電電力量が最大値に素早く追従 していることが確認できた. しかしながら、部分影が生じる場合について は,シミュレーションが難しいことが分かった. 図 2 SOM による最大電力点の選定 SOM を用いるためにはまず太陽電池パネル の特性データが必要である.図 2 には,種々の 気象条件下で,太陽電池パネルの I-V 特性を測 定したデータを用いて,マップ化したものを示 す.このマップを用いて、最大電力点を探索し, 日射量が急変した場合でも安定した MPPT を 実現する. 3.まとめ 山登り法では,日射量の急変には対応できな い.その対策として,種々の気象条件下で,太 陽電池パネルの I-V 特性を測定した.その測定 データを SOM を用いて2次元マップ化して, MPPT に応用した. お問い合わせ先 氏名:宮田仁志 E-mail:[email protected] S T Po L D C IGBT Battery 図 1 降圧チョッパによる MPPT のハードウェア I-001

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

日射量の急変に対応可能な太陽光発電システムの開発
~第 2報~
(米子高専電気情報工学科)
○小西沙季・山本賢人・宮田仁志・石倉規雄・権田英功
キーワード:太陽光発電,MPPT,部分影,SOM 1.緒言 現在,日本の発電方式は火力発電をはじめとする非再生可能エネルギーが年間発電電力量の約 9 割を占めている.このような状況の中,再生可能エネルギーが注目を集めている.中でも,資源が無限で住宅にも設置可能な太陽光発電に期待が集まり,多くの研究がなされている.本研究では再生可能エネルギー発電の中でも太陽光発電に着目し,その高性能化について検討した. 2.日射量の急変に対応した MPPT (Maximum Power Point Tracking) <2.1>SOM(Self- Organizing Maps)を用
いた MPPT 太陽光発電に用いられる太陽電池はエネル
ギー変換効率が低いため,最大電力点追従制御MPPT によって,まず出力を最大に保つ必要がある.MPPT の 1 つに山登り法がある.山登り法とは最大電力が得られるまで,動作電圧と電流を調整し続けるというものである.例えば,動作電圧を高めると出力が増加する場合は,出力が低下し始めるまで動作電圧を高める.そして,出力の低下を検知したら,出力が最大値に戻るまで,動作電圧を引き下げるというものである. 本研究では,まず山登り法について評価した.そして SOM を用いて最大電力点を探索し,それを用いて,山登り法の欠点である部分影が生じたときなど,日射量の急激な変化に対応できる太陽光発電システムの開発を目指す.
<2.2>動作試験 図 1 にシミュレーション回路を示す.実線内
は太陽光パネル,点線内は降圧チョッパ回路になっており,破線内の回路によって MPPT 制御を行っている.日射量の選定には,NEDO (New Energy and Industrial technology Development Organization)日射量データベース閲覧システムを利用し,日射量 600[W/m2]と 1000[W/m2]時について太陽光パネルの P-V特性をシミュレーションした. その結果,発電電力量が最大値に素早く追従していることが確認できた. しかしながら、部分影が生じる場合について
は,シミュレーションが難しいことが分かった.
図 2 SOM による最大電力点の選定
SOM を用いるためにはまず太陽電池パネルの特性データが必要である.図 2 には,種々の気象条件下で,太陽電池パネルの I-V 特性を測定したデータを用いて,マップ化したものを示す.このマップを用いて、最大電力点を探索し,日射量が急変した場合でも安定した MPPT を実現する.
3.まとめ 山登り法では,日射量の急変には対応できな
い.その対策として,種々の気象条件下で,太陽電池パネルの I-V 特性を測定した.その測定データを SOM を用いて2次元マップ化して,MPPT に応用した. お問い合わせ先 氏名:宮田仁志 E-mail:[email protected]
S
T
Po
L
DC
IGBT
Battery
図 1 降圧チョッパによる MPPT のハードウェア
I-001

離床検出システムの開発
(米子高専電気情報工学科)
○大黒和真・宮田仁志・石倉規雄・権田英功
キーワード:褥瘡,離床検出,介護施設,PIC,Rasberry Pi
1.緒言 最近では,高齢者の増加により,介護施設や病院で,離床や褥瘡が大きな問題となっている.高齢者が寝ている際の寝姿を調べることで,離床や褥瘡を予防することが求められている.
従来の離床検出システムでは,人体にセンサを張り付けたり,ベッドにマイクロスイッチを取り付けるなどの方法で寝姿を検出していた. 本研究では,マットレス下に複数のセンサを取り付けることで,人の寝姿を検出できる装置の開発を行う. 2.離床検出装置 <2・1>圧力センサを用いた装置 本研究で用いるセンサの外観を図 1 に示す.
これは,圧力がかかるごとに抵抗値が下がる圧力センサである.これをベッドのマットレスの下に設置し,PIC(Peripheral Interface Controller)マイコンを用いてセンサのデータを取得してそのデータをシングルボードコンピュータである Rasberry Pi を用いて処理する.
図 2は素子を 3つ繋げ,実際にマットレスの下に敷く試作品である.圧力センサから出力される電圧を PIC の A/D コンバータを用いて,デジタル信号に変換し,Rasberry Pi に入力する. <2・2>装置概要
本装置を実際に利用するにあたって,マットレス下に置いても使用者に違和感を感じさせないために、装置全体をウレタン素材を用いて製作した.図 2 のような装置を 3 つマットレス下に敷くことで合計 9 箇所の圧力を測定することができる.装置全体の構成は図 3 の通りである。装置で得たデータを Rasberry Pi にて制御することで,複数の寝姿を同時に測定できる.また,接続においては Bluetooth 接続を用いることで配線を少なくし取り扱いやすくする.
図 1 圧力センサ(FSR406)
図 2 実験装置の外見
図 3 接続図
<2・3>Rasberry Pi を用いた制御 本研究では,Rasberry Pi を用いて,PIC からの
データの読み込みおよび寝姿の検出までの処理を行う.そして,各センサにかかる圧力を電圧として読みとって,各部位にかかる圧力の割合から,寝姿を検出・処理し,Android 端末へ転送する.
<2・4>Android 端末との連携 本装置では,寝姿を検出し,Android 端末で
管理することを目的としている.そのため,Rasberry Piから入力された情報をAndroid端末へ転送するプログラムを作成した.Android 端末では入力された情報から、その時の寝姿を視覚的にわかりやすく表示する.
3.まとめ これまでに,複数の圧力センサ(FSR406)を
用いた時,その圧力データを Rasberry Pi に転送するためのハードウェアとソフトウェアを作成した.今後は実用化に向けたハードウェアの作成と Android アプリケーションの開発を行う. お問い合わせ先 氏名:宮田仁志 E-mail:[email protected]
I-002

真空管を用いたモジュレーション系エフェクトの検討
(仙台高専電気システム工学科)
〇 井上真幸 本郷哲
キーワード:真空管,トレモロエフェクター
1.はじめに
音声や楽器からの信号に様々な効果を付加す
る機材として、エフェクターが存在する。現在は主
にディジタル処理が主流になりつつあるが、一方
で素子として真空管を用いる場合も多い。これは
真空管独自の自然なサチュレーション特性による
が、サチレーション以外の用途で使用されていな
いのが現状である。本研究では、真空管を用いて
振幅変調の音響効果を得ることを目的とする。
2.実験
真空管アンプをパソコンのオーディオ端子に接
続し、信号を録音した。これまでの実験により真空
管に外部から磁界を加えた場合に出力に大きな
変化を与えることがわかっている。
図 1.真空管の見取り図
図 2.真空管に対する磁界付加方向の比較
そこで、有効な磁界変化を与える方法を検討した。
まず、磁界変化の図 1 における(a)と(b)どちら側で
波形変動が大きくなるかを比較する。結果は図 2
のように同様の変化の仕方で大きさの違う波形が
観測でき、(a)のように磁石を動かした場合の波形
変化が大きかった。真空管のプレートとガラス管
の設計寸法から、波形変化の大きさは動磁界を
発生させるプレートまでの距離が近いほうが大きく、
ローレンツ力が作用したものと考えられる。
3.磁界発生用のコイルの製作
これまでの実験では、ネオジウムマグネットを手
で持って動かすという方法で動磁界を発生させて
いたが、定量的な手法で磁界を発生させるため、
コイルを試作した。
3 種類の太さ(φ4,φ8,φ12)のボルトを鉄心に、
コイル長さ 1cm で、コイルの巻数を 100 で統一し
た 3種類と、次式によって空心時 50μHのインダ
クタンスで統一されるよう求めた巻数 193,104,74
の 3 種類を製作し,コイルのインダクタンスを計測
した。長岡の式によると、インダクタンスの理論式
は以下のようになる。
L = 𝐾𝑁𝜇𝑆𝑁2 𝑙⁄ [𝐻]
𝐾𝑁:長岡係数 𝜇:透磁率[𝐻 𝑚⁄ ] S:コイルの断面
積[𝑚2] N:巻き数[回] 𝑙:コイルの長さ[𝑚]
現在、交流磁界を発生させて真空管の出力電流
を変化させるように調整を行っている。
4.まとめ・今後の展望
これまでの実験により、動磁界が熱電子に対し
て働く事と、動磁界を発生させる位置とプレートの
距離が大きく関係していることがわかった。今後は、
10Hz程の交流電界を真空管外部から印加して実
験を行う予定である。
お問い合わせ先
氏名:井上真幸
E-mail:[email protected]
I-003

前面バッフル放射型低音強調ステレオスピーカーシステムの研究
(仙台高専専攻科生産システムデザイン工学専攻)
○舘内弘樹 本郷哲
キーワード:位相制御、エンクロージャー、音響インピーダンス、Python
1.緒言 従来のフルレンジスピーカーユニットを同
一のスピーカーボックス筐体に複数個取り付けることによって, スピーカーボックス自身から低域を放射させる構造及び駆動システムを,考案したので報告する. スピーカを組み合わせて用いる際,低域は位相制御を施した合成信号を利用し, 中高音域では音楽の定位感を損なわずに, 低域は強調できるものを作成する. 本報告では作成した本システムの駆動方法を実現し,信号レベルでの評価を行った. 2.本システムのハードウェア スピーカーのエンクロージャーは後方から
出てくる音を剛体を使用し閉じ込め放射音の打ち消しを防ぐという役割がある [1]. 本研究ではエンクロージャーの前面に低周波振動が起こる振動板を使うことによって低域では音響放射板, 高域ではエンクロージャーとして働く,図 1 のようなスピーカーシステムを作成している.
図 1:作成したスピーカーの構成図
予備検証実験において,作成したスピーカーボックスと, 同じスピーカーユニットを用いたバスレフ型, バックロードホーン型を同相駆動し比較したところ,低域を重視しているバスレフ型, バックロー,ド型と同程度の特性が示された. また, 低音域の各周波数における左右の位相差と音圧の関係を調べたところ,低音域では 位相差がないモノラルの状態が最も放射特音のレベルが上昇することがわかった.
3.駆動システム これまでの研究結果及び,低域は指向性が無
視できる特性をふまえて,ステレオの LRを合成する. 低域は平均のモノラルLR,中高域は指向性が重要なのでステレオの LRのチャンネル特性をそのまま維持させた. 図 2に駆動システムのフローチャートを示
す. Low Passは 200Hzをカットオフ周波数とした. それ以外の周波数は Low Cut側から直接アンプに入力した.
図 2:システムのフローチャート
次に sin波に図2の駆動システムを適用した
結果を図 3に示す.結果はそれぞれ,①入力波形②Lowpass(左)③Highpass(左)④出力波形(左)となっている.スピーカーシステムに入力させて,その性能を評価させる.
図 3:システムの波形
参考文献 [1]鈴木陽一他, 音響学入門, 日本音響学会編, コロナ社
お問い合わせ先 氏名:本郷 哲 E-mail:[email protected]
I-004

剣道競技における有効打突判定システムの開発
(仙台高専専攻科生産システムデザイン工学専攻)
○下重大地・本郷哲
キーワード:剣道,有効打突,圧電素子,無線通信
1.緒言 剣道競技における一本に相当する有効打突は
「充実した気勢,適正な姿勢をもって,竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し,残心あるものとする」と定義されており,多くの他の競技同様に機械判定の必要性が求められている.本研究では,センサを用いた打突を判定するシステムの開発を目的とし,本報告では特に無線通信について検討した結果を述べる.
2.システムの概要
二人の競技者の打突部位と竹刀に衝撃を検知するセンサを取り付け,センサの信号に応じて打突を判定するのが本システムの流れとなる.例えば図1のように競技者 B が面を打たれたときに,B の面と A の竹刀センサ信号により,B が面を打たれたことを判定できる. センサには圧電素子を用いる.打突の衝撃を圧
電素子によって電圧に変換し,その信号を無線によって PC に送信し判定を行う.剣道競技では縦横無尽に動き回り接触が多いという点があり,そのため競技に支障が出ないように,信号の送信に無線を用いる必要がある. センサである圧電素子と無線機は競技者の体
に取り付けるため,なるべく小さく軽量であることが求められる.圧電素子には軟質で薄いという特徴をもつ圧電フィルムを用いる.無線機としては IEEE802.15.4準拠の無線部,マイコン部を有する TWELITEを用いる.圧電素子,TWELITE合わせて重量は 1g程度である.
図1:システムの概要図 3. TWELITE の遅延測定 本判定システムにおいては無線通信の通信遅
延がネックとなる.通信遅延がなるべく短いことが好ましい. TWELITE における通信遅延測定を行った.実験回路を図2に示す.二つの TWELITE DIP の片方を親機,もう片方を子機とし,親機側のスイッチの入力により,無線接続された子機側の LED を点灯させる.親機と子機の距離を 12m 離しそれぞ
れの信号を PCM レコーダーによって記録した.結果を図3に示す.親機の入力から子機の出力まで 0.05[s]ほどの遅延があり,剣道の判定には無視できない長さであるといえる.また,この遅延時間は一定ではないため,竹刀側と防具側の信号送信のずれによる判定ミスにつながる.
図2:実験回路
図3:実験結果 4. タイムスタンプによる判定の検討 通信遅延の問題を回避するためにタイムスタ
ンプの利用を検討している.センサからの信号が入力されたタイミングで時間を記録し,時間のデータを送信することで遅延に関係なく打突のタイミングを確実に知ることができる.これによって竹刀と防具側の信号の整合が確実に取れる.TWELITE はプログラムを書き換えることができるため,C 言語でのプログラミングによってこの動作を実現させることができる. 5.まとめ 無線通信に成功したが無視できない通信遅延
があることが分かり,タイムスタンプによる判定方法の検討に至った.今後は TWELITE によるタイムスタンプの送信方法について検討していく. お問い合わせ先 氏名:本郷 哲 E-mail:[email protected]
I-005

レーザーアブレーションによって生じる
振動・音響の計測
(鈴鹿高専電気電子工学科 1,鈴鹿高専専攻科2)
○中野裕貴 1・渡瀬陸2・柴垣寛治 1
キーワード:プラズマ、レーザーアブレーション、振動、音響
1.緒言 レーザーアブレーションにより放出されるプラズマは複雑で、多くの先進的な計測法も研究開発されているが、研究では将来の学生実験等への適用も念頭に置いて固体材料にレーザー光を集光照射したときの大気中で発生するプラズマの発光と音に注目する。点音源として活用できる可能性が指摘されているが、材料の種類やレーザー強度に対する振動・音響特性については不明な点が多い。そこで各種金属材料をターゲットとした場合に発生する振動や音の信号を、振動センサやマイクロフォンを用いて検出し、それぞれの特性を調査した。 2.実験 レーザーアブレーションのターゲット材料
として、チタン、ニッケル、銅の板材料を図 1のように宙に吊るして設置した。ターゲット表面に垂直方向からパルス Nd:YAG レーザー基本波(エネルギー最大 50mJ、波長 1064nm)を照射する。レーザー照射時に発生する空気中の振動をマイクを使用して取得し、並行してPVDF 圧電センサを設置してレーザーを照射時に生じる電圧を振動波形として取得した。
図 1 実験の概要
3.実験結果
図 2 に大気中に設置したチタンをターゲッ材料とした場合にマイクで取得した音響波形を FFT 解析したグラフを示す。
繰り返し実験を行ったが、ほぼ同様な波形を 観測することができ、再現性のある結果であっ
た。他のターゲット材料の結果と比較したところ材料の種類によって FFT 解析のグラフにおいてのピークの周波数の違いや、低周波数と高周波数の割合の違いがあることが分かった。
マイクの位置をターゲット材料の周りで変化させて同じように実験を行うとターゲット材料の前後で測定した結果にも違いがあることが分かった。
4.考察およびまとめ ターゲット材料による結果の違いから、材料によるアブレーションのしやすさや、アブレーション時の音の周波数特性の違いが分かり、これらのデータから各種ターゲット材料においてプラズマの観測ができると推測する。 マイクの位置を変化させた実験からは、アブレーションによるプラズマの空間分布を調べることができると考えられる。 これらの実験では容易に解析を行うことができる。今後はデータを解析したうえで学生実験等への導入を考える。詳細は講演にて報告する。 お問い合わせ先 氏名:柴垣寛治 E-mail:[email protected]
-90
-80
-70
-60
-50
100 1000 104
Le
vel (d
B)
Frequency (Hz)
図 2 チタンターゲットの FFT 解析結果
I-006

Bi系高温超伝導ウィスカー育成の
高効率化を目指した酸素封入法の導入
(米子高専電気情報工学科 1,鳥取大学2)
○飯田涼太 1・大田修太郎 1・田中祥太 1・田中博美 1・岸田悟2
キーワード:Bi 系超伝導ウィスカー,抵抗-温度(R-T)特性,酸素封入育成法 1.緒言 高温超伝導体は究極の省エネルギー材料とし
て近年、再び注目を集めている。その中でも我々は、銅酸化物高温超伝導体の 1 つであるBi2Sr2Can-1CunOy(n=1-3)高温超伝導針状単結晶(以後、Bi系超伝導ウィスカー)に着目した。Bi系超伝導ウィスカーは、臨界電流密度が大きいことから、導線との複合化により大電流送電が可能な線材に応用できる。しかしながら、育成できる Bi 系超伝導ウィスカーの平均結晶サイズが5mm 程度と非常に小さい。先行研究では、酸素気流の抑制を行うことで炉内温度を安定化し、結晶サイズの大型化に成功した。しかしながら、as-grown 状態では酸素不足により超伝導特性が劣化した。 本研究では、炉内の温度を安定させると同時
に、酸化物高温超伝導体育成に必要な酸素を補うことを目的として、酸素ガスを充満させた密閉空間を作る酸素封入育成法を提案した。
2.実験方法
Bi 系超伝導ウィスカーは Al2O3-Seeded Glassy
Quenched Platelets (ASGQP)法[1]を用いて育成した。原材料の組成比が Bi : Sr : Ca : Cu = 2 : 2 :
2 : 4 となるように計量・混合する。そして次に、混合材料を 1200℃のマッフル炉に投入し溶融する。その後、Al2O3 粉末を散布した鉄板で挟み込み急冷することで、母材を作製した。母材作製後、管状炉内で母材を加熱処理して Bi 系超伝導ウィスカーを育成した。炉内に母材を入れた後、酸素を流量 30ml/min で 5 分間供給し、炉心管内を酸素で完全に置換した後、ゴム栓で炉心管の両端を封止した。その後、育成時間: 24~120 (h)、炉内温度: 890℃としてBi系超伝導ウィスカーの育成を行った。育成後の試料は 4 端子通電法を用いた抵抗-温度(R-T)特性測定により評価した。
3.実験結果 図 1(a)と(b)に、それぞれ酸素気流フリー育成法と酸素封入育成法で得られた Bi 系超伝導ウィスカーの R-T 特性を示す。図(a)より、酸素気流フリー育成法で作られる Bi 系超伝導ウィスカーは測定温度を下げても超伝導特性を示さなかったのに対し、新手法で得られた Bi 系超伝導ウィスカーは測定温度を下げると電気抵抗が 0Ωとなり超伝導特性を示した。このことから、密閉炉心管内の酸素が Bi 系超伝導ウィスカーの育成に十分な
量であることを示唆している。 また、新手法で得られた Bi 系超伝導ウィスカ
ーの超伝導転移温度(Tc)は 90K であった。この結果から、酸素封入育成法により得られた Bi 系超伝導ウィスカーの Tc は従来法に遜色なく、優れた超伝導特性を有していることが分かった。 さらに、従来法に比べ結晶サイズも大型化し、
酸素気流を極力用いないことから、コストを抑えた効率的な育成が可能となった。 4.結言 本研究で提案した手法は先行研究の利点であった結晶サイズの大型化を実現しつつ、短所であった超伝導特性の劣化を克服できた。加えて、本手法では酸素使用量の削減にも直結するため、極めて優れた手法であると考えられる。 参考文献
[1] H. Uemoto et al.,Physica C, 392 (2003) 512.
お問い合わせ先 氏名:飯田涼太 E-mail:[email protected]
図 1 それぞれの手法で育成を行った
Bi 系超伝導ウィスカーの抵抗-温度 (R-T) 特性
[ (a)酸素気流フリー育成法、(b)酸素封入育成法]
I-007

熱可塑性 CFRPと金属のレーザ接合における
温度と接合強度の関係
(近大高専専攻科生産システム工学専攻 1,総合システム工学科2)
○山本大輔 1・山川昌文2
キーワード:半導体レーザ,レーザ接合,熱可塑性 CFRP,接合強度
1.緒言 薄厚のアルミパイプに熱可塑性 CFRP テープを巻くことで補強することを目的に、熱可塑性CFRPとアルミ板との接合の可能性について接合温度と接合強度から検討した。 まず、半導体レーザのアルミ板に対する投入熱
量と温度の関係を調べ、温度から接合の可能性について評価した。この結果から接合の可能温度を予測し、実際に熱可塑性 CFRP の母材である PA6
樹脂のフィルムとアルミ板とのレーザ接合を試み引張試験を行った。 ここでは、母材樹脂と金属との接合の可能性に
ついて考察し結果を報告する。
2.実験装置及び方法 半導体レーザは JDSU 社の IDL Series(波長
940nm)を使用した。温度観察の為のサーモカメラは(株)Apiste FSV-210L を使用した。
図 1:実験装置 概略図
試験片は図 2 に示すサイズのアルミ板を使用
し、事前に混合砂番手 120 番の噴射剤を用いて、噴射距離おおよそ 70mm でアルミ板表面をサンドブラスト処理した。なお、接合する PA6 樹脂フィルムの厚さは 0.053mm である。
図 2:アルミ板のサイズ 以下の方法で実験を行った。
(1) 温度観察:レーザ強度 35W でアルミ板に 60 秒間照射を行い、照射面温度を観察する
(2) 接合実験:レーザ強度 35W で PA6 樹脂フ
ィルムとアルミ板を接合し、引張試験機(島津製作所 UH-300kNl)で接合強度を調べる
3.結果と考察 3.1 アルミ板の照射中心温度観察 アルミ板の温度測定結果を図 3 に示す。
図 3:アルミ板の温度変化
照射開始から約 20 秒でどの板も 270℃近傍に達 する事が確認できた。この結果から次に、レーザ 強度を 35W として照射時間を変えることで投入 熱量と接合強度の関係を調べる。 3.2 接合実験 照射時間を 20 秒(700J)、40 秒(1400J)、60 秒(2100J)とし、接合状態を図 4に示す。
(a) 照射時間 20 秒 (b) 照射時間 40 秒
図 4:接合状態 予測した投入熱量で接合可能である事が確認
できた。また投入熱量の増加に伴い、接合面積が広がる事を確認した。 照射時間 20 秒での接合強度は 2.28MPa であっ たが、40 秒では接合部分の樹脂がアルミ板から 剥がれることなく、PA6 樹脂フィルムが先に切れ るという現象が見られた。
お問い合わせ先
氏名:山本大輔
E-mail:[email protected]
I-008

医療への応用を目指した
高温超伝導ジョセフソン接合素子の簡易作製
(米子高専電気情報工学科 1,物質・材料研究機構 2,筑波大学 3 )
○青戸淳之介 1・中村将大 1・田中博美 1・松本凌 2,3・高野義彦 2,3
キーワード: 超伝導, ジョセフソン素子, 水浸, 脳磁計, SQUID
1. 緒言
超伝導体は現在、リニアモーターカーやMRI
に応用されている。その中でも超伝導量子干渉計(SQUID:Superconducting Quantum Interference
Device)は脳磁計など、医療分野において応用されている素子である。しかしながら、その作製には、高価な装置を用いた基本素子(ジョセフソン接合素子)の作製が必要である。ジョセフソン接合素子は薄い絶縁体を超伝導体で挟んだ構造をしており、従来は収束イオンビーム( Focused Ion Beam)装置を用いて、Bi2Sr2Can-1CunOy(n=1-3)系高温超伝導体(Bi 系ウィスカー)の固有ジョセフソン接合に微細な溝を作製することで実現している。 このジョセフソン接合素子の新しい作製方
法として、内部構造に固有ジョセフソン接合を有する Bi 系ウィスカーの表面に蒸留水を接触させること(水浸処理)により Bi 系超伝導体を部分的に絶縁化し、電流経路を制御する[1]。本研究では先行研究の作成プロセスの見直しを行い、作製効率の向上を試みた。
2.実験方法 水浸処理によるジョセフソン接合素子は固有ジョセフソン接合を有する ASGQP(Al2O3
-Seeded Glassy Quenched Platelets)法[2]を用いて作製した高い結晶性と超伝導性を有する Bi 系ウィスカーと蒸留水によって実現している。始めに、Bi 系ウィスカーの両端に試料の固定およびウィスカー側面からの電流の流入を防止するため酢酸ビニル樹脂系エマルジョン型接着剤を用いた。次に Ag ペーストを用いて 4 端子測定に用いる電極を設置し、その後蒸留水を用いて部分的に水浸処理を行いジョセフソン素子の作製を行った。この時に電気抵抗と水浸開始からの時間との関係を調べ最適化に用いた。その後素子の電流-電圧(I-V)特性測定を行い、ジョセフソン電圧を評価した。 3. 結果 図 1に水浸処理時間と電気抵抗の関係を示
す。水浸開始時刻を 0h とするとグラフが示すように電気抵抗は水浸処理開始直後に急激に 増加し 30 分で約 51%、1 時間で約 71%上昇。
その後は緩やかに増加していき、5 時間後には抵抗が飽和することがわかった。従って水浸処理時間が 1 時間でジョセフソン接合が形成されていると考えられる。そこで水浸時間 1 時間の試料の I-V 特性を測定し、マルチブランチ評価を行った結果、図には示していないが、1 接合分のギャップ電圧があることがわかった。
4. 結言 本研究では先行研究で考案した水浸処理ジョセフソン像観測においての作製プロセスの最適化を目指し、改良をおこなった。その結果、1h の水浸処理で 1 接合分のギャップ電圧の観測されたことから、1h の水浸処理でジョセフソン接合が形成されることが分かった。 参考文献 [1] 田中聖也ら日本高専学会第 21 回年会公演論文集 pp.
143-144(2016). [2] H. Uemoto et al., Physica C, 392 (2003) 512. お問い合わせ先 氏名:青戸淳之介 E-mail:[email protected]
図 1 水浸処理時間と Bi 系高温超伝導ウィスカーの電気抵抗の関係
I-009

4H-SiC(0001)-(1×1)再構成表面上の加熱及び
蒸着時間に伴う ZnPc吸着形態の観測
(宇部高専電気工学科 1,宇部高専専攻科生産システム工学専攻 2,
長岡技術科学大学工学部電気電子情報工学専攻 3)
○碇智徳 1*・河村和哉 1・植杉昌平 2・安井寛治 3
キーワード:フタロシアニン,シリコンカーバイド,表面構造,電子状態
【緒言】
金属フタロシアニンは、熱的・化学的安定性に優れた材料であり、ガスセンサー等の有機デバイス応用に関する様々な研究が行われている[1]。しかし、高感度化や安定性の向上といった課題が有り、これらには薄膜形成過程が影響を与えることが知られている。そのため、基板上での金属フタロシアニン分子の配向を制御することが重要な技術となる。本研究では、金属フタロシアニンの中でもガスセンサーとしての応用が期待されている亜鉛フタロシアニン(ZnPc)に着目し、SiC 基板表面上での蒸着及び加熱時間に伴う吸着形態の変化を調べ、薄膜形成メカニズムの解明を目指した。
【実験方法】
実験は、飛行時間差型ヘリウム準安定原子(He
*)生成源、低速電子線回折(LEED)装置、ZnPc
蒸着源、静電阻止型アナライザを配した超高真空チャンバー内で行った。基板として、4H-SiC(0001)表面を用い、基板加熱することで(1×1)再構成表面を形成した。その表面に対して、ZnPc分子を封入した坩堝を通電加熱することで蒸着し、その後、基板温度150[
oC]で15[h]
の加熱を行った。ZnPc蒸着及び加熱後の最表面の電子状態は準安定原子誘起電子分光法(MIES)を用いて観測し、表面の周期構造はLEED により観察した。
【実験結果と考察】
図 1に 4H-SiC(0001)-(1×1)再構成表面上のZnPc蒸着及び加熱による MIES観測結果を示した。ZnPc蒸着前の(1×1)表面では、7[eV]
付近に Si-3p軌道に起因するピーク構造が確認できた。ZnPcを 400[sec]蒸着した表面では、4
~6[eV]において Pcの σ軌道に起因するピーク、7.5[eV]において Pcの π軌道に起因する構造が確認できた[2]。σ軌道に起因するピーク強度がπ軌道のものよりも高いことから、ZnPc分子は基板に対し傾いた状態で吸着されていると考えられる。さらに、その表面を加熱した結果(図 1(c))では、π軌道による電子放出強度が、大きく変化していることが分かる。このことから、加熱前後では、表面に対して吸着した ZnPc
分子の配向が変化した可能性が考えられる。
図 1 ZnPc/SiC(0001)表面上の MIES 観測結果
(a) (1×1)再構成表面,(b) ZnPc 蒸着,
(c) (b)を加熱した表面
【結言】
SiC-(1×1)再構成表面における ZnPc分子の挙動をMIES観測により調べた。基板加熱前後により吸着形態が異なる可能性を見出した。当日は、蒸着量を変化させ、さらにその表面を加熱することによる吸着状態の変化を電子状態及び表面構造から検討した結果を報告する。
【参考文献】
[1] J.R. Bates, et al.; Sensor Technologies. vol. 1.
152 (1997).
[2] H. Yamane, et al.; J. Appl. Phys. 99. 093705
(2006).
お問い合わせ先
氏名:碇智徳
E-mail:[email protected]
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pc
Pc
(c)
(b)
Intensity [arb.unit]
Kinetic Energy [eV]
Clean 400s 400s 加熱
(a)
Si
I-010

プラズマ殺菌機能を持った輸送用コンテナの制作
(和歌山工業高等専門学校電気情報工学科)
○山澤優・川島夏・竹下慎二
キーワード:プラズマ殺菌,オゾン、輸送用コンテナ
1.はじめに 和歌山県ではみかん等の果実の生産が盛んであるが、従事者数の減少と栽培の際に用いる農薬のコストとリスク管理が問題である。そこで空気を作動流体としたプラズマを発生させることにより、コンテナに収穫したみかんに付着している細菌やカビなどをトラックや船舶等での輸送中に殺菌することで安全性を確保しつつ農薬費の負担を減らし、設備の小型化を実現することを検討した。 2.実験 この実験に使用した回路を図 1 に示す。商用電圧源、スライダック、電圧系、電圧計、作動ガスとして空気(エアポンプ)、ネオントランス、作成したトーチ型リアクタからなるプラズマ発生装置と作成したアクリルケースを用いて構成した。入力条件として印加電圧を 80[V]一定、空気の流量を 7[L/min]一定としてプラズマ照射を行った。 図 2 に実験手順の概要を示す。
プラズマ照射時間としては、インターバル時間を設けた場合と連続照射の場合の殺菌効率を調べるため、6[min]、3(1)3[min]、3(2)3[min]、3(3)3[min]、 3(4)3[min]の場合を検討した(3(2)3[min]照射を例として出すと、三分照射し二分照射をやめ、再度三分照射し計 6 分間の照射をする)。 プラズマ照射後はインキュベータ(28[℃])で
三日間培養する。三日後、PD 平面寒天培地上にコロニーが確認できるので数を数える。死滅率は式(1)を用いて計算した。 死滅率[%]=1-(照射後のカビのコロニー数[個]/未照射時のカビのコロニー数[個])×100 (1) 3.結果及び考察 結果としてインターバル時間を設けた場合、連続照射の時の殺菌効率と比べるとインターバルが一分でもあれば殺菌効率が上がることが分かった。表 1 に示す。 今後の課題として、インターバル時間がある
場合のサンプルを増やしデータの信ぴょう性を増やし、さらに輸送用コンテナ内部の空気を循環させる事を検討する必要がある。
図 1 プラズマ発生装置の回路
図 2 実験手順
表 1 インターバル照射の死滅率
お問い合わせ先 氏名:山澤優 E-mail:[email protected]
死滅率[%] a b c d e 計[%]
6[min] 60 -16.7 -9.1 40 75 29.84
3(1)3[min] 80 66.7 27.3 80 75 65.8
3(2)3[min] 100 50 18.2 100 100 73.64
3(3)3[min] 100 50 9.1 100 50 61.82
3(4)3[min] 100 100 27.3 100 100 85.46
I-011

熱損失ゼロでの長距離送電を目的とした
超伝導接合の研究
(米子高専生産システム工学専攻 1,米子高専電気情報工学科2)
○田中橘平 1・佐伯夏海2・荒木颯太2・田中博美2
キーワード:高温超伝導体,超伝導ケーブル,長距離送電,無損失接合
1.緒言 高温超伝導体(HTS)は Tc 以下で完全導伝性を示すため、この特性を電力ケーブルに応用することで「熱損失ゼロ」で大電流を流すことが可能となる。そして、大幅な省エネルギー化を実現できるとして期待を集めている。現在、世界中で超伝導ケーブルの実用化に向けた研究・実験が進められている。一方で、超伝導ケーブルを世界中に張り巡らせるためには、何万 kmもの長さが必要である。現状、HTS ケーブルの最大長は数百 m程度であるため、HTS ケーブルネットワークを実現するためにはケーブル間の接合点がどうしても必要になる。しかしながら、この接合点は現状では半田等の非超伝導体で構成されているため通電的に熱損失が生じてしまう。そのため、超伝導ケーブルの特徴である「熱損失ゼロ」での送電が実現されなくなってしまう。 本研究は、接合点に超伝導体-超伝導体の直接接合を採用することで、高温超伝導体を用いた長距離送電時の熱損失を低減する方法を提案した。最近の報告で、2 本の HTS 線の表面に段差加工を施すことによって HTS-HTS 接合(以後、HTSジョイント)が実現できることが明らかになっている[1]。しかしながらその加工プロセスは複雑で高度な技術を要するため実用化には不向きである。そこで本研究は、「簡単で安価に HTS ジョイントを実現する手法」の検討を目的として実験を行った。 2.実験方法 本実験では HTS として住友電気工業㈱が製造
している高温超伝導線材 DI-BSCCO(幅:2.9±0.01mm厚さ:0.34±0.01mm)を用いた。そして、以下に示す 2 つの簡易的な手法で HTS ジョイントの研究に取り組んだ。 ①クリップ加熱法
2 本の DI-BSCCO をクリップで挟み、それを炉内温度:600℃、加熱時間:30min の条件下で加熱する手法である。 ②プレス法
DI-BSCCO を重ね、プレス機を用いて 20[MPa]の圧力を印加することで接合する手法である。 また、これらの手法で作製した HTS ジョイン
トの接合面を SEM・EDX を用いて観察した。さらに 4 端子通電法で R-T 特性の測定を行い、DI-BSCCO単体でのR-T特定との比較を行うことで、接合がうまく形成されているかどうかの確認を行った。
3.結果と考察 図 1 に(a)DI-BSCCO 単体、(b)クリップ加熱法および(c)プレス法のそれぞれで形成した HTS ジョイントにおける超伝導転移温度(Tc) と Tc の分布 (ΔT)を示す。図より、クリップ加熱法・プレス法のいずれの手法において、それぞれ Tc=105K、111Kであった。なお、クリップ加熱法では Tcが、DI-BSCCO 単体やプレス法に比べて 5-6 K 低い。これは加熱処理により 超伝導体であるBi-2223HTS のキャリア密度が最適値からずれたためであると考えられる。また、ΔT は両手法とも、DI-BSCCO 単体 (ΔT=16.6K)とほぼ同じ値(ΔT=16.4-16.7)となった。従って、クリップ加熱法・プレス法ともに接合部において超伝導特性が均一であることが分かった。 4.結言 本研究は「簡単で安価に HTS ジョイントを実現すること」を目的に実験を行った。両手法共にTc = 105-111 K の HTSジョイントを実現することができた。今後は、作製した HTS ジョイントの Ic評価を行い、接合部で生じる電流ロスがどの程度かを明らかにする。
参考文献 [1] G. D. Brittles et al., “President current joints between technological superconductors”, Supercond. Sci. Technol.28 (2015) 093001.
お問い合わせ先
氏名:田中橘平
E-mail:[email protected]
(a)
単体
(b)
クリップ加熱
(c)
プレス
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
102
104
106
108
110
112
単体 クリップ加熱 プレス
ΔT
[K]
Tc [
K]
Tc ΔT
図1 簡易型接合法で作製したHTSジョイントのTcとΔT [(a) DI-BSCCO 単体 (b)クリップ加熱法
(c)プレス法]
I-012

マイクロ水力発電システムの電力変換器の製作
〜第 5報〜
(米子高専電気情報工学科)
○西尾有輝・宮田仁志・石倉規雄・権田英功
キーワード:マイクロ水力発電,電力変換,昇降圧チョッパ,PWM 制御,dsPIC
1.緒言 電力が必要不可欠な存在となっている現代において,再生可能エネルギーは資源枯渇がなく,安全で環境に優しいという点から注目され,開発が進められている. 本研究ではその中でも変換効率が高く,多く
の敷設可能箇所が残されているマイクロ水力発電に着目し,出力の不安定性を解消するための電力変換器製作を行った.今回は先行研究で製作された変換器のうち,昇降圧チョッパの改良を行った. 2.電力変換器の構成 図 1 に電力変換器の構成を示す.まず同期発電機から得られる電圧を三相三倍整流器で整流する.この整流回路は整流と同時に昇圧を行うことができ,マイクロ水力発電の最大の問題点である低出力時の不安定性を補完する. 次に整流された変動する直流電圧を一定電圧に変換する.そのため,電圧センサからの情報を用いてフィードバック制御をかけた昇降圧チョッパを接続する.昇降圧チョッパの制御には PWM(Pulse Width Modulation)制御を行うことのできる dsPIC(Digital Signal Peripheral Interface Controller) を使用する.そして dsPICにフィードバックプログラムを書き込むことで電圧の平滑化を行う. 最後にインバータを用いて平滑化された電
圧から交流出力を得る.
3.昇降圧チョッパ <3.1> 動作確認 まず先行研究で製作された三相三倍整流器,
インバータ,および昇降圧チョッパの動作確認を行い,それぞれが正常に動作することを確認した. 昇降圧チョッパの動作確認には直流安定化
電源(0~18V)を用い,電圧を変動させながら入力した時の出力をオシロスコープを用いて観測した.その結果,変動する入力電圧に対し,出力電圧が 7.5V 一定になるように制御されていることを確認した.その後入力電圧を 18V以上に設定し,測定を行ったところ,入力が30V を超えたあたりから出力が入力に比例しながら変動し始めた. 本研究では目標電圧を実際のモータの駆動
電圧である 100V に設定するべく dsPIC のプログラム変更を行った. <3.2>昇降圧チョッパの検討
dsPICプログラムから目標値を変更し実験を行ったところ,過電流が確認された.この電流に対し,機器の損傷を防ぐため負荷抵抗を増加させたところ,電圧が一定に制御されなくなった.これは出力抵抗値を変えたことで回路内に流れる電流量が変化し,電圧センサが検出できない電圧値が入力されたためだと予想される.
4.まとめ 今後の実験ではモータ用の入力電圧で過
電流とならないように,回路シミュレータPSIM を用いたシミュレーションを行い回路定数を算出して素子の最適化を行う.また,フィードバック制御プログラムに積分要素を組み込むことで目標値への応答性を改善することが期待される。 具体的な実験結果については研究の進捗
状況に応じて当日報告する.
お問い合わせ先 氏名:宮田仁志 E-mail:[email protected]
同期発電機
三相三倍整流器
昇降圧チョッパ
フルブリッジインバータ
負荷
変動する三相交流電圧
変動する直流電圧
一定の直流電圧
dsPICPWM信号
60[Hz],100[V]の単相交流電圧
電圧センサ直流電圧値をフィードバック
図 1 電力変換器の構成
I-013

Modular Multilevel Converterを用いた
電気鉄道用パワーラインコンディショナの動作検証 ~負荷不平衡における直流バスラインの共有による補償~
(米子高専専攻科生産システム工学専攻 1,米子高専電気情報工学科2)
○那須翔太 1・石倉規雄2・宮田仁志2
キーワード:不平衡成分,高調波電流,無効電流,PWM 制御,バスラインの共有
1. 緒言 交流電気鉄道は電力系統から大容量の単相
電力を受電すると、電圧不平衡や電圧変動が生じる。また、電気車負荷は電源系統へ無効電流と高調波電流を放出する。これらを補償するため、先行研究にて MMC(Modular Multilevel
Converter)を採用し、マッチングトランスが不要な小型・軽量であるパワーラインコンディショナが提案された[1]。しかしながら、負荷が不平衡である場合、補償できなかった。本研究では直流バスラインを共有し、相間での補償を目的とした回路を提案する。 2.解析方法・結果 図 1 に本研究にて提案する回路構成を示す。MMCの主回路はチョッパセルとバッファリアクトルによって構成されている。今回 MMC は簡略化のために1レグ2段のチョッパセルで構成した。先行研究では各相につき 1レグで制御を行ってきた。しかし、負荷の不平衡に対し、電源電流を平衡させることができなかったことから、本研究では直流バスラインを共有することにより、二相間における不平衡電流を補償できると考える。 改良した制御法の有効性を確認するために、計算機シミュレーションを行った。図 2 に負荷が平衡である場合の解析結果、図 3 に β相の負荷を大きくし、負荷を不平衡にした場合の解析結果を示す。また、表 1 に回路定数を示す。図2、図 3 共に上から負荷電流 ilβ、パワーラインコンディショナの出力電流 icβ、き電系統電流isa、isβを示す。負荷が平衡の場合、isβに高調波による影響等が見受けられないため、この系は有効だといえる。負荷が不平衡の場合、isaと isβ
が不平衡であること、また、き電系統電流が正弦波でないことからこの系は有効でないと言える。 バスラインを共有したセル、非共有のセルの
スイッチングと、回路定数の再検討が必要だと考えられる。
文 献
[1] 西尾 知美, 石倉 規雄, 宮田 仁志,”MMC 電気鉄道用パ
ワーラインコンディショナの検証”, 第 22 回高専シンポジ
ウム inMie講演要旨集, E-22
お問い合わせ先 氏名:那須 翔太 E-mail:[email protected]
表 1 シミュレーションに使用した回路定数
き電系統電源電圧 v, v 100V
き電系統周波数 f 60Hz
バッファリアクタンス l 5mH
バスラインキャパシタ容量 c 10mF
バスラインキャパシタ電圧 vc 150V
搬送波周波数 fc 2.4kHz
等価スイッチング周波数 4fc 9.6kHz
図 3 解析結果(負荷不平衡)
icβ i
l β
Time(s) 50ms
[A]
[A]
isβ
isα
25mm ×
25mm の空白
(提出時,この
枠・文字は削除し
てください。)
図 1 パワーラインコンディショナの主回路構
成
図 2 解析結果(負荷平衡)
icβ i
l β
isβ
isα
Time(s) 50ms
[A]
[A]
I-014

MMCを用いた電気鉄道用 パワーラインコンディショナの
電流制御の基礎実験
(米子高専専攻科生産システム工学専攻 1,米子高専電気情報工学科2)
○勝部佳揮 1・石倉規雄2・宮田仁志2
キーワード:電気鉄道,Modular Multilevel Converter,Dynamic Link Library
1.緒言
現在普及している電気鉄道の電力供給には,交流送電方式が採用されている。これは,一般の三相電力系統から受電し,スコット変圧器を介して二相電力を架線に送電している。負荷となる電気鉄道は,ダイヤに従って加減速を繰り返すため,電源である二相電力が不平衡となり,無効電力や高調波電流も排出する。これらの悪影響は,三相電力系統及び,近隣の電力品質を落とす。そこで本研究室では,上記の問題を解決するためにModular Multilevel Converter(以後,MMC)を用いた手法を提案している[1]。
本稿では、C 言語を用いて記述した制御器を用い,遅れ等を考慮したシミュレーションと実機を製作し理想素子のみの構成と同様の波形が得られるか検証を行った。
2.シミュレーションによる検証
C言語で記述したDLL(Dynamic Link Library)
ブロックを用いた場合における,文献[1]のキャパシタ電圧一定制御が理想素子と同様の働きをするか検証した。図 1に従来の理想素子を用いた制御回路,図 2に DLLブロックを用いた制御回路を示す。入力波形 vCu1,vCu2,iCαは,MMC に実際に現れる波形を参考に設定した。この時,積分は長方形近似,シミュレーションの刻みは 1×10-6[sec],サンプリングの周期は250×10-6[sec]とした。
図 3に PSIMによるシミュレーションの結果を示す。波形は理想素子を用いた出力波形 vCau
と DLLを用いた出力波形 vCau_DLLである。図 3
より,vCauと vCau_DLLは同位相,同振幅である。出力振幅の誤差は最大で約 4×10-7[%]であり,vCauと vCau_DLLはほぼ等しい事がわかる。以上より,理想素子から,プログラミングを用いた制御に置き換えた場合において,問題なく動作することが確認できた。
3.結言
本稿では,C言語で記述した制御器を用いて遅れ等を考慮したシミュレーションを目的として,制御回路を DLL ブロックを用いたものへ変更した。その結果,理想素子からプログラミングを用いた制御に置き換えた場合において,制御器は問題なく動作することが確認できた。
参考文献
[1]勝部佳揮,石倉規雄,宮田仁志,“MMCを用いた電
気鉄道用パワーラインコンディショナ-セルコンバー
タの基礎実験-”,第 22回高専シンポジウム in Mie講
演予旨集,E-23
お問い合わせ先
氏名:勝部佳揮
E-mail:[email protected]
図 1 理想素子を用いた電圧一定制御
図 2 DLLを用いた電圧一定制御
図 3シミュレーション結果
I-015

埋込永久磁石同期モータの
直軸および横軸インダクタンスの算出
(米子高専電気情報工学科)
○米咲翔太・宮田仁志・石倉則雄・権田英功
キーワード:IPMSM,直軸インダクタンス,横軸インダクタンス,フーリエ変換 1.緒言 あ 2015 年部門別二酸化炭素排出量の割合で,運輸部門が 17%を占めており,電気自動車が普及すれば二酸化炭素の排出が抑えられる.しかし,電気自動車は 1度の充電で走行できる距離が短く,走行距離を延ばすためにはバッテリの量を増やすかバッテリの利用効率を上昇させる必要がある.よって,本研究では埋込永久磁石 同 期 モ ー タ IPMSM (Interior Permanent Magnet Synchronous Motor)の直軸および横軸インダクタンスを正確に測定し,等価回路を用いて制御を効率よく行うことのできるシステムの設計を目指す. 2.インダクタンスの算出
<2・1>IPMSM について 永久磁石同期モータ PMSM は永久磁石の配置により埋込磁石形である IPMSM と表面磁石形である SPMSM (Surface PMSM) の 2 種に大別できる. IPMSM は永久磁石が回転子の内部に埋め込まれているため,永久磁石の飛散の心配がない.また,IPMSM はリアクタンストルクの活用により,小型化でき,比較的高効率であるという特徴があるため,電気自動車のモータとして使用されている. <2・2>インダクタンス測定
モータの等価回路定数は,特性算定や制御系の構築に必要であり,形状や材料のデータからも算出することは可能である.しかし,高精度な等価回路定数を得るには実測が必要となる. 直軸および横軸インダクタンスの測定法は,モータを実際に駆動する回転試験法とモータを静止させた状態で行う静止試験法に大別される.前者は駆動時における特性を表す値を直接測定できるが,正確な測定に手間を要するため,本実験では後者の静止試験法を用いた. 式(1)に静止時における IPMSM の dq 座標の電圧方程式を示す.ここで,vd,vq,id,iqは各軸の電圧及び電流であり,P は微分演算子,Raは電機子抵抗,Ld および Lq は各軸のインダクタンス,Lha,Lhb および Lhc はインダクタンス変化の歪みに起因するインダクタンス成分である.θreは回転子の電気角[rad]である.
�𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑞𝑞�=�
𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 00 𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑞𝑞
� �𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑞𝑞�
�𝑃𝑃ℎ𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐6𝜃𝜃𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑃𝑃ℎ𝑏𝑏𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠6𝜃𝜃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃ℎ𝑏𝑏𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠6𝜃𝜃𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑃𝑃ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐6𝜃𝜃𝑟𝑟𝑟𝑟
�P�𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑞𝑞�
(1)
(a)U-VW (b)V-W
図 1 試験回路 式(1)では θre が 0 または π/6 であるとき,他
軸電流に起因した起電力の干渉項が零になるため,インダクタンスの測定が可能となる.本実験では回転子を θre=0 および θre=π/6 に引き込まれるように拘束して実験を行った.
図 1(a)は回転子を θre=0 に固定する回路であり,これにより直軸磁束が発生する.また, 図 1(b)ではそれに対する横軸磁束が発生する.これと同様に回転子を θre=π/6 に固定する回路でも実験を実施した.これにより直軸および横軸のインダクタンス Ld,Lq が測定できる. まず,オシロスコープで測定した波形から,その近似曲線を導出する.そしてそれを,フーリエ変換することでインダクタンスを求めることができる.本研究で使用しているモータの測定結果は Ld=2.05[mH],Lq=1.63[mH]であった. 3.まとめ 今回の実験で求めたインダクタンス Ld,Lqを使用し,パワーエレクトロニクス用制御システムである「PE-Expert3」で無負荷試験を行い,良好な動作を確認した.今後は,この回路定数を用いて種々の制御系を設計する.
お問い合わせ先 氏名:宮田仁志 E-mail:[email protected]
I-016

曲面上磁気光学イメージングの為の
磁気光学センサに関する研究
(鈴鹿高専専攻科総合イノベーション工学専攻 1,
鈴鹿高専電気電子工学科 2)○嶋本紘己 1・中村元輝 1・橋本良介 2
キーワード:磁気光学効果,磁気光学イメージング,磁性ガーネット,磁性フォトニック結晶
1. 背景
現在,日常生活の安全性を維持するために多種多様な非破壊検査が行われている.鉄鋼材料の,破壊原因の一つに疲労亀裂がある.疲労亀裂は,マイクロクラックと呼ばれる開口幅が 10 µm オーダの微小亀裂が進展して生じる.このマイクロクラックを検出するためには,高空間分解能な検査手法の開発が必要である.そこで我々は,磁気光学(Magneto-optical: MO)イメージングに着目した.MO イメージングの空間分解能は,MO センサに用いる磁性体の磁区サイズに依存するため,微細な磁区を有する磁性体を作製することで,高空間分解能化が期待できる.先行研究では,センサに磁性フォトニック結晶(Magnetophotonic
crystal: MPC)を用いることで,高空間分解能なMO イメージングができた 1).しかし,先行研究の MO センサはスパッタ法により作製していたため,成膜後に結晶化熱処理が必要であった.従って,基板は耐熱性のある単結晶基板などに限られており,被検体形状は平面に限られて,曲面に対応していなかった.そこで我々は,曲面上非破壊検査に対応するために,フレキシブル基板を用いた MOセンサの作製を目的に研究を行った.
2. 実験方法
曲面用 MO センサを作製するために,MO 材料をフレキシブル基板上に形成した.MO材料には,市販されているイットリウム鉄ガーネット粒子(組成比:Bi:Y:Fe = 0.5:2.5:5.0,HOSOKAWA
POWDER TECHNOLOGY RESARCH
INSTITUTE 製)を利用した.この粒子を有機バインダ(ポリビニルアルコール)中にスターラを利用して分散させた.分散した溶液を,スピンコータを利用して基板上に塗布した.この時,磁性ガーネット粒子とポリビニルアルコールの質量比率を変化させ,膜ができる比率を探査した.
一方,MO 材料の組成制御のために,磁性ガーネット粒子を,共沈法を利用して作製した.共沈法は,粒子の作製方法の一つで,材料となる金属イオンを含む酸性溶液にアルカリ性の pH 調整剤を添加することで粒子を作製する方法である.pH 調整剤には水酸化ナトリウム(NaOH)を利用して,粒子が生成される質量%濃度を調査した.共沈法で生成された粒子はアモルファスである.そこで,成膜する前に粒子を結晶化熱処理することで,耐熱性の低い基板上への成膜が可能になる.
(a) (b) (c)
Fig1. NaOHの質量%濃度による析出量の違い
質量%濃度が(a) 8%,(b)11%,(c)14%.
3. 実験結果
市販の磁性ガーネット粒子と有機バインダの質量比率が 1:1の溶液を,スピンコータを利用してプラスチック基板上に塗布した結果,多少偏りがみられたものの,フレキシブル基板上にMOセンサが形成できた.
また,共沈法で粒子が生成される pH調整剤の質量%濃度を調査するために,質量%濃度がそれぞれ 8%,11%,14%の NaOH 水溶液を作製して,硝酸化合物溶液に滴下した.その結果を Fig.1
に示す.その結果,質量%濃度が 8%の時は粒子の析出がなく,11%の時に析出が見られ,14%の時には析出量が増加することがわかった.その後,ミリングを施すことで,粒径が数ミクロン程度で形状のそろった粒子が作製できた.従って,作製した粒子に結晶化熱処理を施して,プラスチック基板上に塗布することで,フレキシブル MO
センサが作製可能であることが示唆された.今後は,作製した粒子の特性を評価する計画である.
4. まとめ
本研究は,曲面上非破壊検査のための MO センサの作製プロセスの確立を目的に行った.その結果,有機バインダ中に分散させた磁性ガーネット粒子を,フレキシブル基板上に塗布することができた.さらに,共沈法を利用することで,塗布する磁性ガーネット粒子の材料となる共沈物の生成条件が確立できた.今後は作製した粒子の特性を評価して,フレキシブル基板上に塗布してMO センサを開発する計画である.
参考文献:
1) R.Hsahimoto, T.Yonezawa, H.Takagi, T.
Goto, H.Endo, A.Nishimizu and M.Inoue:
J. Magn. Soc. Jpn, 39, p.213, 2015.
お問い合わせ先
氏名:橋本 良介
E-mail:[email protected]
25mm ×
25mmの空白
(提出時,この
枠・文字は削除し
てください。)
I-017

有限要素法を利用したアルミニウム上磁気光学
イメージングのための漏洩磁界強度の研究
(鈴鹿高専専攻科総合イノベーション工学専攻 1,鈴鹿高専電気電子
工学科2)○中村元輝 1・橋本良介 2・嶋本紘己 1
キーワード:MOイメージング,常磁性体,渦電流,COMSOL,磁界強度
1.はじめに 現在,日常生活の安全性を維持するために
様々な非破壊検査が行われている.本研究では磁気光学(MO)効果を用いたイメージングの非破壊検査への応用に関する研究を行っている.
MOイメージングは,欠陥からの漏洩磁界を画像の光強度として取得できるため,漏洩磁界を介して欠陥が可視化できる.従って,MOイメージングのためには,被検体に磁界を印加するための磁化器が重要である.先行研究では,直流電流を用いた磁化器を使用していたため被検体は強磁性体に限られ,常磁性体の被検体は磁化できなかった 1).しかし,一般に利用されている構造物はアルミニウムのような常磁性体が多く,直流電流磁化器は利用できない. そこで本研究では渦電流磁化器による被検
体の励磁に着目し,有限要素法を用いて欠陥の存在により生じる漏洩磁界の強度分布をシミュレーションした.これまでに本研究室では,欠陥から漏洩する磁界を,2次元的な強度のカラーマッピングとして表現できた.そこで本研究では,欠陥によって漏洩した磁界強度を数値化することを目的とした. 2.調査方法 有限要素法を用いて下記のパラメータを与
えることで,渦電流磁化器の動作を三次元的に解析した.中でも,コイルに流す電流の大きさ,周波数およびコイルのターン数が,欠陥からのz 軸方向の距離に応じた漏洩磁界強度に及ぼす影響を数値として解析した.有限要素シミュレータには COMSOL5.3.0.223を使用した.
図 1 シミュレーションモデル
被検体は,比透磁率:1,電気導電率:1.12×107 S/m のアルミニウム,コイル内は非透磁率:4000の鉄心,周囲は空気(非透磁率:1).
3.結果と考察 コイルの電流 1 A ,ターン数 100 回 ,周
波数 100 kHz ,欠陥からの z軸方向の距離 0.1 mmを基準に各パラメータを変化させた. 図2は欠陥からのz軸方向の距離に対する磁
界強度を示す.この結果から,被検体からの距離が 10 µmのとき磁界強度は 2.5 Oeになることがわかった.先行研究で作製したセンサの磁界感度は数 10 Oeから数 100 Oe程度であった.従って, 厚さ 1 µm のセンサを作製すれば,センサの磁界感度が得られることが示唆された.現在,作製しているセンサの厚さに相当する,センサ材料粒子の粒径は数ミクロン程度であることから,十分達成が可能であると考えられる.今後は MO イメージングのセンサの磁界感度を得るための渦電流磁化器の条件を調査する計画である.
図 2 欠陥からの z軸方向の距離に対する
磁界強度 4.まとめ 本研究では MO イメージングセンサによっ
て検知可能な漏洩磁界を発生させる磁化器の条件をCOMSOL5.3.0.223を用いて探査した.各パラメータのシミュレーション結果より,z軸方向の距離を変えることでセンサで取得可能な磁界感度を得られることがわかった.
参考文献
1)R. Hashimoto, T. Yonezawa, H. Takagi, T.
Goto, H. Endo, A. Nishimizu and M. Inoue,
J. Magn. Soc. Jpn, 39, p.213, 2015.
お問い合わせ先 氏名:橋本 良介 E-mail:[email protected]
I-018

小型分光器を用いたガス雰囲気中での
PLDプロセスの発光分光計測
(鈴鹿高専電気電子工学科 1,鈴鹿高専専攻科電子機械工学専攻 2)
○佐藤滉一 1, 兵働徳仁 2,柴垣寛治
キーワード:PLD 法,レーザー,プラズマ,分光
1.はじめに
PLD プロセスを制御するためにプラズマを計測することは重要であるが,時間的,空間的に変化するため精密な計測は一般的に難しい.これまで,小型の簡易な分光器を用いてこのプラズマを発光分光計測し,学生実験などへ適用できるかを検討してきた.今回の研究では,雰囲気ガスを導入したプラズマを計測対象としてスペクトルの解析を試み,ガスの種類や圧力に対する変化の有無を調べた.
2.実験
レーザー装置はパルス Nd:YAG レーザー(波長1064nm,繰り返し周波数1Hz、強度6J/cm
2).ターゲット材料としてチタンを使用した.実験の流れとしては,常温である真空容器内にターゲット材料(Ti)を設置した.その上で容器内にガスを導入し圧力を変化させた.プラズマ光を集光レンズと光ファイバーを通じて小型マルチチャンネル分光器に導入した.分光器はPCと接続されており,集光時間を 1秒として発光スペクトルのデータを保存した.同様の操作を 5回行い,それらの平均化処理を行った.
3.結果・考察
図 1にN2ガス 40Pa中での発光スペクトルを示す.N2ガス雰囲気中でレーザーアブレーションを行うとプラズマの発光が活発となり,真空中の場合より発光強度は大きくなることがわかった.これはガス雰囲気中でアブレーションを行った場合はプラズマが圧縮されて,観測領域内に発光が集中したためと考えられる.
図 2ではガス圧を 10Paから 20Paに変化させたときに低波長領域(A~D)のピークに変化が見られることが分かった.何らかの要因でプラズマのエネルギー分布が変化して,低波長領域のピーク値の相対的な強度が下がったと考えられる。要因の一つとして,N2がプラズマ化して解離してできた Nと Tiとが反応して TiN
になったことにより,エネルギーが TiNの反応に使われた可能性が挙げられる.さらに詳しく調べるために Ar(希ガス)を用いてさらに実験を行った.詳細は講演にて発表する.
図 1. N2ガス雰囲気中(40Pa)での
発光スペクトル
図 2. 各ガス圧における最大のピーク値とその他の各ピーク値との比較
お問い合わせ先
氏名:柴垣寛治 E-mail:[email protected]
A
B
C D
E
F
G
I-019

PLD法による親水性薄膜の生成と評価
(鈴鹿高専電気電子工学科 1,鈴鹿高専専攻科2)
○三島大和 1・家木和明2・加藤久東2・柴垣寛治
キーワード:PLD法、空気,チタン,アルゴン,親水性
1.はじめに PLD法はレーザーを用いた成膜手法の一つ
であり、多くの材料に対して適用可能であるなどの利点を有する。所属する研究室ではこれまでにもさまざまな材料の成膜を試みてきたが、いずれも真空中での成膜であった。そこで、今回の研究ではガスを導入しての PLD成膜実験を行い、ガスの種類や圧力を変化させて膜サンプルを取得した。膜サンプルの表面を観察するとともに、親水性・撥水性の調査を行った。 2.実験 真空容器内にターゲットとなるチタン板と、
基板となるシリコンウェハを 2.5cm離した状態でセットし、ターゲットにレーザーを照射した。レーザーには波長 1064nm、出力 50mJのパルス Nd:YAGレーザーを使用し、20Hzで15分間、計 18000回の照射を行い、膜サンプルを形成した。容器内の雰囲気ガスを空気、窒素、アルゴンに変え、ガス圧力を変化させて、実験を繰り返した。 成膜実験終了後にターゲットを取り出し、膜
表面の SEM像を撮影し、画像処理ソフトを用いて全体に占める堆積粒子(ドロップレット)の割合を評価した。また、膜サンプル表面に蒸留水を 0.04ml滴下し、接触角を測定して親水性および撥水性を評価した。
3.結果 図 1,2,3は容器内の雰囲気ガスを空気、窒素、アルゴンと変えたときの各ガス圧力での 接触角の変化を示したものである。 空気圧、窒素ガス圧、アルゴンガス圧での膜
サンプルをSEM像で観察したところ、空気圧、窒素ガス圧では 20Pa、40Paの時、アルゴンガス圧では40Paの時に膜表面の凹凸がみられた。この結果と図 1,2,3 を比較すると膜表面の凹凸が膜の親水性に強く影響を及ぼしていることが示唆された。 また、図 1,2を比較すると空気中で作成し
た膜の方が親水性を強く示していることから、窒素以外のガスにより膜の組成が変化し、親水性を強めたと考えられる。 以上より、ガス圧力の制御、雰囲気ガスの種類によって膜特性の制御ができる可能性がある。詳細は講演にて発表する。
図 1 空気圧と接触角の関係
図 2 窒素ガス圧と接触角の関係
図 3 アルゴンガス圧と接触角の関係 お問い合わせ先 氏名:柴垣寛治 E-mail:[email protected]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 10 20 30 40C
onta
ct a
ngle
(deg
)Air pressure (Pa)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 10 20 30 40
Co
nta
ct a
ngle
(deg
)
N2 pressure (Pa)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 10 20 30 40
Co
nta
ct a
ngle
(deg
)
Ar pressure (Pa)
I-020

モデルベース制御設計に適したノンパラメトリックモデリング手法
(石川工業高等専門学校 1,長岡技術科学大学 2)
⃝寺西郁 1・嶋田直樹 1・矢吹明紀 2・大石潔 2・横倉勇希 2
キーワード:MBC,ノンパラメトリックモデリング,TSP,複素ケプストラム,BiQuad フィルタ
1 はじめにモデルベースト制御はプラントのモデルに基づいて制御系の設計を行う.モデルの精度と複雑さはトレードオフの関係にあり,高精度でも複雑なモデルは制御系設計に用いることが難しい.本稿では,ディジタル信号処理の技術を応用した,任意の制御帯域を高精度かつ比較的簡単に表現するモデリング手法を提案する.
2 TSP法TSP(Time-Stretched Pulse) は (1) 式で定義される [1].
S(k) ≜{exp
(jαk2
), for 0 ≤ k ≤ N/2
S∗ (N − k) , for N/2 < k < N(1)
ただし,α = 4mπ/N2,j:虚数単位,k:離散周波数,N:TSP の信号長,m ∈ Z (0 ≤ m ≤ N/2):時間引き伸ばし係数,S∗:S の複素共役である.(1)
式の逆離散フーリエ変換 s(n)をプラントに入力して得られた応答を y(n)とすると,推定インパルス応答h(n)は y(n)と s(N −n)との直線状畳み込みで与えられる.さらに,(2)式により推定周波数伝達関数が得られる.
H(k) =N−1∑n=0
h(n) exp
(−j
2πnk
N
)≜ F
[h(n)
](2)
3 複素ケプストラム分析インパルス応答 h(n)の複素ケプストラム C(q)は
(3)式で定義される.
C(q) ≜ F−1 [logF [h(n)]] (3)
ただし,logH(k) ≜ log |H(k)|+argH(k)とし,q:ケフレンシである.C(q)を低次のケフレンシでリフタリングすることで周波数特性の包絡が得られる.これにより,TSP法によって推定された周波数特性に含まれる量子化誤差の影響を低減できる.
図 1 提案手法によるモデリング結果
4 BiQuadフィルタBiQuadフィルタの一般式は (4)式で定義される.
F (z) ≜ b0 + b1z−1 + b2z
−2
a0 + a1z−1 + a2z−2(4)
従来のモデルと比較して,BiQuad フィルタは周波数特性を表現する自由度が高く,パラメータの調整を行いやすい.図 1 にモデリング結果の例を示す.青の破線はモデリングされるプラントの特性を表し,橙の点線はTSP法と複素ケプストラム分析によって推定されたプラントの特性を表している.緑の実線は,推定された特性を基に BiQuadフィルタを用いてつくられた,低次の共振モードを考慮したモデルの特性である.
5 おわりに提案手法を用いることで,任意の制御帯域において,特徴的な周波数特性を簡単にモデリングすることができる.発表時に詳細な検討を報告する.高専–長岡技科大 共同研究助成
参考文献[1] 鈴木陽一, 浅野太, 曽根敏夫, “時間引き伸ばしパルスの設計法に関する考察”, 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.92, No.380, pp.17–24 (1992).
お問い合わせ先氏名:寺西郁E-mail:[email protected]
I-021
Related Documents