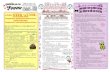Meiji University Title �����������-������������ ����������������� Author(s) ��,�� Citation ��������, 278: 17-35 URL http://hdl.handle.net/10291/5074 Rights Issue Date 1995-03-20 Text version publisher Type Departmental Bulletin Paper DOI https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
-
Meiji University
Titleフェルナンドゥ・ペソア-祖国ポルトガルへの矜恃と
焦慮に引き裂かれた二十面相の思想家
Author(s) 長尾,史郎
Citation 明治大学教養論集, 278: 17-35
URL http://hdl.handle.net/10291/5074
Rights
Issue Date 1995-03-20
Text version publisher
Type Departmental Bulletin Paper
DOI
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/
-
明 治大 学教 養論 集 通 巻278号(1995・3)pp.17-35
フ ェル ナ ン ドゥ ・ペ ソア
祖国ポル トガルへの衿侍 と焦慮 に引 き裂 かれた二十面相の思想家
長 尾 史 郎
「青い空 子供の頃 とかわ らぬ空/虚 ろにして完聖なる永遠の真実
よ
遠い昔か ら黙 して流れる優 しいテージ ョ川/空 を映す小 さな真実よ
ふたたびおれの訪れた苦悩 昔にかわ らぬ現在の リスボンよ
お前はなにもくれぬ 奪わぬ お前は無なるもの そしてそれ こそおれの
かんじているおれだ
放 っ て お い て くれ も う間 もな くだ お れ が 手 間 ど る こ とな どな い か らだ
だ が 深 淵 と沈 黙 が 訪 れ る そ の 時 まで お れ は一 人 だ け で い た い の だ 」
(ア ル ヴ ァロ ・ドゥ ・カム ポ シュ 『LisbonRevisited[再 訪 の リス ボ ン](1923)』,
池上 牛 夫 訳 『フェル ナ ン ド・ペ ソア詩 選 ポ ル トガ ル の海 』 彩流 社,一 九八 五 年)
「再び私 はお前 を再見するま ち
恐 ろ し くも失 わ れた私 の幼 時 の都 市 よ… …ま ち
悲 し くて 楽 し い都 市 よ,私 は再 び こ こで 夢 見 る … …
私,私 だ っ て ~ だ が こ の 私 は,か つ て こ こで 暮 ら し,こ こ に た ち
戻 り,
-17一
-
た ち戻 るべ く身 をひ るが え し,た ち戻 り
こ こに新 た にた ち戻 るべ く身 をひ るが え した の と同 じ私 か?
あ るい は,私 た ち は こ こにいた こ との あ るす べ ての,
一 人 また は多数 の私 は,つらな
一本 の記憶 の糸 で繋 が れ た,ひ と連 りの計 算 単位,
私 の ほか の誰 か につ いて の私 の夢 の ひ と連 りなの か?
再 び私 はお前 を再 見 す る,
よ り疎遠 にな った心 と,よ り少 な く私 の もの で あ る魂 を もって。
再 び私 は お前 を再 見 す る 一 リジボ ア よ,テ ジ ョ川 よ,す べ て の もの よ
,
私 一 この,お 前 と私 自身 とを無為 に通過 す る者,
こ こで も,ど こで も,よ そ者 の私,
魂 にお いて も,生 にお いて も,場 違 い の隙人 者,ま
鼠 の 鳴 き声,羽 目板 の き し りの 音 の 間 に ま に/ふ らふ ら と身 を 震 わ せ て,
生 き る義 務 と い う名 の 呪 い の城 の/追 憶 の 広 間 を さ ま よ い歩 く生 霊 … … 」
(『LisbonRevisited(1926)』,拙 訳)
ポル トガル の顔'
ラ テ ン ・ヨー ロ ッパ の 一 つ ポル トガル だ けは(仏,伊,西 とは異 な り)厳 密
には 「地 中海 国家」 で はな い。 スペ イ ンの トレ ドの北 東 に端 を発 す る大 河 タ ホ
川 が テ ジ ョ川 と名 を変 え てジ ブ ラル タル(地 中海 の西 根)の ず っ と西 で大 西 洋
に注 ぐ広大 な河 口の北岸 に(ポ ル トガル の都 市 は常 に川 の北岸 にあ る)首 都 リ
ジボア(リ ス ボ ン)は あ る。
一18一
-
「テ ジ ョ川 は ス ペ イ ン よ り下 る。い
テ ジ ョ川 はそ して ポル トガル で海 に入 る。/だ れ で もそ れ を知 って い る。」
(カエイロ)
もし もイベ リア半 島 が,西 を向 いた巨大 な世 界 の頭部 だ とす る と,ユ ー ラ シ
ア の怒髪 が天 を衝 き,北 米大 陸 の手 に髪 を握 られ て 吊 り下 げ られ た この メ ドゥ
ー ザの首 は,ジ ブ ラル タル海 峡 で胴体(ア フ リカ)か らムー ア の半月 刀 に よっ
て頸 を は刎 ね られ てい る(海 峡対 岸 の スペ イ ン領 セ ウタ はか つ て ポル トガ ル に
属 してい た)。
ポル トガル はち ょうど この頭部 が被 るマ ス クに当た る(国 境 線 に沿 っ てす っ
ぽ り仮 面 を剥 ぐこ とが 出来 そ うな気 が しまいか?)。ひたい
この偏 平 なマ スクの額 には スペ イ ンの ガ リシア地 方(同 系 の言葉 を話 す ポル
トガル と双 子 の 姉妹)の 前 髪 が掛 か って い る 一 この前髪 か ら滴 り落 ちた ケ
ル トの汗 が仮 面 を伝 って流 れ落 ち,ア フ リカ の胸 元 まで湿 らせ た。
首 都 リジ ボア は テジ ョ川 の河 口で あ る鼻 孔 の位 置 にあ り,鼻 先 は ヨー ロ ッパ
最西端 の ロカ岬 だ(デ リダ は ヨー ロ ッパ全 体 が岬 だ と言 ったか ら,こ れ は 「岬
の岬 」 だ… …)。サ グ レ シ ュ
顎 に 当 た る の は エ ン リケ航 海 王 子 ゆ か りの 聖 な る岬 で あ り(こ の 近 くの
「フアーロ燈 台 」 の町 に大遠 征 のた め の航海 学 校 が あ った),口 は何 か食 欲 を連 想 させ るボル ト
よ うな 明瞭 さを欠 いて い る。 西南 を見 つ め る眼 に当 た る位 置 は 「港 」 とい う
名 の,「 ボル ト ・ガ ル」 自身 の発祥 の地,第 二 の首 都 が 占 め る。仮 面 を引 っ掛
ける耳 は もうポル トガル を離 れて スペ イ ンの マ ドリー ドの辺 りにあ る。
かつ て スペ イ ンもポル トガル もイベ リア は一 つ と考 えたが,前 者 は常 にポル
トガル の仮 面の 下 にスペ イ ンの素顔 を想 定 していた が,後 者 は この面 こそ西 を
向いた イ ベ リアの 「顔 」だ と主 張 した 一一 が,顔 以 上 の要 求 は敢 え て持 ち 出
しは しな か った(半 島 ど こ ろか,両 者 は世 界 を折 半 して共 存 を計 った の だ か
ら)。
一19一
-
そ して,ラ テ ンア メ リカ はア フ リカの胴体 か ら身 二 つに分 かれ た,イ ベ リア
の落 とし子 だ ……。
「テ ジ ョ川 の真 珠 」 と呼 ばれ た 美 しい都市 リジボア は一 二世 紀 のム ー ア人 と
の戦 い と,時 折 の小 さな内戦(一 九一〇 年 の共和 制 革命,一 九一 七年 の シ ドニ
オ ・パ イ シ ュの軍事 クー デ ター,一 九七 四年 のサ ラザ ール打倒 の 「四月 革命 」
な ど)以 外 に は戦 災 を知 らず,今 も,十 八 世 紀 中 葉 の リジボ ア大 地 震 の以 前
(ロー マ時 代 とア ラブ人 の 占領 以 来)と 以 降(宰 相 ボ ムバ ル侯 の都 市計 画)の
両 方 の面 影 をか な り濃厚 に保存 す る,ヨ ー ロ ッパで もユニ ー クな存在 だ。
この都 市 は,そ こでの彼 の存在 ばか りで な く,そ こか らの不在 に よっ て もフ'
エル ナ ン ドゥ ・ペ ソア を培 った の だ った。詩 人 ペ ソア(PessOA)に と って,
ひょうそく
リジボ ア(LisbOA)は 単 に一 つ の都 市 で は な く,真 に平 灰 の合 う 「韻 」
を踏 む,内 部 の リズム が響 き合 う 彼 の 国(ポ ル トガ ル)そ の もの,彼 の
肉体,彼 の幼 時 の世 界 その もの だ った。
何 かの 問題 に解 答 す る とい う こ とは,答 えは ともか く,と りあえず提 出題 の
理 解 を前提 とす る。 だが,ポ ル トガ ルの よ うな,日 本 人 に比 較 的馴染 みの無 い
国 につ い て説 明 す るの は,あ たか もまず出題 意 図 を説 明 した うえで,問 題 に取
り組 ませ る よ うな手続 きが 要 る 一 一 出題 よ りも解 答 が 立 派 な ことは往 々 に し
て ある に して も。 、
ポル トガル の重 要人 物 を あげ よ と言わ れ た 日本人 は,ま ず ヴ ァシ ュコ ・ダ ・
ガマ をあ げ,少 し世 界史 を勉 強 を した受験 生 はエ ン リケ航 海王 子 の名 を あげ よ
うか。 フ ェル ナ ー ンオ ・マガ リャーーンエ シ ュ(マ ゼ ラ ン)に 至 って は スペ イ ン
に 奪 い去 られ か ね な い ほ どだ。 しか し,思 想 家,お ま け に 近 代 の とな る と
・… ・コ さて?
'そこで,一 人 だ けポル トガル の近 代 思想 家 をあ げ よ とい えば,こ の人 に止 め
一20一
-
を刺 す こ とにな る(ポ ル トガ ル版 ラ フカ デ ィオ ・ハ ー ンで,徳 島 で客死 した ヴ
ェンセ シ ュラ ウ ・モ ラエ シ ュは 日本 人 に比較 的知 られ て い るが,主 と して文学
者 だ)。
ヘ テ ロニ ム
「二 十 面相 」 フェル ナ ン ドゥ ・ペ ソア ー 「異 名 」 た ち
「仮 面 を取 ろ う と した とき/仮 面 は顔 に は りつ い て いた/仮 面 を取 っ て
鏡 を見 た とき/ぼ くはすで に老 けてい た」
(カムポ シュ 『煙草屋』,池 上訳,同 上)
不 思議 か つ幸 い な こ とに,フ ェル ナ ン ドゥ ・ペ ソアを と りあ げる とい う こ と
は同時 に数 人(数 は不特 定)の 思想 家 を論 ず る こ とにな るのだ。
と言 うの は,彼 は幾 つ も顔 を持 ってい るの だ。 いや,そ れ どころか フ ェル ナ
ン ドゥ ・ペ ソア とは幾人 か の人格 の総称 なの だ。 それ ぞれ の人 格 はそれ ぞれ の
経歴 を持 ち,生 年 月 日や ホ ロス コープ を持 つ(ペ ソアは神 秘家 だ った か ら,自
分 のは もち ろん,人 間 ばか りか 自分 の主催 す る文学雑 誌 や ポル トガル 国 の ホ ロ
スコ ープ まで作 った。彼 は晩 年 には心 霊術 に も凝 った りした た だ しそれ
よ そ お
も彼 の 「虚構 い」 で な い とは言 えない)。
彼 らは独 立 の人格 で それ ぞれ の生 活 を持 ち,そ れ ぞれ の文学 活 動 をす る詩人
た ちだ。彼 らは単 に独 立 で あ るばか りか,互 い に交遊 関 係 を持 ち,あ るい は師
弟 関係 を持 つ。 あ る者 は ブ ラジル へ移 住 し,あ るい はイギ リス に留学 し,あ る
者 は精 神 病 院 で死 ん だ。彼 らは それ ぞ れ もち ろん別 々 の名 前 を持 つ。 そ れ らヘ テ ロニ ム ヘ テ ロニ ム
は,「 異 名 」 と名 付 け られ た 例 えば,ほ とん どの 主要 な異 名 全 員 の 師 に
当た る人 物 は一 八 八 九年 に生 まれ た こ とにな ってい るアルベ ル トゥ ・カ エ イ ロ
とい う人 だ(一 九 一五 年 没 とい う こ と 「弟 子 」た ちが まだ文筆 を始 め るエル コプ ロプ リオ
前 だ)。 そ れ を 言 え ば,実 は フ ェル ナ ン ド ゥ ・ペ ソ ア 「自 身 」 が そ う し たヘ テ ロニ ム ヘ テ ロニ ム
異 名 た ち(異 名 を持 つ人 々)の 全部 で もあ り,ま た その一人 だ とい う言 い 方
一21一
-
も 成 り立 つ 。 つ ま り,彼 は 「一 」 に し て 「多 」 な の だ(も っ と も,主 要 なヘ テ ロニ ム
異 名 は彼 自身 を入 れ て四人 だが)。 奇 し くもペ ソア とはポル トガル 語 で仮 面 劇ペル ソナ
の仮 面 を意味 す る。ふ
「詩 と真 実」 につ いてのペ ソアの解答 は明瞭 だ。 彼 は偽 る(「 振 り」 をす る)。
よ そ お
「詩人 とは虚 構 う人 だ/そ の虚 構 い のあ ま りに完壁 であ るた め/現 実 に感
じる苦 痛 まで/苦 痛 であ るか の ごと く虚構 う」(池 上訳,同 上)
ヘテロニム プ ソ イ ド ニ ム ペ ンネ ム
異 名 と敢 えて呼んだのは,こ のように彼 らは単なる変名 ・偽名ないし筆 名
と呼んだのでは片づかない独立性 と発達を示すか らだ(彼 らはペソア自身 と同
時的に存在 して生長する一 作風 も幾つもの段階を示す)。ヘ テロ ニ ム
始 め か ら異 名 た ちが 存在 した訳 で はな く,初 期 の 頃 に は単 な る変 名 の よ う
な人 物 も存 在 した。 また極 く幼 い少 年期 か らこう した人格 の複 数化 の傾 向 はあ
った よ うだ(彼 自身 も これ を病 理的 現 象 と考 えてい るフ シが あ るが,異 論 もあ
る)。 六歳 の時 に既 に一 人 の架 空 の 人物 を造 りあげ,彼 自身 に当 て た手紙 を書
かせ て い る。
一人 の子供 が 牛 車 の玩 具 で遊 ん で い る 一 彼 は 「自分 が遊 ぶ の を感 じた/
そ して言 った 僕 は二人 だ!/遊 んで い るのが一人 いて,/そ して別 の一人
が居 て知 って い る,/一 人 が私 の遊 ぶ の を見 てい て,/も 一 人 が,見 て い
る私 を見 て い る こ とを。」(ペ ソア,一 九二七年)
こ こに は,す で に 自我 の中 の 自我 す ぐ後 で述 べ る 「ダ イモ ン」 と して
の カ ムポ シュの よ うな の芽 生 えが あ る。
幼 児性 はペ ソア の基本 的性 格 の一 つで もあ る よ うだ。実 際,彼 は子供 と戯 れ
るの が好 きだ った し,デ ィケ ン ズ を よ く読 ん だ の も これ と関係 が あ る とい う
(彼は南 ア時代以 来,欧 米 とポル トガルの文 学 に親 しんで いた。 ホイ ッ トマ ン,
ボー ドレール の影 響 も顕著 で あ る)。ヘ テ ロ ニ ム
だ が,そ う した傾 向 はあ った ものの・ 異 名 の 出 現 は唐 突 だ っ た・一 九一 四
一22一
-
年 四 月八 日,彼 は箪 笥 に寄 り掛 か って立 った ままで一 気 に カエ イ ロの作 品 で あ
る詩 の三 〇 編 余 を書 き上 げた 。彼 は 「師 」 の 到来 を知 っ た(尤 も,「 弟 子 」 の
レイ シュ の方 が 密 か に形成 され つ つ あ った の だが)。 そ して同 時 に も う一人 の
「弟 子 」 カ ム ポ シュ もその作 品 とと もに一 挙 に生 じた。ヘ テロニム ヘテロニ ム
あ る異 名 の一 人 は,そ の創 作活 動 で も う一人 の異 名 を生 みだ した の で はな
い か と疑 わ れ て い る。 また,実 は人 物 ばか りか,あ る時期 の文 学雑 誌 もそ う し
ヘ テロ ニ ム
た異 名 の ひ とつ で は ないか とい う観 察 もあ る。ヘテロニム ヘ テロニム エル ロプロプリオ
他 の異 名 た ち と異 名 ・ペ ソ ア 自 身 の関 係 は交遊 ・師 弟 関 係 に限 らず,例ヘ テロ ニ ム
えば ア ル ヴ ァ ロ ・ドゥ ・カ ム ポ シ ュ とい う異 名 はペ ソア に とっ て は個 人 的 ダ
イモ ン[良 心]に な って さ えい る。
一 九二 〇 年,精 神 的 に ボロボ ロにな っていた三 三歳 のペ ソア は突然 一一四歳 も
年 の違 う乙女 オ フ エ リア ・ケイ ロシ ュ との恋 に陥 る。 それ は三 月 に始 ま り一 一
月 に終 わ る(こ の頃 ペ ソア は精 神 病 院 へ の入 院 を考 えた ほ ど乱 れ て い た)。 こ
の恋 は,恐 ら く,彼 の母 へ の幼 児 的 なサ ウダ ー ドゥ(あ る種 の憧 れ 一 この
概 念 につ い て は後 述)の 故 に成 立 し,ま た その故 に こそ(こ の恋 は,九 年 を経
て再燃 したが)結 婚 まで至 らなか った もの だ。
そ もそ もペ ソア は人 で な くて愛 を愛 した の であ り,愛 の詩 は愛 の思想 を歌 う
もの なの だ
「私 は そなた を愛 す るよ り,そ なた へ の愛 を よ り愛 す る」(『35Sonnets』XII[)
「愛,是 本 質,是 精 華,/性,只 出於 偶 然/可 以 是 一 回事,/或 是 両 国事 毫 不相
干。/人 不是 禽 獣;/是 有 智 慧的 血 肉,儘 管 他也 有病,那 是有 的 時候。」[愛 こ
そ は本 質,性 は偶 有性,同 じで も異 な って もよい。 人 は動 物 で な く,知 性 を
備 えた 血 肉 だ ・ 一た だ し時 に は病 ん で い るが 。](『伽 素阿選集」,張 維民 編
選 ・翻課和註解,連 関文化學會,一 九八八年)
オ フ エ リア との恋 の成 り行 きに主 として ブ レー キ として効 いた のが ドゥ ・カ
ー23一
-
ム ポ シ ュで あ り(オ フ エ リア は彼 へ の反感 を隠 さな か った),実 際ペ ソア は恋
文 に彼 の指 示 を記 し(カ ムポ シュ自身 がオ フエ リアに奇怪 な手紙 を書 いて もい
る),ま た現 に逢 い引 きに カ ム ポ シ ュが 同行 す る とまで書 くこ とが あ った。 し
か し,当 然 なが らペ ソア の身 は一 つ だか ら実 際 には実現 し得 な いの は もち ろん
だ。
あ る場 合 に は,ペ ソア 自身 が 現 に友人 と会 って いて,自 分 は カムポ シュだ と
名 乗 っ てひ ん しゅ くを買 った りして い る。ヘ テ ロ ニム
もっ と も,ペ ソア を含 む これ ら異 名 た ち は一 つ の特性 を共 有 して い る。 そ
れ は全 員 がペ ソアの分身 だか ら(そ れ には違 いな いが)と い う よ りは,一 部 の
例 外 を除 い て,ペ ソア 自身 を含 め て,「 師」 た るカエ イロの弟 子 だか らだ。 そ
こで,そ の共 有 す る特 性 とは,彼 らが(ネ オ)パ ガ ニ ジモ[(新)異 教 主 義]
の信 奉 者 だ とい うこ とだ。
ポル トガル でパ ガニ ジモ を とる とい う こ とは,二 重 の意 味 が あ ろ う 一 こ
の有 数 の カ トリシ ジモの 国で,と 同時 に,底 流 にあ るケル トと異教 の濃 い伝 統
が あ る国 で は。
パ ガ ニ ジモ はニ ー チ ェ に連 な る反 キ リス ト教 で もあ るが,そ れ は同時 に特殊
ポル トガル で は反 カ トリシ ジモで もあ る。 これ は単 に宗教 的 な意味 が あ るだ け
で な く,反 「ロー マ 帝 国 」 の意 味 もあ る。 彼 らな い しペ ソア の念 頭 にあ るの
は,世 界 帝 国(第 五 帝 国)の 盟 主 としての ポル トガル とい う こ とだ。 これ につ
い て は後 述 す る。
詩人ペソア
芸 術 家 と して のペ ソア は,感 覚 主義,未 来 主義(フ トゥ リジモ),象 徴 主 義
な ど,一 般 にモ ダニ ジモの詩人 で あ り,こ の点 につ い てはポル トガル を代 表 す
る,.国 際 的 に認 知 された 前衛 詩人 の一 人 で あ る。 彼が参加 した初期 の文学運 動
の機 関誌 に 『オ ル フ ェウ』が あ るが,絵 画 の分野 で未来 主義 の一 分野(デ ロ一
-24一
-
二 一や クプカ)を アポ リネ ールが 「オ ル フェウイ スム」 と呼 んだ の と符 合 す る
の は偶 然 だ ろ うか?
た だ,彼 が国外 に も広 く認知 され,高 く評 価 され る ようにな った の は,彼 の
死 後 の ことで あ った。 初期 の頃 には英語 の作品 を公表 して いたが,次 第 にナ シ
オ ナ リジモ に 目覚 め て ポル トガル 語 の作 品 に主体 が 移 って い った。 この た め
に,海 外 で の作 品 の周 知 が遅 れ た こ とは否 めな いだ ろ う。 「小 国 」の悲 哀 が こ
こに もあ る 外 な らぬ,そ の分 野(ポ ル トガ ル語)で 世界 制 覇 を夢 見 た ペ
ソア に とって は皮 肉 な結 果 で もあ った。
フ ェル ナ ン ドゥ ・ペ ソア は何 よ り詩 人 で あ る。 た だ し,他 の詩人 と異 な り,
思考 と感 覚 の比 率 が 逆転 して いて,感 覚 が理知 を通 して現 れ る 感 情 が 思
考す る。とど
「止 まれ,私 の心 臓 よ!/考 え る こ とを止 め よ,お 前1考 え る こ とは頭 に任
せ ろ!」
「私 の感情 は/私 の想 像 か ら こぼれ落 ち る/燃 殻 の灰。/そ して私 は この灰 を落
とす/理 知 の灰 皿 に」
この知 性 の優 越 が,ペ ソア を詩人 で あ りか つ思想 家で もあ らしめ てい る要 因
の一 つだ ろ う。実 際彼 の詩 は非 常 に機 知 に富 んだ理 に満 ちて い る。
彼 は思考 の重圧 に坤吟 した人 で あ ったが,そ こか らの解放(例 えば素 朴 な農
夫 にな る こ と)も 思考 に よ って(素 朴 に なった こ とを意識 しつ つ)成 し遂 げ る
とい う不 可能 を夢 見 て嘆 いた
「あわれ 麦刈 る女 はひ と りうた う
「あ あ うた え うた え た だ うた え
ぼ くのな かの感 覚 す る もの が い ま思 考 す る/ぼ くの心 に注 ぎ こめ
た よ りな げ に高 く低 く流 れ るお まえの声 を
ああ ぼ くであ るま ま お ま えにな るこ とが で きた な ら
一25一
-
陽気 で な に もの も意 識 しな いお まえの心 をわ が もの と し
そ う した 自分 を意識 で きた な ら/空 よ 野 よ うた よ」
(ペソア 『あわれ 麦刈 る女は』,池 上訳,同 上書,強 調引用者)
ヘテロニム ヘ テロニム
上述 の,ほ とん どの主要 な異 名 全 員 の 師 に当 た る人 で あ る異 名 カエ イ ロ と
い う人物 は,そ う した不 可能 を可能 に し,ペ ソアの知 らな い田舎 に住 み,自 然
の表 面 を 一 一 表 面 の深 淵 を 生 きた(表 面 の強調 に私 はニ ーチ ェの影 響 を
見 る)。
「わ た し は羊 飼/羊 の群 は私 の 思 考 た ち
そ して 私 の 思 考 た ち は す べ て わ た しの感 覚 た ち
わ た し は 考 え る 眼 と耳 で/手 と足 で/そ して鼻 と口 で 」
(カ エ イ ロ 『羊飼(OGzイardadordeRebanhos)』IX,拙 訳,
[参 考]池 上訳,同 上 書)
カエ イ ロ はいわ ばペ ソアの 反対 の理 想 を表現 した人 物 だ。 ペ ソア に とって は
逆 に 「私 の感 覚 た ちはす べ てわ た しの思考 た ち」 だ ったの だ。
'カエ イ ロは また,ペ ソア(彼 は都 市 リジボ アのみ を世 界 とす る)に とっ て は
不 可 能 で あ った 田舎 の生 活着 で あ った。
「テ ジ ョ川 は私 の村 を通 っ て流れ る川 よ り美 しい。
テ ジ ョ川 はけれ ど私 の村 を通 って流れ る川 よ り美 し くな い,/な ぜ な ら
テジ ョ川 は私 の村 を通 って流 れ る川 で はな いか らだ。
テ ジ ョ川 に は大 きな船 が あ る。
さ らに そ こで は/何 を見 て も,そ こには無 い もの を見 る人 々 に とって は,ゆ コ
船 たちの記憶 も航 きかう。
-26一
-
「テ ジ ョ川 はスペ イ ン よ り下 る。い
テ ジ ョ川 はそ して ポ ル トガ ル で 海 に入 る。/だ れ で もそれ を知 っ て い る。
で も私 の 村 の川 が何 で あ るか,/そ して そ れ は ど こへ向 か うか,
そ して ど こか ら来 るか,/知 っ て る人 は ほ ん の少 し。
だ か ら,よ り少 い人 々 に属 す るか ら,
私 の村 の川 は よ り自 由 で,よ り大 きい。
テ ジ ョ川 か らは世 界 に行 け る。
テ ジ ョ川 の向 こ うに は ア メ リカが/そ して それ を発 見 した人 々 の幸 せ が あ る。
けれ ど,だ れ 一 人,一 度 で も
私 の村 の 川 の 向 こ う に あ る もの を/考 え た者 はい な い。
私の村の川 は何かを考 え込 ませた りす ることは決 してない。ぽ とり ほ とり
そ の 辺 に 立 つ 者 は た だ そ の辺 に 立 っ て い る だ け だ 。」
(カ エ イ ロ 『OGetardadOideRebanhos』XX,拙 訳)
思想家ペソア
はた して詩人は思想家だろうか ~
思想の無い文学者 はあるまい。 しか し,大 国には独立の,「 専門の」思想家
を抱えることができる。だが,ポ ル トガルのようないろいろの点で規模の小さ
な国は,独 立の思想家 を立てる程 の言わば 「余裕」 は無い。 もっとも,近 年の
傾向の一つだが,「 素人」哲学者に見 るべきものが多いということはある。
ところで,そ もそも過去の思想家に何 を期待できるのか?昔 のある思想家
を現在取 り上 げて論ずる意味 は何か ~ 現代の観点か らは無意味で も,単 に歴
史上その人物がいて,少 な くともその時代には重要な意味を持 っていた(と 思
27一
-
わ れ てい た)と い うこ とで十 分 で はな い か?し か しそ の場 合 に も,そ の 思想
家 の肯 定 ・否 定 ・中立 の評 価 は現 在 の立場 か らな され る以外 に ない。
ペ ソア の場 合 は どうか?特 に現代 の 日本 か ら見 て?
思想 家 としてのペ ソア は例 えば カ ン ト,ヘ ー ゲル タイ プの哲学 者 で は な く,
む しろ問題 関 心 の範 囲 や ス タ イル か ら言 って もパ レー ト,あ るい はまた ニ ー チ
ェ,シ ョーペ ンハ ウエ ル な どの系 統 に属 す るだ ろ う。
大統領一王
事 実,彼 は民 主主義 者 で はな い。 む しろ貴 族 主義 的 共和 主義 者 で(彼 は 自分
に貴族 とユダ ヤ の血 を主 張 して い る 一一 後 者 は彼 の メ シアニ ジモ に関わ る),
君主 主義 者 で,哲 人王 を理 想 とした(実 際 にそれ ら しい文 人大統 領 一一一 「大 統
領 一王 」 シ ドニ オ ・パ イ シュ ー一 が誕 生 し,彼 に共 鳴 したペ ソア は機 関誌 まで
出 して支援 す るが,彼 はす ぐに暗 殺 され て しま う)。 また,ペ ソア は軍 事 独裁
を支持 す る(ポ ル トガル にのみ適 用範 囲 を限 ったが)フ ァシシ タで さ えあ った
(ただ し 「純思想 的 」 で はあ った が 一一 事 実彼 は,軍 事 独裁 の 実際 に仰天 し,
サ ラザ ール 主 義 とい う実 際 の 「フ ァシ ジ モ」 を見 て怯 み,殆 ど自説 を撤 回 し
た)。
ペ ソア はニー チ ェや シ ョーペ ンハ ウエル に も少 なか らず影 響 を受 けた(個 人
的経 歴 で も,ニ ー チ ェ との親 近 性 は大 きい 例 えば,幼 児 にお け る父 との
死別,女 性 関 係 で の不首 尾)。 ペ ソアの上 述 の思想 に もそ の影 響 が現 れ て い る
「超 人 」 と して の 哲人 王 だ(も っ と も,ペ ソア は次第 に 「超 一文 学 」 に近
づ いて行 った が)。 しか し,ペ ソア に つ いて は,こ の側 面 に は ポル トガ ル人 と
して の特 殊 性 が切 り離 せ な い もの が あ る。
そ もそ もペ ソア には い な,後 述 の ように,ポ ル トガル 人全体 に プ
ロ フ ェテ ィジモ(預 言者 信 仰)が あ る。 しか もそれ は特 に 「セバ ス テ ィアニ ジ
モ」.とい う形 を採 る。
一28-一
-
セバ ス テ イア ニ ジ モ
ポ ル トガ ル王 ドム ・セバ ス テ ィア ー ンオ は,ポ ル トガル 王 国 の伝 統 に従 い,
モ ロ ッコ征 服 の野 望 に燃 えて一 五七 八 年,勝 ち 目 の無 い遠 征 に乗 り出 して,ア
ル カ ー セ ル ・ク ィ ビー ル の戦 いで大 敗 を喫 した後,忽 然 と消 え,遺 体 も確 認 出
来 な か った。 この史 実 と,す で に出 来 て い た異端 的 宗 教 の伝 説 が結 合 して 「セ
バ ス テ ィア ニ ジ モ」 つ ま り ドム ・セ バ ス テ ィア ー ンオ が再 来 して 国 を救 う とい
う信 仰 に結 晶 した。 これ は,ペ ソア に限 らず,ポ ル トガ ル人 に共 通 の神 秘 主 義
の現 れ で もあ る。
ペ ソア は さ らに これ に独 特 の 理 論 付 け をす る。 そ れ は 「第 五 帝 国 」 の 思 想
だ。 「帝 国 」 とは必 ず し もホ ブ ソ ンー レー ニ ン的 意 味 に解 す る必 要 は無 い が,
当時 まで の 歴 史 的 な世 界 支配 体 制 とい う意 味 は あ る。
そ れ らの 過 去 の 帝 国 と は ギ リシ ャ,ロ ー マ,キ リス ト教(こ の 両 者 は ロ ー
マ ・カ トリシ ジモ の 支 配 とし て残 存 す る),イ ギ リスの 四 帝 国 だ とい う。 そ し
て,ポ ル トガル が盟 主 とな るべ きは 「第 五 帝 国 」 だ。 そ の理 念 は,人 間 精神 を
司 る二 つ の 力 つ ま り,知 性 的,理 知 的 な もの と,直 観 的,神 秘 的 な もの
の 統 合 だ。 この よ うな 世 界 的 「文 治 」帝 国,文 化 の,言 語 の 帝 国 の 主 宰
者 と して ポ ル トガ ル が,そ の 首 都 とし て リ ジ ボ ア が,擬 せ られ て い る。 そ し
て,フ ェル ナ ン ドゥ ・ペ ソア は この 帝 国 の 予 言 者 として,一 七 世 紀 のA・ ヴ ィ
エ イ ラ神 父 あ げ るが,他 方 で は 自 らを その 予 言 者 に擬 した フ シ もあ る。
思 想 家 と して の詩 人 ・文学 者 は一 般 に その(「 理 想 主義 的」)極 端 さな い しラ
デ ィ カル な 理想 主 義 に価 値 が あ るの で あ っ て,彼 な い し彼 女 に現 実 政 治 の処 方
を期 待 す る者 は あ る まい 。 実 際 の政 治 に つ い て は,ニ ー チ ェ もペ ソア も結 局 は
見 当違 いだ った の で あ って,現 実 の 解 決 は結 局 ドイ ツ もロシ ア もポル トガ ル も
(EUの 中 で生 活 も政 治 も安 定 を増 して きて い る よ うに見 え る),議 会 的 民 主 主
義 プ ラス 「資 本 主 義 」 的 市 場 社 会 とい う極 め て散 文 的 な解 決 が 得 られ て い る
一29一
-
し,平 均 的 庶 民 に とっ て は そ れ以 外 の 解 決 は余 りに過 酷 で あ った り,悲 惨 で あ
っ た りす るだ ろ う。 そ れ は,ソ ア ー レ シ ュ ・ドシ ュ ・レ イ シ ュ ー 一 も う一 人
の翼 翼茗 一 に とって と同 じ く,政 治理 念 も,綱 領 で な く,当 代 の諸 事物 の現
状 の否 定 とい う意義 を持 つ とい う こ となのだ。
サ ウ ダー ドゥ
ポ ル トガ ル 語 に 「サ ウ ダ ー ド ゥ(saudade)」 とい う言 葉 が あ る 一 これ は,
ソリタ リイ
英語 の孤 独 と語 源 を同 じ くす るが(soedade・"only-ty"),詳 しい成立 は不 明 の
語 だ 。 これ が民 族歌 謡 フ ァ ドに代 表 され るポル トガル 人 の心情 の基礎 に あ る と
い う もの で,こ れ は広 くケル ト人,ケ ル ト文 化 に共 通 の,ほ とん ど実存 的 な感
情 で あ る とか,あ るい は,民 族 大移 動 の波 に とって は言 わ ば 「筋筋 」 だ った ガ
リシア(ポ ル トガル北部 と境 を接 す るスペ イ ン領 で,サ ンチ ャ ゴ ・デ ・コ ンポ
ス テ ラの聖地 を抱 く)お よび ポル トガル にだ け特 有 な心情 で はな いか とも,あ
るい は特 に ポル トガル に強力 に残存 した ものか,等 々 と考 察 され るが,い ずれ
に して も,語 彙 として は この両地 域 に しか存在 しない。 それ で も,前 者 は比 較
的 内陸 的 だが,ポ ル トガル は,欧 州最 西端 の 「地 の果 て」 で あ り,海 外へ の雄
飛 は,単 な る経 済 的切 迫 で は説 明 の着 か な い情 熱 の産 物 だ と言 わ れ る。 それ
が,サ ウ ダー ドゥに発 す る遠 方 ・未 知 への憧 れ だ。 エ ン リケ航海 王子 に指 導 さ
れ,中 で もヴ ァシ ュコ ・ダ ・ガ マ に率 い られ たポル トガル人 に よる世 界 に先 駆
けた大航 海 時代 の幕 開 け を叙 事詩 と して謳 い あ げた のが,ポ ル トガ ルの シ ェイ
クス ピア た る いや,ポ ル トガル人 に とって は まさ にそれ以 上 の意 味 を帰
されて い る 一一 ル ー イ シ ュ ・ドゥ ・カモー ンエ シ ュだ。
ペ ソアは,こ の カモー ンエ シ ュの叙述 した物 理 的遠 征 を精 神 世界 で再 度,よ
り上 の レベル で実 現 す る こ と,つ ま り,物 理 的空 間 内 に は存在 しない新 イ ン ド
を求 めて,「 夢 と同 じ素材 で 出来 た船 」 に乗 って これ に到達 して スー プ ラ[超]
ポ ル トガル を建 設 す る こ とを夢 み,こ の運 動 を 〈スー プ ラーカモ ー ンエ シ ュ〉
一30一
-
と呼 んだ。
この新 帝 国 は存 在 しな いだ け にそれ だ け素 晴 ら しい もので あ り(そ れが サ ウ
ダー ドゥだ),そ れ に比 べれ ば,一 六 世紀 の達 成 は卑 しい地 上 的 な前座 の茶 番
に過 ぎない とさ え思 わ れ る。
実 は この カ モー ンエ シ ュな る作家 自身 が謎 の 冒険 児 で あ り,そ の没地 も末期
も知 られ て い ない。 ダ ・ガ マの遠征 を祈 願 して船隊 出航 地 に建 て られ た,ベ レ
ム の塔 近 くの ジ ェ ロニモ シュ修 道 院 には,ダ ・ガ マ の枢 と並 ん でカ モー ンエ シ
か ら パ ンテア ンオ
ユの空 の棺 が祀 られ て い る。他 方,奇 し くも国 家 功 労 者 を祀 る万 禅 堂 に は,
ス プラ
超 カ モ ー ンエ シ ュ を 目指 した フ ェ ル ナ ン ド ゥ ・ペ ソ ア と共 に ドム ・セ バ ス テ
ィア ー ン オ の 棺 が 祀 られ て い る の だ(当 然,空 の棺 だ)。
都市案内を書いた思想家
私 が この原稿 を書 こ う と して,一 昨 年 夏,「 取 材 」 のた め にポル トガ ル を訪
れ,リ ジボア市 内 の本 屋 を漁 って い る と,何 と,ち ょう どその年,リ ジボア市
役所 出版 局 か ら,『 リジボ ア1旅 行 者 の見 るべ き もの』 とい うペ ソアの著 作 が
英一ポ語 対訳 で刊 行 され てい た(企 画 は生 誕 一一〇 〇周 年 の 一 九八 八 年 に向 け ら
れ て い たが実 現 は延 び た の だ。 ペ ソアの遺 稿 彼 は原 稿 を伝 説 的 な 「つづ
ら」 に入 れ て い たが,今 はす べ て 国立 図 書館 に収 め られ,未 発表作 品の公刊 が
続 い てい る の整 理 過程 で完 成 原稿 と して発 見 された)。
これ は,恐 ら くペ ソ ア が 「身過 ぎ世 過 ぎ」 の た め に 書 い た もの で あ ろ う
と私 も考 えた 。 とい うの も,彼 の晩 年 は,経 済 的 にか な り窮 乏 して いた
し(〈 ペ ソア〉 とい う 自分 と同 名 の食 堂 で友 人 か ら借 金 して昼食 を とった と日
記 に記 して あ る),か つ文 学 的革新 の志 向 と比 しての時 間 的切 迫,世 人 の不理
解,等 々 で不 遇 だ った。 色 々 な会社 で事 務 員 として働 いた(恋 人 オ フェー リア
は この事務 所 にアル バ イ トと して や って きた良 家 の お嬢 さ んだ った)。 会 計 実
務 の本 も書 い てい る し(南 ア で は商 業 学校 を出 て い る),出 版 を は じめ幾 つか
一31一
-
の事 業 に も手 を染 めて は速 やか に失敗 してい る。他 方 で は,文 学 のた め の時 間
を確保 す るた め に有利 な職(例 えば大学講 師)を 諦 めた こ ともあ る。
この本 は,こ ん な記述 で始 まる
船 が大 西 洋 か らテ ジ ョ川 を遡 りマ ヌエ リノ[ド ム ・マ ヌ エル1世 朝 風]様 式
と呼 ばれ る白亜 の要塞 監獄 ベ レムの塔 を過 ぎ,リ ジボアの港 に入 る。 こ こか ら
観光案 内風 に首都 リジボ アの解説 が続 く一 一 「.ヒ陸 は迅速 かつ容易 で,河 岸 の
交通機 関が豊 富 にあ る地 点 だ。馬 車,自 動車,電 車 さえ もが異郷 の旅客 た ちを
数分 で都 心 へ運 んで行 く。 埠頭 で はあ らゆ る設備 が整 い,係 官 た ち は例 外 な く
丁重 で,ど んな要 望 に も応 えるべ く待 機 してい る。 … …
「今 度 は リジボ ア最 大 の 広場,コ メル シウ広場[リ ジボ アの正 面 玄 関 に当た
る埠頭 の広場]… … に着 く。 これ は… …世 界 で も最大級 の広場 だ。 ……
ロ ッシウ駅'「 正 面 は 〈マ ヌエ リノ〉様 式 で,豪 勢 にdentel6e[鋸 歯 状]
になっ てい て,窓 の つ いた大 きな馬蹄 形 の扉が 幾 つ もあ る。頂 上部 の時計 は電
気時計 で,内 部 の時 計 と連 動 してい る。 ……エ レベ ー ターが ……最 上 階[駅 は
山 の斜 面 に沿 っ て い て,四 階 に相 当]の ホ ー ム の レベ ル まで 連 れ て い く。
……」
これ は普 通 の観 光案 内で もあ るが(記 述 は建 物 ・ス ポ ッ ト毎 に詳細 を極 め る
序 で に言 えば,こ の一 九 二五 年 前 後 に成 った 案 内書 は,大 部 分 が 現在 も
有用 だ),し か も無 邪 気 な,な い しは悪 くす る と鼻 持 ち な らな いお 国 自慢 と,
少 しの誇 大 広告 と背 伸 び が あ る とさ え感 じ られ よ う。
そ うい う訳 で,こ れ は彼 の資金稼 ぎだ と考 える向 きが あるか も知 れ ないが,
ペ ソア は大 真面 目だ し,こ れ は遠 大 な 「愛 国 的 プ ロジ ェク ト」 の重 要 な一 環 な
のだ(完 成稿 が 出版 され ず にあ った の は その傍 証 に な る 出版 時期 を見計
らってい たの だ)。
以下 で述 べ る よ うに,幼 ~ 青年期 を異郷南 ア フ リカで過 ごしたペ ソア は,そ
こで 人 々が ポ ル トガ ル に つ い て 何 も知 ら な い 外 な ら ぬ あ の 希 望 峰カボ ドウ ボ ア エシ ュペ ラ ンサ
[良.き 希 望 の 岬]の 地 を 「発 見 」 した の が ポル トガ ル だ とい う こ とさ え知
一32一
-
らない 一 の を,屈 辱 を もっ て痛感 した。
一 〇 年後 帰 国 して 見て も,ポ ル トガ ル の 日陰 の身 は変 わ らない。彼 はボル ト
デカテ ゴリザサンオ ●シヴィリザ シオナル デ カ テ ゴ リ ザ サ ン オ ・ エ ウ ロ ペ ァ
ガ ル の 「文 明 的 脱 範 疇 化 」,「ヨー ロ ッパ 的脱 範 疇化 」,つ ま リポル トガ ル
が ヨー ロ ッパ 文明 の範 鴫 か ら脱落 す る危 機 と捉 えた の だ この 「航 海 者 と
帝 国創 出者 」 の 国,未 来 の 「第 五 帝 国」 の盟 主が 。 この ポル トガ ル の真 の価 値
と存 在 を世 界 に広 め るべ き 〈コ スモ ポ リタ ノーナ シオ ナル〉 な愛 国 的 企 画 をペ
ソア は 『AllabOtttPortZtgal[ポ ル トガル の総 て]』 と して 考 えて い た が,こ
の都市 案 内 書 はその重 要 部分 を成 す はず だ ったの だ。
ポル トガ ル の各都 市 に は りベ ル ダー デ ィ[解 放]通 りが あ るが,リ ジ ボア の
それ は,上 述 の ロ ッシ ウ駅 の近 くの 「再 独 立」 記 念碑 か ら北 方へ延 びた,フ ラ
ンス の シ ャンゼ リゼ の向 こうを張 った イ(規模 はず っ と小 さ いが)見 事 な大 通 り
だ。 その突 き当た りに は獅 子 を足元 に従 えた ボ ムバ ル侯 の大 記念碑 が あ り,そ
の背後 にエ ドゥアル ドゥVll世公 園 が あ る。 ペ ソアの案 内書 はボムバ ル に つい て
は一 言 も言 わ な い が,公 園 に つ い て は,こ こに上 述 の 「大 統 領 一王 」 シ ドニ
オ ・パ イ シュが リジ ボア守 備 隊 の若干 の連 隊 と ともに 自 ら暫壕 にた て籠 もって
「『民 主』 政 府 」 を倒 した こ とが特 筆 して あ る。 ここは こう した拠 点 に向 いた 管
制 高地 なの だ。
いず れ に して も,こ こに は 「小 国」 の悲 哀,し か もか つ て栄光 を見 て しまっ
た しか も余 りに早 く,余 りに昔 だ った の で,そ の思 い 出 さえ も既 に慰 め
にな らない よ うな 国 の焦 りの よ うな もの が あ るだ ろ う。
「私 が属 す るの は あの類 の ポル トガ ル人,/発 見 され た イ ン ドその もの で
あ った,そ の後 で/職 に もあ りつ け な い で い る/そ うい うポル トガル人 だ」
(カム ポ シ ュ)。サ グ レ シ ュ
こ こか ら,ま た新 た な 「聖 な る岬 」 か ら船 出 し,「 絶 対 の 海 」 を越 えて超 時
空 間 に新 た な イ ン ドを発 見 す る とい う 「第五 帝 国」 の夢 想 も生 まれ る。あ くが いつ
この 「イ ン ド」 は心 の 中 に しか ない。 だが,憧 れ 出 るのが サ ウダー ドゥだ。
それ は,〈(純 粋 な)遠 方 〉,確 か さ よ りも 〈(不確 かな/抽 象 の)距 離 〉 〈外 部 〉
-33一
-
〈不 確定 な もの〉 〈彼 方(へ の熱 病)〉 だ。
「それ は それ だ け善 い こ とだ,霧 に包 まれ た とき/ド ム ・セ バ ス テ ィア ー ンオ
を待 ち望 むの は/本 当 に来 るか来 ない か は別 に して!」
確 か に これ は 〈狂 気〉 だが,狂 気 は 〈偉 大 さ〉 を生 み 〈英雄 〉 を生 む。
生い立ちと最期
フェル ナ ン ドゥ ・ペ ソアの 父 は美術 批評 家 だ った が(こ の血 筋 ない し環境 が
彼 の資 質 に現 れ た の だ ろ う),フ ェル ナ ン ドゥは五 歳 の と き父 と死 別 し,二 年
後,母 は再婚 した。 義 父 の海 軍 大佐 はポル トガル領事 として南 ア フ リカの ダ ー
バ ンに赴 任 して いたが,母 に連 れ られ てか の地 に渡 った八歳 の フ ェル ナ ン ドゥ
は小学 校 か ら現 地 の高校(こ こで作 文 もち ろん英 語 の で一 等 賞 を得
る),そ して商 業 学 校 に進 む(こ こで ケー プ大 学 入 学 試 験 で ヴ ィク トリア女 王
賞 を受 賞 す る 大 学 に は行 か な か っ た が,一 部,該 当 コー ス を取 っ て い
た)。
後 に は両 親 と分 か れ て単独 で ポル トガル に帰 国 した。 ず っ と後 に,再 び夫 に
死 別 して帰 国 す る老 いた母 と再 会 して リジボア の外 れ に同居 し(母 は五年 後 死
去),終 生 そ こに定住 す る こ とに な る。
彼 は初 め に英語 教育 を受 けたわ けだが,上 述 の よう に英語 は堪 能 で,詩 作 は
英語 お よび ポル トガル語 で したが(最 初 の詩 は八 歳 の時 のポル トガ ル語 の 『愛
す る母 さん』 だ),後 に はナ シオ ナ リジモの情 か らポル トガ ル語 に重 点 が移 る。
私 には判 断の しよ う もな いが,彼 の ポル トガ ル語 は完壁 で はな か った と言わ
れ るが(語 法 の誤 りも散 見 され る し,か な り強 い造語 癖 が あ る),そ の こ と と
彼 の理屈 の勝 った叙 情 の詩 とが微 妙 に関 連 して い る とい う。
・英 語 は言語 で あ る とと もに文化 で あ るか ら,彼 はイ ギ リス文化 に触 れ て,ラ
ー34一
-
テ ン的,フ ラ ンス的 な 「悪 しき文化 」 か ら 「内 に向 か って解放 され た」 と述 べ
て い る。
ペ ソアの評 価 は生 前 よ りは彼 の死 後 高 まった。 フ トゥ リジモ の詩 人 と して
は,フ ラ ンスの アポ リネー ル,ロ シアのマ ヤ コフス キー と並 ぶ者 であ り,ラ テ
ン文 化 圏 で はスペ イ ンよ りも先 ん じていた。 に もかか わ らず評 価 が遅 れ たが,
この点 につ いて は,ポ ル トガル語 に よる創作 とい うハ ンデ ィキ ャ ップ はあ った
だ ろ う。 「コ スモ ポ リタ ノ ・ナ シオ ナ リジモ」 を標 榜 した彼 に とって はい さ さ
か皮 肉 と悲 哀 を感 じさせ る結 果 か もしれ な い。
*******
一 九 三 五 年(五 三 歳)一 一 月 二 九 日,つ ま り死 の 前 日,肝 臓 を患 っ て入 院 中
の ベ ッ ドで紙 と鉛 筆 を請 うて,英 語 で こ う書 い た 「Iknownotwhat
tomorrowwillbring[llE日 の 日の もた らす もの を余 は知 らず]」。
翌 日,夜 八 時 頃,そ の最 期 は,ゲ ー テ に似 な いで もな いが 一 「眼 鏡
を下 さい」 と眩 いて視 力 が絶 え,絶 命 した。
(なが お ・しろ う 経 営学部 教授)
一35一
Related Documents