臨床病態学 要点整理ノート 1 臨床病態学 要点整理ノート 目次 1. 肥満・メタボリックシンドローム 2 2. 糖尿病 9 3. 脂質異常症 24 4. 高尿酸血症・痛風 33 5. 先天性代謝異常症 37 6. 胃腸疾患 40 7. 肝胆膵疾患 51 8. 高血圧症 61 9. 動脈硬化症・心不全 68 10. 腎疾患 73 11. 内分泌疾患 82 12. 精神・神経疾患 87 13. 呼吸器疾患 94 14. 血液疾患 98 15. 運動器疾患 103 16. 感染症 108 17. 免疫・アレルギー疾患 111 18. 悪性腫瘍 117 19. 老年症候群 121 2019.9.13 改訂

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

臨床病態学 要点整理ノート
1
臨床病態学 要点整理ノート
目次
1. 肥満・メタボリックシンドローム 2
2. 糖尿病 9
3. 脂質異常症 24
4. 高尿酸血症・痛風 33
5. 先天性代謝異常症 37
6. 胃腸疾患 40
7. 肝胆膵疾患 51
8. 高血圧症 61
9. 動脈硬化症・心不全 68
10. 腎疾患 73
11. 内分泌疾患 82
12. 精神・神経疾患 87
13. 呼吸器疾患 94
14. 血液疾患 98
15. 運動器疾患 103
16. 感染症 108
17. 免疫・アレルギー疾患 111
18. 悪性腫瘍 117
19. 老年症候群 121
2019.9.13 改訂

臨床病態学 要点整理ノート
2
1.肥満・メタボリックシンドローム
1.病態
(1)定義
・肥満(obesity)とは、体に占める脂肪組織が過剰に蓄積した状態をいう。
・脂肪細胞は、細胞内にトリグリセリド(中性脂肪)を蓄積する。
・脂肪細胞の数は乳幼児、思春期に増加する。(脂肪細胞数増加型肥満)
・成人の肥満では、脂肪細胞が肥大する。(脂肪細胞肥大型肥満)
・成人の肥満は、減量しても脂肪細胞の数は減少しない。
・成人であっても、脂肪細胞が肥大すると細胞分裂して細胞数が増えるといわれており、リバウンドを
繰り返すと、成人であっても脂肪細胞数が増加するので、やせにくい体質になる可能性がある。
(2)成因
1)過剰なエネルギー摂取
・消費エネルギーに対して摂取エネルギーが大きいとき、体内に過剰エネルギーが生じる。
・過剰エネルギーは、脂肪組織にトリグリセリドとして蓄積される。(エネルギー保存の法則)
・体脂肪 1 ㎏には 7,000 ㎉のエネルギーが蓄えられている。
・1 年間で 5 ㎏の体重増加(脂肪組織の増加)があったとすると、1 年間で 5×7,000=35,000 ㎉のエネ
ルギーの過剰摂取があったことになる。
・これを 1 日あたりに換算すると、96 ㎉の過剰(35,000÷365=96 ㎉)になる。
・1 日の摂取エネルギーを 2,000㎉とすると、わずか 4.8%(96 ㎉)のエネルギー過剰が 1年間で 5 ㎏
の体重増加につながることになる。(実際は、摂取エネルギーや体重の変化に伴って消費エネルギー
も変化するので、このような単純な計算どおりにはいかない)
2)摂取エネルギーが消費エネルギーを上回る要因
・加齢に伴い、基礎代謝量・エネルギー消費量は減少する
・若年期の食事の量のまま中年になると、いわゆる「中年ぶとり」になる。
・加齢とともに運動不足が加わると、さらに肥満が加速する。
・エネルギー消費量には、個人差がある
・現体重を維持する摂取エネルギーとして 30㎉/㎏/日がよく使われるが、体重あたり 30㎉はあくまで
も平均値であり、個人差は±20%以上ある。
・個人差には遺伝因子、環境因子(運動不足など)が関与する。
3)症候性肥満
視床下部性肥満 ・脳腫瘍、炎症などによる食欲中枢の障害
内分泌性肥満
・クッシング症候群(副腎皮質ホルモンの過剰産生、中心性肥満)
・インスリノーマ(膵β細胞の腫瘍、低血糖発作)
・甲状腺機能低下症(甲状腺ホルモンの不足、粘液水腫)
肥満を伴う
遺伝性症候群
ブレイダー・ウィリー症候群(肥満、低身長、停留睾丸、知能低下、筋緊張低下)
バーデッド・ビードル症候群(肥満、網膜色素変性、知能障害、性器発育不全、
多指症、家族性)
薬剤性肥満 向精神薬、アルコール、副腎皮質ホルモンなど

臨床病態学 要点整理ノート
3
(3)食欲と熱産生の調節
1)ホメオスタティック・モデル
2)レプチン(Leptin、Leptos=やせている、ギリシャ語)の発見(1994)
・脂肪細胞から分泌されるアディポサイトカイン(adipocytokine)の 1種である。
・脂肪組織の量に比例して、分泌量が増加する。
・視床下部において NPY(neuropeptide Y)の合成・分泌を抑制することにより食欲を抑制する。
・代謝を亢進させ、エネルギー消費を増加させる。
・レプチン欠損による肥満は、まれである。
・肥満者の多くは、レプチン抵抗性(レプチンの分泌が増えても食欲が抑制されない)がある。
(4)肥満による健康障害(肥満症)(日本肥満学会、肥満診断基準 2011)
・肥満に起因する健康障害(11種類)を合併しているか、あるいは将来合併が予測される場合で、脂肪
組織の減量を必要とする病態を肥満症という。
・肥満者では、生活習慣病罹患の相対危険度は非肥満者に対し約 2倍である。
1)脂肪細胞の質的異常による健康障害(9種類)
・耐糖能異常/2型糖尿病
・脂質異常症
・高血圧
・高尿酸血症・痛風
・冠動脈疾患(心筋梗塞、狭心症)
・脳梗塞(脳血栓症、一過性脳虚血発作)
・脂肪肝(非アルコール性脂肪性肝疾患)
NAFLD: non-alcoholic fatty liver disease、NASH: non-alcoholic steatohepatitis
・月経異常・妊娠合併症(妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、難産)
・肥満関連腎臓病
2)脂肪細胞の量的異常により健康障害(2種類)
・睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群(睡眠時の無呼吸発作による睡眠障害で、日中傾眠、チ
アノーゼ、痙攣、多血症、右室肥大、肥満を認める)
・整形外科的疾患(変形性関節症(膝、股関節)、変形性脊椎症、腰痛症)
3)肥満に関連する悪性腫瘍(4種類)
・胆道癌、大腸癌、乳癌、子宮内膜癌
(5)アディポサイトカイン(adipocytokines)
・脂肪組織から分泌されるサイトカインをアディポサイトカインという。
1)肥満で分泌が増加するアディポサイトカイン
腫瘍壊死因子
(TNF-α, tumor necrosis factor-α)
・炎症性サイトカインの一種
・インスリン抵抗性を起こす。
レプチン(leptin) ・交感神経緊張させ、高血圧を起こす。
アンギオテンシノーゲン(angiotensinogen) ・高血圧を起こす。

臨床病態学 要点整理ノート
4
PAI-1(plasminogen activator inhibitor-1) ・血栓形成を促進する。
レジスチン(resistin) ・脂肪組織に侵入したマクロファージから分泌
・インスリン抵抗性を起こす。
2)肥満で分泌が減少するアディポサイトカイン
アディポネクチン(adiponectin) ・動脈硬化抑制作用
・インスリン抵抗性改善作用
(7)インスリン抵抗性(insulin resistance)と死の四重奏(deadly quartet)
・動脈硬化症の危険因子である肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧が重積して出現する。
・心筋梗塞や脳卒中による死亡の危険が相乗的に高くなることを死の四重奏という。
・肥満は、糖尿病、高脂血症、高血圧などの生活習慣病を引き起こす病態の上流に存在する。
・肥満がこれらの生活習慣病を引き起こす病態の中心には、インスリン抵抗性がある。
・インスリン抵抗性とは、「インスリンの各種の作用得るのに、通常量以上のインスリンを必要とする
状態」であり、代償的に高インスリン血症を伴うことが多い。
・インスリン抵抗性は、糖尿病を引き起こす。
・インスリン抵抗性に伴う高インスリン血症により、腎臓の Na 再吸収増加、NO(一酸化窒素)産生低
下、交感神経緊張、血管平滑筋増殖などの作用を介して高血圧を引き起こす。
・インスリン抵抗性はリポタンパク質リパーゼの発現減少をきたし、高トリグリセリド血症、低 HDL-C
血症を引き起こす。
(7)メタボリックシンドローム(metabolic syndrome、WHO1998)
・虚血性心疾患や脳卒中を引き起こす動脈硬化症には複数の危険因子があり、それぞれの危険因子は相
乗効果がある。
・X症候群、死の四重奏、インスリン抵抗性症候群、内臓脂肪症候群などが提唱されてきたが、1998年
WHO は、これらは同じ病態であるとしてメタボリックシンドロームという名称を提唱した。
・メタボリックシンドロームとは、高血糖、脂質異常症、血圧高値など複数の動脈硬化症危険因子が重
積し、心血管病を発症するリスクが高い状態をいう。
X症候群
(Reaven、1988)
死の四重奏
(Kaplan、1989)
インスリン抵抗性症候
群(Defronzo、1991)
内臓脂肪症候群
(松沢,徳永、1987)
インスリン抵抗性
高インスリン血症
耐糖能異常
高 VLDL-TG血症
低 HDL-C血症
高血圧
耐糖能異常
高 TG血症
高血圧
上半身肥満
高インスリン血症
NIDDM
異常脂質血症
高血圧
肥満
動脈硬化性心疾患
耐糖能異常
高 TG血症
低 HDL-C血症
高血圧
内臓脂肪蓄積

臨床病態学 要点整理ノート
5
(8)異所性脂肪沈着
・肝臓、筋肉など、脂肪の貯蔵臓器である皮下脂肪組織以外の部位に脂肪が沈着することが、インスリ
ン抵抗性を引き起こす。
・沈着部位には、肝細胞内、筋肉細胞内、筋肉細胞間脂肪組織、腸間膜脂肪組織(内臓脂肪)、心外膜
脂肪組織などがある。
2.診断
(1)肥満の診断基準(日本肥満学会、肥満症診断基準 2011年)
・BMI(Body Mass Index)=体重(㎏)÷(身長 m)2
判定 日本肥満学会(2011) WHO*基準(1997) WPRO**基準(2000)
低体重
普通体重
~18.4
18.5~24.9
Underweight
Normal range
Underweight
Normal range
Overweight at risk
~18.4
18.5~22.9
23.0~24.9
肥満(1度)
肥満(2度)
肥満(3度)
肥満(4度)
25~29.9
30~34.9
35~39.9
40~
Preobese
Obese class I
Obese class II
Obese class III
Obese I
Obese II
25.0~29.9
30~
*WHO(World Health organization)
**WPRO(Western Pacific Regional Office of WHO)
・肥満 3度以上(BMI≧35)を、「高度肥満」(日本成人の 0.2~0.3%)とする。
欧米では肥満 2度以上(BMI≧30)が 10~25%いるが、日本では 2~3%と少ない。
・肥満 1 度は、WHO 基準(1997)では前肥満(Preobese)であるが、日本人は肥満 1 度で生活習慣病の
発症率が増加するので、日本肥満学会では BMI 25以上を肥満としている。
・WPRO(Western Pacific Regional Office of WHO)基準では、アジアでは23.0以上を過体重(overweight)、
25.0以上を肥満(obese)としている。
・わが国では肥満者(BMI≧25)の割合は 30~69歳で約 30%である。
・肥満者の割合は 20 年前に比べて約 1.5倍に増加している。
男性では全年齢層で増加している。
女性では 60歳以上で増加し、30~50 歳代で減少している。
(2)小児肥満の判定基準(日本肥満学会 2002 年)
・学校保険統計調査による年齢、性別標準体重をもとに肥満度を計算する。
・18歳未満の小児では肥満度が 20%以上、かつ有意に体脂肪率が増加した状態。
体脂肪率基準値 男児(小児期全般)は 25%。11歳未満の女児は 30%、11歳以上は 35%。

臨床病態学 要点整理ノート
6
(3)メタボリックシンドローム(metabolic syndrome)の診断基準(メタボリックシンドローム診断基
準検討委員会、2005)
腹腔内脂肪蓄積(必須事項)
ウエスト周囲径 男性≧85㎝
女性≧90㎝
(内臓脂肪面積 男女とも≧100 ㎝ 2に相当)
上記に加え以下のうち 2項目以上
高トリグリセリド血症 ≧150㎎/㎗
かつ/または
低 HDLコレステロール血症 <40㎎/㎗(男女とも)
収縮期血圧 ≧130㎜ Hg
かつ/または
拡張期血圧 ≧85 ㎜ Hg
空腹時高血糖 ≧110㎎/㎗
3.治療
(1)治療の目的
・減量することより、肥満による健康障害(肥満症)を予防する。
・肥満者では、現体重の 5%を減量するだけでも、血液検査などで望ましい効果が得られる。
・除脂肪体重(lean body mass)を維持しつつ、体脂肪を減少させるようにする。
(2)体重コントロールの原則(エネルギー保存の法則)
・摂取エネルギー>消費エネルギー → 体重増加
・摂取エネルギー=消費エネルギー → 体重維持
・摂取エネルギー<消費エネルギー → 体重減少
(3)食事療法
1)適切な摂取エネルギーを決める。
・摂取エネルギーが消費エネルギーを下回る負のエネルギーバランスにする。
1ヵ月で 1㎏減量するためには、一日に 200~300㎉マイナスにする必要がある。
脂肪組織 1㎏は 7,000㎉を含む。7,000÷30=233㎉
・実際には、標準体重×25 ㎉/日を基準に、1,200~1,600 ㎉/日とする場合が多い。
・1 ヵ月 1~2㎏のペースで、3~6ヵ月かけて目標値まで減量する。
・消費エネルギーは個人差が大きいので、食事療法の実施状況と体重の変化をモニターして適宜修正す
る必要がある。
2)適切な栄養素の配分を決める。
・たんぱく質は、1.0~1.2ℊ/㎏(標準体重)/日を維持する(除脂肪体重の維持のため)。
・糖質:55~65%(血糖値の維持とケトン体産生抑制のため、1日最低 100ℊは確保する)
・脂質:20~30%(必須脂肪酸、脂溶性ビタミンを確保するため、1日最低 20ℊは確保する)
・ビタミン、ミネラル、食物繊維、水分は、十分に摂取する。
・減量中の全身倦怠感は,ビタミン・ミネラルの不足による場合が多い。
3)食習慣を改善する。
・偏食、夜食、間食、2回食など肥満をまねく要因を是正する。
・よく噛むことは、歯や舌の感覚を刺激して食欲中枢を抑制し、また交感神経を刺激して脂質の燃焼を
促す作用がある。

臨床病態学 要点整理ノート
7
(4)入院を必要とする食事療法
1)低エネルギー食療法(Low Calorie Diet、LCD)
・入院して 600~1,000㎉で治療する。
・栄養素の配分は通常の減食療法に準じる。
2)超低エネルギー食療法(Very Low Calorie Diet、VLCD)(半飢餓療法)
・入院して 200~600㎉で治療する。約 4週間、医師の監視下で実施すれば安全に実施できる。
・BMI≧35の高度肥満症(小児、妊婦を除く)が適応となる。
・糖尿病を合併した高度肥満者にも適応される。
・粉末、液体などの規格食品(フォーミュラ食)を用いる。
・栄養素の配分 タンパク質 30~70ℊ/日
糖質 20~50ℊ/日
脂質 1~2ℊ/日
ビタミン・ミネラル 1日所要量
水分は十分に取る(起立性低血圧の予防)
・副作用としてケトアシドーシス、起立性低血圧、嘔気、嘔吐、便秘などがある。
・LCD、VLCD ともに短期的には減量に有効な方法であるが、長期的にはほとんどがリバウンドする。
(5)運動療法
1)軽度~中等度の持続性有酸素運動の効用
・運動能力・心肺機能の改善(筋肉の酸素消費能を増加、心拍出量の増加)
・心筋酸素消費量の減少(運動負荷に対する血圧と心拍数上昇率の減少)
・インスリン感受性の改善
・脂質・糖質代謝の改善(中性脂肪減少、HDL-C増加)
・内臓脂肪の減少
・骨粗鬆症の予防
・精神的効果(うつ減少、自立増加)
2)ウェートトレーニングの効用
・筋肉量の増加:筋力増加、基礎代謝増加、酸素消費量増加、骨塩増加
3)運動療法の実施
・必ずメディカルチェック(問診、身体診察、尿・血液検査)を行った上で実施する。
運動負荷テスト:自転車エルゴメーターで、段階的に運動を負荷(25~125watt)
処方する運動強度の範囲で、自覚症状、脈拍、血圧、心電図に変化がないことを確認する。
・運動強度:最大酸素摂取量の約 50%の運動
%HR reserve(カルボーネンの式)
={(220-年齢)-安静時心拍数}×運動強度(k)+安静時心拍数
={(220-40)-60}×0.5+60=120(40歳、安静時心拍数 60、運動強度 50%の場合)
・運動量:300㎉/日を目標とする。
・実施頻度:週 3回(できれば毎日)、1回に 20~30分程度。
1回 10 分未満で,1日数回に分けても有効という報告もある。
・補助運動として、ウェートトレーニング、ストレッチングを適宜取り入れる。
(6)薬物療法
・中枢性アドレナリン作動薬(マジンドール)
BMI 35以上に適応。
1992年から日本で肥満の治療薬として、唯一保険適用になっている薬品である。
習慣性があるために投与期間は 3ヶ月以内に限定されている。
副作用:口渇感、便秘、胃部不快感、悪心、睡眠障害など

臨床病態学 要点整理ノート
8
・二糖類分解酵素阻害剤(アカルボース、ボグリボース) 糖尿病治療薬として承認
・リパーゼ阻害剤(オルリスタット) 日本では未承認
・代謝促進薬(防風通聖散) カフェイン様作用による交感神経の緊張による代謝促進を期待
甲状腺剤は代謝を亢進させるが、内臓や筋肉のたんぱく質異化作用があるので使用しない。
(7)行動療法
1)肥満治療は、継続が大切
・治療により脂肪細胞の体積は減少するが、数は減らない。
・治療開始 1~2ヵ月後に体重減少が止まる適応現象が出現する。
・適応現象は急激な減量ほど出現しやすく、リバウンド効果(Weight cycling)も起こり易くなる。
2)行動療法は肥満治療の実践に有効である。
・まず,日常行動を分析する。
・次に、悪い食習慣、運動不足を助長している行動(負の行動因子)を抽出する。
・負の行動因子を除去する。
・行動の記録、自己評価を行う。
・個人またはグループで行う。
3)患者教育に必要なこと
・病気に関する知識
・治療に対する動機付け
・患者の心理過程を把握した具体的な展開
・個々の患者に合わせた目標設定(個別指導)
・臨床心理学やカウンセリングの手法を取り入れる。
4)行動変化のステージと援助(エンパワーメント)
・個々の患者のステージ、心理過程に合わせた目標設定をすることが重要である。
ステージ 状態 援助
前熟考期 問題を認識していない、否認あるいは逃避、燃
え尽き 考えや感情を聞く、情報提供
熟考期 行動開始を考えているが、それに対する阻害
要因もあり迷っている
利益と障害を知り、利益を高め、障害
を減らす
準備期 すぐに始めるつもりである、または、自分なり
に行動を開始している 具体的な行動目標を設定、行動強化
行動期 望ましい行動が始まって 6 ヶ月以内、再発が
もっとも多い 問題解決技術、再発予防対策
維持期 望ましい行動が 6 ヶ月を超えて継続されてい
る QOL配慮、ライフイベント対策
(8)手術療法
・適応:内科治療で有意な体重減少および肥満関連健康障害の改善が認められない BMI≧35の高度肥満
症
・Bariatric surgeryの適応:18 歳~65歳の原発性肥満で、6ヵ月以上の内科治療で有意な体重減少お
よび肥満関連健康障害の改善が認められない BMI≧35の高度肥満症
・糖尿病など代謝性合併症の治療を主目的とする手術(metabolic surgery)の適応:BMI≧32で糖尿病、
または糖尿病以外の二つ以上の肥満関連健康障害を有する患者
・術式:胃バンディング術、スリーブ状(袖状)胃切除術、胃バイパス術などがある。

臨床病態学 要点整理ノート
9
2.糖尿病
1.成因と分類
(1)定義
・糖尿病(diabetes mellitus)とは、インスリン作用の不足による慢性高血糖を主徴とし、種々の特
徴的な代謝異常を伴う疾患群である。
・その発症には、遺伝因子と環境因子がともに関与する。
・代謝異常の長期間にわたる持続は、特有の合併症をきたしやすく、動脈硬化症をも促進する。
・代謝異常の程度によって、無症状からケトアシドーシスや昏睡にいたる幅広い病態を示す。
(2)1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)
1)成因
・膵ランゲルハンス島β細胞に対する自己抗体が産生されて、細胞障害性 T細胞により細胞が破壊さ
れることが原因である。
遺伝因子 ・HLA(human leukocyte antigen)のうち、DR4または DR9のいずれかを持つ場合、発症
の危険率が 4倍、両方を持つ場合、12倍になる。DR2を持つ場合は、発症しにくい。
環境因子
・ウイルス感染:おたふく風邪ウイルス、コクサッキーウイルス、サイトメガロウイルス、
肝炎ウイルスなど
・食事抗原:牛乳タンパクなど
自己抗体
・膵島細胞抗体(islet cell antibody, ICA)、抗グルタミン酸脱炭酸酵素(glutamic
acid decarboxylase, GAD)抗体、抗インスリノーマ関連抗原(insulinoma-associated
antigen-2, IA-2)抗体など、自己抗原に対する自己抗体が出現する。
2)分類
急性発症 1型糖尿病 ・数週間~数ヶ月の経過で進行する。25歳以下の若年者に多い。好発年齢は
8~12歳である。
劇症 1型糖尿病 ・急性発症Ⅰ型糖尿病の 10~20%をしめ、数日でケトアシドーシスに陥り生
命の危険にさらされる。
緩除進行性 1型糖尿
病
・発症当初は 2 型糖尿病のような臨床症状を呈するが、自己抗体が陽性であ
り、数年かけて徐々にインスリン依存状態に進行する。発症年齢は 30~50
歳代である。
3)臨床経過
・遺伝素因を持つ人が、ウイルス感染などがトリガー(きっかけ)になって、β細胞に対する自己抗体
が作られる。(免疫異常の出現)
・自己抗体により膵島炎が起こり、β細胞の破壊によりインスリン分泌が減少する。
・残存β細胞による代償ができなくなると糖尿病を発症する。
・トリガーから発症に至るまでの期間は、数週から数年のことがある。

臨床病態学 要点整理ノート
10
(3)2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus)
・遺伝因子:多くの場合不明である。
・環境因子:過食、肥満、運動不足など
・遺伝因子と環境因子により、インスリン分泌不全とインスリン抵抗性が出現する。
・インスリンの需要に対して、分泌による供給が不足(インスリンの相対的作用不足)すると高血糖、
高遊離脂肪酸血症が起こる。
・高血糖と高遊離脂肪酸血症は、さらにインスリン分泌不全とインスリン抵抗性を促進して悪循環が起
こる。(糖毒性 glucotoxisityと脂肪毒性 lipotoxisity)
・症例によりインスリン分泌不全が優位な場合と、インスリン抵抗性が優位な場合がある。
・日本人はインスリン分泌不全が優位な場合が多く、欧米ではインスリン抵抗性が優位な場合が多い。
・皮下脂肪を蓄積する能力が低いものは、異所性脂肪沈着(肝臓、骨格筋)を起こしやすい。
・異所性脂肪沈着は、インスリン抵抗性を引き起こす。
(4)1型糖尿病と 2型糖尿病の比較 1型糖尿病 2型糖尿病
年齢
発症
インスリン不足
インスリン抵抗性
ケトアシドーシス
肥満
経口血糖降下薬
インスリン注射
遺伝傾向
発症機構
特定の HLAとの関連
若年(25歳以下)
急激(日~週)
絶対的不足
少ない
起こしやすい
少ない
無効
必須
約 50%
自己免疫を基礎にしたβ細胞破壊
強い
成人(40歳以上)
緩徐(年)
相対的不足
多い
起こしにくい
多い
有効
時に必須
90%以上
インスリン分泌不全+インスリン抵抗
性
少ない
(5)その他の特定の機序、疾患による糖尿病
A.遺伝因子として遺伝子異常が同定されたもの
膵β細胞機能にかかわる遺伝子異常
インスリン遺伝子、グルコキナーゼ遺伝子、ミトコンドリア DNA、転写因子など
インスリン作用の伝達機構にかかわる遺伝子異常
インスリン受容体遺伝子など

臨床病態学 要点整理ノート
11
B.他の疾患,条件に合うもの
膵外分泌疾患(膵炎、膵摘、ヘモクロマトーシスなど)
内分泌疾患(クッシング症候群、先端巨大症、褐色細胞腫、甲状腺機能亢進症など)
肝疾患(慢性肝炎、肝硬変)
薬剤や化学物質によるもの(グルココルチコイド、インターフェロンなど)
感染症(先天性風疹、サイトメガロウイルス、EBウイルスなど)
免疫機序によるまれな病態(インスリン受容体抗体、インスリン自己免疫症候群など)
その他の遺伝的症候群で糖尿病を伴うことが多いもの(Down 症候群など)
(6)妊娠糖尿病(gestational diabetes)
・定義:妊娠中にはじめて発見または発症した、糖尿病に至っていない糖代謝異常
・診断基準:75gOGTT において、次の基準の 1点以上を満たした場合に診断する。
空腹時血糖値≧92㎎/㎗
1時間値≧180㎎/㎗
2時間値≧153㎎/㎗
ただし、臨床診断において糖尿病と診断されるものは除外する。
・胎児の合併症
胎児死亡、先天奇形、巨大児、新生児低血糖、高ビリルビン血症など
・母体の産科合併症
流産、早産症、妊娠高血圧症候群、羊水過多など
・妊娠糖尿病は、糖尿病発症の危険因子である。
・明らかな糖尿病がある場合は、「糖尿病合併妊娠」という。
2.糖尿病合併症
(1)急性合併症
・口渇、多飲、多尿
尿糖排泄閾値(約 170㎎/㎗)以上の高血糖が持続すると尿糖が出現する。
グルコースにより尿の浸透圧が増加して尿量が増加する。これを浸透圧利尿という。
浸透圧利尿のために脱水が起こり、口渇、多飲、多尿の症状が出現する。
・体重減少
・易感染性:高血糖が持続する状態では免疫能が低下し、急性感染症(結核、尿路感染症、皮膚感染症、
術後感染症など)を引き起こす頻度が高くなる。
・糖尿病昏睡
高浸透圧高血糖症候群
・脱水による循環不全である。
・高齢者(口渇の自覚症状が乏しい)の 2型糖尿病患者に多い。
・血糖値は 600~1500 ㎎/㎗、浸透圧は 335mOsm以上になる。
糖尿病ケトアシドーシス ・1型糖尿病患者に多い。
・血糖値は 250~1000 ㎎/㎗、浸透圧正常~330mOsmである。
低血糖 ・過剰なインスリン注射や経口血糖降下薬の服薬による。

臨床病態学 要点整理ノート
12
・インスリンの絶対的不足と肝臓でのケトン体産生
・脂肪酸の酸化により生じるアセチル CoAが、クエン酸回路に入るためにはオキサロ酢酸が必要だ
が、インスリンの絶対不足のために、オキサロ酢酸が不足する。(解糖の減少と糖新生の増加によ
る)
・このためアセチル CoAは、クエン酸回路に入れずに細胞内に蓄積する。
・アセチル CoAが蓄積するとケトン体(アセトン、アセト酢酸、ヒドロキシ酪酸)が生成する。
・ケトン体の生成により、脂肪酸の酸化に必要な CoAが遊離するので酸化を継続する。
・ケトン体は、血液中に放出され、脳や筋肉でエネルギー源として利用される。
・ケトン体により血液の pHが低下することを、ケトアシドーシス(ketoacidosis)という。
(2)細小血管障害(microangiopathy)
1)糖尿病網膜症(diabetic retinopathy)
・網膜血管壁細胞の変性、基底膜の肥厚による血流障害、血液成分の漏出が原因で起こる。
・血糖値、血圧、糖尿病罹病期間、年齢が危険因子となる。
・眼底所見により単純網膜症、増殖前網膜症、増殖網膜症に分類される。
・特に増殖網膜症では、運動や急激な血糖値の正常化、低血糖などにより悪化することがある。
・糖尿病網膜症は、成人の失明の主要な原因である。
2)糖尿病腎症(diabetic nephropathy)
・病理:糸球体硬化症(血管基底膜の肥厚とメサンギウムの拡大)がみられる。
・診断に必要な検査:尿たんぱく、尿中微量アルブミン排泄、クレアチニン・クリアランス
・試験紙による尿検査で尿たんぱくが陽性のものを顕性腎症という。
・尿中微量アルブミン排泄は糖尿病腎症の早期発見に有用な検査である。
・透析療法の新規導入患者の約 40%が糖尿病性腎症であり、新規導入の原因第 1位である。
・5 年生存率は 50%以下でその他の疾患によるものに比べて予後不良である。

臨床病態学 要点整理ノート
13
3)糖尿病神経障害(diabetic neuropathy)
・末梢神経の軸索変性、脱髄などが原因である。
・主として知覚神経と自律神経が障害される。
知覚障害 ・グローブ・ストッキング型知覚障害
・初期はしびれ感、痛み、後期は知覚消失
自律神経 ・心臓神経の障害、消化管の運動障害(便秘、下痢)、発汗障害、起立性低血圧、瞳孔の
変化、膀胱の機能障害、勃起障害など
・検査:知覚障害、振動覚閾値低下、腱反射低下・消失、神経伝導速度、起立性低血圧、RR間隔など
・治療後神経障害:長期高血糖が持続した患者では、治療により急に血糖値を正常化すると疼痛が増強
することがある。
4)高血糖が細胞障害を引き起こすメカニズム
・血管内皮細胞や神経細胞など、グルコースの細胞内取り込みがインスリンに依存しない細胞では、細
胞内のグルコース代謝が増加する。
細胞内ソル
ビトール蓄
積説
・ソルビトール経路(グルコース→ソルビトール→フルクトース)に流れるグルコース
が増加し、ソルビトールが蓄積する。
・ソルビトールは細胞膜を通過できないので、細胞内の浸透圧が増加し、細胞障害が起
こる。
・ソルビトール経路の律速酵素であるアルドース還元酵素の阻害薬は神経障害の治療薬
として利用されている。
活性酸素発
生増加説
・グルコースの酸化増加に伴い、電子伝達系を流れる電子が増加し、活性酸素の発生が
増加し、細胞障害が起こる。
(3)大血管障害(macroangiopathy)
・糖尿病は、動脈硬化症の重要な危険因子のひとつである。
・糖尿病を合併した高血圧症や脂質異常症は、非糖尿病患者より厳格な治療目標値を設定する必要があ
る。
・糖尿病患者の動脈硬化症の特徴
進行が早く、若年者(30歳代)から出現する。
病変は大血管・中血管・小血管に及び、バイパス手術などの処置が困難になることがある。
脳梗塞は多発性の小梗塞(ラクナ梗塞)が多く、痴呆が起こりやすい。
無症候性心筋梗塞を起こすことがある。
高齢者では足の血流障害が多い。
(4)糖尿病壊疽
・神経障害(痛覚消失)と下肢動脈硬化症(血流障害)あるところに外傷を合併しても、痛みなど自覚
症状がないので放置することが多く、感染などを合併して壊疽に進展する。

臨床病態学 要点整理ノート
14
3.診断
(1)診断手順(「糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告」日本糖尿病学会(2010))
1)初回検査で、①早朝空腹時血糖値≧126 ㎎/㎗、②75gOGTT2時間値≧200㎎/㎗、③随時血糖値≧200mg/
㎗、④HbA1c(国際基準値)≧6.5%(HbA1c(JDS 値)≧6.1%)のうちいずれかを認めた場合は「糖
尿病型」と判定する。別の日に再検査を行い、再び「糖尿病型」が確認されれば糖尿病と診断する。
但し、HbA1c のみの反復検査による診断は不可とする。また、血糖値と HbA1c が同一採血で糖尿病型
を示すこと(①~③のいずれかと④)が確認されれば、初回検査だけでも糖尿病診断してよい。
2)血糖値が糖尿病型(①~③のいずれか)を示し、かつ次のいずれかの条件がみたされた場合は、初回
検査だけでも糖尿病と診断できる。
・糖尿病の典型的症状(口渇、多飲、多尿、体重減少)の存在
・確実な糖尿病網膜症の存在
3)過去において、上記 1)ないしは 2)の条件がみたされていたことが確認できる場合には、現在の検
査値が上記の条件に合致しなくても、糖尿病と診断するか、糖尿病の疑いを持って対応する必要があ
る。
4)上記 1)~3)によっても糖尿病の判定が困難な場合には、糖尿病の疑いを持って患者を追跡し、時
期をおいて再検査する。
5)初回検査と再検査における判定方法の選択には、以下に留意する。
・初回検査の判定に HbA1c を用いた場合、再検査ではそれ以外の判定方法を含めることが診断に必須で
ある。検査においては、原則として血糖値と HbA1cの双方を測定するものとする。
・初回検査の判定が随時血糖値≧200 ㎎/㎗で行われた場合、再検査は他の方法によることが望ましい。
・HbA1c が見かけ上低値になり得る疾患・状況の場合には、必ず血糖値による診断を行う。
・疫学調査:糖尿病の頻度推定を目的とする場合は、1 回だけの検査による「糖尿病型」の判定を「糖
尿病」と読み替えてもよい。なるべく HbA1c(国際標準値)≧6.5%(HbA1c(JDS値)≧6.1%)ある
いは OGTT2時間値≧200㎎/㎗の基準を用いる。
・検診:糖尿病およびその高リスク群を見逃すことなく検出することが重要である。スクリーニングに
は血糖値、HbA1c のみならず、家族歴、肥満などの臨床情報も参考にする。
(2)75g経口糖負荷試験(OGTT)の判定基準(日本糖尿病学会 2010)
正常域 糖尿病域
空腹時値
75ℊOGTT2時間値
<110㎎/㎗
<140㎎/㎗
≧126㎎/㎗
≧200㎎/㎗
75gOGTT の判定 両者をみたすものを正常型とする。 いずれかをみたすものを糖尿病型とする。
正常型にも糖尿病型にも属さないものを境界型とする。
(3)境界型の考え方と指導方針
・境界型には、糖尿病が治療により軽快したもの、糖尿病へ移行する過程にあるもの、ストレスなどに
より一過性に血糖値が上昇したものが含まれる。
・メタボリックシンドロームであることが多い。
・2時間値が高値(170~199mg/dl)のもの、インスリン分泌初期反応が低いものは糖尿病へ移行する可
能性が高い。
・1 時間値が 180mg/dl以上のものは、境界型に準じて取り扱う。
・生活習慣の改善を指導し、3~6ヵ月後に再検査する。
・脂質異常症、高血圧、肥満などを伴っているときはメタボリックシンドロームとして積極的に治療す
る。

臨床病態学 要点整理ノート
15
(4)病態を把握するための検査
1)血糖値のコントロール状態の判定
グリコヘモグロビン
(HbA1c, hemoglobin
A1c)
・ヘモグロビンのアミノ基とグルコースのアルデヒド基が非酵素的、非
可逆的に結合したもの
・過去 1~2ヶ月の平均血糖値を反映する。
・基準範囲(国際標準値)は、4.7~6.2である。
・出血、鉄欠乏性貧血、溶血性貧血では、低値となる。
・ヘモグロビン異常症では、通常と異なる値になる可能性がある。
フルクトサミン
(FA, fructosamine)
・血清たんぱく質のアミノ基とグルコースアルデヒド基が、非酵素的、非可
逆的に結合したもの
・過去 1~2 週間の平均血糖値を反映する。
グリコアルブミン
(GA, glycoalbumin)
・アルブミンのアミノ基とグルコースのアルデヒド基が、非酵素的、非可逆
的に結合したもの
・過去 1~2 週間の平均血糖値を反映する。
1,5-アンヒドロ-D-グルシ
トール
(1,5-AG, 1,5-anhydro-D-
glucitol)
・ポリオールの 1 種で、糸球体で自由に濾過され、ほとんどが尿細管から再
吸収される。
・グルコースとよく似た構造をしており、グルコースと同じ輸送担体で再吸
収されるので、尿中グルコース濃度が上昇すると、再吸収が抑制される。
・尿糖が陽性のときは再吸収が抑制されるので、尿中排泄量が増加し、血中
濃度が低下する。
・過去 1 週間以内の血糖値の変動を反映する。
2)インスリン分泌能の判定
・インスリン分泌初期反応
75ℊOGTT において測定する。
⊿IRI(30分)÷⊿血糖値(30 分)が 0.4未満では、インスリン分泌能低下の可能性がある。
IRI(immunoreactive insulin):血中インスリン濃度
⊿IRI(30分):75ℊブドウ糖負荷 30分後の血中インスリン濃度上昇
⊿血糖値(30分):75ℊブドウ糖負荷 30分後の血糖値上昇
・血中 C-ペプチド濃度および尿中 C-ペプチド排泄量
C-ペプチドは、インスリン分泌と同時にインスリンと当モル分泌されて尿中に排泄されるので、イ
ンスリン分泌能の指標として利用される。

臨床病態学 要点整理ノート
16
3)HOMA(Homeostasis Model Assessment)
・空腹時血糖値とインスリン濃度から、インスリン抵抗性とインスリン分泌不全を診断
63-360
405
空腹時血糖値
インスリン濃度β=
インスリン濃度空腹時血糖値=
×−
×−
HOMA
RHOMA
HOMA-R(正常:~2.5、疑い:2.5~5.0、インスリン抵抗性:5.0~)
HOMA-β(正常:40~50%、分泌低下:~40%)
4)膵島細胞関連自己抗体(1型糖尿病で陽性)
・抗グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)抗体(anti-glutamic acid decarboxylase antibody)
・抗 IA-2抗体(anti-insulinoma associated antigen-2 antibody)
4.治療方針
(1)目的
1)エネルギーや各栄養素などの代謝異常を正常化する。
・高血糖による自覚症状(口渇、多飲、多尿、体重減少)をなくす。
・ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡などの急性合併症を予防する。
2)合併症の危険因子を除去・減少させ、慢性合併症を予防する。
・三大慢性合併症(腎症、網膜症、神経症)の予防
・動脈硬化症の予防
3)生活の質(Quality of Life)を維持・向上させる。
・健常人と変わらない社会生活を維持し、寿命を全うする。
(2)治療方針
1)1型糖尿病
・診断がつき次第、直ちにインスリン注射を開始する。
・インスリンを十分に投与し、ケトーシスが消失したら食事療法・運動療法を加える。
・インスリン療法は、原則として強化インスリン療法を行う。
・早期に強力な治療を行うと、蜜月期(一時的にインスリンの必要量の減少または不要になる期間)を
もたらすことがある。
・小児の食事療法では、正常な発達・発育が行われるように、健常児と同等の栄養を与える。
2)2型糖尿病
・まず、食事療法、運動療法、生活習慣の改善による治療を開始する。
・著しい高血糖の場合は一時的にインスリンを使用する場合もある。
・3 ヶ月治療を続けても目標の血糖値を達成できない場合は、経口血糖降下薬を用いる。
・経口血糖降下薬は最少量から開始し、徐々に増量する。
・1 種類の薬で目標が達成できない場合は作用機序の異なる薬を追加する。
・経口薬で目標を達成できない場合はインスリン注射を開始する。
・インスリンを開始する場合は経口薬をすべて中止する。
・重篤な感染症、全身管理が必要な外科手術時、妊娠糖尿病などがあるときは、インスリン注射による
厳格な血糖コントロールが必要となる。
・代謝状態の改善により、インスリン注射の減量・中止、経口薬の減量・中止が必要になることがある。

臨床病態学 要点整理ノート
17
(3)コントロール目標
1)血糖値
評価 優 良 可 不可
HbA1c(%)
(JDS値)
HbA1c(%)
(国際標準値)
5.8未満
6.2未満
5.8~6.5未満
6.2~6.9未満
6.5~7.0未満(不十分)
7.0~8.0未満(不良)
6.9~7.0未満(不十分)
7.4~8.4(不良)
8.0以上
8.4以上
空腹時血糖値
食後 2時間血糖値
80~110 未満
80~140 未満
110~130未満
140~180未満
130~160未満
180~220未満
160以上
220以上
2)その他
・体重:標準体重(BMI 22)を維持する。
・血圧:130/80mmHg 未満(尿蛋白 1ℊ/日以上の場合、125/75mmHg 未満)
・血清脂質:LDL-C 120㎎/㎗未満(肝動脈疾患がある場合、100㎎/㎗未満
HDL-C 40㎎/㎗以上
トリグリセリド:150㎎/㎗未満(早朝空腹時)
・合併症:発症しない、または進展しない。
・目標値は、年齢、合併症の有無などにより、個々に設定する。
妊娠糖尿病、若年者では、より厳密にコントロールする必要がある。
5.食事療法
(1)食事療法の原則
・成人では、適正な体重を維持し、小児では,健常児とかわらない成長と発育をするために必要な栄養
を供給する。
・妊娠中、授乳中、あるいは消耗性疾患から回復に必要なエネルギーを供給する。
・エネルギー制限のため、健康に必要な栄養素の不足をすることがないように注意する。
・適正な体重とは、短期的にも長期的にも達成可能で維持可能な体重をいう。
・身長を基にした標準体重は、あくまでも目安である。
・肥満がある場合、現体重から 5~10㎏減量するだけで、血糖値、血清脂質、血圧に対して好影響を及
ぼすことが示されている。
・食事療法の優先順位は、エネルギー>栄養素配分>食品選択(glycemic indexなど)である。
(2)適正なエネルギー量の決め方
・軽労作(デスクワーク、主婦など)の場合 標準体重×25~30㎉/㎏/日
・普通の労作(立ち仕事が多い職業)の場合 標準体重×30~35㎉/㎏/日
・重い労作(力仕事の多い職業)の場合 標準体重×35~㎉/㎏/日
(3)適正な栄養素の配分
1)糖質(50~60%)
・種類や形態よりも総量を厳格に管理することが重要である。
・ショ糖の摂取が血糖値に悪影響を与える証拠はないが、ショ糖を多く含む食品は、総量の増加につな
がりやすいので注意を要する。
2)たんぱく質(15~20%)
・1.0~1.2ℊ/㎏を確保するようにする。
・糖質と一緒に摂取することにより、インスリン分泌促進作用、血糖値上昇抑制作用がある。
・肥満のためにエネルギー制限をしている場合は、体内たんぱく質の異化が促進するので、除脂肪体重
を維持するためにたんぱく質不足にならないように注意する。
・過剰摂取は糖尿病性腎症の発症と進展に関与する。

臨床病態学 要点整理ノート
18
・動物性タンパク質に多く含まれるアミノ酸は腎機能に悪影響を及ぼす可能性がある。
・糖尿病性腎症ではたんぱく質制限を行う。
・妊娠、授乳中のたんぱく質必要量:妊娠中は+10ℊ、授乳中+20ℊ付加する。
3)脂質(25%以下)
・飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸をそれぞれ 10%以内に制限する。
・n-3系多価不飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸は、総量 25%以内であれば制限しない。
・動脈硬化性疾患予防ため、コレステロール摂取は 200㎎/日未満とする。
4)食塩
・高血圧や腎症を合併している場合は、6ℊ/日未満とする。
・高血圧症の合併がない場合には、高血圧発症を予防するため、男性で 9ℊ/日未満、女性で 7.5ℊ/日未満
とする。
5)食物繊維(20~25ℊ)
・糖質の吸収速度を遅くし、脂質、コレステロールの吸収を抑制するので糖尿病の治療には有効。
・食物繊維単独で血糖値を低下させるには 1日 50ℊ 以上が必要である。
・野菜を 1日 300ℊ(健康日本 21 では 350ℊ)摂取することを目標とする。
6)ビタミン・ミネラルのサプリメント
・適正なカロリーと栄養素の配分に従った食事であれば、ビタミン、ミネラルの補充は必要ない。
・厳重なカロリー制限、極端な菜食主義者、高齢者、妊婦、授乳中の婦人では補充が必要になる場合が
ある。
(4)糖尿病食事療法のための食品交換表
・1単位=80㎉とする。
・表 1~表 6、調味料に配分
(5)糖尿病腎症の食事療法
・低たんぱく、減塩食が原則
病期 総エネルギー
(㎉/㎏/日)
たんぱく質
(ℊ/㎏/日)
食塩
(ℊ/日)
第 1期
第 2期
第 3期
第 4期
第 5期(血液透析)
(持続携帯型腹膜透析)
25~30
25~30
25~30
25~35
30~35
30~35
1.0~1.2
1.0~1.2
0.8~1.0
0.6~0.8
0.9~1.2
0.9~1.2
高血圧あれば 6
高血圧あれば 6
6
6
6
制限せず
(6)妊娠糖尿病の食事療法
・非肥満妊婦(BMI<25)の場合 妊娠初期 標準体重×30㎉+50㎉
妊娠中期 標準体重×30㎉+250㎉
妊娠末期 標準体重×30㎉+450㎉
授乳期 標準体重×30㎉+350㎉
・肥満妊婦の場合(BMI≧25)の場合 標準体重×30㎉
・許容体重増加 BMI<18.5 9~12㎏
BMI 18.5~25 7~12㎏
BMI≧25 個別対応(およそ 5㎏を目安)

臨床病態学 要点整理ノート
19
6.運動療法
(1)期待される効果
・肥満を合併した糖尿病患者で、食事療法による減量を促進する。
・食事療法とともにエネルギー摂取と消費のバランスを改善する。
・エネルギー制限による筋肉量(除脂肪体重)の減少を防止する。
・インスリン抵抗性、高血糖、脂質異常症,高血圧症を改善する。
(2)運動療法を制限または中止した方が良い場合
・極端なコントロール不良(空腹時血糖 250mg/dl以上、尿ケトン体陽性)の場合
・増殖網膜症で新鮮な眼底出血がある場合
・腎不全、心疾患、心肺機能に異常がある場合
・糖尿病神経障害で、足の感覚喪失、心血管系の自律神経障害がある場合
(3)運動療法の実施
・運動療法を実施する前に必ずメディカルチェックを受ける。
・歩行運動では 1 回 15~30 分間、1日 2 回、1 日の運動量として歩行は 1万歩、消費エネルギーは 160
~240kcal程度が適当とされる。
・運動の強度は脈拍が 100~120 程度になる運動が適当である。
・経口血糖降下剤、インスリン使用中は原則として空腹時に運動しない。
・空腹時に運動する時は、低血糖予防のため補食する。
7.薬物療法
(1)インスリン分泌を促進する薬
①スルホニル尿素薬(SU, sulfonyl urea)
・β細胞の SU受容体(ATP感受性 Kチャネル)に直接働いてインスリンを分泌させる。
・第 3世代は、膵外作用を併せ持ち、低血糖が少ない、食後血糖低下作用が強いなどの特徴がある。
・作用時間は長い。(6~24 時間)
・副作用:低血糖、肝・腎障害など
・β細胞を疲弊させる可能性があり、投与中に効果がなくなることがある。(二次無効)
②速攻型インスリン分泌促進薬(フェニルアラニン誘導体)
・β細胞の SU受容体(ATP感受性 Kチャネル)に直接働いてインスリンを分泌させる。
・作用発現時間は 15~30分、作用時間は短い。(3時間)
・薬物の吸収・代謝が早いので食後高血糖の抑制に有効である。
・食直前に服用する。
・副作用:低血糖、肝・腎障害など
③GLP-1アナログ(Glucagon-like peptide-1 analog)(皮下注射薬)
・十二指腸粘膜から分泌されるインクレチンの 1種である。
小腸から分泌され、グルコースによるインスリン分泌を増強する消化管ホルモンを総称してインク
チン(incretin)という。
インクレチンには、GLP-1(glucagon-like peptide-1)と GIP(glucose-dependent insulinotropic
polypeptide)がある)
・グルコース刺激によるインリン分泌を増強する。
・低血糖が少ない。
・副作用:下痢、便秘、嘔気など胃腸障害

臨床病態学 要点整理ノート
20
④DPP-4阻害薬(dipeptidypeptidase-4 inhibitor)
・DPP-4は、GLP-1と GIPを分解し、不活性化する。
・DPP-4阻害薬は、GLP-1と GIPの分解を抑制する。
・インスリン分泌作用は、血糖値に依存するので、低血糖を起こしにくい。
・副作用:SU薬との併用で低血糖
(2)インスリン抵抗性を改善する薬
⑤ビグアナイド類
・肝臓からのグルコース放出抑制が主作用である。
・その他、消化管の糖吸収抑制作用、筋肉のインスリン感受性改善作用など
・近年、安全性と有効性が再評価され利用が増加した。
・副作用:乳酸アシドーシス、肝・腎障害など
⑥チアゾリジン誘導体
・脂肪細胞の核内転写因子 peroxisome proliferator-activated receptor-γ(PPAR-γ)に結合する。
大型脂肪細胞のアポトーシス、小型脂肪細胞が増殖・分化をもたらす。
TNF-α、レジスチン、アディポネクチンなど adipocytokineの分泌動態を改善し、インスリン抵抗
性を改善する。
・体重が増加しやすい。
・副作用:浮腫(集合管での Na 再吸収促進)、貧血、LDH上昇、CPK上昇、肝障害など
・水分貯留傾向のため、心不全患者では投与しない。
・妊婦・授乳中の女性には投与しない。
(3)食後の血糖値上昇を抑制する薬
⑦α-グルコシダーゼ阻害薬
・腸管粘膜上での二糖類の分解を抑制し、グルコースの吸収を遅らせる。
・食直前に服用する。食後服用では効果がない。
・副作用:腹部膨満感、放屁の増加、下痢など
・SU薬やインスリンとの併用で低血糖が起こった場合はブドウ糖を投与する。ショ糖は不可。
(4)尿糖の排泄を促進する薬
⑧SGLT2 阻害薬(SGLT2, sodium glucose cotransporter-2)
・SGLT2 は、近位尿細管に発現し、グルコースの再吸収を行う。
・SGLT2 阻害薬は、グルコースの再吸収を抑制することにより血糖値を低下させる。
血糖値が高いほど尿糖の排泄が多くなり、血糖値は低下すると尿糖の排泄は少なくなる。
→低血糖症状を起こしにくい。(他の血糖降下薬やインスリンとの併用では、重篤な低血糖を起こ
す可能性がある)
・グルコースのエネルギーを利用することなく排泄するので、エネルギーバランスが負になり体重が減
少する。
・尿糖排泄増加による浸透圧利尿のため、脱水を起こす可能性がある。

臨床病態学 要点整理ノート
21
(5)インスリン療法
1)インスリン製剤
2)投与方法
3)低血糖時の対応
・低血糖症状
交感神経興奮症状:空腹感、脱力感、冷汗、不安、動悸、手指振戦、顔面蒼白、頻脈)
中枢神経症状:頭痛、悪心・嘔吐、眼のかすみ、動作緩慢、集中力低下、意識障害、痙攣、昏睡
・無自覚性低血糖
自律神経障害を合併している人では低血糖症状が現れにくく、突然重篤な中枢神経症状が出現する
ことがある。
・処置
①経口可能な場合はグルコースで 5~10ℊ、ショ糖で 10~20ℊまたは清涼飲料水(150~200 ㎖)摂取す
る。(グルコース 10ℊの摂取で血糖値は 100㎎/㎗上昇する)
②経口不可能な場合は、グルカゴン筋肉注射する。
③病院での処置:50%グルコース 20~40 ㎖を静注する。

臨床病態学 要点整理ノート
22
3)Sick Day(シックデイ)の対応
・Sick Dayとは、糖尿病治療中、発熱、下痢、嘔吐のため食欲不振となることをいう。
・インスリン治療を行っている患者は、ケトアシドーシスを起こしやすくなる。
・処置
①できるだけ摂取しやすい形(お粥、麺類、果汁など)でエネルギー、糖質(1日最低 150g摂取)を補
給する。
②十分な水分補給(1日 1,000ml 以上)を行う。
③3~4時間ごとに血糖値を自己測定し、適宜速効性インスリン注射を行う。
④できれば尿ケトン体を測定する。
⑤食事ができないからといって、インスリン量を極端に減らしたり、中止したりしてはいけない。
⑥早めに主治医と連絡をとる。
(3)インスリン以外の注射薬(GLP-1アナログ Glucagon-like peptide-1 analog)
・十二指腸粘膜から分泌されるインクレチンの 1種(小腸から分泌され、グルコースによるインスリン
分泌を増強する消化管ホルモンを総称してインクレチン(incretin)という。
・インクレチンには、GLP-1(glucagon-like peptide-1)と GIP(glucose-dependent insulinotropic
polypeptide)がある)
・GLP-1受容体作動薬(Glucagon-like peptide-1 receptor agonist)
GLP-1のアナログ製剤で、DPP-4による分解、不活性化を受けにくい。
1日 1回、朝または夕に皮下注射(作用時間は 24時間以上)
グルコース刺激によるインリン分泌を増強する。
・低血糖が少ない。
・副作用:下痢、便秘、嘔気など胃腸障害
8.合併症の治療
(1)糖尿病網膜症の治療
・単純網膜症
血糖コントロールと高血圧の治療など内科的治療
・増殖性前網膜症、早期の増殖網膜症
光凝固療法
・進行した増殖網膜症
硝子体出血・網膜剥離 → 硝子体手術
増殖網膜症では、急激な血糖値の改善や低血糖により、網膜出血など症状が悪化することがあるの
で注意を要する。
(2)糖尿病腎症の薬物療法
・原則として、インスリン注射による厳格な血糖値のコントロールを行う。
・高血圧に対して降圧薬を使用する。
・降圧目標値は、130/80mmHg 未満とする。
・1 日 1g以上のたんぱく尿を伴う場合は、125/75mmHg 未満を降圧目標とする。
・アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬、アンギオテンシン受容体Ⅱ(A-Ⅱ)拮抗薬は、第 3期以上
の腎症で腎機能保護作用がある。
(3)フットケア
・毎日手を洗うように、人肌のお湯で石鹸をつけて洗う。
・洗った後、足をよく乾かす。指の間もきれいに拭く。
・爪はまっすぐに切り、深爪しないようにする。
・皮膚を滑らかにするために、ローションを塗る。
・ちょうど足に会う軟らかいきれいな靴下を毎日とりかえる。
・足を暖かく、湿らせるようにする。

臨床病態学 要点整理ノート
23
・裸足は厳禁
・足に合った靴を選ぶ。
・毎日靴を点検する。小石や針、皮膚を刺激する変形など。

臨床病態学 要点整理ノート
24
3.脂質異常症
1.コレステロールの体内動態
2.リポたんぱく質(lipoprotein)代謝
(1)リポたんぱく質の構造と種類
・外側にリン脂質と遊離コレステロールが、内部にトリグリセリドとコレステロールエステルが存在す
る球状の粒子で、たんぱく質(アポリポたんぱく質)を含む。
(2)キロミクロン(chylomicron)の代謝
・もっとも大きな粒子で、トリグリセリドを多く含む。
・食事に含まれる脂質を材料に小腸で合成され、末梢組織にトリグリセリドを運ぶ。
・キロミクロンに含まれるトリグリセリドは、末梢組織の血管内皮細胞上にあるリポタンパク質リパー
ゼ(lipoprotein lipase、LPL)により加水分解され、末梢組織の細胞に脂肪酸を供給する。
・グリセロールは、肝臓に運ばれて解糖または糖新生に利用される。
・トリグリセリドが分解された残りの粒子を、キロミクロンレムナントといい肝臓に取り込まれる。
(3)超低比重リポたんぱく質(very low density lipoprotein、VLDL)の代謝
・肝臓で合成されるリポたんぱく質で、トリグリセリドを多く含む。
・肝臓で合成されたトリグリセリドを末梢組織に運ぶ。
・VLDL に含まれるトリグリセリドは末梢組織の血管内皮細胞上にあるリポたんぱく質リパーゼ(LPL)
によりが加水分解され、末梢組織の細胞に脂肪酸を供給する。
・グリセロールは肝臓に運ばれて解糖または糖新生に利用される。
・トリグリセリドが分解された残りを VLDL レムナント(または中間型リポたんぱく質、IDL)という。
・VLDL レムナントは肝臓に取り込まれるか、肝臓の類洞において肝性リパーゼの作用を受けて LDLに変
換される。
食物由来の
コレステロール
肝で合成した
コレステロール
コレステロール・プール
細胞膜の成分 ミネラルコルチコイド
グルココルチコイド
(副腎皮質)
男性ホルモン
女性ホルモン
(性腺)
胆汁酸
(肝臓)
胆汁中に排泄
20~30% 70~80%

臨床病態学 要点整理ノート
25
(4)低比重リポたんぱく質(low density lipoprotein、LDL)の代謝
・肝臓の類洞で肝性リパーゼの作用を受けて VLDLレムナントから変換されて合成される。
・コレステロールを肝臓から末梢組織へ運ぶ。
・末梢組織および肝臓の LDL受容体を介して細胞内に取り込まれる。
・末梢組織にコレステロールが十分にあるときは LDL受容体が減少して LDLの取り込みが減少する。
(5)高比重リポたんぱく質(high density lipoprotein、HDL)の代謝(逆転送系)
・肝臓・小腸で合成されるリポたんぱく質でコレステロールを多く含む。
・合成直後はコレステロール含量の少ない円盤状の粒子(原始 HDL)であるが、末梢組織の細胞膜に存
在する余分なコレステロールを LCAT(レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ)の作
用で HDL内に取りこみ、コレステロール含量の多い円形の粒子(成熟 HDL)になる。
・成熟 HDL は、肝臓に取り込まれるか、コレステロールをキロミクロンや VLDL にわたして原始 HDL に
戻る。
・コレステロールエステル転送たんぱく質(Cholesterol ester transfer protein、CETP)は成熟 HDL
からキロミクロンや VLDLにコレステロールを転送する酵素である。
(6)アポリポたんぱく質(apolipoprotein)の種類と機能
リポたんぱく質 アポリポたんぱく質 機能
LDL B ・LDL受容体に結合する。
キロミクロン・VLDL C-Ⅱ ・LPLを活性化する。
E ・レムナント受容体と結合する。
HDL A-Ⅰ ・LCAT を活性化する。

臨床病態学 要点整理ノート
26
3.分類
(1)定義
・脂質異常症(dyslipidemia)とは、血液中の LDLコレステロールとトリグリセリドの両方または一方
が増加、あるいは HDL コレステロールが低下した状態をいう。
・脂質異常症は動脈硬化症の重要な危険因子である。
・血液中の LDLコレステロールとトリグリセリドの両方または一方が増加するものを高脂血症ともいう。
(2)分類
原発性脂質異常症
・血清脂質の代謝に関わる遺伝子の先天的異常によるものである。
・原発性のうち、遺伝が強く関係して家族内発生がみられるものを家族性脂質
異常症という。
続発性脂質異常症
・全体の約 40%を占めている。
・糖尿病、肥満、甲状腺疾患、性ホルモン、ネフローゼ症候群、腎不全、胆汁う
っ滞など
(3)家族性脂質異常症の分類(厚生省特定疾患原発性高脂血症調査研究班)
1)原発性高キロミクロン血症
家族性 LPL欠損症
・LPL欠損症であり、常染色体劣性遺伝する。
・頻度は 100 万人に 1人といわれる。
・Ⅰ型またはⅤ型を呈する。
アポリポたんぱく CⅡ
欠損症
・アポリポたんぱく CⅡ欠損症であり、常染色体劣性遺伝する。
・まれな疾患で、わが国では 16家系が報告されている。
・Ⅰ型またはⅤ型を呈する
原発性Ⅴ型高脂血症
・空腹時にキロミクロンと VLDL の増加(Ⅴ型)が見られるが、LPLやアポリ
ポたんぱく CⅡの欠損は認められないものをいう。
・病因は不明で、原因遺伝子は同定されていない。
・頻度は 1万人に 1~2人である。
その他の原因不明の
高キロミクロン血
症
・高キロミクロン血症で①、②、③に該当しないもの。
・LPL阻害物質を有する家系が報告されている。
2)原発性高コレステロール血症
家族性高コレステロ
ール血症
・LDL受容体欠損症であり、常染色体優性遺伝する。
・頻度は、ホモ接合体は 100 万人に 1 人であるが、ヘテロ接合体は 500 人に
1人で比較的多い。
・Ⅱa型を呈する。
家族性複合型高脂血
症
・家族内に IIa、IIb、IV型がそれぞれ 3分の 1の割合で混在するもの。
・病因は不明で、原因遺伝子は同定されていない。
・頻度は 100~200人に 1人で 2番目に多い。
3)内因性高トリグリセリド血症
家族性Ⅳ型高脂血症
・家族内にⅣ型高脂血症認めるが、他の型の高脂血症を認めないものである。
・VLDL 合成亢進によるもので、常染色体優性遺伝する。
・最も多く、一般人口中の頻度は 1~数%といわれるが、診断基準が明確で
ないために正確には不明である。
・インスリン抵抗性を伴う遺伝子異常が推定されているが、原因遺伝子は同
定されていない。
・過食、アルコール過飲、糖尿病が合併するとⅤ型を呈することもある。

臨床病態学 要点整理ノート
27
特発性高トリグリセ
リド血症
・キロミクロンではなく、VLDL の増加によりⅣ型を呈するが、家族内の集積
を認めないものである。
・病態は家族性Ⅳ型高脂血症と同様であると考えられている。
4)家族性 III型高脂血症
・アポ Eの遺伝子型が E2/E2 のホモ接合体はレムナント受容体との結合能が低いために、血中レムナン
トが停滞して高レムナント血症を起こす。
・頻度は 1万に 1~2人である。
5)原発性高 HDLコレステロール血症
・血清 HDLコレステロール値が 100mg/dl以上で、家族歴が明瞭なものである。
・病因として CETP欠損症、肝性リパーゼ欠損症、アポ A-Ⅰ欠損症などがある。
(4)表現型分類(WHO分類)
増加するリポタンパク質 コレステロール トリグリセリド
Ⅰ型 キロミクロン 正常またはやや増加 増加
Ⅱa 型 LDL 増加 正常
Ⅱb 型 LDL+VLDL 増加 増加
Ⅲ型 IDL 増加 増加
Ⅳ型 VLDL 正常またはやや低下 増加
Ⅴ型 キロミクロン+VLDL 正常またはやや増加 増加
*高中性脂肪血症では、HDL コレステロールは低下していることが多い。
4.粥状動脈硬化症(atherosclerosis)
(1)成立機序
脂肪斑
・血管内腔から動脈壁の内膜に侵入した LDLは酸化的修飾を受ける。
・酸化的に修飾された LDLはマクロファージにより貪食される。
・マクロファージに取り込まれたコレステロールは HDLにより運び去られるが、細胞内
に多量のコレステロールが蓄積すると泡沫細胞となる。
・泡沫細胞が集まった病変を脂肪斑という。
・脂肪斑は 10 歳代の大動脈でも散見され、動脈硬化の初期病変と考えられているが、
まだ可逆的病変である。
線維斑
・泡沫細胞が崩壊し、コレステロールが細胞間質に沈着する。
・コレステロール沈着部位に炎症反応が起こり、内膜が線維性に肥厚(線維斑)する。
・炎症反応は血管内皮細胞の障害、中膜の平滑筋細胞の遊走・増殖などを引き起こす。
複合病変 ・線維斑に壊死、潰瘍、出血、石灰沈着、血栓形成など多彩病変が起こり、粥状硬化巣
が完成する。

臨床病態学 要点整理ノート
28
(2)脂質異常症と動脈硬化症
悪玉コレステ
ロール説
・Ⅱa、Ⅱb型(高 LDL-C血症)において動脈硬化症の発症頻度が高い。
超悪玉コレス
テロール説
・Ⅲ型(高 VLDL レムナント血症)では動脈硬化症が高頻度に見られる。
・VLDLレムナントから LDLへの変換が障害されると、血中の VLDLレムナントの上昇
とともに、小型・緻密 LDLの産生が増加する。
・小型・緻密 LDL は正常な LDL に比べて LDL 受容体との親和性が低く、代謝が遅い
ために血液中に長く停滞する。
・VLDL レムナントや小型・緻密 LDL が血液中に長く停滞すると酸化的修飾を受けや
すくなり、動脈壁の内膜に侵入して粥状硬化巣(動脈硬化症)の形成を促進する。
(3)インスリン抵抗性と脂質異常症
・日本人の高脂血症の特徴は、血清コレステロール値は正常範囲あるいは軽度上昇にとどまるが、高ト
リグリセリド血症、低 HDL-C血症、耐糖能異常、高血圧、内臓脂肪型肥満を高頻度に合併(メタボリ
ックシンドローム)していることが多い。
・これらの病態の中心にはインスリン抵抗性があると考えられている。
・インスリン抵抗性は脂肪細胞からの遊離脂肪酸(FFA)の放出を増加させ、肝臓での VLDL産生を促進
する。
・また、インスリンの作用不足により VLDL の代謝障害が生じるため、高トリグリセリド血症、低 HDL-
C血症、高 VLDL レムナント血症を引き起こし、小型・緻密 LDLが増加すると考えられている。
5.診断
(1)症状
・結節性黄色腫:コレステロールを主成分とする脂質が皮膚や皮下組織に沈着したもので、眼瞼、肘や
膝の関節の伸側などに多い。主に家族性高コレステロール血症(Ⅱa型)でみられる。
・発疹性黄色腫:キロミクロンが組織に蓄積したもので、臀部から腰背部に直径 2~3mm のオレンジ色
から淡赤色の丘状発疹が出現する。キロミクロンが増加するⅠ型、Ⅴ型高脂血症でみられる。
・手掌線条黄色腫:Ⅲ型でみられる。
・アキレス腱肥厚:コレステロールがアキレス腱に沈着して肥厚。Ⅱa型でみられる。
・角膜輪:角膜周辺部にコレステロールが沈着したもので、白~黄白色の輪状の混濁が見られる。加齢
によって起こる老人環と同じであるが、家族性高コレステロール血症(Ⅱa型)では 50歳以下の若年
でもみられる。
・急性膵炎:キロミクロンが増加するⅠ型、Ⅴ型高脂血症でみられる。
・動脈硬化症:Ⅱa型、Ⅱb型、Ⅲ型、Ⅳ型に多い。
Ⅳ型では、しばしは耐糖能異常、高血圧、肥満、高尿酸血症を合併する。

臨床病態学 要点整理ノート
29
(2)検査
・脂質プロフィール:総コレステロール(TC)
トリグリセリド(TG)
HDLコレステロール(HDL-C)
・LDLコレステロール(LDL-C):直接測定または LDL-C=TC-HDL-C-TG÷5
・アポリポタンパク質(AⅠ、AⅡ、B、CⅡ、CⅢ、E)
・リポタンパク(a)(Lp(a)):高分子糖タンパク質であるアポ(a)と LDL様粒子の複合体。Lp(a)の血
中濃度の増加と動脈硬化性疾患の関連が指摘されている。LDL よりも酸化的修飾を受けやすいことや
血栓形成を促進することが動脈硬化症を促進すると考えられている。
・電気泳動法による血清リポタンパク質の分画
α分画が HDLに、β分画が LDLに、Pre-分画が VLDLに、原点がキロミクロンに相当
・その他、リポタンパク質リパーゼ(LPL)、レムナント様リポタンパク質コレステロール(RLPコレス
テロール)
(3)診断基準(動脈硬化性疾患ガイドライン 2014年版)
1)スクリーニングのための診断基準(空腹時採血)
・診断基準は冠動脈疾患を起こす頻度が増加する閾値として決められている。
LDL コレステロール 140㎎/㎗以上 高 LDLコレステロール血症
120~139㎎/㎗ 境界域高 LDLコレステロール血症
HDL コレステロール 40㎎/㎗未満 低 HDLコレステロール血症
トリグリセライド 150㎎/㎗以上 高トリグリセリド血症
Non-HDL コレステロール 170㎎/㎗以上 高 non-HDLコレステロール血症
150~169㎎/㎗ 境界域 non-HDLコレステロール血症
・10時間以上の絶食を「空腹時」とする。
・スクリーニングで境界域 LDL-C血症、境界域 non-HDL-C血症を示した場合は、高リスク病態がないか
検討し、治療の必要性を考慮する。
6.治療
(1)リスク区分別脂質管理目標(動脈硬化性疾患ガイドライン 2014年版)
治療方針の原則 管理区分 脂質管理目標値(㎎/㎗)
LDL-C non HDL-C TG HDL-C
一次予防
まず生活習慣の改善を行っ
た後、薬物治療の適応を
考慮する
低リスク <160 <190
<150 ≧40
中リスク <140 <170
高リスク <120 <150
二次予防
生活習慣の改善とともに薬
物療法を考慮する
冠動脈疾患の既往 <100
(<70)*
<130
(<100)*
*家族性高コレステロール血症、急性冠症候群、他の高リスク状態を合併する糖尿病の時に考慮する。
(2)生活習慣の改善(動脈硬化性疾患診療ガイドライン 2014年版)
・禁煙し、受動喫煙を回避する。
・過食と身体活動不足に注意し、適正な体重を維持する。
・肉の脂身、動物脂、鶏卵、果糖を含む加工食品の大量摂取を控える。
・魚、緑黄色野菜を含めた野菜、海藻、大豆製品、未精製穀類の摂取量を増やす。
・糖質含有量の少ない果物を適度に摂取する。
・アルコールの過剰摂取を控える。
・中等度以上の有酸素運動を、毎日合計 30分以上を目標に実施する。

臨床病態学 要点整理ノート
30
(3)食事療法
1)血清脂質に影響する栄養素
・過剰な脂質:飽和脂肪酸は肝臓の LDL受容体活性を低下させるので、血液中に LDLが停滞するといわ
れている。飽和脂肪酸のコレステロール増加作用は、不飽和脂肪酸のコレステロール低下作用の 2倍
である。食事コレステロール摂取の血清コレステロールに対する効果は、不変または上昇で個人差が
ある。
脂肪酸の種類 VLDL LDL HDL
飽和脂肪酸 → ↑↑ ↑
一価不飽和脂肪酸 → ↓ ↑
n-6 系多価不飽和脂肪酸 → ↓↓ ↑(過剰になると↓)
n-3 系多価不飽和脂肪酸 ↓↓ ↑ ↑(過剰になると↓)
トランス型不飽和脂肪酸 → ↑↑ →
・過剰な糖質:TGを上昇させ、HDL-Cを低下させる。
過剰なショ糖・果物(フルクトース)は脂肪酸合成を促進する。
・大豆タンパク(レジスタント・タンパク質):血清コレステロールを低下させる。
・水溶性食物繊維(ペクチン、グルコマンナンなど):小腸での胆汁酸、コレステロールの吸収を抑制
してコレステロールの異化を促進する。
・アルコール:TGを上昇させる。適量であれば HDL-Cを上昇させる。
2)動脈硬化性疾患予防のための食事(動脈硬化性疾患診療ガイドライン 2014年版)
・総エネルギー摂取量(kcal/日)は、一般に標準体重(kg、(身長(m))2×22)×身体活動量(軽い
労作で 25~30、普通の労作で 30~35、重い労作で 35~)とする。
・脂肪エネルギー比率を 20~25%、飽和脂肪酸を 4.5%以上 7%未満、コレステロール摂取量を 200 ㎎
/日未満に抑える。
・n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取を増やす。
・工業由来のトランス脂肪酸の摂取を控える。
・炭水化物エネルギー比率を 50~60%とし、食物繊維の摂取を増やす。
・食塩の摂取は 6ℊ/日未満を目標にする。
・アルコールの摂取を 25ℊ/日以下に抑える。
(4)運動療法の効果と実施
・運動療法は筋肉組織の LPL 活性を増加させ、キロミクロン、VLDL の異化を促進することにより、TGを
低下させ、HDL-Cを増加させる。
・運動療法は、インスリン抵抗性を改善する。
・運動療法は、代謝症候群や動脈硬化症の予防・治療効果がある。
・運動療法自体は、TGの低下には有効だが、LDL-Cには影響しない。
運動療法の結果、体重減少があると、LDL-Cは低下する。
・運動療法として軽い有酸素運動を毎日 30分以上続けることが推奨される。
・運動療法の実施に際しては定期的にメディカルチェックを行う。

臨床病態学 要点整理ノート
31
(5)薬物療法
1)LDL-C低下を目的とした薬物
①HMG-CoA還元酵素阻害薬(3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase inhibitor、スタチン)
・細胞内のコレステロール合成を抑制→LDL受容体による細胞内への LDL-C取り込みを促進→血中
LDL-C減少(最も効果的な薬剤)
・肝臓のコレステロール合成抑制→VLDL 分泌抑制→血中 TG減少
・LDL-Cを 18~55%低下、HDL-Cを 5~15%増加、TGを 7~30%低下
・副作用:横紋筋融解症(腎機能低下時にゲムフィブロジルとの併用で出現)、胃腸症状、肝障害、催
奇形性
②陰イオン交換樹脂(レジン)
・胆汁酸と結合して便中排泄を増加→胆汁酸の腸肝循環を抑制→コレステロールから胆汁酸への異化
を促進→体内コレステロール・プールの減少、肝臓 LDL受容体の増加→血中 LDL-Cの低下
・肝臓コレステロール合成を増強する。
・スタチンと併用で LDL-C低下効果が増強する。
・LDL-Cを 15~30%低下、HDL-Cを 3~5%増加、TGは変化なし。
・副作用:腹部膨満感、便秘、脂溶性ビタミンの吸収障害
・スタチン、ジギタリス、ワーファリン、サイアザイド利尿薬、甲状腺製剤を吸着するので、間隔を
あけて内服する。
③小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)
・小腸のコレステロールトランスポーター(NPC1L1)を阻害する。
・コレステロール吸収を選択的に阻害→脂溶性ビタミンの吸収には影響しない。
・LDL-Cを約 11%低下(スタチンと併用で 35~50%低下)、HDL-Cを 8~9%増加、TGを 20~30%低下
・副作用:横紋筋融解症
④ニコチン酸誘導体
・ホルモン感受性リパーゼの活性化抑制(脂肪酸動員抑制)→肝臓でのリポタンパク質合成抑制
→VLDL、LDL療法低下
・アポ A-Ⅰ異化抑制→HDL上昇
・Lp(a)低下効果
・LDL-Cを 5~25%低下、HDL-Cを 15~35%増加、TGを 20~50%低下
・副作用:皮膚掻痒感、顔面紅潮、頭痛、ほてり、インスリン抵抗性悪化(高血糖)、高尿酸血症、肝
障害
⑤プロブコール
・LDLの異化促進、胆汁中へコレステロール排泄促進→LDL-C低下
・ABCA-1抑制、CETP 亢進、SR-B1 亢進→HDL-C低下
・抗酸化作用
・副作用:消化器症状、肝障害、発疹、心電図異常
⑥PCSK9 阻害薬(ヒト抗 PCSK9モノクローナル抗体薬)
・肝臓 LDL受容体の分解に関わる PCSK9(proprotein convertase subtilisin/kexin type 9、プロた
んぱく転換酵素サブチリシン/ケキシン 9)の活性を阻害し、LDL受容体のリサイクルを増加させて
血中 LDLを減少させる。
・家族性高コレステロール血症または心血管イベントの発症のリスクが高く、最大容量のすたちん治
療下でも血中コレステロール値の低下が不十分な場合に、投与適応になる。
・2週間に 1回の皮下注射で LDL-Cを 70~75%低下、HDL-Cを 10~15%増加、TGを 20~25%低下

臨床病態学 要点整理ノート
32
⑦MTP阻害薬
・MTP(microsomal triglyceride transfer protein、ミクロソームトリグリセライド転送たんぱく)
は、VLDLとキロミクロンの合成・分泌に関わるたんぱく質である。
・MTP阻害薬は、VLDL 合成を抑制するもとにより、VLDL から LDLへの変換を減少させ、結果として血
中 LDLを減少させる。
2)トリグリセリド(TG)低下を目的とした薬物
⑧フィブラート系薬
・PPAR-α活性化→脂肪酸β酸化亢進、肝臓 TG合成低下、リポタンパク質リパーゼ合成増加、VLDLか
ら LDLへの転化促進、アポ A-Ⅰ、A-Ⅱ増加による HDL増加
・VLDL 異化促進(筋肉の LPL活性増加)
・LDL-Cを 5~20%低下、HDL-Cを 10~20%増加、TGを 20~50%低下
・横紋筋融解症(腎機能低下時、スタチン系薬と併用時に出現頻度増加)、肝障害
④ニコチン酸誘導体
・上述
⑨エイコサペンタエン酸(eicosapentaenoic acid, EPA)
・肝臓での VLDL 合成抑制→TG低下
・抗血小板作用、抗炎症作用
・副作用:出血傾向、発疹
(6)LDLアフェレーシス
・体外循環により、血液から LDL を取り除く治療法である。
・ホモ型あるいは重症のヘテロ型の家族性高コレステロール血症で、総コレステロールが 400 ㎎/㎗を
超え、黄色腫を伴い、冠動脈病変が明らかな場合が適応となる。

臨床病態学 要点整理ノート
33
4.高尿酸血症・痛風
1.プリン代謝と尿酸の生成
(1)プリンリボヌクレオチドの生合成と尿酸の生成
1)プリンリボヌクレオチドの生合成と尿酸の生成
・プリン塩基には、アデニンとグアニンがある。
・プリンリボヌクレオシドには、アデノシンとグアノシンがある。
・アデノシンは、アデニンデアミナーゼの作用でイノシンとなり、続いてプリンヌクレオシドホスホリ
ラーゼの作用でヒポキサンチンとなり、さらにキサンチンオキシダーゼの作用でキサンチンになる。
・グアノシンは、プリンヌクレオシドホスホリラーゼの作用でグアニンとなり、続いてグアニンデアミ
ナーゼの作用でキサンチンになる。
・キサンチンは、キサンチンオキシダーゼの作用で尿酸になる。
(2)尿酸の排泄
・血液中の尿酸は糸球体で濾過された後、尿細管での再吸収・分泌を経て、最終的に濾過された 10%が
尿中に分泌される。
(3)血液・体液中および尿中の尿酸
・尿酸は、血液中では 98%が Na 塩として存在し約 7.0㎎/㎗で飽和する。
それ以上の濃度では、過飽和となって溶けている(80㎎/㎗まで溶解可能)。
血液中には、タンパク質など何らかの安定化因子が存在すると考えられている。
・血清尿酸濃度は、男性では加齢とともに上昇する。
・女性は、男性より低値である。
女性ホルモンは尿酸値上昇に抑制的に働く。
・尿中では、尿素、タンパク質、ムコ多糖類などの作用でより溶けやすくなる。
尿中での溶解度は、酸性で低下する。
pH5.0では 6~15 ㎎/㎗で飽和するが、pH7.0では 158~200㎎/㎗で飽和する。

臨床病態学 要点整理ノート
34
2.病態
(1)定義
・痛風とは、核酸に含まれるプリン体の代謝異常による高尿酸血症を基礎病態とし、尿酸塩結晶に起因
する急性関節周囲炎(痛風発作)と腎障害(痛風腎、尿酸結石)を主症状とする疾患である。
・高尿酸血症には、肥満、高脂血症、糖尿病、高血圧など生活習慣病が高率に合併する。
・男性の高尿酸血症の頻度は、約 25%である。30歳台でもっとも多く、約 30%に達する。
男性の痛風の頻度は、1~2%である。
・女性の痛風は閉経後にみられ、閉経前の女性ではまれである。
女性ホルモンは、尿酸排泄能を高める。
・死因は、以前は腎不全による尿毒症が多かったが、現在は、動脈硬化症の合併率高く、虚血性心疾患、
脳血管障害による死亡が増加している。
(2)分類
1)血液中の尿酸が増加するメカニズムによる分類
尿酸産生亢進型(11%)
尿酸排泄低下型(56%)
混合型(29%)
2)原因による分類
・一次性高尿酸血症:尿酸代謝の異常によるが、ほとんどは原因不明
・遺伝性高尿酸血症:Lesch-Nyhan病(サルベージ経路の酵素欠損によるもので、伴性劣性遺伝(X染色
体)する)
・二次性高尿酸血症:腎不全(尿酸排泄の減少)、白血病(腫瘍細胞の崩壊による核酸分解の増加)
3)高尿酸血症の発症に関係する生活習慣
飲酒
・アルコール飲料(ビールなど)に含まれるプリン体の摂取が増加ずる。
・アルコールから酢酸ができアセチル-CoAのなる過程で ATPが消費されプリン体の産生が
増加する。
・アルコール代謝は NADHを増加し、ピルビン酸から乳酸の産生が増加する。
エタノールは、アルコールデヒドロゲナーゼとアルデヒドデヒドロゲナーゼの作用に
よりアセチル CoA に代謝される。
CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+
CH3CHO +NAD+ + CoA → アセチル CoA + NADH + H+
この時、細胞内の NADHが増加し、以下の反応を促進して乳酸の産生を増加させる。
ピルビン酸 + NADH + H+ → 乳酸 + NAD+
・乳酸産生増加は腎臓からの尿酸排泄低下を引き起こす。
乳酸と尿酸は、尿細管の交換輸送体(URAT1)で反対方向に輸送される。
尿細管上皮内の乳酸が増加すると、URAT1 を介した乳酸排泄が増加し、それに伴って
尿酸の再吸収が増加する。
肥満
・内臓脂肪の蓄積は、門脈の遊離脂肪酸濃度を上昇させ、肝臓でのトリグリセリド合成が
増加する。
・その結果、NADPH 合成が増加するので、ペントース・リン酸回路が亢進してプリン体の産
生が増加する。
・インスリン抵抗性による高インスリン血症は、尿細管からの尿酸排泄を低下させる。
・高インスリン血症は尿細管のナトリウム再吸収を促進する。この時、URAT1 が共役して
尿酸の再吸収を促進する。
高血圧 ・糸球体濾過率が低下して尿酸排泄が低下する。
・降圧薬(利尿剤)により、尿酸の再吸収が増加する。
糖尿病 ・インスリン抵抗性、腎症合併により尿酸排泄が低下する。

臨床病態学 要点整理ノート
35
3.診断
(1)症状
・痛風結節:尿酸塩が耳介、関節周辺に沈着。粟粒大から大豆大の無痛性の結節を作る。
・痛風発作
尿酸塩の針状結晶が関節腔の壁に沈着し、それがはがれて関節腔に広がったときに、白血球が血症
を貪食するために集まってきて急性関節炎を起こす。
第一中足趾関節に好発、疼痛は 24時間で頂点に達し、10日以内に自然緩解する。
過度の運動(特に無酸素運動)、外傷、過食、過剰な飲酒などが急性発作の誘因となる。
急激に高尿酸血症を改善すると、発作が誘発されることがある。
発作中に尿酸低下薬を使用して尿酸値を下げると、発作が増強・長期化することがある。
・その他:痛風腎、腎機能低下、腎不全、尿路結石など。
(2)検査
・血清尿酸値 7.0㎎/㎗以上
・高尿酸血症の病型分類
尿中尿酸排泄量(EUA)(㎎/㎏/時) 尿酸の産生量を表す。
=尿中尿酸濃度×60 分尿量÷体重
尿酸クリアランス(CUA)(㎖/分) 尿酸の排泄能力を表す。
=尿中尿酸濃度×60 分尿量÷血漿尿酸濃度×1.73÷体表面積
病型 EUA CUA
産生過剰型 >0.51 および ≧7.3
排泄低下型 <0.48 あるいは <7.3
混合型 >0.51 および <7.3
・%尿酸クリアランス(CUA÷Ccr×100)
基準範囲 4~14%(4%以下は排泄低下、14%以上は産生過剰)
・尿中尿酸/クレアチニン比(0.8 以上ならば尿酸産生過剰)
4.治療
(1)治療指針(日本痛風・核酸代謝学会、高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第 2版、2010)
・血清尿酸値 7.0㎎/㎗以上で、痛風の症状があれば薬物療法を考慮する。
・血清尿酸値 8.0㎎/㎗未満であれは、生活指導のみで経過を見る。
・血清尿酸値 8.0㎎/㎗以上で、合併症があれば薬物療法を考慮する。
・血清尿酸値 9.0㎎/㎗未満で、合併症がなければ、生活指導のみで経過を見る。
・合併症がなくても、血清尿酸値 9.0 ㎎/㎗以上であれば薬物療法を考慮する。
・血清尿酸値の治療目標は、6.0㎎/㎗以下である。
(2)食事療法
適正体重の維持 総エネルギーの適正化、バランスのよい食事
プリン体制限 ・高プリン食品(100ℊあたりプリン体 200㎎以上含むもの)を避ける。
・プリン体の 1日の摂取量は、400㎎以下とし、極端なプリン体制限はしない。
アルコール制限 ・日本酒なら 1合未満、ビールなら 500㎖未満、ウイスキーならダブル 60㎖未満
・禁酒日を週に 2日以上もうける。
ショ糖・果糖の
過剰摂取の制限
・ショ糖・果糖の摂取量に比例して、血清尿酸値は上昇する。
・果糖の過剰摂取は、尿路結石の形成を促進する。

臨床病態学 要点整理ノート
36
(3)尿路管理
・1 日 2,000 ㎖の尿量を保つように指導し、就寝前の飲水も勧めて尿が濃縮するのを避ける。
・発汗時、運動時には飲水を促す。
・海草、野菜など、尿のアルカリ化に効果がある食品(アルカリ性食品)を勧める。
・尿アルカリ化薬(重曹、クエン酸 K・クエン酸 Na配合製剤)を必要に応じて使用する。
(4)生活指導
・適度な運動(有酸素運動)を行う。
・ストレスの解消に心がける。
・メタボリックシンドロームの合併に注意する。
(5)薬物療法
尿酸排泄促進薬
(ベンズブロマ
ロン、プロベ
ネシド)
・尿酸排泄低下型で使用する。
・尿細管での尿酸再吸収を阻害し尿酸排泄を促進する。
・副作用:尿路結石症、胃腸障害、劇症肝炎など
・尿路結石を予防するために尿アルカリ化薬を併用する。
・尿酸産生過剰型で使用すると、尿酸結石の頻度が高まる。
尿酸生成抑制薬
(アロプリノー
ル、フェブキ
ソスタット)
・尿酸産生亢進型で使用する。
・キサンチン酸化酵素を阻害して、ヒポキサンチン、キサンチンから尿酸への酸化
が抑制され、尿酸の生成が減少する。
・ヒポキサンチンとキサンチンが蓄積するが有害ではなく、PRPP 消費増加によりプ
リン体生成抑制効果もある。
・副作用:皮疹、中毒症候群、骨髄抑制など。
・尿酸排泄低下型で使用するとアロプリノールの代謝産物であるオキシプリノー
ルの排泄が障害されて副作用の頻度が高くなる。
疼痛に対する
治療薬
・コルヒチン:細胞内の微細小管に結合することにより多核白血球が炎症部位へ遊
走するのを阻害する。
足がムズムズする前兆症状の時期に使用すると有効である。
副作用:下痢、脱毛、骨髄抑制
・非ステロイド系抗炎症薬:痛みが強く、コルヒチンが無効な時に使用する。
・副腎皮質ステロイド薬:上記薬剤が、使用できないか、無効な時に使用する。

臨床病態学 要点整理ノート
37
5.先天性代謝異常症
1.先天性代謝異常症の考え方
・先天性代謝異常症は、酵素欠損により生じる。
・症状は、本来の生成物の不足による症状と、副生成物の過剰産生による症状が出現する。
2.新生児マススクリーニング
・1977 年 先天性代謝異常症(inborn errors of metabolism)のマススクリーニングを開始
フェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症、ホモシスチン尿症、カラクトース血症、ヒスチジン
血症の 5疾患
・1979 年 クレチン症のマススクリーニング開始(6疾患)
・1988 年 先天性副腎過形成症のマススクリーニング開始(7疾患)
・1992 年 ヒスチジン血症を先天性代謝異常症のマススクリーニングから除外(6疾患)
・2011 年 タンデム型質量分析計を使ったタンデムマス・スクリーニング法が取り入れられ、対象疾患
は 19疾患になった。
・アミノ酸代謝異常:フェニルケトン尿症、ホモシスチン尿症、メープルシロップ尿症(楓糖尿症)、
シトルリン血症 I型、アルギニノコハク酸尿症
・有機酸代謝異常症:メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症、イソ吉草酸血症、メチルクロトニ
ルグリシン尿症、ヒドロキシメチルグルタル酸血症、複合カルボキシラーゼ欠損症、グルタル酸
血症 1型
・脂肪酸代謝異常症:中鎖アシル CoA 脱水素酵素欠損症(MCAD欠損症)、極長鎖アシル CoA脱水素
酵素欠損症(VLCAD欠損症)、三頭酵素/長鎖 3-ヒドロキシアシル CoA脱水素酵素欠損症(TFP/LCHAD
欠損症)、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-1欠損症(CPT-1欠損症)
・内分泌疾患:先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)、先天性副腎皮質過形成
・糖質代謝異常症:ガラクトース血症
3.フェニルケトン尿症(phenylketonuria)
・原因:フェニルアラニン水酸化酵素の欠損(フェニルアラニン→チロシン)
常染色体劣性遺伝(新生児 8万人に 1人)
・病態:チロシン不足→甲状腺ホルモン不足→身体発育障害
→メラニン不足→赤毛,白皮症
→DOPA,エピネフリン不足→精神発達の障害
フェニルアラニン蓄積→フェニールピルビン酸、フェニル酢酸の尿中排泄増加(カビ様尿臭)
・食事療法
診断後直ちに、無フェニルアラニンミルクまたは低フェニルアラニン治療乳を開始する。
血中フェニルアラニン濃度を 2~4㎎/㎗程度に維持する。
離乳開始後は、治療乳を中心にした低たんぱく食とする。
1日のエネルギーは、健常児と同等にする。
たんぱく質は所要量を確保するが、大部分は治療乳から摂取する。
フェニルアラニンは必須アミノ酸なので完全除去しない。
発育に必要なフェニルアラニン最低量は 15~30㎎/㎏/日である。

臨床病態学 要点整理ノート
38
低タンパク食であるが、たんぱく質の不足分は、フェニルアラニンを除いた治療乳や、アミノ酸粉
末で補い、血中フェニルアラニン濃度を適正に保つように投与する。
4.ヒスチジン血症(histidinemia)
・原因:ヒスチダーゼの欠損(ヒスチジン→ウロカニン酸)
常染色体劣性遺伝(新生児 8,000 人に 1人)
・病態:高ヒスチジン血症
ヒスチジンとイミダゾール代謝産物の尿中排泄増加
一部に知能障害、言語障害が出現するが、高ヒスチジン血症と無関係
・治療:以前:低ヒスチジン食
現在:無治療(新生児マススクリーニングから除外されている)
5.ホモシスチン尿症(homocystinuria)
・原因:シスタチオニン合成酵素の欠損(ホモシステイン+セリン→シスタチオニン)
常染色体劣性遺伝(新生児 20万人に 1人)
・病態:ホモシステイン蓄積→血中ホモシスチン増加→ホモシスチンの尿中排泄増加
→血中メチオニン増加
シスタチオニン不足→システイン不足
水晶体脱臼、骨粗鬆症、長身、くも状指、精神運動発達遅延、痙攣、血栓塞栓症
・治療:低メチオニン・高シスチン食
ビタミン B6反応型では VB6大量療法(500㎎/日)

臨床病態学 要点整理ノート
39
6.メープルシロップ尿症(maple syrup urine disease)
・原因:分岐鎖ケト酸脱水素酵素複合体の欠損(ケト酸→アシル CoA)
常染色体劣性遺伝(新生児 50万人に 1人)
・病態:ケト酸の蓄積 → 尿中排泄(楓(メープル)シロップ臭)
生後 1~2週から哺乳困難、痙攣、後弓反張、神経障害、低血糖、ケトアシドーシス
・治療:ロイシン、イソロイシン、バリン制限食
7.ガラクトース血症(galactosemia)
・原因:ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼの欠損
(ガラクトース-1-リン酸+UDP-グルコース
→UDP-ガラクトース+グルコース-1-リン酸)
常染色体劣性遺伝(新生児 4万人に 1人)
・病態:ガラクトース、ガラクトース-1-リン酸が蓄積 → 血中、尿中濃度増加
嘔吐、下痢、黄疸、肝硬変、白内障、知能障害
・治療:乳糖除去食
8.糖原病(glycogen storage disease)
・Ⅰ型(von Gierke 病) もっとも多い。
原因:グルコース‐6‐ホスファターゼの欠損
症状:肝臓と腎臓にグリコーゲンが蓄積、低血糖、高乳酸血症
治療:低血糖予防のため、高糖質の頻回食とする。
ガラクトース(乳糖に含まれる)、フルクトース(ショ糖に含まれる)は、グルコースとし
て利用できず、乳酸産生を増加させるので、控える。
9.ウィルソン病(Wilson disease)
・細胞内銅輸送たんぱく質の異常により、組織に銅が沈着する。
・肝硬変、錐体外路症状、角膜のカイザー‐フライシャー輪が 3大症状である。
・セルロプラスミン(銅輸送たんぱく質)の合成障害により、血中セルロプラスミン値は低値になる。
・治療には、銅キレート薬を使用する。

臨床病態学 要点整理ノート
40
6.胃腸疾患
1.胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease, GERD)
(1)病態
・胃液や十二指腸液の消化液が食道内に逆流して、食道粘膜を障害する。
・原因:下部食道括約筋部圧の低下、腹圧の上昇、食道裂孔ヘルニアなど
・高脂肪食が胃排泄速度を遅延させる機序として、十二指腸に流入した脂肪の刺激により分泌されるコ
レシストキニンが胃の運動に対して抑制的に働く内分泌説や、迷走神経(副交感神経)の活動の抑制
する神経説などがある。
(2)診断
・症状:嚥下障害、嚥下痛、胸焼け、酸っぱいものの逆流(呑酸)、胸骨後部痛など
・検査:X線透視による造影剤の逆流、内視鏡による食道粘膜の発赤、びらん、潰瘍
(3)治療
・食事療法:過食を避け、一回の食事量を少なくする。
・下部食道括約筋部圧を低下させる要因(脂肪、菓子類、喫煙、飲酒)を避ける。
・胃酸分泌を亢進させる要因(アルコール、カフェイン、香辛料)を避ける。
・食後に、半座位を取る。
ファーラー位:上半身を 30~60 度起こした体位
セミファーラー位:上半身を 15~30 度起こした体位
・薬物療法:H2ブロッカーやプロトンポンプ阻害薬など胃酸分泌抑制薬
・手術療法:内科的治療で改善しない場合
2.急性胃炎(acute gastritis)
(1)病態
・急性の腹部症状があり、胃粘膜の急性炎症(粘膜の発赤、びらん、出血、潰瘍)を伴う。
・急性胃粘膜病変(acute gastric mucosal lesion):内視鏡検査により、表層性胃炎(粘膜の発赤、
浮腫を呈するもの)、びらん性胃炎、出血性胃炎の混在が確認されたもの。
・男性に多い。(2~3:1)
・原因を特定しやすく、原因が除かれると速やかに症状が消失し、短期間で治癒する。
非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)など薬剤(約 50%)、重症火傷、頭部外傷、外科手術などによ
るストレス(約 20%)、アルコール(約 10%)が多い。その他、酸・アルカリなど腐食性物質、異
物、寄生虫(アニサキス)、細菌やウイルスの感染など
・若年者ではストレスによるもの、高齢者では薬剤によるものが多い。
(2)診断
・症状:急激に発症する上腹部痛、心窩部不快感、悪心、嘔吐、吐血、下血など
・検査:胃内視鏡(最も有効)、胃 X線透視、便潜血反応など
(3)治療
1)原因の除去
2)食事療法(原則は、胃の安静)
・症状が強いとき:絶食(当日)→湯冷まし、番茶、流動食(翌日)→軟食(3~5日)→常食
・症状があるうちは糖質中心の庇護食(低脂肪、低残渣、易消化、非刺激性の食事)
・脂質は、乳化脂肪(胃内停滞時間を短くするため)を使用する。

臨床病態学 要点整理ノート
41
3)薬物療法
・軽症:胃粘膜保護剤(スクラルファート)(病巣部を被覆保護)
・中等症以上:胃酸分泌抑制薬(H2受容体拮抗薬、プロトンポンプ阻害剤)
・重傷の場合や大量の出血があれば、輸液、輸血、外科的治療が必要なこともある。
3.慢性胃炎(chronic gastritis)
(1)病態
・慢性胃炎は、病理組織学的診断名であり、胃粘膜の持続性の炎症性変化のことをいう。表層性胃炎に
始まり、萎縮性胃炎(胃粘膜固有腺の減少)を経て、胃萎縮に至る進行性非可逆性の過程をとる。
・自覚症状から診断する症候学的胃炎は、機能性ディスペプシア(functional dyspepsia)と呼ぶ。
・原因による分類と原因
A型胃炎
(約 10%)
・自己免疫疾患(抗壁細胞抗体、抗内因子抗体)による胃炎である。
・壁細胞の破壊により、キャッスル内因子の分泌が低下するので、ビタミン B12吸収
不良による悪性貧血を合併する。
B型胃炎
(約 90%)
・遺伝、加齢、アルコール、喫煙、H.ピロリなどが原因となる。このうち、H.ピロリが約 80%を占める。
・加齢とともに幽門腺領域から胃底腺領域に向かって進行する。
・病理学的分類
表層性胃炎 ・胃粘膜表層部に炎症細胞(リンパ球中心)が浸潤する。
・粘膜が肥厚した場合を肥厚性胃炎といい、一般に過酸性となる。
萎縮性胃炎 ・胃粘膜全層に炎症細胞(リンパ球中心)が浸潤する。
・胃腺の萎縮、粘膜の菲薄化があり、一般に低(無)酸性となる。
(2)診断
1)症状
・持続する上腹部不定愁訴(上腹部の痛み、不快感、食欲不振、悪心、胸焼けなど)
・表層性胃炎では、食直後(食事による胃酸分泌の増加)の心窩部痛が特徴である。
・A 型胃炎では、ビタミン B12不足による悪性貧血を合併する。
2)検査
・胃 X線透視、胃内視鏡、胃液検査
・貧血検査(悪性貧血)
3)機能性ディスペプシアの診断基準(RomeⅢ基準)
1つまたは複数の以下の症状がある。
・ひどい食後の腹部膨満感
・食後早期の腹満感(食べられない)
・心窩部痛
・心窩部の焼けるような感じ
症状の原因となる器質的疾患(消化性潰瘍、胃癌、逆流性食道炎など)がない。
診断の 6か月以前に発症し、3か月の症状持続
(3)治療
1)原因の除去
2)食事療法
・原則は、胃の負担を除くことである。過食を避け、規則正しい食生活を心がける。
・たんぱく質、ビタミン、ミネラルを十分に補給し、粘膜機能を改善させる。
・食物繊維、脂質など胃内停滞時間が長くなるものを控える。
・表層性胃炎(過酸性):アルコール、カフェインなど胃酸分泌を亢進させる食品を避ける。
・萎縮性胃炎(低酸性):少量の香辛料やアルコールは胃液の分泌を亢進するのでよい。

臨床病態学 要点整理ノート
42
3)薬物療法
・胃粘膜保護剤:スクラルファートなど
・胃酸分泌抑制剤:制酸剤、小量の H2受容体拮抗薬(胃潰瘍使用時の半量)
・悪性貧血になれば,ビタミン B12筋注
・H.ピロリ除菌療法
H.ピロリの感染が証明され、胃内視鏡検査により慢性胃炎の所見(ピロリ感染胃炎)があることが
確認されれば、ピロリ感染胃炎として、除菌治療が可能となった。(平成 25年 2月 21日承認)
4.胃十二指腸潰瘍(gastric ulcer and duodenal ulcer)(消化性潰瘍 peptic ulcer)
(1)概念
・胃酸および消化酵素ペプシンの消化作用により胃・十二指腸壁に欠損が生じるもの。
・欠損の深さにより,Ul-Ⅰ(粘膜内)、Ul-Ⅱ(粘膜下層)、Ul-Ⅲ(筋層)Ul-Ⅳ(筋層を超える)に
分類される。(Ul-Ⅰを「びらん」、Ul-Ⅱ以上を潰瘍という)
・胃潰瘍は、40~50 歳代の男性、十二指腸潰瘍は 30歳代の男性に多い。
・治療によりいったん治癒しても再発を繰り返す(潰瘍症)。
・罹患率は、成人の約 10%である。
・日本では、従来胃潰瘍の頻度が多かったが(2~3:1)、近年の食生活の欧米化に伴い十二指腸潰瘍の
発生率が増加している(都市部では 1:1)。
・原因の大半は、H.ピロリと非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)である。
(2)Sun and Shayの天秤説
1)攻撃因子
・胃酸:“No acid, no ulcer”といわれ、最も重要な攻撃因子である。特に十二指腸潰瘍では分泌が亢
進している。幽門部・胃角部の潰瘍では高酸性のことが、体部の潰瘍では低酸性のことが多い。
・ペプシン:胃粘膜や結合組織のたんぱく質を分解する。
・H.ピロリ:十二指腸潰瘍では 100%で、胃潰瘍では 80~90%で陽性。他の攻撃因子対する粘膜防御の
閾値を低下させ,潰瘍の治癒を遷延させる。
・非ステロイド系消炎鎮痛剤(NSAIDs):プロスタグランジン Eの産生を阻害して、粘膜防御機構を抑
制する。
・ガストリン:ガストリン産生腫瘍(Zolinger-Ellison 症候群)で、難治性の十二指腸潰瘍が出現する。
・迷走神経:手術、外傷、脳卒中など肉体的ストレスおよび精神的なストレス
2)防御因子
・粘液:胃粘膜は約 500mの粘液ゲル層で被われている。アルコールは粘液ゲルをはがす。
・重炭酸イオン:粘膜上皮から分泌され、粘液ゲル層内で H+を中和する。
・粘膜血流(微小循環):粘膜上皮に細胞に酸素や栄養素を供給。プロスタグランジン Eは粘膜血流を
増加させる。
・十二指腸ブレーク:胃酸が十二指腸に入るとセクレチンが分泌され、胃酸分泌を抑制する。
3)ヘリコバクター・ピロリ(H.ピロリ)
・従来,胃内は強酸性のため無菌と考えられてきたが、1983 年オーストラリアで、ヒト胃粘膜から H.ピロリが発見された。
・H.ピロリは発育が遅いために、通常の培養法では検出できなかったが、担当の研修医が培地をふらん
器の中に置き忘れて、イースターの休暇に入り、帰ってきてみたらコロニーが形成されていたことか
ら発見された。
・H.ピロリは、ウレアーゼ活性をもち、尿素を分解してアンモニアを発生させる。そのアンモニアによ
り胃酸(塩酸)を中和して胃内で生き延びる場所を確保している。
・研究者が自分で菌を飲んで胃炎発症、除菌により治癒を確認したことから、胃炎、胃潰瘍との関連が
指摘された。
・1994 年には WHO により H.ピロリを胃癌発ガン関与物質と認定された。食道癌は逆に発症率を低下さ
せるといわれている。

臨床病態学 要点整理ノート
43
・日本人では,40歳以降で 70~80%が感染している。
・不活性な球状構造で糞便や唾液に存在し、経口感染により胃内に入って活性ならせん上の桿菌となる
と考えられている。
(2)診断
1)症状
・上腹部痛、特に空腹時の心窩部痛(食事より軽快)は十二指腸潰瘍の特徴
・痛みは、鈍い、重苦しい鈍痛で、疝痛は少ない。潰瘍部に一致した部位に圧痛
・穿孔性の場合は背部痛をおこすことがある。その他、悪心、嘔吐、食欲不振など
・三大合併症
出血:吐血の場合は新鮮血またはコーヒー残渣様(血液が胃酸によりヘマチン化)の血液、下血の
場合はコールタール様の便(タール便)になる。
狭窄:瘢痕収縮によるもので、通過障害を起こす。(十二指腸潰瘍、幽門部潰瘍)
穿孔:腹膜腔への穿孔は、十二指腸潰瘍で多く、腹膜炎を起こす。
2)検査
・胃 X線透視、胃内視鏡
・胃酸分泌検査:基礎酸分泌量、最高酸分泌量、持続的 pHモニタリング
・H.ピロリの検出:胃液細菌培養,鏡検,迅速ウレアーゼ試験,尿素呼気試験,血清抗 H.ピロリ抗体、
便中 H.ピロリ抗原、PCR遺伝子診断法など
迅速ウレアーゼ試験:尿素を含む培地で胃組織を培養。アンモニアの発生を pHの変化で判定
尿素呼気試験:13Cでラベルした尿素を服用。発生した二酸化炭素が粘膜から吸収され、呼気中に排
泄されるのを測定
(3)治療
1)薬物療法
・初期治療:活動性の潰瘍を瘢痕治癒させるまでの治療。通常 2~3ヶ月で 90%が瘢痕治癒に至る。
・攻撃因子抑制薬(主体的)
胃酸分泌抑制薬:H2受容体拮抗薬(1980 年代)、プロトンポンプ阻害薬(1990年代)
その他、抗コリン薬、抗ガストリン薬、プロスタグランジン誘導体、制酸薬など。
・防御因子増強剤(補助的)
粘膜の被覆(スクラルファートなど)、粘液の分泌促進(テプレノンなど)、粘膜血流の改善(塩
酸セトラキサートなど)を促す薬剤を補助的に使用する。
・維持治療:再発防止のための治療
半量の H2受容体拮抗薬による維持療法が有効(再発率 25%)。
中止すると再発率増加(50~70%)。

臨床病態学 要点整理ノート
44
2)H.ピロリ除菌療法(2000年 11 月から保険適用開始)
・3 剤併用療法(LAC 療法)、1日 2回、7日間投与
プロトンポンプ阻害剤(ランソプラゾール 30㎎)
ペニシリン系抗生物質(アモキシシリン 750㎎)
マクロライド系抗生物質(クラリスロマイシン 200㎎)
・成功率:60~70%
・除菌療法の副作用
胃内に抗生物質は到達しにくいので、通常量の 1.5~2倍を 1~2週間投与する必要がある。
主な副作用は、下痢、味覚異常、耐性菌の出現、偽膜性腸炎、出血性腸炎などである。
除菌成功例では、胃酸分泌の回復により、胃食道逆流性症の発生が増加する。
3)食事療法
・出血、穿孔など合併症がない場合:以前は入院して厳重な庇護食を処方していたが、現在は特に制限
する必要ない。
・粘膜の修復促進:エネルギー・タンパク質・ビタミン・ミネラルが不足しないようにする。
・胃酸分泌抑制:アルコール、コーヒー、香辛料、炭酸飲料などを避ける。
・潰瘍面の庇護:物理的な刺激食品(熱い、冷たい、固い)を避ける。
脂肪、繊維など胃内滞留時間の長いものは避け、乳化脂肪を使用する。
・出血がある場合:絶食→止血後に流動食→軟食→常食
・日常生活・食生活を規則正しくし、ストレスを避けるようにする。喫煙は粘膜血流を障害し、潰瘍の
治癒を遅らせるので禁煙とする。
・合併症対策
出血:緊急内視鏡による止血(エタノール局注、クリップ止血など)、外科手術
穿孔:内科的保存療法(絶食、胃管挿入、H2ブロッカー)、外科手術
5.胃切除後症候群(ダンピング症候群 dumping syndromeと術後栄養障害)
(1)早期ダンピング症候群
・食物が直接空腸に流入→高浸透圧刺激と急激な拡張刺激→神経内分泌反応を引き起こす。
・食後 10~30分後に腹部症状:腹痛、悪心、嘔吐、腹鳴、下痢など
全身症状:動悸、発汗、冷や汗、めまい、呼吸困難、失神など
(2)晩期(後期)ダンピング症候群
・糖質の急速な吸収→高血糖(1時間以内)→インスリン過剰分泌→反応性低血糖
・食後 90分~3時間後:脱力感、めまい、冷や汗、動悸、手の震え、意識障害など低血糖症状が出現し、
30~40 分持続する。
(3)後期症候群(術後栄養障害)
・胃酸不足は、セクレチンの分泌低下、膵液分泌低下の原因となり、消化・吸収障害をもたらす。
・Fe3+から Fe2+への変換が低下するため、鉄の可溶性が低下して、鉄の吸収が低下するために鉄欠乏
性貧血が出現する。Fe3+は中性では難溶。酸性で溶解し Fe2+(中性で可溶)に還元されて十二指腸
で吸収される。
・カルシウムの溶解性が低下するので、吸収障害が起こり、骨粗鬆症や骨軟化症の原因となる。
・脂肪の消化吸収障害のために、ビタミン Dの吸収が障害され、骨粗鬆症や骨軟化症の原因となる。
・キャッスルの内因子の不足により、ビタミン B12 の吸収障害が起こり、悪性貧血(巨赤芽球性貧血)
が出現する。ビタミン B12は肝臓に 3~6年分貯蔵されているので、術後数年して出現する。
(4)逆流性食道炎
・食道下部には、胃液の逆流を防ぐ下部食道括約筋があるが、胃切除により下部食道括約筋の機能が障
害されると胃液や胆汁、膵液が食道に逆流して食道炎を起こす。

臨床病態学 要点整理ノート
45
(5)胃切除後症候群の治療
1)早期ダンピング症候群
・高浸透圧を押さえるため、糖質を控えて、たんぱく質、脂肪は十分に取る。
・1 回摂取量を少なくする(小量頻回食:1日 5~6食)。
・水分は食間に取る。
2)晩期(後期)ダンピング症候群
・糖質の摂取を控える。小量頻回食(1日 5~6食)
・食後 1~2時間に適当な間食をとる。
3)後期症候群
・鉄欠乏性貧血には、鉄剤、ビタミン Cを経口投与する。
・悪性貧血には、ビタミン B12を筋肉注射(非経口投与)する。
・骨粗鬆症・骨軟化症には、カルシウム製剤、ビタミン D3製剤を経口投与する。
6.たんぱく漏出性胃腸症
(1)病態
・血漿中のアルブミンが、胃や腸管の粘膜から管腔内に漏出し、低アルブミン血症をきたす症候群
・たんぱく質が漏出するメカニズム
腸リンパ管の異常 ・腸リンパ管の異常によりリンパ液の漏出。
・腸リンパ拡張症、うっ血性心不全、クローン病
毛細血管透過性亢進 ・毛細血管の透過性亢進によるタンパク質の漏出増加。
・アレルギー性胃腸炎、セリアック病、膠原病
消化管の潰瘍形成
・潰瘍からの出血や血漿の滲出。
・消化管の癌、感染性腸炎、炎症性腸疾患、メネトリエ病、セリアッ
ク病
・メネトリエ病:巨大肥厚性胃炎とも呼ばれ、胃粘膜のヒダが巨大になり大脳回のような肉眼所見を示
すものをいう。成因としてアルコールや喫煙との関連が指摘されている。
・セリアック病:小麦たんぱくのグルテンに対するアレルギー性腸炎であり、腸粘膜の萎縮により吸収
面積の縮小が起こる。
(2)診断
1)症状
・低アルブミン血症による全身の浮腫、胸水・腹水の貯留
・脂肪の吸収障害が強い場合は、脂肪便やテタニー(低 Ca血症によるけいれん)を生じることがある。
(未消化の脂肪は Ca と不溶性の塩を形成し、Caの吸収を阻害する)
2)検査
・たんぱく質漏出の証明には、便中へα1-アンチトリプシンの排泄を測定
・標識アルブミンを用いたシンチグラフィー(アルブミンの漏出の有無と部位の同定)
(3)治療
・原疾患の治療(セリアック病では無グルテン食)
・食事療法
栄養不足を防止するために高エネルギー、高たんぱく質食とする。
低脂肪食:長鎖脂肪酸はリンパ管から吸収され、リンパ管圧を上昇させるので、腸管の浮腫とたん
ぱく質の漏出を助長する。
15~40g/日の低脂肪食とする。
中鎖脂肪酸は門脈経由で吸収されるので、利用が勧められる。
栄養障害が強い場合は、経腸栄養法、経静脈栄養法を行う。
・薬物療法
浮腫に対しては利尿薬を投与する。

臨床病態学 要点整理ノート
46
7.クローン病(Crohn disease)
(1)病態
・原因不明の消化管の肉芽腫性炎症性疾患である。
・慢性に経過し、寛解と再燃を繰り返しつつ、徐々に進行する。
・昭和 51年、厚生省の特定疾患治療研究事業の対象疾患に指定された。
・欧米に比べて日本では少ないが、近年急増している。登録患者数は昭和 51年には 128人であったが、
平成 25年で約 38,271 人となっている。
・10~20歳代の男性に多い。男女比は 2~3:1である。
・区域性で単発あるいは多発する。
・口腔から肛門までいずれの部位でも起こりえるが、回盲部(約 50%)、結腸、直腸、肛門(35%)、
小腸、上部消化管(15%)が多い。
・非乾酪性類上皮細胞肉芽腫:回腸末端に好発し、小腸、大腸に非連続的に広がる。
・腸管粘膜病変:縦走潰瘍、敷石像、飛び越し病変を形成する。病変は粘膜にとどまらず、筋層、漿膜
に、さらに腸管周囲の脂肪組織まで及び、他臓器との瘻孔を形成する。
・細菌や食事抗原により刺激されたマクロファージが分泌する TNF-αにより炎症が引き起こされる。
・家族内発生があり、何らかの遺伝因子に、高たんぱく食、高脂肪食、腸内細菌叢の異常など環境因子
が加わって発症すると考えられている。
(2)診断
1)症状
・消化器症状:腹痛(70.1%)、下痢(67.9%)、肛門病変(54.7%)食欲低下(31.4%)、下血(27.0%)、
腹部膨満感(21.2%)など
・全身症状:体重減少(53.3%)、発熱(44.5%)、倦怠感(32.8%)など
・合併症:腸管合併症:腸管通過障害、瘻孔、出血、腸穿孔など
管外合併症:口内アフタ、皮膚炎、関節炎、胆石症、尿路結石など
2)検査
・小腸・大腸の X線検査、大腸内視鏡検査、生検など
・血液検査:鉄欠乏性貧血、低たんぱく血症、低コレステロール血症など低栄養状態を示す。
(3)治療
1)栄養療法
・栄養療法の目的は、腸管の安静、低栄養の防止、食餌性抗原(たんぱく質、脂肪)の負荷軽減による
病態の改善である。
・活動期:経腸成分栄養または中心静脈栄養により寛解導入する。
・寛解期:寛解導入後、普通の経口食に戻すと高率に再発するので、在宅経腸成分栄養(自己挿管法)
を行うのが原則である。その後、再燃しないことを確かめながら少しずつ経口食に移行する。
・スライド方式:成分栄養、半消化態栄養、経口食(低脂肪、低残渣食)を組み合わせる比率を症状に
合わせて変化させる。

臨床病態学 要点整理ノート
47
・経口食:高エネルギー食(35~40kcal/㎏/日):低栄養の予防、消化吸収のよいものを選ぶ。
摂取カロリーの不足は再発を促進する。
低たんぱく質・低脂肪食:食餌性抗原の負荷軽減
ただし、魚類のたんぱく質と脂質は問題が少ないので推奨される。
低脂肪食(20ℊ/日以下):n-3系脂肪酸摂取の比率を増やす。(抗炎症作用を期待)
食物繊維(10ℊ/日以下):腸管に狭窄があると腸閉塞を起こす可能性がある。
牛乳、乳製品:原則として禁止する。(乳糖不耐症を合併していることが多い)
・クローン病の栄養療法の原則は、成分栄養療法である。食事療法を行う場合は、易消化性、高エネル
ギー、低たんぱく、低脂肪、低線維食とする。たんぱく質を制限する理由は、食餌性抗原の負荷を軽
減するためである。窒素源の不足分はアミノ酸で補給する。アミノ酸は抗原性がないので安全に使用
できる。脂質は、20ℊ/日以下とし、抗炎症作用を期待して n-3系脂肪酸摂取の比率を増やす。食物繊
維は、腸管に狭窄があると腸閉塞を起こす可能性があるので、10ℊ/日以下に制限する。
2)薬物療法
・サラゾピリン、ペンタサ(5-アミノサリチル酸製剤)、副腎皮質ホルモン、免疫抑制剤など
・抗 TNF-α抗体製剤
TNF-αは、マクロファージやリンパ球などの免疫担当細胞から分泌されサイトカインの一種である。
抗 TNF-α抗体製剤は、血液中の TNF-αに結合して中和するだけでなく、免疫担当細胞に結合して TNF-
αの産生を抑制する作用がある。
3)手術療法
・栄養・薬物療法が無効のときは外科的治療を行う。
8.潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)
(1)病態
・原因不明の大腸粘膜のびまん性非特異性炎症性疾患である。
・慢性に経過し、寛解と再燃を繰り返す。
・昭和 50年、厚生省の特定疾患治療研究事業の対象疾患に指定された。
・欧米に比べて日本では少ないが、近年急増した。登録患者数は昭和 50 年には 965 人であったが、平
成 25年で約 155,116人となっている。
・20~30歳台に多いが、小児や 50歳以上にも見られる。男女比は 1:1である。
・主として粘膜と粘膜下層を侵し、びらん・潰瘍を形成する。
・直腸に始まり、連続性に大腸粘膜を侵し、大腸全体にびらんや潰瘍を形成する。
直腸炎型(35.6%)、左側大腸炎型(27.8%)、全大腸炎型(36.6%)、右側のみや区域性はまれ
・病変は粘膜、粘膜下層の非特異的炎症(うっ血、充血、びらん、潰瘍、主として好中球の浸潤、陰窩
膿瘍など)で、筋層・漿膜の変化は少ない。
・臨床経過により再燃寛解型(90%以上)、慢性維持型、急性劇症型、初回発作型に分類される。
・原因は不明(感染症説、食事アレルギー説、心身症説などがある)であるが、腸管免疫担当細胞の機
能異常が指摘されている。家族内発生が報告されており、何らかの遺伝因子が関与している。
(2)診断
1)症状
・消化器症状:粘血膿便、下痢、腹痛、食欲不振など
・全身症状:発熱、体重減少など
2)検査
・注腸検査、大腸内視鏡検査、生検など
・血液検査:炎症反応(白血球増加、CRP増加、赤沈亢進)、低タンパク血症、A/G比低下、貧血、70%
で抗好中球細胞質抗体が陽性など

臨床病態学 要点整理ノート
48
・合併症:腸管合併症:大腸癌、大腸穿孔、大量出血、中毒性巨大結腸症など。
腸管外合併症:関節炎、皮膚炎、肝臓の脂肪変性,胆管炎など。
(3)治療
1)薬物療法(治療の主体)
サラゾピリンⓇ
・消炎鎮痛剤(もともと慢性関節リュウマチの治療薬として開発された薬)
・大部分が吸収されることなく大腸に達し、腸内細菌によりサルファピリジン(SP)
と 5-アミノサリチル酸(5-ASA)に分解され、5-ASA(有効成分)の 2/3が大腸内
にとどまり糞便中に排泄される。
・SPは容易に吸収され、肝腎で代謝され尿中に排泄されるが、吸収された SPが溶
血、顆粒球減少、肝障害など主な副作用の原因とされる。
ペンタサⓇ
・サラゾピリンの有効活性成分 5-ASA製剤
・副作用は少ないが、小腸で吸収されるため大腸への到達はサラゾピリンより少な
い。
免疫抑制剤 ・副腎皮質ホルモン(プレドニンなど)、免疫抑制剤(シクロスポリン、6-MP)
2)栄養療法
・栄養療法の目的は、消化吸収障害による栄養不足を防止し、活動期の患者の症状を緩和することであ
る。
・食事療法の原則は、易消化性、高エネルギー、高たんぱく、低脂肪、低線維食とする。
腸管への負担、刺激を少なくするために消化吸収のよいものを選ぶ。
たんぱく質は、1日 1.2~1.5ℊ/㎏とする。
脂質は、下痢を悪化させるので 30~50ℊ/日に制限にする。
n-6 系多価不飽和脂肪酸は炎症を助長するので、n-3 系多価不飽和脂肪酸や中鎖脂肪酸の利用が勧
められる。
低線維にするために野菜の使用量を押さえる。(食物繊維 10ℊ/日に制限)
水溶性食物繊維は、下痢の軽減に有効である。
・しばしば乳糖不耐症を合併し、活動期には腸内醗酵を起こす可能性があるので、牛乳・乳製品を制限
または禁止する。
・重症例では経腸栄養、中心静脈栄養、劇症例では絶食、中心静脈栄養とする。
3)その他の治療法
・白血球除去療法:薬物療法無効の難治性潰瘍性大腸炎で有効とされている。
・外科的治療:重症、劇症で内科的治療が無効の時や穿孔、中毒性巨大結腸症、大量出血、癌化などの
合併症が認められた時には、手術療法行う。
9.過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome, IBS)
(1)病態
・腸管の機能的な過敏性を特徴とし、腸管の運動、緊張、分泌が亢進する結果、大腸内容物を移動させ
るための蠕動運動、協調運動がうまくできなくなり、便秘や下痢をきたす疾患で、器質的な病変を同
定できないものいう。
・原因不明で、内臓知覚過敏、心因性ストレス、自律神経失調症などが考えられている。
・症状により、下痢型(大腸全体が細かく痙攣して筒状になり、便の通過が早くなる)、便秘型(S 状
結腸の運動が亢進して内圧が上昇し、便の通過を阻害する)、交代型(便秘と下痢を繰り返す)に分
類される。
・便秘、下痢、腹痛、腹部膨満など消化器不定症状に加えて、頭痛、易疲労感、動悸、手足の冷えなど
自律神経症状を伴うことが多い。
・消化・吸収障害はなく、栄養障害は起こらない。
・診断のためには、便潜血検査、胃透視、注腸検査などにより器質的疾患を除外する必要がある。

臨床病態学 要点整理ノート
49
(2)治療
1)ストレスを避け、規則正しい生活習慣、食習慣、排便習慣に留意する。
2)食事療法
・栄養障害を起こさないので、特別な栄養療法は必要としない。
・水溶性食物繊維は、症状を改善させる作用があるので推奨される。
・過剰な脂質摂取は、胃排泄時間を延長させ、腹部膨満感を悪化させることがある。
・下痢型では、不溶性食物繊維の多い食品、香辛料、炭酸飲料、アルコール飲料、冷たいものなど刺激
物を避ける。
・便秘型では、高食物繊維食とする。
3)薬物療法
・消化器症状に対して下剤、止痢薬、整腸薬などを投与する。
・ポリカルボフィルカルシウム(ポリフルⓇ):高分子重合体で吸水・膨潤化作用により水溶便をゲル
化する。また、便秘型では便の水分含量を増加させて便通を良くする。
・マレイン酸トリメプチン(セレキノンⓇ):消化管平滑筋に直接作用して消化管運動を整える。
・塩酸ロペラミド(ロペミンⓇ):腸管の神経末端からのアセチルコリン放出を抑制して腸管の蠕動運
動を抑制することにより、強力な止痢作用を示す。
・精神症状に対して、抗うつ薬、抗不安薬など。
4)カウンセリング、心理療法など
10.短腸症候群
(1)定義と診断基準
・小腸を大量切除することにより、残った小腸が短くなる。
・小腸が短くなれば、栄養素を吸収する面積が狭くなるので、消化吸収障害が出現する。
・一般に、小腸の 70~80%が切除されると、消化吸収障害による栄養障害が出現する。
・小腸の長さは、小児で 200~250㎝、成人で 500~600㎝なので、短腸症候群の診断基準としては、小
児で 75㎝以下、成人で 150 ㎝以下が用いられている。
(2)原因疾患
・成人:上腸間膜動脈血栓症、クローン病、外傷、絞扼性イレウスが多い。
・小児:壊死性腸炎、中腸軸捻転、多発性小腸閉塞、ヒルシュスルング病が多い。
(3)症状
・消化吸収障害による消化管の症状と栄養障害による全身症状が出現する。
・消化管症状:下痢が最も多い
・全身症状:体重減少、脱水、PEM(protein-energy malnutrition)が出現する。
(4)治療
術後早期 ・下痢により多量の水と電解質が失われ、栄養素の消化吸収障害が著しいので、中
心静脈栄養法(TPN)を実施する。
術後 1~3か月 ・残存腸管の機能が亢進し、下痢が治まってくる。
・この時期は、経腸栄養法を導入することにより、残存腸管粘膜の機能改善を図る。
術後 3~12か月
・残存腸管の適応が進み、TPNから経腸栄養法への離脱を目指した治療が行われる。
・しかし、残存腸管の長さ、適応の程度により、すべての患者が TPNから離脱でき
るわけではない。
・その場合、在宅静脈栄養法が適応となる。

臨床病態学 要点整理ノート
50
・術後早期は、消化吸収機能が著しく低下するので、経口摂取はできないが、術後数か月のうちに、残
像腸管粘膜の再生、肥厚、機能亢進などによる適応が起こり、下痢を起こすことなく、経口摂取を行
うことが可能となる。
・経腸栄養法には、残存腸管の適応を促進する作用がある。
11.小児の消化器疾患
(1)消化不良症(dyspepsia)(乳児下痢症、diarrhea in infancy)
1)原因
・ウイルス性(ロタウイルス rotavirus、ノロウイルス norovirus)が多い。
・その他:細菌性、食事性、内分泌性、抗生物質など
2)症状
・下痢→塩基喪失→アシドーシス
・脱水→循環不全、意識障害
3)治療
・原因の除去
・軽症:調整乳の希釈、適切な水分補給、下痢が治まるまで低脂肪食
・中等症・重症:絶食、輸液
(2)周期性嘔吐(cyclic vomiting、acetonemic vomiting)(自家中毒、autointoxication)
1)原因
・原因不明
・2~10歳の情緒的に不安定な小児に多い。(心因反応?)
・脂肪酸の分解亢進→アセチル CoA過剰→ケトン体合成増加
2)症状
・嘔吐のくり返し、脱水、意識消失
・呼気にアセトン臭、尿中・血中ケトン体増加
3)治療
・嘔吐が強い時:糖を加えた輸液(ケトーシスの改善)
・嘔吐、ケトーシスなくなれば経口投与(糖質→タンパク質→脂質の順に増やす)

臨床病態学 要点整理ノート
51
7.肝胆膵疾患
1.急性肝炎(acute hepatitis)
(1)概念
・急激な肝細胞の壊死と炎症細胞の浸潤により肝機能が障害される状態をいう。
・食欲不振、吐き気、黄疸、全身倦怠感などの臨床症状を呈する。
・通常、6ヵ月以内に治癒する。
・50歳以下の若年に多く、男女比は 2:1で男性に多い。
・原因は肝炎ウイルスによるものが最も多い。
A型肝炎が 40%、B型肝炎が 25%、C型肝炎が 15%、診断不能が 20%
その他、アルコール、薬物中毒などが原因となる。
(2)肝炎ウイルスの種類と特徴
A 型肝炎ウイルス
・HAV(hepatitis A virus)、RNA ウイルス
・流行性肝炎。経口感染。開発途上国に多い。
・日本人の 40 歳以上では約半数が抗体を持つ。
・大部分は治癒し、慢性化することはまれである。
B 型肝炎ウイルス
・HBV(hepatitis B virus)、DNA ウイルス
・血清肝炎。血液、体液を介して感染する。
・母児感染の場合、持続感染(キャリア)になりやすい。
・母子感染で発症した場合 90%は治癒するが、10%は慢性肝炎となる
このうち 20~30%が肝硬変に移行、このうち 1 年に 5%が肝癌を発症
・成人後の感染の場合、慢性化はまれである。
C 型肝炎ウイルス
・HCV(hepatitis C virus)、RNA ウイルス
・輸血、性的接触で感染する。
・1989 年に発見されたが、それ以前に非 A 非 B 型肝炎(NANB)と呼ばれていた輸
血後肝炎の 90%は C 型とされる。
・持続感染者は 200 万人以上で、慢性肝炎、肝硬変に移行しやすい。
・肝細胞癌の約 70%が HCV 陽性(今後 2010~2015 年まで肝癌が増加)
D 型肝炎ウイルス
・HDV(hepatitis D virus)δ肝炎ウイルス、RNA ウイルス
・D 型は、血液・体液を介して感染する。
・しばしば B 型と重複感染する。
E 型肝炎ウイルス ・HEV(hepatitis E virus)、RNA ウイルス
・E 型は、汚染された食物や水により経口感染する。
(3)診断
1)症状
・前駆期(1~2週間):食欲不振、悪心、嘔吐、心窩部痛、発熱
・黄疸期(2~4週間):黄疸、皮膚のかゆみ、肝腫大。自覚症状は軽減し食欲は回復
・回復期:約 3ヵ月で肝機能は正常化する。
2)検査
・血清ビリルビン増加:直接(抱合型)ビリルビンが優位
・トランスアミナーゼ高度上昇:500以上
初期から極期は AST(GOT)>ALT(GPT)、回復期は AST<ALT
・血清膠質反応(ZTT、TTT)が上昇する。
・肝炎ウイルスマーカー:A型:IgM 型 HA抗体、IgG型 HA抗体
B型:HBe 抗原・抗体、HBc抗原・抗体

臨床病態学 要点整理ノート
52
C型:HCV抗体、HCV-RNA
(4)治療
・安静:症状があるうちは入院してベッド上で安静にすることが原則である。
・食事療法
前駆期
黄疸期
・低脂肪食が原則。
・食欲不振が強いときは糖質中心の消化のよいものを摂取する。
・カロリー、水分の摂取不足は末梢静脈栄養で補う。
回復期
・従来、高エネルギー、高たんぱく、高ビタミン食が原則といわれてきたが、現在の食生
活の現状から「日本人の食事摂取基準」に準じる。
・アルコールは、治癒後 6ヶ月まで禁止する。
・エネルギーの過剰摂取による肥満、脂肪肝に注意する。
(5)劇症肝炎(fulminant hepatitis)
・急性肝炎の経過中(発症後 8週間以内)に、意識障害など肝不全症状が出現し、短時間のうちに死亡
するもの
・発症すると、生存率は 20~30%である。
・急性肝炎の約 1%に出現し、年間患者発生数は約 700人である。
・原因は B型がもっとも多く、ついで D型、E型が多い。A型、C型の頻度は少ない。
2.慢性肝炎(chronic hepatitis)
(1)病態
・肝臓の慢性炎症(門脈域のリンパ球を主体とした細胞浸潤と線維化、種々の程度の肝細胞の変性・壊
死)の結果、AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇を主とする肝機能検査の異常が 6ヶ月以上持続している
もの
・原因はウイルス性が多く、C型が 70%、B型が 20%である。
・その他アルコール性、薬剤性、自己免疫性肝障害などが原因となる。
・肝炎ウイルスの持続感染により、免疫細胞による感染肝細胞の破壊が持続するため、組織の線維化が
進行する。
(2)診断
1)症状
・一般に自覚症状に乏しい。全身倦怠感、食欲不振、心窩部不快感、体重減少など
・肝腫大、脾腫を認めることが多い。
・その他、クモ状血管腫、手掌紅斑、黄疸など認めることがあるが肝硬変ほどではない。
2)検査
・肝細胞の壊死によりトランスアミナーゼが中等度に上昇、AST(GOT)<ALT(GPT)
・慢性炎症により ZTT、TTT 上昇、血清グロブリンが増加する。
・肝炎ウイルス感染によるものでは、肝炎ウイルスマーカーが陽性である。
(3)予後
1)B型肝炎
・HBe抗原陽性から、HBe抗体陽性へ移行した場合(セロコンバージョン)、炎症は沈静化する。
・HBe 抗原陽性が続く場合は、炎症も持続し、肝硬変への移行、肝細胞癌の発生につながる可能性が高
い。
2)C型肝炎
・自然に沈静化することはまれで、10~20年で肝硬変に移行し、20~30年で肝細胞癌に進展する。

臨床病態学 要点整理ノート
53
(4)治療
1)安静
・食後 30~90分程度の安静が基本
・激しい運動を避けること以外は、健常人と同様の日常生活でよい。
・過度の安静による肥満,脂肪肝に注意する。
・急性増悪時は、急性肝炎に準じた安静を必要とする。
2)食事療法
・バランスの取れた規則正しい食生活をする。
・原則として禁酒、禁煙
・エネルギー過剰と運動不足による肥満、脂肪肝に注意する。
・アルコール性肝炎の場合は、栄養不良を伴っていることが多いので、高エネルギー、高タンパク質食
とする。
3)薬物療法
・インターフェロン(抗ウイルス作用、免疫賦活作用)
Peg-IFNα2a皮下注、週 1回 24~48 週投与、治療反応率 20~40%
・B 型肝炎治療薬
核酸アナログ(DNAポリメラーゼ阻害作用)
経口投与、治療反応率 80~90%
第 1選択薬:エンテカビル(entecavir, ETV)とテノホビル(tenofovir, TDF)、
ラミブジン(lamivudine, LAM):最初に発売された核酸アナログ
アデヒボル(adefovor, ADV):LAM耐性例に追加投与
・C 型肝炎治療薬
直接作用型抗ウイルス薬(DAA, direct-acting antivirals)
HCV の増殖に
必要なたんぱく質 機能 阻害薬
NS3 HCVの蛋白を適切に切断するプロテアーゼ アスナプレビル、パリタプレビル
リトナビル、グラゾプレビル
NS5B HCVの RNA複製を司るポリメラーゼ ソフォスブビル
NS5A HCV複製過程の複合体形成で主役を演じる ダクラタスビル、レディパスビル
オムビタスビル、エルパスビル
遺伝子型1
ダクラタスビル+アスナプレビル(ダクルインザ錠+スンベプラ錠)
ソフォスブビル+レディパスビル(ハーボニー配合錠)
オムビタスビル+パリタプレビル+リトナビル(ヴィキラックス錠)
エルパスビル+グラゾプレビル(エレルサ錠+グラジナ錠)
遺伝子型2
ソフォスブビル+リバビリン(ソバルディ錠+レベトールカプセルまたはコペガス錠)
オムビタスビル+パリタプレビル+リトナビル+リバビリン(ヴィキラックス錠+レ
ベトールカプセル)
・肝庇護薬(AST、ALTの改善作用)
グリチルリチン製剤(SMMC 療法)、ウルソデオキシコール酸
4)鉄制限食(7㎎/日以下)または瀉血
・C 型慢性肝炎では、肝臓組織に鉄が蓄積している。
・組織鉄の増加は、活性酸素を発生させ、肝細胞の壊死、線維化を促進する。
・組織鉄の上昇は、血清フェリチン値の上昇でモニターする。
・血清フェリチン値が基準値以上の場合は、鉄制限食または瀉血を行う。

臨床病態学 要点整理ノート
54
3.肝硬変症(cirrhosis)
(1)病態
・慢性肝障害の終末像であり、組織学的には肝細胞の壊死後の線維化と再生結節が特徴である。
・臨床的には肝機能の低下と門脈圧亢進症状を示す。
・原因はウイルス性が多く、C型が 60~70%、B型が 20%である。
・その他アルコール性(10%)、薬剤性、自己免疫性肝障害、ヘモクロマトーシス、ウィルソン病など
が原因となる。
(2)病態と症状
病態 症状
肝実質組織の炎症,壊死,線維化 肝の硬化、縮小
たんぱく質・脂質の
合成能低下
血清アルブミン合成の低下 浮腫、腹水
凝固因子合成の低下 プロトロンビン時間延長、出血傾向
血清コレステロール合成の低下 低コレステロール血症
門脈圧の上昇 側副血行路増加、脾腫 食道静脈瘤、腹壁静脈怒張、脾腫、
痔疾、汎血球減少症
代謝障害
ビリルビン代謝の低下 黄疸
尿素合成の低下 高アンモニア血症、肝性脳症
高エストロゲン血症 クモ状血管種、手掌紅斑、女性化乳房
高アルドステロン血症
Na、水再吸収増加 浮腫・腹水
肝臓での芳香族アミノ酸取り込み低下と高インスリン血
症による筋肉での分岐鎖アミノ酸取り込み増加
→血中フィッシャー比低下→脳内アミンの代謝異常
肝性脳症
(3)非代償期肝硬変患者の代謝の特徴
・糖質の利用障害、脂質の利用増加が見られる。(マラスミック・クワシオルコル)
・肝臓のグリコーゲン貯蔵量が減少するために、空腹時に血糖値が低下する。
・糖新生により、空腹時の血糖値を維持するために、たんぱく質の異化が亢進する。
・分岐鎖アミノ酸(BCAA、branched chain amino acids、バリン、ロイシン、イソロイシン)が減少し、
芳香族アミノ酸(AAA、aromatic amino acids、チロシン、フェニルアラニン)が増加してフィッシャ
ー比(BCAA/AAAモル比)が低下する。
AAAは主に肝臓で代謝されるが、肝臓の代謝機能低下により、血中濃度が増加する。
BCAA は主に骨格筋で代謝されるが、エネルギー消費増大に伴う異化の亢進により、血中濃度が低
下する。また、高インスリン血症により筋肉への取り込みが増加する。
・脳内のアミノ酸バランスの異常(アミノ酸インバランス)は脳内アミンの代謝障害を引き起こし肝性
脳症の一因となる。
・BCAA が代謝されるときのアミノ基転移反応で生成するグルタミン酸からグルタミンが生成するとき
にアンモニアを取り込むので、高アンモニア血症を改善する。
(4)診断
代償期
・自覚症状は軽度である。
・トランスアミナーゼは正常範囲または軽度上昇する。
AST(GOT)>ALT(GPT)
・ZTT、TTT、血清グロブリンは増加する。
・肝機能の低下に伴いアルブミン、A/G比、コリンエステラーゼが低下する。
・線維化が進行すると線維化マーカーであるヒアルロン酸、Ⅳ型コラーゲンが上昇する。
・門脈圧亢進症状が進行すると、汎血球減少症(脾腫による血球の破壊亢進)が出現する
・血小板の減少が線維化の程度の予測因子になる。

臨床病態学 要点整理ノート
55
非代償期
・黄疸、腹水、浮腫、肝性脳症などが出現する。
・血中トランスアミナーゼ(AST、ALT)が中等度以上に増加する。
・血中アンモニアが増加する。
・血中フィッシャー比が低下する。
・プロトロンビン時間(PT)が延長する。
その他 ・血中α-フェトプトテイン濃度の上昇(肝細胞癌の腫瘍マーカー)
(5)肝硬変症の死因
・食道静脈破裂など消化管出血(41%)、肝不全(25%)、肝癌(17%)
(6)治療
1)食事療法
・摂取エネルギーは、25~30kcal/kg(標準体重)/日とする。
「日本人の食事摂取基準」に準じる。
・脂質エネルギー比は、20~25%とする。
・たんぱく質は、1.2~1.3g/kg(標準体重)/日とする。
・非代償期で、たんぱく不耐症(高アンモニア血症)がある場合は、0.5~0.7g/kg(標準体重)/日とし、
窒素源の不足は分岐鎖アミノ酸製剤で補う。
・浮腫、腹水がある場合は、減塩食(6g/日)とする。
・就寝前に、200㎉程度の夜食(Late evening snack, LES)をとる。
・食物繊維は、便秘を予防し、腸内細菌によるアンモニア発生を予防する。
・血清フェリチン値が基準値以上の場合は、鉄を 7㎎/日以下に制限する。
2)薬物療法
・肝庇護薬:グリチルリチン製剤(強力ネオミノファーゲン C®、SNMC, stronger neo minophagen C)
・消化管出血:H2ブロッカー
・肝性脳症:分岐鎖アミノ酸製剤(アミノレバン)投与
・ラクツロース投与:ラクツロースは、ガラクトースとフルクトースからなる二糖類で、腸内の乳酸菌
で分解され、乳酸と酢酸が産生される。その結果、腸内 pHが低下し、アミノ酸分解菌の増殖を抑制す
ることにより、アミノ酸の分解によるアンモニアの産生を抑制する。
・非代償期肝硬変患者に対する分岐鎖アミノ酸製剤投与の意義
・筋たんぱく質の合成促進と崩壊抑制
・アミノ酸インバランスの是正による肝性脳症の改善
・血清たんぱく質の増加
・末梢組織でのアンモニア処理促進
4.脂肪肝(fatty liver)
(1)病態
・脂質が肝湿重量の 5%以上蓄積した状態(正常では 2~4%)
・蓄積する脂質は中性脂肪で、肝湿重量の量が 40~50%になることもある。
・原因は、栄養過多、肥満、糖尿病、飲酒(毎日 3合、5年以上でなる可能性高い)が多い。
アルコールは、肝臓での中性脂肪合成を亢進させ、VLDL 産生・放出を抑制する。
男性は 40~80ℊ/日以上で、女性は 20ℊ/日以上で脂肪肝を生じる。
・低栄養状態(タンパク欠乏により VLDL の合成障害)、薬剤性(テトラサイクリン系抗生物質、副腎皮
質ホルモン)、妊娠、ウイルス感染(ライ症候群)が原因になることもある。
・非アルコール性脂肪肝炎(NASH, non-alcoholic steathepatitis)
アルコール飲酒暦がないにもかかわらず肝細胞の壊死、炎症、線維化など、アルコール性肝炎と類
似の組織所見を伴うもの
肥満、糖尿病、高脂血症など過剰栄養に伴う生活習慣病に合併する。

臨床病態学 要点整理ノート
56
共通の病態として、インスリン抵抗性が背景にある。
約 50%が進行性で、10年間に 20%が肝硬変に移行し、肝癌の発生率も高い。
(2)診断
1)症状
・多くは無症状。ときに、肝腫大、上腹部圧痛があることがある。
2)検査
・血清コリンエステラーゼと-GTP の軽度上昇が特徴である。
・トランスアミナーゼ(AST、ALT)は軽度上昇することがある。
・アルコール性では、-GTPの上昇が顕著で、AST>ALTのことが多い。
・肥満、糖尿病を伴う場合は AST<ALTのことが多い。
・腹部超音波エコー(Bright liver)、CT検査(CT値低下)が診断に有効である。
・NASH が疑われる場合(脂肪肝に線維化マーカー上昇、炎症所見があるとき)は、生検による組織診断
を行う。
・肝組織では、鉄の過剰蓄積がみられる。
・肝炎ウイルス(HBV、HCV)の感染はない。
(3)治療
・原因の除去
・食事療法
過栄養性では、低エネルギー食とする。
たんぱく質、ミネラル、ビタミンなどが不足しないように注意する。
アルコール性では、禁酒とバランスのとれた栄養摂取にする。
肥満がない場合は、所要量を満たすようにする。
低栄養性では、高カロリー、高たんぱく質、高ビタミン食とする。
5.胆石症(gallstone)
(1)概念
・胆石症とは、胆道(胆嚢・胆管)内に固形物(胆石)ができることをいう。
・発生する部位により肝内胆石(8%)胆嚢胆石(85%)、総胆管胆石(12%)に分類される。
・肥満した中年の女性に多い疾患である。
・成分による分類
コレステロール胆石(70%) 純コレステロール石(10%)、混成石(10%)、混合石(50%)
色素胆石(30%) 黒色石(15%)、ビリルビンカルシウム石(15%)
まれな胆石 炭酸カルシウム石、脂肪酸カルシウム石、他の混成石
(2)病態
1)コレステロール胆石
・コレステロールは、胆汁酸、レシチンと複合ミセルを形成して胆汁中に溶解している。
・胆汁中のコレステロールの比率が増加し、コレステロール溶存能を越えるとコレステロールが析出し
て胆石を形成する。
・胆嚢内結石が多い。
・日本、欧米、都会、中年女性、妊婦、肥満者に多い。
2)色素胆石
・ビリルビンは、グルクロン酸抱合され、胆汁中に溶解している。
・胆道感染(大腸菌など)があると、感染菌がβ-グルクロニダーゼを産生し、胆汁中の抱合型ビリルビ
ンを脱抱合し、不溶性の非抱合型ビリルビンを産生する。これが、Caと結合して析出し、胆石(ビリ

臨床病態学 要点整理ノート
57
ルビンカルシウム石)を形成する。
・胆管結石が多い。
・発展途上国、農村、男性に多い。
(3)診断
1)症状
・胆石三主徴(右季肋部の疝痛発作、発熱、黄疸)
疝痛とは疼痛が一定の時間をおいて発作的に繰り返すものである。
脂肪の過剰摂取、暴飲暴食、過労、ストレス、飲酒などが誘因となってコレシストキニン(CCK)が
分泌され、胆嚢平滑筋が痙攣性収縮し、胆石が胆嚢頚部に嵌頓することにより発生する。
痛みは右肩、右背部に放散(関連痛)し、嘔気、嘔吐を伴う。
・無症状胆石(Silent Stone):全剖検例の 10~15%で胆石が見つかる。
・人間ドックの超音波エコー検査では 3~5%の頻度で発見される。
・胆石症のうち 50~70%は無症状である。
2)検査
・胆石症の診断には超音波エコー、CT検査が有効である。
・その他、腹部単純 X線撮影、胆嚢造影検査(経口的、経静脈的、内視鏡的)がある。
・血液検査:胆嚢炎を合併していれば、白血球増加、CRP増加などの炎症所見が出現
ビリルビン、アルカリホスファターゼ、γ-GTP上昇など胆汁うっ滞の所見が出現
(3)治療
・無症状胆石:経過観察のみ(胆嚢癌の合併の注意)
・内科的治療
胆石溶解剤(ウルソデオキシコール酸、ケノデオキシコール酸)
15mm以下の X線透過性石、胆嚢機能がある場合に有効(有効率 44%)
体外衝撃波胆石破砕療法(Extracorporeal shock wave lithotripsy,ESWL)
30mm以下の X線透過石、胆嚢機能がある場合に有効である。
・外科的手術(内科的治療が無効な場合に行う)
開腹手術(20%)(入院日数 18 日)に比べて、腹腔鏡下胆摘術(80%)(入院日数 9日)では入院
日数が少ない。
・食事療法
発作期
・1~2日絶食とし、静脈栄養を行う。
・疼痛に対して、鎮痙剤、鎮痛剤を投与する。
・症状が治まれば、糖質中心の流動食から開始。少量・分割食とする。
回復期
・低脂肪食(30ℊ/日以下):胆嚢収縮の抑制と疝痛発作の誘発を防止
・胃酸分泌を刺激するアルコール、カフェイン、炭酸飲料、香辛料などは控える。
・エネルギー、タンパク質は日本人の食事摂取基準を目安にする。
寛解期
・暴飲・暴食をさけ、規則正しい食生活を心がける。
・適量の脂質(エネルギー比 20~25%)を摂取する。
極端な脂肪制限は、脂溶性ビタミンの不足や,胆嚢収縮抑制による胆嚢内の胆汁停滞
を促進する。
・コレステロール、動物性脂肪の過剰摂取を控える。
・不飽和脂肪酸の多い植物油を適当量摂取する。(コレステロール生成抑制)
・食物繊維を多くする。(血清コレステロール低下作用、便秘改善作用)

臨床病態学 要点整理ノート
58
6.胆嚢炎(cholecystitis)
(1)病態
・胆嚢炎とは、胆石症、胆汁うっ滞を背景に、細菌感染により炎症を起こしたものである。
・原因菌として、大腸菌、クレブシエラなどグラム陰性桿菌と腸球菌が多い。
・胆石の合併率は 90%である。
(2)診断
1)症状
・心窩部~右季肋部の痛みがある。
・悪寒、戦慄、高熱を伴う。
・ときに軽い黄疸を伴う。
2)検査
・診断には腹部エコー検査が有効である。
・血液検査では白血球増加、CRP増加など炎症所見が見られる。
(3)治療
・抗生物質を投与する。
・経皮経肝胆嚢ドレナージにより胆嚢の膿を排膿する。
・壊疽性胆嚢炎、胆嚢穿孔のときは緊急手術により胆嚢摘出を行う。
・食事療法
急性期:絶食→流動食→軟食→常食
慢性期:胆石症の緩解期と同じ。
7.急性膵炎(acute pancreatitis)
(1)概念
・膵組織内で活性化された消化酵素により膵実質細胞が自己消化され、浮腫、出血、壊死が起こる。
・重症の場合、血流に入った膵酵素により、ショック、多臓器不全を引き起こす。
・年間 15,000例発症し、その約 10%が重症群で、その約 30%が死亡する。
・原因は、アルコール(約 40%)、特発性(25%)、胆石症(約 20%)が多い。その他、高脂血症(Ⅰ
型、Ⅴ型)、感染、妊娠、薬剤、暴飲暴食、外傷などが原因となる。
(2)病態
・何らかの原因による膵管内圧の上昇のために膵液の流出障害が起こり、膵管内で消化酵素が活性化し
て膵実質組織の自己消化が起こる。
・アルコールは微小膵管の流出障害を引き起こす。
・胆石が膵管の乳頭開口部を閉塞すると、膵液の流出障害が引き起こされる。
(3)診断
1)症状
・心窩部から左季肋部の持続性の鈍痛、激痛で、背部に放散(関連痛)する。
・腹痛は座位前屈位で軽減する。(膵臓痛)
・悪心・嘔吐、腹部膨満感、腹部膨隆、発熱などを伴う。
・重症例では、ショック、多臓器不全を引き起こす。
2)検査
・血清アミラーゼ(発症 2~3時間後)、尿中アミラーゼ(発症 2~4日後)が増加する。
・その他の膵酵素の血中・尿中濃度が増加する。
・腹部エコー、X線検査、内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)など画像診断

臨床病態学 要点整理ノート
59
(4)治療
1)急性期
・重症例では、絶食とし、静脈栄養を行う。
・トリプシン阻害薬(FOY)の持続点滴と抗生物質を投与する。(消化酵素の阻害)
・抗生物質:腸内細菌のバクテリアル・トランスロケーションによる膵臓および膵周囲の感染症や敗血
症を予防する。
2)回復期
・腹痛と検査所見(炎症、アミラーゼ)の改善を確認しながら、糖質中心の流動食から開始して、徐々
に粥食を上げていく。
・エネルギーは、1,000kcal/日程度から開始し、症状に応じて徐々に増量する。
・脂肪は、10ℊ/日以下に制限する。
3)寛解期
・炎症が完全に治まるまで、脂肪制限(30ℊ/日以下)を続ける。
・アルコールは厳禁
・炭酸飲料、カフェイン、香辛料など、膵液分泌を刺激するものを避ける。
8.慢性膵炎(chronic pancreatitis)
(1)概念
・6 ヵ月以上持続する炎症により非可逆的な線維化と膵実質の破壊が起こる。
・膵外分泌および内分泌機能が障害される。
・原因は、アルコール性(約 60%)、特発性(約 30%)、胆石性(約 10%)である。
・膵実質の荒廃→ランゲルハンス島の破壊・減少→インスリン分泌減少→糖尿病
(2)病態
・アルコール→膵液中へのムコタンパク分泌増加→膵液粘稠度増加→微小膵管にタンパク栓形成→膵液
流出障害→膵管内で消化酵素が活性化→膵実質の消化・破壊・炎症・線維化→外分泌腺減少→消化酵
素分泌減少→消化吸収障害
・アルコールが直接、腺房細胞や腺房中心細胞を障害する可能性もある。
(3)診断
1)症状
・持続性の上腹部痛(過食、飲酒後に増悪) (炎症)
代償期:膵機能は保たれているが、疼痛発作や急性再燃を生じやすい。
非代償期:膵機能が荒廃した状態で、疼痛は軽減する。
・消化吸収障害:食欲不振、体重減少、脂肪便
・内分泌障害:糖尿病
2)検査
・腹部エコー、X線検査、CT:膵臓の石灰化、膵石の描出
・ERCP:膵管の不規則な拡張,膵石の描出
・膵外分泌機能検査(BT-PABA試験)
PFD 試験(pancreatic functional diagnostant test)ともいう。
BT-PABA(N-benzoyl-L-tyrosyl-para-aminobenzoic acid)が、キモトリプシンにより分解され
ると、PABA が体内に吸収されて、尿中に排泄される。
・セクレチン試験:セクレチン刺激による膵液分泌
・膵生検:実質の減少、線維化の証明。

臨床病態学 要点整理ノート
60
(4)治療
1)代償期
・急性再燃時:急性膵炎の急性期と同じ。
・間欠期:疼痛に対して、抗コリン薬、中枢性鎮痛薬(習慣性に注意)を用いる。
食事療法は禁酒、脂肪制限など急性膵炎の寛解期と同じ。
エネルギー、タンパク質が不足しないよう十分に摂取する。
2)非代償期
・消化吸収障害:通常使用量の数倍の消化酵素による補充療法
・中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)は、リパーゼに依存せずに吸収される。
・糖尿病が合併した場合はインスリン療法
・慢性膵炎に合併した糖尿病は、グルカゴン分泌低下を伴っているので、低血糖発作を起こしやすく、
血糖値のコントロールが困難なことが多い。
・食事は糖尿病食に準じる。

臨床病態学 要点整理ノート
61
8.高血圧症
1.病態
(1)定義
・恒常的な血圧上昇があり、脳、心臓、腎臓などに臓器障害を起こす疾患である。
・高血圧症の 90%以上は、原因不明で本態性高血圧(essential hypertension)である。
・本態性高血圧症は、遺伝因子に環境因子(生活習慣)が加わって発症する。
(2)成因
1)遺伝因子
・アンギオテンシノーゲン、アンギオテンシン変換酵素など水分・Na代謝に関連した遺伝子の異常が知
られているが、高血圧患者の 90%以上を占める本態性高血圧症の原因遺伝子は不明である。
2)環境因子
食塩過剰
摂取
・食塩摂取の増加は、体内の Na量を増加させて細胞外液量の増加をもたらす。
その結果、心拍出量を増加させるので血圧が上昇する。
・人類が出現した頃の食塩摂取量は、3g程度であったいわれる。
1 日最低必要量は 1g 以下なので、現在の食塩摂取量はすべての人にとって過剰に
なっている。
・日本人の食塩摂取量は、徐々に低下しきた。
平成以後やや増加したが、平成 10年以降徐々に低下している。
・圧-利尿曲線:高血圧患者は過剰な Na を排泄するために、より高い血圧を必要とす
る。
・食塩感受性:食塩の過剰摂取量により、血圧が 10%以上上昇することをいう。
高血圧患者の約 30~40%でみられ、高齢者の高血圧患者に多い。
カリウム
摂取不足
・カリウムは、Na排泄増加作用、交感神経抑制作用、血管拡張作用を介して降圧効果を
示す。
・人類が出現したころの Naと K摂取の比は、1:1程度であったといわれている。
・我が国の Naと K摂取の比は、約 2:1である。
肥満
・体重増加により循環血液量が増加し、心拍出量も増加して血圧を上昇させる。
・インスリン抵抗性(高インスリン血症)は、腎臓での Na再吸収増加、交感神経緊張、
血管平滑筋増殖などを引き起こし、血圧を上昇させる。
・レプチン分泌増加は、交感神経緊張を引き起こし、血圧を上昇させる。
飲酒習慣 ・飲酒は、血管拡張作用により一過性に血圧が下がるが、長期的には血圧を上昇させる。
・一回の飲酒量、飲酒の頻度が多いほど血圧を上昇させる効果が大きくなる。
運動不足 ・体重増加、インスリン抵抗性亢進などを介して血圧を上昇させる。
ストレス ・交感神経緊張を介して血圧を上昇させる。

臨床病態学 要点整理ノート
62
(3)血圧が上昇するメカニズム(血圧に影響する液性、神経性因子)
(4)二次性高血圧症(高血圧全体の約 10%以上)
腎実質性高血圧(2~5%) ・慢性糸球体腎炎、糖尿病性腎症など
腎血管性高血圧(1%) ・線維筋性異形成、動脈硬化症、大動脈炎症候群など
内分泌性高血圧(3~10%) ・原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫など
血管性高血圧 ・大動脈狭窄症など
薬剤誘発性高血圧 ・糖質コルチコイド、グリチルリチン製剤、漢方薬など
(5)高血圧症による臓器障害
1)硝子化細動脈硬化症
・血管壁が硝子化により肥厚し、内腔が狭くなる。
・高血圧性網膜症(細動脈の閉塞による網膜の壊死)、腎硬化症(糸球体の血流の減少による萎縮壊死
変化)を起こす。
2)過形成性細動脈硬化症
・重篤な血圧上昇(悪性高血圧)と関連する。
・血管平滑筋が肥大と過形成により血管壁が玉ねぎの皮様に肥厚して内腔が狭くなる。
・類線維素の沈着と壊死を伴う(壊死性細動脈炎)
3)高血圧性臓器障害
高血圧性網膜症 ・眼底動脈の狭窄、綿花状白斑(動脈閉塞による虚血病変)、硬性白斑(網膜の
瘢痕)、乳頭浮腫、網膜出血など
脳 ・高血圧性脳症、脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、一過性脳虚血発作など
心臓 ・左室肥大、心不全、狭心症、心筋梗塞など
血管 ・粥状動脈硬化症の発症・進展の促進、大動脈瘤、閉塞性動脈疾患など
腎臓 ・たんぱく尿、腎硬化症、腎不全など
・心血管病の危険因子としては、拡張期血圧よりも収縮期血圧の方が重要である。
2.診断
(1)高血圧症の自覚症状
・一般に無症状
・頭痛、めまい、肩こり、動悸、息切れ、鼻血などが出現することがある。
血圧上昇 = 心拍出量増加 × 末梢血管抵抗増加
交感神経緊張
体液量増加
Na 再吸収亢進 レニン・アンギオテンシン・
アルドステロン系の亢進
NO 産生低下
遺伝因子 + インスリン抵抗性
静脈収縮による
静脈還流増加 心臓の収縮力増強
細動脈の収縮

臨床病態学 要点整理ノート
63
(2)診断基準(高血圧治療ガイドライン 2019)
診察室血圧(mmHg) 家庭血圧(mmHg)
収縮期血圧 拡張期血圧 収縮期血圧 拡張期血圧
正常血圧
正常高値血圧
高値血圧
<120 かつ <80
120~129 かつ/または 80~84
130~139 かつ/または 85~89
<115 かつ <75
115~124月 かつ/または 75
125~134 かつ/または 75~84
Ⅰ度高血圧
Ⅱ度高血圧
Ⅲ度高血圧
140~159 かつ/または 90~99
160~179 かつ/または 100~109
≧180 かつ/または ≧110
135~144 かつ/または 85~89
145~159 かつ/または 90~99
≧160 かつ/または ≧100
(孤立性)
収縮期高血圧 ≧140 かつ <90 ≧135 かつ <85
(3)血圧に関する用語のまとめ
外来血圧測定 ・病院の外来で医師または看護師によって測定される。
・診断基準に用いられる。
家庭血圧測定 ・外来血圧に対し、一般に家庭血圧が低い。
・外来血圧 140/90mmHgは家庭血圧 125~135/80~85mmHgに相当する。
血圧の
日内変動
・血圧の日内変動では、一般に夜間に低下する。
・夜間 10%以上低下する人を dipperという。
・夜間の血圧低下ない人を non-dipperという。
・Dipperに比べて、non-dipper のほうが臓器障害を起こしやすく予後が悪い。
白衣高血圧 ・外来血圧は高いが、家庭血圧が正常範囲にあるものをいう。
・治療の必要はないが、高血圧症予備軍が含まれる可能性がある。
仮面高血圧 ・外来血圧は正常範囲だが、家庭血圧が夜間や早朝に高血圧を呈するものをいう。
・適切な治療が遅れて、臓器障害が進みやすく、予後不良である。
早朝高血圧 ・早朝の血圧上昇が著しいもの(Morning surge)をいう。
・早朝高血圧を示すものでは、脳卒中を起こす頻度が高い。
悪性高血圧
・拡張期血圧 130mmHg以上で、網膜の浮腫、出血、腎不全、脳症状、心不全など臓
器障害の症状を伴うものをいう。
・放置すれば数ヶ月以内に過半数が死亡する。
(4)高齢者の高血圧症の特徴
・動脈硬化の進展により拡張期血圧が低下して脈圧が開大するので収縮期高血圧が多い。
・血圧が動揺しやすい。
・起立性低血圧を起こしやすい。(圧受容器反射機能の低下)
・Non-dipperが多い。
・食塩感受性高血圧が多い。
3.治療
(1)高血圧患者の脳心血管リスク層別化(高血圧治療ガイドライン 2019)
高値血圧 Ⅰ度高血圧 Ⅱ度高血圧 Ⅲ度高血圧
リスク第一層
予後影響因子がない 低リスク 低リスク 中等リスク 高リスク
リスク第二層
年齢(65 歳以上)、男性、脂質異常症、喫煙の
いずれかがある
中等リスク 中等リスク 高リスク 高リスク

臨床病態学 要点整理ノート
64
リスク第三層
脳心血管病既往、非弁膜症性心房細動、糖尿
病、蛋白尿のある CKD のいずれか、または、
リスク第二層の危険因子が 3つ以上ある。
高リスク 高リスク 高リスク 高リスク
(2)初診時の血圧レベル別高血圧管理計画(高血圧治療ガイドライン 2019)
正常血圧 ・適切な生活習慣の推奨
・1年後に再評価
正常高値血圧 ・生活習慣の修正
・3~6ヵ月後に再評価
高値血圧
・生活習慣の修正/非薬物療法
・低・中等リスク:おおむね 3 ヵ月後に再評価→十分な降圧がなければ生活習慣
の修正/非薬物療法の強化
・高リスク:おおむね 1 ヵ月後に再評価→十分な降圧がなければ生活習慣の修正
/非薬物療法の強化と薬物療法に開始
高血圧
・生活習慣の修正/非薬物療法
・低・中等リスク:おおむね 1 ヵ月後に再評価→十分な降圧がなければ生活習慣
の修正/非薬物療法の強化と薬物療法に開始
・高リスク:ただちに薬物療法を開始
(3)降圧目標(高血圧治療ガイドライン 2019)
診察室血圧 家庭血圧
75 歳未満の成人
脳血管障害患者(両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞なし)
冠動脈疾患患者
CKD 患者(蛋白尿陽性)
糖尿病患者
抗血栓薬服用中
130/80mmHg未満 125/75mmHg未満
75 歳以上の高齢者
脳血管障害患者(両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり、
または未評価)
CKD 患者(蛋白尿陰性)
140/90mmHg未満 135/85mmHg未満
(4)生活習慣の修正項目(高血圧治療ガイドライン 2019)
食塩制限 ・6g/day未満
野菜・果物の積極的摂取 ・飽和脂肪酸、コレステロールの摂取を控える。
・多価不飽和脂肪酸、低脂肪乳製品の積極的摂取
適正体重の維持 ・BMI(体重㎏÷身長 m2)25未満
運動療法 ・軽強度の有酸素運動(動的および静的筋肉負荷運動)を毎日 30分、
または 180分/週以上行う。
節酒 ・エタノールとして男性 20~30㎖/日以下、女性 10~20㎖/日以下に
制限する。
禁煙 ・禁煙

臨床病態学 要点整理ノート
65
・個々の生活習慣の修正の効果は小さいが、複合的な生活習慣の修正は大きな効果を生む(健康日本21)
生活習慣の修正 収縮期血圧の低下効果
食塩摂取を 5.8g 減少 3mmHg
Kの摂取を 585mg 増加 1mmHg
アルコール摂取を 30ml減少 5mmHg
BMIを 1低下 2mmHg
早歩き 1日 30分 5mmHg
複合的効果 16mmHg
(5)薬物療法
1)利尿薬
①サイアザイド系利尿薬
・尿細管での Na再吸収を抑制して循環血液量を減少させて血圧を低下させる。
遠位尿細管の Na+-Cl-共輸送体に作用して、Na再吸収を抑制
・K 排泄も促進するので低 K血症きたしやすい。
体液量の減少に伴い、二次的にレニン分泌が増加し、アルドステロンの作用で K+排泄が増加
・腎機能が低下している場合、効果が減弱し、腎機能も悪化させる。
・副作用:低 K血症、痛風、高脂血症、耐糖能異常(糖尿病)、勃起不全、脱水に基づく血液濃縮など
②ループ利尿薬
・尿細管での Na再吸収を抑制して循環血液量を減少させて血圧を低下させる。
ヘンレループの Na+-K+-Cl-共輸送体に作用して、Na再吸収を抑制
・K 排泄も促進するので低 K血症きたしやすい。
体液量の減少に伴い、二次的にレニン分泌が増加し、アルドステロンの作用で K+排泄が増加
・ループ利尿薬は腎機能が低下した高血圧患者で使用できる。
・副作用:低 K血症、痛風、高脂血症、耐糖能異常(糖尿病)、勃起不全、脱水に基づく血液濃縮など
③カリウム保持性利尿薬
・アルドステロン拮抗薬(スピロノラクトン)は、アルドステロンの作用に拮抗することにより、集合
管での Na再吸収と K排泄を抑制することにより Kを喪失することなく血圧を低下させる。
・副作用:構造が男性で勃起不全、女性化乳房(代謝産物がエストロゲン様作用を有する)、女性では
乳房痛、月経異常をきたしやすい。腎障害があるものでは高 K血症をきたすことがある。
2)血管拡張薬
④α遮断薬
・心拍出量低下作用、レニン産生・分泌低下作用、交感神経活動抑制作用により、血圧を低下させる。
インスリン治療中の糖尿病患者では、低血糖による交感神経刺激作用が抑制されるため、低血糖発
作の症状が抑制され、発見が遅れることがある。
・α受容体によるインスリン分泌抑制を遮断→インスリン分泌回復→脂肪分解抑制
・総コレステロールとトリグリセリドを低下させ、HDL コレステロールを上昇させるなど脂質代謝を改
善する。
・副作用:気管支喘息の誘発、慢性閉塞性肺疾患の悪化、徐脈、房室ブロック、活力・運動能力の低下
⑤β遮断薬
・交感神経末端の筋接合部平滑筋側に存在する1 受容体を遮断することにより血管を拡張して血圧を
低下させる。
・糖・脂質代謝に悪影響を与える。
β受容体の遮断→α受容体の作用優位→インスリン分泌抑制
・長期予後の改善効果は示されていない。

臨床病態学 要点整理ノート
66
・副作用:立ちくらみ、めまいなど
⑥カルシウム拮抗薬
・血管平滑筋への Ca 流入を抑制して血管を拡張して血圧を低下させる。
・脳、腎臓、冠動脈など臓器血流が保たれる。
・糖・脂質代謝に悪影響がない。
・副作用:顔面紅潮、頭痛、動悸、上下肢の浮腫、便秘、歯肉増生など。
・グレープフルーツジュースは Ca拮抗薬の血中濃度を上昇させ、作用を増強することがある。
3)レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系の抑制薬
⑦アンギオテンシ変換酵素阻害薬
・アンギオテンシ変換酵素(angiotensin converting enzyme、ACE)を阻害してアンギオテンシンⅡの
産生を抑制することにより血圧を低下させる。
・心臓(心肥大の改善)、腎臓(タンパク尿の改善)などの臓器保護作用があるとされる。
・糖・脂質代謝に悪影響がない。
・副作用:咳(20~30%にみられる)、呼吸困難(まれ)など
・妊婦への投与は禁忌である。
・高 K血症を有する高血圧患者には使用を避ける。
・ACE阻害薬であるカプトプリルは、食事直後に摂取すると吸収率が低下する。
⑧アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB, angiotensin II receptor blocker)
・アンギオテンシンⅡがアンギオテンシンⅡ受容体に作用するのを抑制して血圧を低下させる。
・心臓(心肥大の改善)、腎臓(タンパク尿の改善)など、臓器保護作用があるとされる。
・糖・脂質代謝に悪影響がない。
・副作用:めまい、動悸など
・妊婦への投与は禁忌である。
・高 K血症を有する高血圧患者には使用を避ける。
4.妊娠高血圧症候群
(1)定義
・妊娠高血圧症候群の定義は、「妊娠 20 週以降、分娩後 20週まで高血圧がみられる場合、または高血
圧に蛋白尿を伴う場合のいずれかで、かつこれらの症状が単なる妊娠の偶発合併症によるものではな
いもの」である。
(2)病態
・病態として、血管の攣縮が考えられている。
全身の血管で攣縮が起これば、末梢血管抵抗が上昇して高血圧が出現する。
腎血管系の攣縮が起これば、たんぱく尿や腎機能障害が出現する。
血圧上昇に対する脳血流の自動調節機能が破綻し、血流の増加による脳浮腫が起こると子癇や脳内
出血が出現する。
子癇とは、妊娠 20週以降に初めて痙攣発作を起こし、てんかんや二次痙攣が否定されるもの
・レニン・アンギオテンシン系が亢進し、体液の貯留、浮腫が出現する。
従来「妊娠中毒症」と呼ばれていたもので、定義に浮腫が含まれていたが、浮腫は妊娠中の生理的
反応であるとされ、定義から除外された。
(3)病型分類
妊娠高血圧 ・妊娠 20 週以降にはじめて高血圧(収縮期 140mmHg もしくは拡張期 90mmHg 以
上)が発症し、分娩後 12週までに正常に復する場合

臨床病態学 要点整理ノート
67
妊娠高血圧腎症
・妊娠 20 週以降にはじめて高血圧(収縮期 140mmHg もしくは拡張期 90mmHg 以
上)が発症し、かつたんぱく尿(基本的には 300㎎/日以上)を伴うもので、
分娩後 12週までに正常に復する場合
子癇
・妊娠 20週以降にはじめてけいれんを起こし、てんかんや二次性けいれんが否
定されるもの。
・けいれん発作の起こった時期により、妊娠子癇、分娩子癇、産褥子癇と称する。
加重型妊娠高血
圧腎症
・高血圧が妊娠前あるいは妊娠 20 週までにすでに認められ、妊娠 20 週以後た
んぱく尿を伴う場合
・高血圧とたんぱく尿が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以
降、いずれか、または両症状が増悪する場合
・たんぱく尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠 20週までに存在し、妊
娠 20週以降に高血圧が発症する場合
(4)重症度分類(血圧とたんぱく尿で分類)
軽症
次のいずれかに該当する場合
①収縮期血圧が 140㎜ Hg以上で 160㎜ Hg未満
②拡張期血圧が 90㎜ Hg以上で 110㎜ Hg未満
③たんぱく尿が原則として 24時間尿を用いた定量法で判定し、300mg/日以上で 2g/日
未満
重症
次のいずれかに該当する場合
①収縮期血圧が 160㎜ Hg以上
②拡張期血圧が 110㎜ Hg以上
③たんぱく尿が 2ℊ/日以上
(5)治療(日本産婦人科学会周産期委員会 1998から抜粋)
・生活指導 安静、ストレスを避ける
・栄養指導
エネルギー 非妊時 BMI24以下の妊婦:30㎉×理想体重(㎏)+200㎉
非妊時 BMI24以上の妊婦:30㎉×理想体重(㎏)
減塩食 7~8ℊ/日
水分制限 1日尿量 500 ㎖以下や肺水腫があれば、前日尿量+500㎖
それ以外は制限しない。
たんぱく質 理想体重×1.0ℊ/日
糖質と脂質 動物性脂肪と糖質を制限し、高ビタミン食とする。

臨床病態学 要点整理ノート
68
9.動脈硬化症、心不全
1.動脈硬化症(atherosclerosis)
(1)病態
・動脈硬化症とは、動脈の血管壁が肥厚、硬化、改築し、機能低下きたした病変である。
・動脈硬化症に関連した死因(脳卒中、心疾患)が全体の約 3分の 1を占める。
・病理学的分類
粥状動脈硬化:大・中動脈内膜に巣状のコレステロール沈着。高コレステロール血症と関連強い。
中膜硬化(Mönckeberg 型):中・小動脈中膜の石灰化。原因不明。高齢者の四肢の動脈にみられる
が、臨床症状はない。
細小動脈硬化:内膜の肥厚硝子化と中膜の(たんぱく質の沈着)。高血圧と関連強い。
・動脈硬化病変が起こりやすい部位と症状
冠状動脈 ・狭心症、心筋梗塞
脳動脈 ・脳卒中、神経症状、記憶力減退、理解力減退、認知症など
下肢動脈 ・壊疽、間欠性跛行(下肢の血流障害のために長時間歩行できないこと)など
大動脈 ・動脈瘤など
腎動脈 ・腎動脈の狭窄をきたし、腎性高血圧、たんぱく尿、腎不全などを起こす。
・動脈硬化症の危険因子
脂質代謝異常 ・高コレステロール血症(Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ型高脂血症)、高中性脂肪血症(Ⅳ型高脂
血症)、低 HDLコレステロール血症、高 Lp(a)血症
メタボリックシ
ンドローム ・肥満、高血圧、糖尿病、耐糖能異常、インスリン抵抗性(高インスリン血症)
生活習慣 ・ストレス、運動不足、喫煙
性別 ・男性ホルモン:LDL 増加作用、女性ホルモン:LDL低下、HDL増加作用
性格 A型行動パターン(競争的、精力的、野心的、時間切迫性、攻撃性)
感染 ・H.ピロリ菌(血小板凝集促進物質放出)、歯周病など。
その他 ・加齢、遺伝、内分泌因子、高ホモシステイン血症など。
(2)診断
動脈の形態
・X線写真:石灰化、動脈拡大など
・CT、MRI、頚動脈超音波エコー検査(頚動脈の内膜中膜複合体肥厚度)
・脳動脈・冠動脈造影
・眼底検査
・血管内エコーなどによる血管壁の観察
心電図 ・ST低下、T波平低化または逆転など心筋虚血の所見
血液検査 ・CRP、白血球数(炎症反応)
(3)治療
・危険因子(喫煙、運動不足など)を除去・軽減する。
・食事療法
総エネルギー ・標準体重×25~35 ㎉/日(標準体重(BMI 22)を維持するようにする)
糖質 ・糖質エネルギー比 50~60%
・糖質のとりすぎによる耐糖能障害、高脂血症、肥満の合併に注意する。
たんぱく質
・1.0~1.2ℊ/㎏/日(除脂肪体重の維持)
・動物性たんぱく質:植物性たんぱく質=1:1
・大豆たんぱく、魚肉たんぱくを多くとる。
・過剰の動物たんぱく質はコレステロールを増加させる。

臨床病態学 要点整理ノート
69
脂質
・脂肪エネルギー比 20~25%
・コレステロール制限:300㎎/日以下
・飽和脂肪酸:一価不飽和脂肪酸:多価不飽和脂肪酸=3:4:3
・多価不飽和脂肪酸(n-6系:n-3系=3~4:1)
・動物性脂肪を制限し、植物油、魚油を多くとる。
ビタミン
ミネラル
・野菜・果物などから十分に取る。特に抗酸化作用を持つビタミン E、C。
・食塩 10ℊ/日以下(高血圧予防には、目標 8ℊ/日以下)
・カリウム 2~4ℊ/日(降圧作用)(生野菜、果物に多く含まれる)
食物繊維
・20~30ℊ/日。ペクチン、グルコマンナンなど水溶性食物繊維を多くとる。
・食物繊維は、脂肪、糖質の吸収抑制し、胆汁酸、コレステロールの排泄を増加さ
せる。
その他 ・-カロチン、ポリフェノールなど抗酸化作用を持つ食品を多くとる。
・ビタミン B6、B12、葉酸の不足は高ホモシステイン血症を引き起こす。
2.虚血性心疾患(ischemic heart disease, IHD、coronary heart disease, CHD)
(1)病態
・虚血性心疾患とは、冠動脈の器質的病変、粥腫(プラーク)の破綻と血栓形成、冠攣縮、冠塞栓、貧
血などが原因となって、心筋の代謝に必要な十分な血液を送ることができないために生じた心臓の機
能障害をいう。冠動脈性心疾患、冠動脈疾患、冠疾患、心血管病などと呼ぶこともある。
・虚血性心疾患の危険因子には、高脂血症(高 LDLコレステロール血症、低 HDLコレステロール血症)、
肥満、糖尿病、高血圧、喫煙、遺伝などがある。
・大動脈起始部から左右の冠動脈が出て、左冠動脈は前室間枝と左回旋枝に分かれる。
・狭心発作の病態と分類
高度な器質的狭窄
(安定プラーク)
・狭心発作は労作(運動など)により誘発されることから労作狭心症と呼ばれ
る。
・症状は安定していることから安定狭心症とも呼ばれる。
冠攣縮
・発作は労作とは無関係に安静時に起こるので安静時狭心症と呼ばれる。
・症状は不安定で重症化しやすいことから不安定狭心症ともいう。
・心筋梗塞に移行しやすい。
不安定プラーク
の破綻
・不安定プラークはコレステロールの含有量が多く薄い線維性の被膜で被わ
れた病変をいう。
・不安定プラークの破綻により血栓が形成され、不安定狭心症や急性心筋梗塞
を起こすことを急性冠症候群という。
・心筋梗塞の原因の多くは不安定プラークの破綻による血栓形成であるとい
われている。

臨床病態学 要点整理ノート
70
(2)診断
狭心症
(angina pectoris)
心筋梗塞
(myocardial infarction)
病態 一過性、可逆性心筋虚血 心筋壊死
胸痛 2~3分(最大でも 15分以内) 15分以上
ニトログリセリン舌下 有効 無効
心電図
ST 下降または ST 上昇が発作時に出
現し、非発作時は正常範囲のこと
が多い。
T波増高、ST上昇、異常 Q波、T波陰
転などが時間経過に伴って出現す
る。発作後も残る。
血液検査 異常なし
AST、ALT、LDH、
トロポニン T(心筋壊死)
白血球、CRP、赤沈(炎症反応)
・無症候性心筋虚血
心筋虚血が存在するにもかかわらず、胸痛などの症状が生じないものをいう。
高齢者、糖尿病患者の狭心症、心筋梗塞に多い。
院内死亡率は胸痛ありの 9.3%に対し、胸痛なしでは 23.3%と高率である。
自覚症状がないために受診が遅れ血栓溶解療法、血管形成術などの治療を受ける機会が少なくなる
ことが原因と考えられる。
・虚血性心疾患の死亡率
入院中の死亡率は、65歳未満では 10%以下であるが、高齢者では 10~30%と高い。
入院中の死亡の約 50%は、発症後 2時間以内に死亡する。
退院後の予後は比較的良く、5年生存率は 70歳未満で約 80%、70歳以上で約 60%である。
(3)治療
狭心症
・労作、喫煙など発作誘発因子を除去する。
・心臓の負担にならない程度の軽度の運動は勧められる。
・薬物療法:発作時:ニトログリセリン(血管拡張作用)
非発作時:亜硝酸剤、Ca 拮抗剤、遮断薬など(心筋の負担を軽減)
・冠動脈形成術
カテーテルを冠動脈内に挿入し、閉塞部位を再開通させるもの。血管内にステント
(金属製ワイヤ)を留置し再閉塞を予防する。
・外科治療(冠動脈バイパス手術)
内胸動脈、胃大網動脈、大伏在静脈を利用する。
・食事療法は動脈硬化症と同じ。
心筋梗塞
・急性期:心臓への負担を最小限にするために絶対安静とする。
急性期では、不整脈・心不全の管理が主体となる。
胸痛に対しては、塩酸モルヒネ(麻薬性鎮痛薬)を投与する。
鎮痛作用、鎮静作用、交感神経緊張抑制作用、末梢静脈拡張作用が、心筋梗
塞発症後の病態を改善する。
発症当日は、絶食とする。
絶食→流動食(糖質、タンパク質中心)→徐々に常食にもどす。
・数日以降:リハビリテーション開始
・退院後:心臓の負担にならない程度の軽度の運動は勧められる。
・食事療法は動脈硬化症と同じ。

臨床病態学 要点整理ノート
71
・薬物療法
抗血小板薬
(アスピリン)
・血小板凝集を促進するトロンボキサンの合成を抑制する。
抗凝固薬
(ワーファリ
ン)
・ビタミン K の作用に拮抗して、肝臓での凝固因子(Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ)の合成を
抑制する。
・ビタミン K を多く含む食品(ホウレン草、ブロッコリーなど)の摂取により作
用が減弱する。
・納豆に含まれる納豆菌はビタミン K 合成能が高く、ワルファリンの作用を抑制
する。
3.心不全(heart failure)
(1)病態(心拍出量の低下に対する代償機転)
・心臓が血液を送り出すときに打ち勝たなければならない動脈圧を後負荷という。
・心臓が収縮する直前の心室の容量を前負荷という。
・収縮直前の心室の容量が大きくなるにつれて収縮力が強くなることをスターリングの法則という。
・後負荷に打ち勝つために心室容量を増加させて心拍出量を維持しようとする調節をフランク・スター
リング機構という。
・心不全では、フランク・スターリング機構により前負荷が増大している。
・心不全では、交感神経系の亢進により心臓の収縮力を維持しようとしている。
・心不全では、レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系を亢進させて体液を貯留させ、血圧、臓
器の血流を維持しようとしている。
・これらの代償機転が破綻すると体液・Na量の過剰な負荷による心不全症状が出現する。
(2)診断
低拍出症状 ・易疲労性、息切れ、動悸、狭心症状、低血圧など。
・乏尿、夜間多尿:腎血流低下による。夜間は安静により腎血流が改善する。
肺うっ血症状
(左心不全)
・労作時の息切れ、発作性夜間呼吸困難、心臓喘息
・重症では起座呼吸(臥位により静脈灌流が増加して肺水腫を起こす)
・チアノーゼ(肺ガス交換の障害により還元ヘモグロビンが増加して皮膚、粘膜、
爪が暗紫赤色になる)
末梢うっ血症状
(右心不全)
・全身浮腫、胸水・腹水の貯留、肝臓・脾臓の腫大、頚静脈怒張など。
・腸管のうっ血による食欲不振。
胸部 X線写真 ・心拡大、肺血管陰影増強、胸水など。
血液検査所見
・肝うっ血→肝機能検査異常(GOT、GPT、ビリルビンの上昇)
・腎血流低下→腎機能低下(BUN、クレアチニン上昇)
・水排泄低下→希釈性低 Na血症
・消化吸収障害→栄養障害(低タンパク血症、低アルブミン血症)

臨床病態学 要点整理ノート
72
(3)治療
1)原因疾患の治療
・誘因の除去:感染症、不整脈、過剰な塩分・水分投与、貧血、妊娠、甲状腺機能亢進症など
・身体活動の制限:運動制限をしすぎるとかえって運動耐容能を低下させるので、適度な運動は必要
2)食事療法
減塩食
・軽症(Ⅰ度):8~10ℊ/日
・中等症(Ⅱ・Ⅲ度):6~7ℊ/日
・重症(Ⅳ度):3~5ℊ/日
水分制限 ・軽症では、制限しない。
・中等症以上で、低 Na血症があるときは、前日の尿量+500ml 以下に制限する。
K摂取
・利尿剤の使用により低 K血症になりやすいので、K(野菜,果物)は十分に摂取する。
・利尿薬にスピロノラクトン(アルドステロン拮抗薬)を使用している場合は、高 K血
症に注意する。
3)薬物療法
利尿剤
・体液量を減少させる。
・スピロノラクトン(アルドステロン拮抗薬)を使用している場合は高カリウム
血症に注意する。
血管拡張薬 ・前負荷と後負荷を軽減する。
β遮断薬 ・交感神経の過緊張を抑制する。
アンギオテンシン
変換酵素阻害薬
・前負荷、後負荷を軽減する。
ジギタリス
(強心薬)
・心筋収縮力を増加させる。
・心不全の増悪を抑制できるが、不整脈死が増加することから生命予後を改善
することはできない。
・治療域が狭く、中毒域が接近している。
・ジギタリス中毒は、心室性期外収縮、房室ブロック、心室頻拍、心室細動など
致命的な不整脈を生じる。
・低 K血症ではジギタリス中毒を起こしやすくする。

臨床病態学 要点整理ノート
73
10.腎疾患
1.病態
(1)免疫学的機序による糸球体障害(糸球体腎炎)
・何らかの原因により、体内で生成した抗体あるいは抗原抗体複合物が糸球体に沈着する。
・その結果、補体が活性化されて、白血球(好中球とマクロファージ)が集まってきて炎症が起きる。
・炎症は、基底膜など糸球体の濾過膜を構成する成分を破壊し、糸球体の透過性を亢進させる。
・その結果、たんぱく質、赤血球が尿中に排泄されるようになる。(血尿、たんぱく尿)
・血小板は、炎症を起こした糸球体内で凝集して、糸球体障害を促進する。
・最終的に糸球体が瘢痕化・硝子化して、機能する糸球体が減少すると腎臓の濾過機能が低下するので
体内に老廃物が蓄積する。(腎不全)
(2)腎除去後糸球体症
・何らかの原因により一部の糸球体機能が障害されて腎臓の濾過機能が一定以下に低下すると、正常な
残存糸球体に負荷がかかり代償性肥大か起こる。
・その結果、残存糸球体の透過性亢進、メサンギウム基質へのタンパク質・脂質の蓄積、フィブリン沈
着などが起こって濾過機能が障害される。
・腎疾患の種類に関わらず腎臓の濾過機能が一定以下に低下すると、糸球体障害の悪循環が起こって、
一定の速度で末期腎不全に進行する。
(3)WHO臨床症候分類
1)急性腎炎症候群(acute nephritic syndrome)
・発症が明らかであり、血尿、タンパク尿、高血圧、糸球体濾過値の減少、浮腫が急激に出現する。
・80~90%は、上気道の A群溶血連鎖球菌(streptococcus)感染が原因である。
・感染 1~2週間後、免疫複合体が糸球体基底膜に沈着し、糸球体に炎症を起こす。
・溶連菌感染により、血清 ASO(抗ストレプトリジン O、anti-streptolysin O)値が上昇する。ストレ
プトリジン Oは、溶連菌が分泌する菌体外毒素
・経過
乏尿期
(1~2週間)
・全身倦怠感、タンパク尿、血尿、乏尿、尿毒症、浮腫、高血圧などが
出現する。
利尿期
(3~4週間)
・濾過機能回復は回復するが、尿細管の尿濃縮機能の回復は遅れるの
で、多量の低張尿が出現する。
回復期治癒期 ・完全に回復するには、数ヶ月~1年かかる。
・予後は良好である。(小児では 1~3ヵ月でほぼ 100%が、成人では 60~80%が治癒する。)

臨床病態学 要点整理ノート
74
2)急性進行性腎炎症候群(rapidly progressive glomerulonephrotitis, RPGN)
・急性あるいは潜行性に血尿、タンパク尿、貧血を認め、数ヶ月で腎不全に進行
・半月体形成性糸球体腎炎(半月体がボーマン腔を占拠し、糸球体を圧迫)が原因となる。
3)反復性あるいは持続性血尿症候群
・肉眼的または顕微鏡的血尿が潜行性あるいは急激に出現し、タンパク尿はみられないかあるいは軽微
であり、かつ高血圧、浮腫など腎炎症状はみられない糸球体疾患である。
・微小変化群、巣状糸球体腎炎、メサンギウム増殖性糸球体腎炎、IgA腎症などが原因となる。
4)慢性腎炎症候群(chronic nephritic syndrome)
・タンパク尿・血尿が 1 年以上持続し、しばしば高血圧,浮腫とともに腎機能障害が緩徐に進行する病
態である。
・原発性糸球体疾患は原因不明のことが多い。
・続発性糸球体疾患は糖尿病腎症、高血圧性腎硬化症、SLE(全身性エリテマトーデス)によるループス
腎炎などがある。
5)ネフローゼ症候群(nephrotic syndrome)
・大量のタンパク尿、低タンパク血症、高脂血症、浮腫を呈する症候群である。
・糸球体透過性亢進の結果、大量のタンパク尿のために血清タンパク質の尿中喪失が増加し、その結果、
低たんぱく血症(特に低アルブミン血症)になり、血液の膠質浸透圧が低下して浮腫が出現する。
・肝臓でのアルブミン合成増加に伴う VLDL、LDL合成亢進と、末梢での VLDL、LDL異化低下が起こるた
めに高コレステロール血症になる。
・組織型は小児では微小変化群(リポイドネフローゼ)が、成人では膜性糸球体腎炎が多い。
・続発性ネフローゼ症候群の原因としては、糖尿病性腎症、SLEが多い。
・予後は組織型による。(微少変化群は良好、膜性や増殖性などは不良)
(4)腎不全(renal failure)
・著しい腎機能の低下の結果、老廃物・有害物質が体内に蓄積し、尿毒症(uremia)を引き起こす。
・尿毒症とは、生体内の最終代謝産物の尿中への排泄障害にために、生体に有害な物質が体液中に蓄積
し、特徴的な尿毒症症状を呈することをいう。
・原因の如何にかかわらず、腎機能が一定以下に低下するとそれ自身が腎機能低下の原因となり腎不全
に進行する。
・尿毒症症状
・精神症状:集中力の低下、頭重感、無気力、錯覚、幻覚、混迷、昏睡など
・神経症状:痙攣、振戦、下肢のしびれ感、灼熱感など
・循環器症状:高血圧、心不全、肺うっ血など
・消化器症状:食欲不振、悪心、嘔吐、口臭、胃・十二指腸潰瘍、吐血、下血など
・血液症状:貧血(エリスロポイエチン、鉄、葉酸などホルモンと栄養素の不足)
・皮膚症状:茶褐色の乾燥した皮膚(ウロビリンの沈着)
・骨症状:骨粗鬆症、骨軟化症(ビタミン D不足、Ca吸収不良、二次性副甲状腺機能亢進症)
・原因
急性腎不全
・腎前性:大量出血やショックなどによる腎血流の低下(腎組織の酸素不足)
・腎性:急性糸球体腎炎、毒物など
・腎後性:尿路閉塞(結石、腫瘍、前立腺肥大など)
慢性腎不全
・糸球体腎炎、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群など

臨床病態学 要点整理ノート
75
・経過
第 1期 腎予備能低下期 GFR 50 ㎖/分以上 ・無症状
第 2期 腎機能障害期 GFR 30~50㎖/分
・正常なネフロンあたりの Na 排泄が増加する
ので浸透圧利尿により尿量が増加する。
・さらに、尿細管の尿濃縮障害も加わり多尿(1
日 2ℓ以上、低張尿)になる。
第 3期 腎不全期 GFR 10~30㎖/分 ・血清中 BUN、クレアチニンが増加する。
第 4期 尿毒症期 GFR 10 ㎖/分以下 ・尿毒症症状が出現する。
(5)慢性腎臓病(CKD、chronic kidney disease)
1)CKD の定義(CKD診療ガイド 2012)
①尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らか、特に 0.15ℊ/ℊクレアチニン以上のたんぱ
く尿(30㎎/ℊクレアチニンのアルブミン尿)の存在が重要
②糸球体濾過値(GFR)<60㎖/分/1.73㎡
①、②のいずれか、または両方が 3ヶ月以上持続する。
2)推算 GFR(㎖/分/1.73㎡)(eGFR, estimated glomerular filtration rate)
・血清クレアチニン値を利用する場合の推算式
男性 194×(クレアチニン)-1.094×(年齢)-0.287
女性 194×(クレアチニン)-1.094×(年齢)-0.287×0.739
・血清シスタチン C値を利用する場合の推算式
男性 (104×(シスタチン C)-1.019×(0.996)年齢)-8
女性 (104×(シスタチン C)-1.019×(0.996)年齢×0.929)-8
3)CKD の意義
・CKDは、末期腎不全の危険因子である。
・CKDは、心血管疾患(冠動脈疾患、心筋梗塞、心不全、脳血管疾患など)の危険因子である。
2.診断
(1)症状
原因 病態 症状
糸球体基底膜の炎症 持続的透過性亢進 たんぱく尿、血尿
糸球体濾過機能の
低下
Na,水の排泄障害による体液増加 浮腫、高血圧
老廃物(窒素代謝産物)の排泄低下 尿毒症
K,P排泄障害 高 K血症、高 P血症
尿細管機能の低下 尿濃縮能低下 等張尿
酸の排泄低下 代謝性アシドーシス
内分泌機能異常
エリスロポイエチン分泌低下 貧血
ビタミン D活性化不足(Ca吸収低下)
二次性副甲状腺機能亢進症
骨から Caと P放出(骨吸収亢進)
低 Ca血症
骨粗鬆症、骨軟化症
レニン分泌亢進 高血圧

臨床病態学 要点整理ノート
76
(2)検査
尿検査
・たんぱく尿(proteinuria)と血尿(hematuria)の出現。
・円柱の出現。(尿が尿細管内で停滞したとき、尿細管から分泌されるムコたんぱく
質とアルブミンが結合してゲル化し、尿細管を鋳型に円柱が生成する)
腎機能検査
・血中尿素窒素(Blood Urea Nitrogen, BUN)とクレアチニン値の上昇。(糸球体濾
過値が 30%以下になると血中濃度が上昇する)
・糸球体濾過値(GFR)の低下
・GFRの測定
イヌリン・クリアランス:最も正確に測定できる。
クレアチニン・クリアランス:クレアチニンは尿細管から少量分泌されるので、
イヌリン・クリアランスより高く算出される。
血清 Ca 濃度
・血漿中の Caは、50%が遊離イオン(Ca2+)として存在し、残りはたんぱく質(45%)
または陰イオン(5%)とイオン結合している。
・低たんぱく血症では見かけ上低 Ca血症となるが遊離 Ca2+濃度は低下していない。
・血清アルブミン値が 4ℊ/㎗未満の時は、以下の式(Payne の式)で補正する。
補正カルシウム値(㎎/㎗)=血清カルシウム値(㎎/㎗)+(4-血清アルブミン
値(ℊ/㎗))
腎生検 ・組織分類(原因の検索と予後判定)
栄養状態 ・BMI、体重変化率、体脂肪量、体筋肉量、血清アルブミン濃度など
BUN/クレア
チニン比
・摂取たんぱく質が増加すると BUNは上昇するが、クレアチニンは変化しない。
・腎疾患でたんぱく質制限を行っている患者で、BUN/Cr 比が 10 以上の場合はたんぱ
く質過剰と判定する。
・低たんぱく食が守れている場合は 8 以下、低たんぱく食を守り、かつ十分なエネル
ギー摂取ができている場合は 5以下になる。
Maroni の式 ・たんぱく質摂取量(ℊ/日)の推定式=((尿中尿素窒素排泄量(g/日)+0.031×体
重(㎏))×6.25
推定食塩
摂取量
・早朝第 1尿による食塩摂取量(ℊ/日)の推定式
=21.98×早朝第 1尿 Na(mEq/ℓ)/尿クレアチニン(ℊ/ℓ)×〔-2.04×年齢+14.89×
体重(㎏)+16.14×身長(㎝)-2244.45〕0.392
(3)IgA腎症(IgA nephropathy)
・IgAを主体とする免疫複合体がメサンギウム細胞に沈着する。
・日本人の慢性糸球体腎炎の原因で最多(成人で 30~40%,小児で 20%)
・急性腎炎症候群、慢性腎炎症候群、ネフローゼ症候群など様々な臨床症候を示し、腎不全に至ること
もある。
(3)ネフローゼ症候群(nephrotic syndrome)の診断基準
①蛋白尿: 3.5g/日以上が持続する。
(随時尿において尿蛋白/尿クレアチニン比が 3.5g/gCr以上の場合もこれに準ずる)
②低アルブミン血症: 血清アルブミン値 3.0g/dL以下
血清総たんぱく 6.0ℊ/㎗以下も参考になる。
③浮腫
④脂質異常症(高 LDL コレステロール血症)
注)1)上記の尿蛋白量、低アルブミン血症(低蛋白血症)の両所見を認めることが本症候群の診断の
必須条件である。
2)浮腫は本症候群の必須条件ではないが重要な所見である。
3)卵円形脂肪体は本症候群の診断の参考になる。

臨床病態学 要点整理ノート
77
3.食事療法
(1)食事療法の原則
低たんぱく質食
・窒素代謝産物産生を抑制するため
・高たんぱく食は腎機能低下を助長する可能性がある。
糸球体の輸入動脈を拡張し、糸球体内圧が上昇する。
腎血流量、糸球体濾過量は増加し、窒素代謝産物の排泄が増加する。
糸球体内圧の上昇が長期間持続することは糸球体の荒廃をまねき、濾過機能が
障害される。
・腎機能が低下した患者では、低たんぱく食にすることにより、糸球体内圧の上昇
と糸球体濾過量の増加を抑制して、残存糸球体の機能低下を遅らせることができ
る。
高エネルギー食
・たんぱく質の利用効率を上げて、異化を抑制するため(エネルギーによるたんぱ
く質節約効果)
・以前は、35 ㎉/㎏/日が推奨されていたが、現在は日本人の食事摂取基準に準じ
る。
食塩制限 ・Na、水分の貯留を抑制するため
・過剰な Naは体液量を増加させ、糸球体内圧を上昇させて腎機能低下を助長する。
水分制限
・浮腫の予防のため
・軽症の場合、Na制限のみで水分制限はしない。
・重症で浮腫が著しい場合:前日の尿量+500㎖に制限する。
K制限 ・高 K血症(不整脈、心停止の危険)を予防するため

臨床病態学 要点整理ノート
78
(2)急性腎炎症候群の食事療法(高エネルギー、低たんぱく質、減塩食)
病期 総エネルギー
(㎉/㎏/日)
たんぱく質
(ℊ/㎏/日)
食塩
(ℊ/日)
カリウム
(ℊ/日) 水分
急性期
乏尿期
35 0.5 0~3
5.5 mEq/ℓ以上の
ときは制限す
る
前日の尿量+
不感蒸泄量 利尿期
回復期
治癒期 35 1.0 3~5 制限せず 制限せず
・総エネルギー:高齢者、肥満者にはエネルギーの減量を考慮する。
・香辛料を利用して減塩食を食べやすくする。
(3)慢性腎炎症候群の食事療法
1)クレアチニン・クリアランスが 71 ㎖/分以上の場合
・7ℊ/日の食塩制限のみとする。
・進行性が認められる場合、たんぱく質制限(0.6~1.0ℊ/㎏/日)を加える。
・浮腫・高血圧がある場合、食塩制限をさらに厳しくて(5ℊ/日)、水分制限を 1 日尿量×1.2~1.3 を
目安とする。
2)クレアチニン・クリアランスが 70 ㎖/分以下の場合の場合
・慢性腎不全の食事療法を行う。
(4)ネフローゼ症候群の食事療法(高エネルギー、軽度タンパク質制限,減塩食)
総エネルギー
(㎉/㎏/日)
たんぱく質
(ℊ/㎏/日)
食塩
(ℊ/日)
カリウム
(ℊ/日) 水分
微小変化型ネフローゼ
症候群以外 35 0.8 5 血清カリウ
ム値によ
り増減
制限せず 治療反応性良好な微小変化
型ネフローゼ症候群 35 1.0~1.1 0~7
・従来、ネフローゼ症候群には高タンパク食が処方されてきたが、必要以上の高タンパクはかえって腎
機能を悪くするといわれ、日本人の食事摂取基準を目標とするか、あるいは軽度タンパク質制限食が
良いとされている。
・浮腫がある場合は、食塩制限を厳しくする。
・高度の難治性浮腫がある場合には、水分制限を要する場合もある。
・浮腫が著しく、利尿剤が無効のときはアルブミン製剤の輸注を行う。
・高コレステロール血症がみられる時は、動脈硬化症予防の観点から、脂質エネルギー比を 20~25%と
し、コレステロール摂取を 200㎎/日未満に制限する。(「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012」)
(5)急性腎不全の食事療法
・高エネルギー:35~40㎉/㎏/日
・たんぱく質制限:内科的急性腎不全 0.5~0.8ℊ/㎏/日
外科的急性腎不全 0,7~1.0ℊ/㎏/日
透析療法を併用している急性腎不全 0.9~1.2ℊ/㎏/日
・多量の体液喪失を伴う例や火傷ではより多くのたんぱく質摂取が必要となる。
・食塩制限:7ℊ/日以下とする。
・水分制限:尿量+不感蒸泄量+腎以外の経路からの喪失量
・カリウム制限:血清カリウム値が 5.5mEq/ℓ 以上であれば制限する。

臨床病態学 要点整理ノート
79
(6)慢性腎臓病に対する食事療法基準 2014年版(日本腎臓学会)
ステージ(GFR) エネルギー
(kcal/kgBW/日)
たんぱく質
(g/kgBW/日)
食塩
(g/日)
カリウム
(mg/日)
ステージ 1
(GFR≧90)
25~35
過剰な摂取をしない
3≦ <6
制限なし
ステージ 2
(GFR 60~89) 過剰な摂取をしない 制限なし
ステージ 3a
(GFR 45~59) 0.8~1.0 制限なし
ステージ 3b
(GFR 30~44) 0.6~0.8 ≦1,500
ステージ 4
(GFR 15~29) 0.6~0.8 ≦1,500
ステージ 5
(GFR<15)
5D
(透析療法中)
0.6~0.8 ≦1,500
別表
注)エネルギーや栄養素は、適正な量を設定するために、合併する疾患(糖尿病、肥満など)のガイド
ラインなどを参照して病態に応じて調整する。性別、年齢、身体活動度などにより異なる。
注)体重は基本的に標準体重(BMI=22)を用いる。
4.薬物療法
・浮腫・高血圧があるときは、利尿剤(ループ利尿薬)、降圧剤を投与する。
・腎炎に対して、副腎皮質ホルモン、免疫抑制剤、抗血小板薬などを投与する。
一次性ネフローゼ症候群では副腎皮質ホルモン投与が基本になる。
特に、微小変化型では副腎皮質ホルモン投与が著効する。
・貧血に対しては、エリスロポイエチン製剤を投与する。
・骨症状に対しては、活性型ビタミン Dを投与する。
5.透析療法
(1)人工透析(dialysis)
・生体膜(主として腹膜)や人工半透膜を介しての物質の移動により、体液組成の異常や体液量を是正
する治療法である。
・2009 年の統計では、慢性透析患者数は、290,675人である。
このうち、昼間血液透析が、238,878人(82.2%)、夜間血液透析が、41,712 人(14.4%)、在宅
血液透析が、229人(0.1%)、腹膜透析が、9,856 人(3.4%)になっている。
・透析新規導入の原因疾患の 1位は、糖尿病腎症(約 40%)、2位は慢性糸球体腎炎(約 30%)

臨床病態学 要点整理ノート
80
(2)血液透析(hemodialysis)
・血液を体外循環回路に導き、透析器の人工半透膜を介して、血液と透析液との間で物質交換を行う。
・透析液に陰圧をかけることにより水分の除去(除水)を行う。
・利点は、物質除去能が高いことである。
・欠点は、操作が煩雑で週に 2~3回通院必要とすることである。
・合併症として、短時間での水、溶質の除去による不均衡症候群(頭痛、悪心、嘔吐、低血圧)、体外
循環による空気塞栓、抗凝固薬の使用による出血、感染などがある。
・長期透析の合併症として、心筋肥大(透析心)、アルミニウム中毒、二次性副甲状腺機能亢進症、透
析アミロイドーシスがある。
透析アミロイドーシスでは、β2 ミクログロブリンが組織に沈着し、手根管症候群や破壊性脊椎関
節症などを起こす。
・食事療法では、1 回の透析による除水を体重の 3~5%以内にとどめるために水分、塩分、K を厳重に
制限する必要がある。
(3)腹膜透析(peritoneal dialysis)
・透析液を腹腔に入れて、腹膜を半透膜として物質交換を行う。
・水分の除去は高張ブドウ糖液(13~40g/Lグルコース、350~500mOsm/L)による浸透圧差を利用する。
・利点は、操作が簡便。持続式携帯型腹膜透析(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, CAPD)
の進歩により、家庭で透析療法が可能となったことである。
・欠点は、物質除去能が低い、腹膜炎を生じやすい、約 10年で透析できなくなることなどである。
・食事療法では、K制限、タンパク質制限が血液透析より緩やかである。
(4)小児の透析
・成人では 90%が血液透析であるのに対し、小児では 90%が腹膜透析である。
・腹膜透析に比べて血液透析はタンパク質制限など食事制限がより困難になることや、小児の成長・発
育を保障するためにも腹膜透析のほうが優れているとされる。
(5)人工透析の開始基準
・GFR 10%以下
・血清中 BUN 80~100 ㎎/㎗以上
・血清中クレアチニン 8~12㎎/㎗以上
・尿毒症症状のため通常の身体活動ができない。
(6)透析患者の食事療法
1)慢性腎臓病に対する食事療法基準 2014年版(日本腎臓学会)
エネルギー
(㎉/kgBW/日)
たんぱく質
(ℊ/kgBM/日)
食塩
(ℊ/日) 水分
カリウム
(㎎/日) リン
血液透析
(週 3回) 30~35 注 1,2) 0.9~1.2 注 1) <6 注 3)
できるだ
け少な
く
≦2000 ≦たんぱく質
(ℊ)×15
腹膜透析 30~35 注 1,2,4) 0.9~1.2 注 1)
PD 除水量
(L) ×
7.5
+ 尿 量
(L)×5
PD除水量
+尿量 制限なし注 5)
≦たんぱく質
(ℊ)×15
注 1)体重は基本的に標準体重(BMI=22)を用いる。
注 2)性別、年齢、合併症、身体活動度により異なる。
注 3)尿量、身体活動度、体格、栄養状態、透析間体重増加を考慮して適宜調整する。
注 4)腹膜吸収ブドウ糖からのエネルギー分を差し引く。

臨床病態学 要点整理ノート
81
注 5)高カリウム血症を認める場合には血液透析同様に制限する。
2)腹膜からのブドウ糖の吸収
・腹膜からのブドウ糖吸収エネルギー量は、使用透析液濃度、総使用液量、貯留時間、腹膜機能などの
影響を受ける。
・1.5%ブドウ糖濃度液 2ℓ、4時間貯留では約 70 ㎉が、2.5%ブドウ糖濃度液 2ℓ、4時間貯留では約 120
㎉が、4.25%ブドウ糖濃度液 2ℓ、4時間貯留では約 220 ㎉が吸収される。
3)腹膜透析患者のたんぱく質摂取量(2009年版日本透析医学会腹膜透析ガイドライン)
・わが国では栄養状態が良好に維持されている腹膜透析患者のたんぱく質摂取量は 0.9ℊ/㎏/日である
こと、1.2ℊ/㎏/日以上の症例はほとんどいないこと、1.5ℊ/㎏/日以上のたんぱく質摂取による栄養指
標の改善は報告されておらず、むしろ高リン血症のリスクが問題となることを挙げ、たんぱく質摂取
量は、適正なエネルギー摂取を前提とした場合、0.9〜1.2ℊ/㎏/日を目標とすることを推奨している。
6.尿路結石
・シュウ酸カルシウム結石が、約 80%を占めている。
・シュウ酸カルシウム結石には、リン酸カルシウムを含んでいるものもある。
・その他、リン酸マグネシウムアンモニウム結石が 7%、尿酸結石が 5%、シスチンが 1%である。

臨床病態学 要点整理ノート
82
11.内分泌疾患
1.甲状腺機能亢進症(hyperthyroidism)
(1)病態
・甲状腺によるホルモンの合成・分泌が亢進するために血液中の甲状腺ホルモン濃度が上昇し、過剰な
ホルモンによる特徴的な臨床症状を呈する。
・20~50歳代の女性に多い。男女比は 1:4~7である。
・発生頻度は 1,000人に対し 0.4~0.8人である。
・分類と原因
バセドウ病
(Basedow病、Graves 病)
甲状腺の TSH受容体に対する自己抗体が出現する自己免疫疾患
甲状腺ホルモン産生腫瘍
(Plummer's disease)
甲状腺ホルモンを産生する結節性の甲状腺腫
まれ
TRH 産生腫瘍 まれ
亜急性甲状腺炎 甲状腺組織の破壊により一過性にサイロキシンが放出される。
(2)診断
1)症状
・甲状腺腫大、眼球突出、心悸亢進(動悸)を Merseburg の三徴という。
・その他の主な症状 精神症状:いらいら、不安感、落ち着きのなさ
身体症状:発汗、手指振戦、暑さに弱い、心房細動
代謝亢進症状:食欲亢進にも関わらず体重減少、基礎代謝亢進
・低カリウム性周期性四肢麻痺:甲状腺ホルモンは、細胞膜の Na-Kポンプを活性化し、細胞内への K 移
行を促進する。その結果、細胞膜は過分極となり、活動電位が発生しにくくなるので麻痺が出現する。
2)検査
・甲状腺ホルモン(T4、T3)高値、甲状腺刺激ホルモン(TSH)低値(負のフィードバック作用)
・甲状腺シンチ:甲状腺放射性ヨード摂取率高値
・自己抗体陽性:抗 TSH受容体抗体、抗ミクロソーム抗体、抗サイログロブリン抗体
・血中コレステロール値低下:甲状腺ホルモンは、体内でのコレステロール生合成を促進すると同時に、
胆汁酸への異化・排泄を促進し、末梢組織の LDL受容体数を増加させる。生合成よりも異化・排泄の
効果が大きいために、血清コレステロール値は低下する。
・食後高血糖:甲状腺ホルモンは、小腸でのグルコースの吸収を促進する。
(3)治療
・薬物療法:抗甲状腺薬(甲状腺ホルモンの合成抑制)
βブロッカー(交感神経緊張症状の抑制)
・手術療法:薬物療法が無効の時(切除が不十分だと再発し、過剰だと機能低下になる)
・食事療法
・代謝亢進時:高エネルギー(35~40㎉/㎏/日)、高たんぱく質(1.2~1.5ℊ/㎏/日)
・ビタミン・ミネラル・水分も、不足しないよう十分に投与する。
・体温上昇、発汗増加により水分を失いやすいので、脱水を予防するために、十分に補給する。
・治療により、代謝が正常化した場合は、特別な食事療法は必要ない。
2.甲状腺機能低下症(hypothyroidism)
(1)病態
・甲状腺ホルモンの作用不足による特徴的な臨床症状を呈する。
・甲状腺ホルモンの分泌低下、あるいは甲状腺ホルモン受容体の欠損(まれ)によって起こる。

臨床病態学 要点整理ノート
83
・20~50歳代の女性に多い。
・出生時から甲状腺機能低下があり、独特の顔貌(眼瞼がはれぼったく、鼻は低く、いつも口をあけ、
大きな舌を出している)、低身長、短い四肢、知能低下をきたすものをクレチン症(cretinism)とい
う。
・クレチン症の頻度は約 7,000人に 1人である。
・分類と原因
慢性甲状腺炎(橋本病) ・自己免疫疾患(慢性炎症→甲状腺組織の破壊→ホルモン産生低下)
その他まれな原因 ・TSH欠損、甲状腺ホルモン不応症、ヨード欠乏または過剰など
クレチン症 ・先天性の甲状腺発生異常、先天性酵素欠損症など
(2)診断
1)症状
・皮膚乾燥、嗄声、疲労感、動作緩慢、無気力、思考力の低下、基礎代謝低下、粘液水腫(圧痕を残さ
ない、ムコ多糖類の沈着)、寒さに弱い、食欲不振にもかかわらず体重増加など
・クレチン症では、低身長、知能低下など
2)検査
・甲状腺ホルモン(T4,T3)低値、甲状腺刺激ホルモン(TSH)高値(負のフィードバック作用の欠如)
・甲状腺シンチ:甲状腺放射性ヨード摂取率低値
・自己抗体陽性:抗サイログロブリン抗体、抗ミクロソーム抗体
・高コレステロール血症:コレステロールの生合成も低下するが、異化・排泄の低下がより大きいため
に、血清コレステロール値は上昇する。
・貧血:代謝の低下による
(3)治療
・薬物療法:甲状腺ホルモンの補充療法
・ヨード不足がある場合:ヨード含量の多い食品の摂取を増やす。
・ヨード過剰がある場合:慢性甲状腺炎がある場合、過剰なヨード摂取が甲状腺ホルモン合成を障害す
ることがあるので、過剰なヨード摂取を制限する。
・食事療法
低エネルギー食
・肥満予防を予防し、標準体重を維持する。
甲状腺ホルモンが不足している状態では、エネルギー代謝が低下しているの
で、体重が増加しないように、摂取エネルギーを制限する。
・甲状腺ホルモン補充療法により代謝が正常化すると、特別な食事療法は必要な
い。
脂質制限 ・高コレステロール血症を合併している場合は、コレステロール摂取を 300 ㎎/日
以下にし、P/S比を 1.2~2.0とする。
3.原発性アルドステロン症(primary aldosteronism、Conn症候群)
(1)病態
・副腎皮質からアルドステロンが過剰に分泌されて、高血圧、低 K血症、代謝性アルカローシスなどが
出現する疾患である。
・アルドステロンが過剰に分泌される原因として一側の良性腫瘍(80~90%)が多く、両側の過形成(10
~20%)のこともある。
・30~50歳代の女性に多い(男女比は 1:2)。
(2)診断
1)症状
・高血圧(Na+、水の貯留)

臨床病態学 要点整理ノート
84
・多飲・多尿(低 K血症による尿濃縮障害)
・筋力低下、周期性四肢麻痺(Na+濃度の上昇と K+濃度の低下→筋細胞の過分極)
四肢の麻痺発作を繰り返す。K代謝異常による筋線維内の興奮伝導障害が原因で起こる。
・テタニー(高度の低 K血症→代謝性アルカローシス→たんぱく質と結合する Ca2+が増加→イオン化し
た Ca2+濃度が低下→低 Ca血症の症状)
2)検査
・Conn の 3徴候
・血中アルドステロン高値(アルドステロン分泌過剰)
・血中レニン活性低値(レニン分泌抑制)
・尿中 17-ヒドロキシコルチコステロイド(17-OHCS)および 17-ケトステロイド(17-KS)排泄量正常
(主にコルチゾールの代謝産物)
・低 K血症(K排泄促進)
低 K血症は、尿細管上皮の空砲変性や間質の線維化を引き起こす。(低 K血症性腎症)
・代謝性アルカローシス(H+の排泄促進、低 K血症に伴う H+の細胞内への移動)
・CTなど副腎腫瘍を検出するための画像検査
(3)治療
・外科治療:腺腫の摘出
・薬物療法:利尿薬:抗アルドステロン薬(スピロノラクトンⓇ)を用いる。(K排泄性利尿薬(サイア
ザイド、ループ利尿薬)は、低 K血症を助長するので用いない。
・食事療法:減塩食
4.クッシング症候群(Cushing syndrome)
(1)病態
・慢性の糖質コルチコイド過剰分泌により、中心性肥満、高血圧、低 K血症、代謝性アルカローシスな
どが出現する疾患である。
・下垂体の ACTH 過剰分泌が原因である場合をクッシング病(Cushing's disease)という。
・クッシング病の 80~90%は下垂体の ACTH産生腺腫が原因である。
・副腎の過形成または腺腫による糖質コルチコイド過剰産生が原因である場合を、狭義のクッシング症
候群という。
・クッシング病と副腎腺腫の頻度は約 1:1である。
・20~40歳代の女性に多い(男女比 1.3:5)。
(2)診断
1)症状
・中心性肥満、満月様顔貌、水牛様脂肪沈着
・皮膚線条、多毛症、座瘡
・月経異常(無月経)
・高血圧(過剰のグルココルチコイドによりミネラルコルチコイド様の作用が出現する)
・四肢の筋萎縮、筋力低下
・骨粗鬆症
2)検査
・血中コルチゾール高値(デキサメタゾン抑制試験でも抑制されない)
・ACTH(クッシング病では高値、副腎腺腫では低値)
・赤血球と白血球増加(リンパ球と好酸球は減少)
・耐糖能障害(糖新生の促進、筋肉細胞や脂肪細胞へのグルコース取り込み抑制)
・高コレステロール血症
・低 K血症(K排泄の増加)

臨床病態学 要点整理ノート
85
・代謝性アルカローシス(低 K血症による細胞内 K+の流出に共役して、血中の H+が細胞内に移行する)
・下垂体・副腎の腫瘍検索のための画像検査
(3)治療
・下垂体腫瘍であっても副腎腺腫であっても、手術による摘出が原則である。
・肥満、糖尿病、脂質異常症を合併している場合は、低エネルギー食とする。
・高血圧症を合併している場合は、減塩食とする。
・骨粗鬆症を合併している場合は、カルシウム、ビタミン Dを補給する。
5.褐色細胞腫
(1)病態
・副腎髄質の細胞(交感神経節後ニューロン由来)から発生した腫瘍である。
・腫瘍細胞はカテコールアミン(アドレナリン、ノルアドレナリン、ドパミン)を産生・分泌する。
・「10%病」と呼ばれる。
副腎外発生が 10%、悪性例が 10%、両側発生が 10%、家族内発生が 10%ある。
(2)診断
・主な症状は、過剰なカテコールアミンの作用による高血圧、高血糖、代謝亢進、頭痛、発汗過多であ
る。
・診断は、尿中・血中カテコールアミンおよびその代謝産物を測定して行う。
アドレナリン、ノルアドレナリン、メタネフリン、バニリルマンデル酸(VMA)
(3)治療
・外科的腫瘍摘除
・薬物療法 高血圧 α遮断薬、β遮断薬
6.尿崩症
(1)病態
・下垂体後葉から分泌される抗利尿ホルモン(バソプレシン、AVP, arginine vasopressin、ADH, anti-
diuretic hormone)の合成、分泌、作用障害により、尿の濃縮ができないことが原因で起こる疾患で
ある。
・視床下部・下垂体後葉系の腫瘍、炎症、手術などによる傷害が原因となる。
・器質的な病変を認めない原因不明のものを、特発性中枢性尿崩症という。
(2)診断
・主な症状は、多尿、脱水、口渇、多飲である。
・主な検査所見は、尿浸透圧低下、血清 Na濃度軽度上昇、高張食塩水負荷試験での AVP反応不良、デス
モプレシン投与による尿浸透圧の上昇などである。
(3)治療
・デスモプレシン投与
デスモプレシンは、AVPの構造を修飾し、作用時間を延長、副作用を軽減したもの
7.抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH, syndrome of inappropriate secretion of ADH)
(1)病態
・抗利尿ホルモン(AVP)の分泌亢進により、体内に水が過剰貯留する病態である。
・原因は、異所性 AVP 分泌腫瘍(肺癌が多い)、AVP 分泌調節機構の異常(視床下部の浸透圧受容体の
異常、動脈の圧受容体の異常、肺炎などによる炎症性サイトカインによる AVP分泌過剰など)がある。

臨床病態学 要点整理ノート
86
(2)診断
・主な症状は、一般に無症状であるが、重症例では頭痛、倦怠感、悪心などが出現する。
・診断は、低血漿浸透圧にもかかわらず、血漿 AVP値が高値であることにより行う。
(3)治療
・水分摂取制限
・高張食塩水による血漿浸透圧の補正

臨床病態学 要点整理ノート
87
12.精神・神経疾患
1.脳血管障害(cerebrovascular disease, CVD)
(1)概要
・脳血管の破綻、狭窄、閉塞が原因となって、脳組織の障害を引き起こし、意識障害、言語障害、運動
障害、頭痛など障害部位に特有な症状(脳局所症候または巣症状という)が現われる。
・死因順位の第 4位(8.7%)である。(平成 27年人口動態統計)
1位 悪性腫瘍(28.7%)、2位 心疾患(15.2%)、3位 肺炎(9.4%)
・介護が必要になる原因疾患の第 2位(16.6%)である。(平成 28年国民生活基礎調査)
・近年、脳出血が減少し、脳梗塞が増加している。
(2)危険因子
・加齢、家族暦、高血圧、糖尿病、心臓病、脂質代謝異常、血液凝固異常、喫煙、多量飲酒など
・特に高血圧は脳卒中と関係が深く、脳卒中の危険は、至適血圧(110~119mmHg)に対し、軽症高血圧
で(140~159mmHg)約 3倍、中等度・重症高血圧で(160~mmHg)約 7倍になる。
(3)分類
1)脳梗塞(脳血管の閉塞、狭窄による血流が低下して、脳組織が壊死に陥る)
ラクナ梗塞
(30~45%)
・脳内の深部穿通動脈の閉塞による脳梗塞で、直径 15㎜未満の小梗塞巣が出現。
・睡眠中、朝覚醒時、安静時に発症することが多い。
・発生部位により感覚障害、運動麻痺が出現する。
・意識障害が出現することはない。
アテローム血
栓性脳梗塞
(20~
30%)
・脳動脈の粥状硬化巣に血栓が形成されて発症する。
・ふらつき、しびれ、など一過性脳虚血発作(数分)の前駆症状があることが多い。
・睡眠中、朝覚醒時、安静時に発症することが多い。
・閉塞部位により片麻痺など脳局所症候を示す。
・意識障害は軽いことが多い。

臨床病態学 要点整理ノート
88
心原性脳塞栓
(20~
35%)
・心房細動、心臓弁膜症など脳以外で形成された血栓が脳動脈に塞栓して発症する。
・昼夜を問わず突然発症し、前駆症状はない。
・塞栓部位により片麻痺など脳局所症候を示す。
・脳梗塞にくらべて意識障害が強いことが多い。
・CHADS2スコア:心房細動患者の心原性脳塞栓症のリスクファクターの評価
Congestive heart failure(うっ血性心不全)、Hypertension(高血圧)
Age(年齢 75歳以上)、Diabetes Meillitus(糖尿病)、Stroke or TIA(脳梗
塞または TIA の既往)、S は 2 点で、S 以外は 1 点でスコアを算出して合計点が 2
点以上の場合に抗凝固薬の適応
2)脳出血
・脳内の深部穿痛動脈に細小動脈瘤が形成され、それが破裂して脳実質内に出血が起こって発症する。
・出血はしばしば脳室内に穿破する。
・日中、活動中に発症することが多い。
・出血部位に特有な脳局所症候を示し、意識障害が強いことが多い。
3)クモ膜下出血
・クモ膜下腔を走行する動脈に脳動脈瘤が形成され、それが破裂してクモ膜下腔に出血が起こって発症
する。
・動・静脈奇形が原因でクモ膜下腔へ出血が起こって発症する場合もある。(10~15%)
・突然の激しい頭痛、髄膜刺激症状(項部硬直)を示すが、脳局所症候はない。
・40~60歳に好発する。
(4)発症率と死亡率
・頻度:脳梗塞(60~70%)>脳出血(20~30%)>くも膜下出血(10~15%)
・死亡率:クモ膜下出血(50%)>脳出血(10~20%)≒ 脳梗塞(10~20%)
(5)診断
1)症状
・脳局所症候:片麻痺、意識障害、運動麻痺、感覚障害、言語障害、視野障害など障害部位に特有な神
経学的症を示す。
・クモ膜下出血では脳局所症候は出現しない。
2)検査
・CTスキャン:脳出血:血腫(高吸収域)
脳梗塞:低吸収域(発作後 24時間以後出現)
・その他の画像診断:脳血管造影、MRIによる動脈瘤、動・静脈奇形の証明
・髄液検査:血性またはキサントクロミー(黄色)(脳室、クモ膜下腔への出血)
(6)治療
急性期
・安静
・脳浮腫予防のために 10%グリセロール液(浸透圧利尿作用)を点滴する。
・重症の脳出血では手術による血腫の除去。
・高齢者の脳梗塞で高血圧の治療に降圧剤を使う場合は血圧が下がり過ぎないように注
意する。
・脳梗塞発症 3時間以内であれば血栓溶解療法(プラスミノーゲン・アクチベーター)
が有効とされている。
・経口摂取ができないときは経腸栄養または経静脈栄養を行う。
・肺炎の予防のために定期的な体位変換を行う。

臨床病態学 要点整理ノート
89
回復期 ・急性期(約 1週間)を過ぎたら、後遺症ができるだけ残らないように積極的にリハビ
リテーションを行う。
予防
・危険因子の除去:高血圧、動脈硬化症など
高血圧の治療は、発症リスクを 38%減少させる。(Lancet (2001) 358, 1003)
・血栓,塞栓形成の予防:抗血小板薬(アスピリン)、抗凝固薬(ワルファリン)
食事療法 動脈硬化症と同じ。
2.認知症(dementia)
(1)概要
・認知症の 80%は、アルツハイマー病(Alzheimer’s disease)と脳血管性認知症(vascular dementia)
によって占められている。
・わが国では、脳血管性認知症が多いとされてきたが、近年の統計ではアルツハイマー病が過半数を占
めている。
・食事因子とアルツハイマー病発症
危険因子:高エネルギー、高脂質
防御因子:野菜、果物、魚
(2)主な認知症の型
アルツハイマー病 ・老人斑、アルツハイマー神経原線維変化、神経細胞消失、大脳萎縮が特徴
脳血管性認知症 ・まだら認知症、情動失禁(わずかな刺激で、情動がそのまま出てしまうこ
とで、些細なことで泣いたり、怒ったり、笑ったりする状態)
レビー小体型認知症 ・進行性認知障害、幻視体験、パーキンソン症状
前頭側頭型認知症
(ピック病など)
・前頭側頭葉の限局的で高度な萎縮を呈する認知症
・早期から人格障害、行動障害が出現することが特徴
(3)アルツハイマー病の病態
・老人斑にはアミロイドβたんぱく質(Aβ、amyloid β-protein)が沈着している。
・Aβの前駆体タンパク質である APP(β-amyloid precursor protein)は、神経細胞で作られる膜たん
ぱく質である。
・Aβは、APPが 2つのたんぱく質分解酵素(β-セレクターゼとプレセリニン)によって分解されて生
成する。
・正常な Aβは、ネプリライシンによって無害な断片に分解される。
・沈着した Aβには神経細胞に対する毒性があり、神経細胞を死滅させ脳萎縮を引き起こす。
・Aβは、グリア細胞に作用してシナプスでのグルタミン酸による伝達を抑制する。
(4)診断
1)認知症を疑う症状
・同じことを何回も言うようになった。
・とんちんかんな話が多くなった。
・以前のように外出したがらなくなり、家で何もせずじっとしていることが多い。
・中等症になると、火の不始末、物盗られ妄想が出現する。
・重症になると計算障害、尿失禁、着衣困難、迷子など日常生活の支障が目立つようになる。
2)主な症状
中核症状 ・もの忘れ、進行性、病識にかける、もの忘れは自覚しているが、深刻に考えない。
周辺症状
・痴呆の行動・心理学的兆候(BPSD、behavioral and psychological symptoms of
dementia)
・怒りっぽい(「人が盗んだ」などと怒り、人を責めるようになる)、夜間に大声を出す、
徘徊、迷子、食欲の異常、睡眠の異常など

臨床病態学 要点整理ノート
90
・夕暮れ症候群:夕方になると落ち着かなくなり、「家に帰る」と言ったり、幻覚・妄想
が出やすくなること
(5)治療
1)薬物療法
中核症状 ・ドネペジル(アリセプトⓇ):コリンエステラーゼ阻害薬
・進行を抑える可能性をもつ薬、臨床的な改善は 30%程度、主な副作用は消化器系症状
周辺症状 ・不眠 → 睡眠薬(短時間作用型)
・多動、不穏、暴力行為 → 非定型抗精神病薬
2)非薬物療法
・回想法、音楽療法、美術療法、園芸療法、学習療法、動物療法など
3.パーキンソン病(Parkinson disease)
(1)病態
・パーキンソン病の原因は、中脳黒質のドパミン神経細胞の消失である。
・ドパミン神経細胞の消失により、軸索の投射部位である線条体のドパミン含有量が低下することが、
パーキンソン病の症状に関係している。
・大脳基底核の機能障害により、錐体外路症状が出現する。
(2)診断
・パーキンソン病の 4大症状は、①安静時振戦、②無動、③筋固縮、④姿勢反射障害である。
安静時振戦
・振戦とは、ふるえのことで、安静時振戦とは、安静にしているときに手指や足が
細かく震える不随意運動ことをいう。
・症状は、片側の上肢または下肢から始まり、徐々に進行して両側性になる。
・随意運動によりふるえは減弱する。
無動 ・動作減少、動作緩慢、小声、小書字、瞬き減少、寝返り減少、仮面様顔貌、流涎
(唾液の嚥下減少による)など
筋固縮 ・腕の関節を伸展・屈曲するときにガクガクガクと断続的な抵抗を感じる歯車様固
縮が特徴である。
姿勢反射障害 ・前屈姿勢、突進現象、小刻み歩行、加速歩行(festinating gait)
自律神経障害 ・脂漏性顔貌、便秘、発汗が出現する。
精神症状 ・うつ傾向、認知症が出現する。
嚥下障害 ・約 50%に出現。咀嚼力の低下、嚥下力の低下が原因
(3)治療
・薬物療法:L-ドーパ(levodopa)、ドパミン受容体作動薬
・L-ドーパは、中性アミノ酸(large neutral amino acids, LNAA、ロイシン、バリン、イソロイシン、
チロシン、フェニルアラニン、メチオニン)の血液脳関門通過と拮抗するので、たんぱく質と一緒に
摂取すると作用が減弱する。
4.神経性食欲(食思)不振症(anorexia nervosa)
(1)病態
・肉体的に原因がなく、心因的な理由から拒食に陥り、極度のやせをきたす疾患である。
・主に、10~20代の女性において、多くはその年代に特有の心理的ストレスに対処できないことを契機
に、やせ願望や肥満恐怖に基づく食行動の異常のためにやせを来たす。
・思春期に特有な心理的ストレスを適切に処理する能力(コーピングスキル)が未熟なことが原因とな
って発症する心身症の一つである。

臨床病態学 要点整理ノート
91
(2)診断
1)厚生労働省特定疾患・神経性食欲不振症調査研究班による診断基準(1990)
1.標準体重の-20%以上のやせ
2.食行動の異常(不食、大食、隠れ食いなど)
3.体重や体型についての歪んだ認識(体重増加に対する極端な恐怖など)
4.発症年齢:30歳以下
5.(女性ならば)無月経
6.やせの原因と考えられる器質性疾患がない。
(備考)1、2、3、5は、既往歴を含む。(例えば、-20%以上のやせがかってあれば、現在はそうで
なくても基準を満たすとする。)6項目すべてを満たさないものは、疑診例として経過観察する。
1.ある時期に始まり、3ヶ月以上持続。典型例は、-25%以上やせている。-20%は、一応の目安で
ある。(他の条項をすべて満たしていれば、初期のケースなどでは、-20%に達していなくてもよ
い。)アメリカ精神医学会の基準(DSM-III-R)では-15%以上としている。標準体重は 15歳以上
では身長により算定(例、平田の方法)するが、15歳以下では実測値(例、日比の表)により求め
る。
2.食べないばかりでなく、経過中には大食になることが多い。大食には、しばしば自己誘発性嘔吐や
下剤・利尿剤乱用を伴う。その他、食物貯蔵、盗食などがみられる。また、過度に活動する傾向を
伴うことが多い。
3.極端なやせ願望、ボディーイメージの障害(例えば、ひどくやせていてもこれでよいと考えたり、
肥っていると感じたり、下腹や足など体のある部分がひどく肥っていると信じたりすること)など
を含む。これらの点では病的と思っていないことが多い。この項は、自分の希望する体重について
問診したり、低体重を維持しようとする患者の言動に着目すると明らかになることがある。
4.まれに 30歳をこえる。ほとんどは 25歳以下で思春期に多い。
5.性器出血がホルモン投与によってのみ起こる場合は無月経とする。その他の身体症状としては、う
ぶ毛密生、徐脈、便秘、低血圧、浮腫などを伴うことがある。ときに男性例がある。
6.精神分裂病による奇異な拒食、うつ病による食欲不振、単なる心因反応(身内の死亡など)による
一時的な摂食低下などを鑑別する。
2)その他の症状
・低体温、骨量減少、骨粗鬆症、貧血、白血球減少、血小板減少、低ナトリウム血症、低カリウム血症、
AST・ALT上昇、低血糖、歩行困難や起き上がれないなどの運動障害、意識障害などがある。
(2)治療
・治療はカウンセリングなど心理療法、行動療法、薬物療法を行う。
・薬物療法で使用される薬
・抗うつ剤(気分高揚、意欲亢進、不安沈静作用)
・抗不安薬(不安・緊張を解除、催眠作用)
・抗精神病薬(強い鎮静作用、主として精神分裂病に使用)
・栄養療法
・経口栄養を原則とし、患者が食べられるというものからはじめる。
・食べることを指示、強制しない。
・経口摂取が困難で、生命の危険が考えられるときは、本人の合意を得て経腸栄養または中心静脈栄養
による強制栄養実施する。
・強制栄養は体重増加には有効だが、輸液を捨てたり、針を抜いたりすることがある。

臨床病態学 要点整理ノート
92
5.神経性大食症(bulimia nervosa)
(1)病態・診断
・神経性食欲不振症の 1側面と考えられている。
・いわゆる過食と異なり体重増加はない。
・症状の特徴
・通常の食事とは異なる時間帯に大食することを反復する。
・食べ始めると自己制御できない。
・体重増加への嫌悪から自己誘発性嘔吐、下剤・利尿剤の使用、食事制限・絶食、激しい運動を行う
・少なくとも 3ヵ月間に、最低 1週間に平均 2回の大食のエピソードがある。
・体の形や体重に関心があり過ぎる。
(2)治療
・治療はカウンセリングなど心理療法、行動療法を行う。
・大食後の食欲を無理に抑制しないようすると大食すむようになることがある。
6.アルコール依存症(alcoholism)
(1)病態
・アルコール依存症は、精神依存型(飲酒抑制不能型)、精神身体依存型(離脱症状発現型)、身体症
状型に分類される。
・アルコールは、精神的抑制を解除し不安・緊張を除くので精神依存を生じやすい。
・また、アルコールの常用により耐性が形成されるため、次第に使用量が増加して身体依存も形成され
るようになる。
・そうなると飲酒の中断により離脱症状が出現するのでますます飲酒をやめられなくなる。
・アルコール依存症の人は、1 日に必要なエネルギーのほとんどをアルコールから摂取していることが
多く、本来の食事から摂取すべき栄養素が不足している場合が多い。
・振戦せん妄(小動物視、小人幻覚が特徴)、コルサコフ症候群(健忘症候群)、ウェルニッケ脳症(眼
球運動障害、失調性歩行、意識障害が三主徴、ビタミン B1欠乏が原因)などが出現することをアルコ
ール精神病という。
(2)診断
1)身体症状
・消化器系症状(胃炎、下痢、脂肪肝、肝硬変、膵炎)
・心血管系症状(心筋症、心肥大、動脈硬化症、末梢血管拡張、浮腫、腎障害)
・神経系症状(手の振るえ、ビタミン欠乏による多発性神経炎)
2)離脱症状
・振戦(手指、上下肢の振るえ)、幻覚、幻聴、軽い意識混濁、けいれん発作など。
(3)治療
・第一に禁酒が重要である。(制限は意味がない。制限できるのであれば、依存症にならない)
・禁酒後の離脱症状に対しては、適切な栄養補給、水・電解質の補液、ビタミン(B1、B2、C、ニコチン
酸など)投与を行う。
・必要に応じて精神安定剤や抗てんかん薬などを使用することがある。
・禁酒の継続のために抗酒薬・断酒補助剤が処方される場合がある。
抗酒薬は、エタノールが酸化してできるアセトアルデヒドの代謝を抑制し、アセトアルデヒドが蓄
積して頭痛、呼吸困難、血圧低下、嘔気、嘔吐などの症状が出現してそれ以上飲酒できなくする。
断酒補助剤は、中枢神経に作用して、アルコール依存により亢進したグルタミン酸作動性神経活動
を抑制することにより、飲酒に対する欲求を抑制する。
・アルコール依存症は、個人で禁酒を維持することが困難な場合が多く、カウンセリングなど適切な個
人精神療法、集団精神療法、社会復帰のためリハビリテーションなどが必要になる。

臨床病態学 要点整理ノート
93
・食生活の改善により、低栄養の予防と改善を図る。
7.薬物の乱用(drug abuse)
・ある物質を反復使用した後に、その物質の使用をやめることが困難になり、その物質の使用を中止す
ると特有な離脱症状が出現するようになったり、その物質の使用に対する耐性が出現したりするよう
になることをその物質に対する依存症という。
・薬物依存には、①薬物の特性、②薬物使用者の特性、③環境要因の 3つが関わっている。
・多幸感、陶酔感、興奮を起こす薬物は、精神依存を起こしやすい。
・耐性を作りやすい薬物は、身体依存を起こしやすい。
・麻薬は、モルヒネ型(アヘンアルカロイド、合成麻薬)、コカイン型,幻覚型(LSD など)に分類さ
れる。

臨床病態学 要点整理ノート
94
13.呼吸器疾患
1.慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)
(1)病態
・慢性の咳、痰、呼吸困難を主訴とし、緩やかに進行する不可逆的な疾患である。
・慢性気管支炎と肺気腫の病変がさまざまな程度に存在する。
慢性気管支炎とは、1 年のうち 3 か月以上(冬季)の咳・痰が 2 年以上持続するものをといい、臨
床症状に基づく診断である。
肺気腫とは、肺胞壁の破壊により終末細気管支より末梢の気腔が拡大した状態をいい、病理組織学
に基づく診断である。
・空気を吸い込むときは、肺が膨張するので、気道も開く。
・空気を吐き出すときは、肺が収縮するので、気道も押しつぶされて閉塞し、肺胞に入った空気を吐
き出せなくなる。
・肺の中に残る空気(残気量)が増加して、肺の過膨張が起き、肺胞構造が破壊される。
・中高年以降に発症し、わが国では 50歳以上の男性に多い。
・タバコ・大気汚染などの障害性の物質に対して異常な炎症反応が起こり、非可逆性の気道閉塞が進行
する。
外因性危険因子 喫煙、大気汚染、呼吸器感染症など
内因性危険因子 α1アンチトリプシン欠損症、気道過敏症、気管支喘息(慢性炎症による気道の
リモデリング)など
(2)診断
症状 ・自覚症状:慢性の咳、痰、息切れ、喘鳴、呼吸困難など
・他覚症状:口すぼめ呼吸、呼気の延長、呼吸音の減弱など
検査
・X線:肺野の透過性亢進、滴状心(tear drop heart)
・呼吸機能検査:気管支拡張薬投与後の 1秒率が 70%未満(診断基準)
全肺気量の増加、残気量・機能的残気量の増加
・動脈血ガス分析:血中 O2分圧の低下、血中 CO2分圧の上昇(ガス交換の障害)
・血液検査:血中フィッシャー比の低下
・口すぼめ呼吸は、呼吸効率を高め、息切れを軽減するために、口笛を吹くように口をすぼめてゆっく
りと息を吐く呼吸法である。気道内圧が上がるので、気道の閉塞・虚脱を防ぐことができる。
・高齢、喫煙指数高値、肺過膨張、低 O2血症、高 CO2血症、低栄養状態、体重減少、運動耐容能低下な
どは、予後が悪い因子である。
・COPD の病期分類
病期 1秒量
Ⅰ期 軽度の気流閉塞 80%以上
Ⅱ期 中等度の気流閉塞 50~80%
Ⅲ期 高度の気流閉塞 30~50%
Ⅳ期 きわめて高度の気流閉塞 30%未満
(3)治療
1)禁煙
・喫煙は、COPD 発症要因の 90%を占めている。
・喫煙は、加齢による 1秒率の低下を加速する。

臨床病態学 要点整理ノート
95
2)薬物療法
・安定期の薬物療法
・気管支拡張薬:抗コリン薬(副交感神経遮断薬)、β2刺激薬(交感神経刺激薬)、テオフィリン
薬)
・抗炎症薬:ステロイド薬(吸入)
・増悪期の薬物療法
・ABC 療法:抗菌薬(antibiotics)、気管支拡張薬(bronchodilators)、ステロイド薬
(corticosteroids)(内服)
3)在宅酸素療法
・安静時室内空気呼吸下で動脈血 O2分圧が 60Torr(mmHg)以下の場合は酸素吸入が必要
・在宅酸素療法は、患者の QOL改善、入院回数の減少、生命予後を改善する。
4)栄養療法
高エネルギー食
・努力して呼吸を行うために安静時エネルギー消費量が増加しており、さらに食欲
低下が加わってたんぱく質・エネルギー欠乏症(protein energy malnutrition,
PEM)をきたしやすい。
・投与エネルギー=実測 REE×1.5または予測 REE×1.7とする。
少量頻回食 ・肺の過膨張により、横隔膜が押し下げられるために生じる腹部膨満感を予防
分岐鎖アミノ酸
・分岐鎖アミノ酸(branched chain amino acids,BCAA)は骨格筋量の減少を抑制
する。
・分岐鎖アミノ酸は、筋肉たんぱく質の約 35%を占めている。
高脂質食
・呼吸商が低下し、CO2 産生量が少なくなるので有利とする考え方もあるが、適正
なエネルギー量では、糖質と脂質の比率は CO2産生量に影響しないという報告も
ある。
2.気管支喘息(bronchial asthma)
(1)病態
・気道閉塞が特徴で、発作性の咳、喘鳴、呼吸困難を生じる気道の慢性炎症性疾患である。
・発作時にみられる気道閉塞は可逆的であり、自然にあるいは治療により改善する。
・気道の過敏が原因であり、アレルゲンによる特異的刺激や寒冷・大気汚染など非特異的刺激により気
道が閉塞して発作が生じる。
・アスピリンなど非ステロイド系解熱性鎮痛薬により誘発されるものをアスピリン喘息という。
・運動により換気が増大し、気道の冷却、水分の喪失により誘発されるものを運動誘発喘息という。
・原因アレルゲンがあるものをアトピー型、ないものを非アトピー型という。
・小児の 90%以上がアトピー型であり、成人の 30%は非アトピー型である。
(2)診断
1)症状
・自覚症状:発作性の咳、喘鳴、呼吸困難
・他覚症状:呼気延長、連続性ラ音
・安定期には無症状のことが多い。
2)検査
・呼吸機能検査:発作時の 1秒率低下(閉塞性換気障害)、ピークフロー低下
・アレルゲン検索:皮膚テスト、特異的 IgE陽性(RAST, radioallergosorbent test)

臨床病態学 要点整理ノート
96
RIST
(radioimmunosorbent test)
・抗 IgE 抗体と 125I でラベルした IgE の結合を患者の IgE がどの程
度阻止するかを測定する。(総 IgE 量を測定)
RAST
(radioallergosorbent test)
・抗原に結合した患者の IgE を 125I でラベルした抗 IgE 抗体で検出
する。(特異的なアレルゲンの検出に有用)
(3)治療
・気管支拡張薬:2刺激薬やテオフィリン薬を軽症では吸入で、中等・重症では静注で使用する。
・抗炎症薬:吸入ステロイド薬(中等症以上で吸入)
3.気管支炎(bronchitis)・肺炎(pneumonitis)
(1)病態
・気管・気管支の炎症を気管支炎といい、肺胞腔内に炎症が及んだものを肺炎という。
・気管支炎は、かぜ症候群に引き続いて起こることが多く、ウイルスや二次性細菌感染が原因になる。
・通常の生活をしている健康人のみられる肺炎を市中肺炎といい、入院中の患者が肺炎を発症した場合
を院内肺炎という。
・市中肺炎は、肺炎双球菌やインフルエンザ菌など一般細菌感染による細菌性肺炎とマイコプラズマ、
肺炎クラミジア、ウイルスによる非定型肺炎に分類される。
・院内肺炎の原因菌は、緑膿菌と黄色ブドウ球菌(MRSA など)が多い。
・食物や吐物の誤嚥による肺炎を、嚥下性肺炎という。
(2)診断
1)症状
・自覚症状:発熱、咳、痰
・他覚症状:聴診によるラ音の聴取
2)検査
・X 線検査:肺野の異常陰影
・血液検査:白血球増加、赤沈亢進、CRP上昇(陽性)など炎症所見
マイコプラズマ肺炎など非定型肺炎では白血球は増加しない。
・喀痰の細菌検査:菌の検出、薬剤感受性
(3)治療
・一般細菌に対しては、ペニシリン系・セフェム系の抗生物質が第 1選択薬になる。
・マイコプラズマに対しては、マクロライド系・テトラサイクリン系の抗生物質が第 1 選択薬になる。
・クラミジア肺炎に対しては、テトラサイクリン系の抗生物質が第 1選択薬になる。

臨床病態学 要点整理ノート
97
4.肺結核症(pulmonary tuberculosis)
(1)病態
・結核とは、結核菌による感染症であり、肺に病巣を形成したものを肺結核症という。
・結核の多くは、飛沫感染により気道を介して感染する。
・感染者のうち発症するのは、約 10%である。
・体内に侵入した結核菌は、マクロファージに貪食され、特異的細胞性免疫を誘導する。
・結核菌が活性化したマクロファージにより病巣に封じ込められ、殺菌されることにより感染は終息す
るが、一部の結核菌は生存し続ける。
・初感染により発症したものを一次結核症という。
・初感染を封じ込めた後、数年~数十年して宿主の免疫力が低下してしたときに発症するものを再燃性
結核症という。
・平成 14 年現在の結核の登録者数は 82,974 人であり、死亡者数は 2,316 人、死因順位は 25 位であっ
た。
(2)診断
1)症状
・自覚症状:咳、血痰、発熱、寝汗、体重減少、全身倦怠感など。
初感染は無症状であることが多い。
2)検査
・胸部 X線検査:浸潤影、結節影、空洞など。上肺野に多い。
・ツベルクリン検査陽性(感染の有無を判定する。発症の判定ではない)
・PPD(purified protein derivative)を皮内に摂取して 48 時間後に発赤や硬結の有無により判定す
る。PPD は、結核菌から抽出したたんぱく質であり、結核菌感染の既往がある人では、細胞性免疫に
よる遅延型過敏反応を誘発する。感染がなくても BCG 接種によって陽性になる。患者の免疫能が低下
すると感染していても陰性になることがある。
・喀痰・胃液の結核菌検査
・血液検査では赤沈亢進以外に異常を認めないことが多い。
(3)治療
1)薬物療法(化学療法)
・抗結核薬:イソニアシド(INH)、リファンピシン(RFP)、ストレプトマイシン(SM)ピラジナミド
(PZA)、エタンブトール(EB)など
・通常は 2~3剤を併用して治療する。(耐性菌の発現頻度を減少させるため)
2)外科療法
・薬物療法が無効なときに行われる。
(4)予防
・わが国では結核予防法に基づいて健康診断(ツベルクリン反応・胸部 X線検査)、予防接種(BCG)、
患者管理、医療の公費負担が体系化されている。
・BCG(Bacille de Calmette et Guérin カルメット・ゲラン桿菌)は、ウシ型結核菌の実験室培養を繰
り返して、ヒトに対する毒性が失われて抗原性だけが残った結核菌である。BCG は、ワクチンとして
ヒトに摂取して結核に対する免疫を獲得させることにより、結核感染を予防する。
・医師は、結核症患者の治療を開始するときには 2日以内に保健所に届け出る義務がある。
・若年者の結核罹患率およびツベルクリン検査で発症が発見される確率が極めてひくいため、小学 1年
および中学 1年時のツベルクリン検査と BCG再接種は平成 15年から中止された。
・BCG接種前の乳幼児ではほとんどが陰性であるため、平成 17年から乳幼児の BCG接種前のツベルクリ
ン検査を廃止した。

臨床病態学 要点整理ノート
98
14.血液疾患
1.赤血球恒数(mean corpuscular constants)
平均赤血球容積
(mean corpuscular volume, MCV)
・赤血球 1個あたりの容積を表す。
・MCV = Ht÷RBC×10(fl)(f:femto,10-15)
・MCVの基準範囲:83~93(fl)
平均赤血球ヘモグロビン量
(mean corpuscular hemoglobin, MCH)
・赤血球 1個あたりのヘモグロビン量を表す。
・MCH= Hb÷RBC×10(pg)(p:pico,10-12)
・MCHの基準範囲:27~32(pg)
平均赤血球ヘモグロビン濃度
(mean corpuscular hemoglobin
concentration, MCHC)
・赤血球中のヘモグロビン濃度を%表す。
・MCHC = Hb÷Ht×100(%)
・MCHC: 32~36(%)
・赤血球恒数による貧血の分類
大球性貧血(一般に正色素)
MCV>93、MCH>32
・DNA 合成障害により細胞分裂ができないので大球性(巨赤芽
球)になる。成熟できずに崩壊(無効造血)して貧血になる。
・悪性貧血(ビタミン B12欠乏)、葉酸欠乏
正球性正色素性貧血
MCV 正常、MCH正常、MCHC 正常
・急性の失血、溶血などにより血液中の赤血球が失われて貧血
になる。
・骨髄での赤血球産生が低下するために貧血になる。
・再生不良性貧血、白血病、癌の骨髄転移、放射線、抗ガン剤
小球性低色素性貧血
MCV<83、MCH<27、MCHC<32
・ヘモグロビン合成障害のためにヘモグロビン含量の少ない小
型の赤血球が産生される。
・鉄欠乏性貧血、ヘモグロビン異常症
2.鉄欠乏性貧血(iron deficiency anemia)
(1)病態
・鉄の摂取不足あるいは喪失増加が原因となり、赤芽球でのヘモグロビン合成が低下するために、小球
性低色素性の貧血を呈する。
・人口の約 10~20%が貧血で、その約 70%が鉄欠乏性貧血である。
・主な原因
吸収の低下 ・胃切除後症候群、偏食、甲状腺機能低下症など。
喪失の増加
・男性では胃潰瘍、腸ポリープ、痔など消化管出血が多い。
・女性では、子宮筋腫、月経過多などが多い。
・その他、寄生虫(鉤虫症)による消化管出血など。
需要の増加 ・妊娠、授乳、乳児期、思春期の発育、スポーツ貧血など。
・体内の鉄が欠乏する順序
①貯蔵鉄の減少 ・潜在的な鉄欠乏状態で、血清フェリチン値が低下する。
②貯蔵鉄枯渇 ・血清鉄が低下する。
③顕性貧血 ・ヘモグロビン合成が低下する。
④組織鉄欠乏 ・重症の鉄欠乏が長期間続くと皮膚・粘膜の異常が出現する。
(2)診断
1)症状
・ヘモグロビン不足による酸素供給低下症状
・全身症状:倦怠感、動悸、息切れ、頻脈
・中枢神経症状:頭痛、頭重感、めまい、眠気
・皮膚症状:皮膚・粘膜蒼白,眼瞼結膜蒼白

臨床病態学 要点整理ノート
99
・組織鉄の不足による症状
・爪のスプーン状陥凹、舌炎、口腔粘膜の萎縮、下咽頭と食道の間に水かき様の粘膜形成物(ウェッブ)、
嚥下困難(プランマー・ビンソン症候群)、異食症(土をかじる)
2)検査
・ヘモグロビン:男 14g/dl未満、女 12g/dl未満(国民栄養調査の基準)
男 13g/dl未満、女 12g/dl未満、小児・妊婦 11g/dl(WHO基準)
・小球性低色素性貧血(MCV<80,MCH<25、MCHC<31)
・血清鉄低下、総鉄結合能(TIBC)と不飽和鉄結合能(UIBC)は増加
通常,血清鉄は、トランスフェリンの鉄結合部位の約 3分の 1を占めている。
TIBCは、トランスフェリンが結合できる鉄の総量、UIBC=TIBC-血清鉄
・血清フェリチンは低下
フェリチンは鉄と結合して、鉄を組織に貯蔵するたんぱく質である。
血清フェリチンは、一部が血液中に流出したもので、貯蔵鉄量を反映している。
・骨髄は小型の赤芽球の過形成
(3)治療
1)原因疾患の除去
2)薬物療法(顕性貧血の場合、食事療法だけでは回復しない)
・紅茶・緑茶などタンニンを含むものは鉄の吸収を抑制することから、従来、鉄剤投与前後 1 時間は、
緑茶、コーヒーを禁止するとされてきたが、投与される鉄剤は比較的大量(100~200 ㎎/日)である
ためタンニンの影響は少ないと考えられ、現在では禁止する必要はないとされている。
・貯蔵鉄の不足を補うために、ヘモグロビン正常化後数ヵ月は投与を続ける。
・重症、吸収不全がある時は鉄剤を静脈注射する。40~80㎎/日ずつ投与する。
・中尾の式:投与量(mg)={2.7×(16-Hb値)+17}×体重(kg)
3)食事療法(薬物療法の補助及び貧血の予防)
・鉄を多く含む食品:肝臓、シジミ、ひじき、など
・ヘム鉄を多く含む動物性食品(肉,レバー)は鉄の吸収率が良い(15~25%)
・非ヘム鉄の吸収率は 2~5%である。動物性蛋白質と同時に摂取すると吸収率増加する。
・香辛料による胃酸分泌亢進やビタミン Cの摂取は鉄の吸収を促進する。
3.巨赤芽球性貧血(megaloblastic anemia)
(1)病態
・テトラヒドロ葉酸は、メチレンテトラヒドロ葉酸、ジヒドロ葉酸を経て、再びテトラヒドロ葉酸に戻
る。メチレンテトラヒドロ葉酸をジヒドロ葉酸に変換する酵素がチミジル酸合成酵素であるが、この
時同時に UMP(ウリジル酸)を TMP(チミジル酸)へ変換する。葉酸が欠乏するとテトラヒドロ葉酸が
減少するで、結果として TMP の産生も減少する。TMP は、DNA 合成の材料なので、DNA 合成が遅れて、

臨床病態学 要点整理ノート
100
赤芽球の分裂も遅れる。一方、UMP を利用する RNA 合成は障害されないので、たんぱく質合成は継続
する。その結果、骨髄中に巨赤芽球が出現する。
・これとは別に、メチレンテトラヒドロ葉酸は、メチルテトラヒドロ葉酸を経てテトラヒドロ葉酸に戻
る経路もある。メチルテトラヒドロ葉酸をテトラヒドロ葉酸に変換する酵素がメチオニン合成酵素で、
ビタミン B12を補酵素として、ホモシステインをメチオニンに変換する。ビタミン B12が欠乏するとメ
チルテトラヒドロ葉酸が蓄積する。これを葉酸トラップという。その結果、テトラヒドロ葉酸が欠乏
し、その影響で葉酸欠乏と同様の機序で DNA合成が遅れ、巨赤芽球が出現する。
・巨赤芽球は、結局成熟することができずに崩壊するので貧血になる。これを無効造血という。
・ビタミン B12または葉酸が欠乏すると UMP(ウリジル酸)から TMP(チミジル酸)への変換(チミジル
酸合成酵素)が障害される。TMP は DNA 合成の材料になるので、DNA 合成が阻害されて赤芽球の分裂
が遅れる。一方、UMPを利用する RNA合成は障害されないのでたんぱく質合成は継続する。その結果、
骨髄中に巨赤芽球が出現する。
・巨赤芽球の多くは、成熟できずに崩壊することから貧血になる。(無効造血)
・悪性貧血(pernicious anemia)は、内因子欠乏によるビタミン B12吸収障害があって貧血をきたす疾
患で、放置するとメチオニン不足による神経障害を伴って死にいたる。
・悪性貧血の原因は、胃粘膜の萎縮(慢性萎縮性胃炎)または自己抗体による壁細胞の破壊である。
・メチオニン合成酵素機能低下→髄鞘の維持不十分→亜急性連合性脊髄変性症
脊髄後索障害(深部感覚障害)、脊髄側索障害(錐体路障害)、末梢神経障害
・胃切除後、萎縮性胃炎、先天性内因子欠損などが原因となる。
・ビタミン B12は通常肝臓に 3~6年分貯蔵されているので、胃切除後 3~6年して発症する。
・葉酸欠乏による巨赤芽球性貧血では神経障害はみられない。
(2)内因子とビタミン B12の吸収
・食物中のビタミン B12は、まず唾液中の R因子と結合する。
・胃の壁細胞から内因子が分泌される。
・十二指腸で R因子は分解され、ビタミン B12は内因子と結合する。
・内因子―ビタミン B12複合体は回腸末端の腸上皮細胞の内因子受容体を介して吸収される。
・吸収されたビタミン B12はトランスコバラミンと結合して肝臓に運ばれ貯蔵される。
(2)診断
1)症状
・貧血症状
・DNA合成障害:ハンター舌炎(赤みを帯び、つるつるし、痛みを伴う)
・神経障害:四肢のしびれ、知覚麻痺、歩行障害など
2)検査
・大球性貧血(MCV>101,MCH>32)(一般に正色素性)
・汎血球減少症(赤血球、白血球、血小板すべてが減少)がみられる。
・好中球の核の過分葉がみられる。
成熟した好中球(分葉核好中球)の核は、正常でも 2~4個に分葉している。
ビタミン B12欠乏による悪性貧血では、核が 5個以上に分葉する過分葉が出現する。
・骨髄検査:巨赤芽球増加
・血清中ビタミン B12または葉酸低値
・シリング試験(ビタミン B12吸収試験)
放射性コバルトでラベルしたビタミン B12を経口投与して、尿中に排泄される放射活性を測定する。
第 1ステップは、B12のみ、第 2ステップは B12+内因子を投与する。
・無効造血により骨髄内での赤血球崩壊が促進するので、間接ビリルビン値と LDH(LDH1アイソザイム)
が上昇する。

臨床病態学 要点整理ノート
101
(3)治療
1)ビタミン B12欠乏
・ビタミン B12筋肉注射(経口投与は吸収率が悪い)
・ビタミン B12を多く含む食品(肝、肉、貝、海草)を多く摂取する。
2)葉酸欠乏
・葉酸経口投与
・葉酸を多く含む食品(肉、緑黄色野菜、酵母など)を多くする。
・葉酸は加熱で分解されやすいので、調理法に注意する。
4.その他の貧血
(1)溶血性貧血(hemolytic anemia)
・成熟した赤血球の末梢血中での寿命が短縮したために起こる貧血(正球性正色素性)である。
・赤血球の産生は亢進し、幼弱な網赤血球が末梢血中に多数出現するようになる。
・ヘモグロビン分解の増加により、間接ビリルビン優位の黄疸が出現する。
・血中ハプトグロビン濃度は、溶血した赤血球から放出される多量のヘモグロビンを処理するために消
費されるので、低下する。
ハプトグロビンは、ヘモグロビンの輸送たんぱく質である。
ヘモグロビン‐ハプトグロビン複合体は、網内系の細胞に取り込まれて分解される。
・赤血球に対する自己抗体による自己免疫性溶血性貧血などがある。
・先天性の場合は摘脾(脾臓の摘出手術)を行う。(脾臓は赤血球破壊の場なので)
・自己免疫性溶血性貧血の場合は副腎皮質ステロイドホルモンが使用される。
・貧血に対しては輸血が行われる。
(2)再生不良性貧血(aplastic anemia)
・骨髄の多能性幹細胞の障害のために貧血(正球性正色素性)だけでなく、白血球,血小板も減少する
汎血球減少症が出現する。
・まれに急性肝炎後に出現することがある。
・貧血に対して輸血が行われる。
・薬物療法:副腎皮質ホルモン、たんぱく質同化ホルモン、男性ホルモンなど
(3)慢性炎症に伴う貧血
・炎症性サイトカイン IL-6の作用で、肝臓からヘプシジンの分泌が増加する。
・ヘプシジンは、フェロポルチンを介して、腸管からの鉄の吸収を抑制し、網内系からの鉄の動員を抑
制するホルモンである。
・フェロポルチンは、細胞膜に存在して細胞内の鉄を細胞が排出する輸送担体である。
・慢性炎症では鉄の利用障害が起こり、小球性低色素性貧血を起こす。
・血液検査では、血清鉄と総鉄結合能(TIBC)は減少し、フェリチンが増加する。
5.白血病(leukemia)
・白血病とは悪性化した血液細胞(白血病細胞)が著明に増加する疾患である。
・白血病細胞の形態により急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性
白血病などに分類される。
・骨髄は白血病細胞で占められるために、赤血球と血小板の合成が低下して貧血(正球性正色素性)、
血小板減少による出血、正常白血球の減少による感染症が出現する。
・染色体異常
・t(8;14) バーキットリンパ腫
・t(8;21) 急性骨髄性白血病〈M2〉
・t(9;22) 慢性骨髄性白血病や急性リンパ性白血病の一部(いわゆるフィラデルフィア染色体)
・t(14;18) 濾胞性リンパ腫

臨床病態学 要点整理ノート
102
・t(15;17) 急性前骨髄球性白血病(急性骨髄性白血病〈M3〉)
6.多発性骨髄腫(multiple myeloma)
・形質細胞(plasma cell)由来の悪性腫瘍である。
・薬物療法
分子標的薬 ボルテゾミブ
カルフィルゾミブ
・不要となったタンパク質を分解する酵素であるプロテアソー
ムの働きを阻害することにより骨髄腫細胞の増殖を抑制する。
免疫調節薬
レナリドミド
サリドマイド
ポマリドミド
・体内の免疫の働きを調整することで、骨髄腫細胞の増殖を抑制
する。
MP療法 メルファラン
プレドニゾロン
・従来の標準治療
6.出血傾向(bleeding tendency)
(1)血管の異常
・先天的なもの:遺伝性出血性毛細血管拡張症(オスラー病)など
・後天的なもの:単純性紫斑病、老人性紫斑病、ビタミン C不足など
(2)血小板の異常
・血小板数が減少するもの:特発性血小板減少性紫斑病(ITP、idiopathic thrombocytopenic purpura)
など。ITPの原因は、自己抗体による血小板の破壊亢進
・血小板数が増加するもの:血小板増多症など
・血小板の機能異常によるもの:血小板機能異常症など
(3)凝固異常
・血友病には血友病 A(第Ⅷ因子欠乏、古典的血友病)、血友病 B(第Ⅸ因子欠乏、Chrismtmas 病)の
二病型がある。
・血友病は、伴性劣性遺伝するので発症するのは男性だけであり、女性は保因者となるが発症しない。
・von Willebrand病は von Willebrand因子が欠乏する先天的凝固異常で、常染色体優性遺伝する。
・von Willebrand因子は第Ⅷ因子と複合体を形成し、第Ⅷ因子の安定化に関与している。
(4)播種性血管内凝固症候群(DIC, disseminated intravascular coagulation)
・何らかの理由で、全身の血管内で血栓が作られ、消費による血小板と凝固因子の減少による出血傾向
が出現する。
・検査所見
・血小板数の減少
・血漿フィブリノーゲン値の低下
・血栓の分解産物であるフィブリン分解物の増加
・プロトロンビン時間(PT)の延長

臨床病態学 要点整理ノート
103
15.運動器系疾患
1.骨粗鬆症(osteoporosis)
(1)概要
・全身的に骨量が減少し、骨微細構造の変化が起こる。
・その結果、骨脆弱性が増大し、骨折の危険性が高まる。
・骨組織中のミネラル成分と非ミネラル成分の比率が、著しく低下することはない。(骨の質的変化は
少ない)
・骨量は、16~18歳で最大骨塩量に達し、30~40歳以後、加齢とともに減少する。
・危険因子
低栄養、低体重、高年齢、女性、運動不足、喫煙、過度のアルコール摂取、過度のカフェイン摂取(利
尿作用により Ca排泄増加)、Ca摂取不足、ビタミン D 不足、ビタミン K不足、女性ホルモン不足
状態など
(2)分類
老人性骨粗鬆症
・加齢によりビタミン Dなどホルモン産生が低下する。
・腸管からの Ca 吸収が低下し、体内の Ca量が減少する。
・骨形成・骨吸収ともに低下するが、骨形成速度がより低下するために骨の減
少が起こる。(低代謝回転型)
・血中 Ca 濃度が低下すると、副甲状腺から PTHが分泌されて、血清 Ca濃度を
基準範囲内に保つ。(二次性副甲状腺機能亢進症)
・70歳以上の男性に多く、進行は遅い。
閉経後骨粗鬆症
・閉経によりエストロゲン不足となり、骨吸収が亢進する。
・骨形成・骨吸収ともに亢進するが、骨吸収速度がより高いために骨の減少が
起こる。(高代謝回転型)
・血中 Ca 濃度が上昇すると、副甲状腺から PTHの分泌が低下し、尿中 Ca排泄
を増加させて、血清 Ca濃度は基準範囲内に保つ。(二次性副甲状腺機能低下
症)
・PTH の分泌が低下により、活性型ビタミン D 産生が低下するので、腸管から
の Ca吸収が低下して、さらに骨形成が低下する。
・50~60歳台の閉経後の女性に多く、進行は速い。
3)続発性骨粗鬆症
副腎皮質ホルモン
・腸管での Ca 吸収の抑制、腎での Ca 再吸収抑制により、二次性副甲状腺機能
亢進症を引き起こす。
・骨組織に対しても、骨芽細胞の活動を抑制し、破骨細胞の活動を亢進させる。

臨床病態学 要点整理ノート
104
糖尿病
・インスリンの作用不足により骨芽細胞の活動が低下する。
・尿糖の排泄は Caの尿中排泄を促進し、二次性副甲状腺機能亢進症を引き起こ
す。
腎不全 ・ビタミン D 活性化の障害により、Ca 吸収が低下して二次性副甲状腺機能亢進
症を引き起こす。
胃切除後症候群 ・胃酸の不足により Caのイオン化が減少し、Ca吸収が低下して二次性副甲状腺
機能亢進症を引き起こす。
甲状腺機能亢進症
(バセドウ病)
・甲状腺ホルモンが破骨細胞を活性化する。
(3)診断
1)症状
・腰痛、背部痛、骨折(腰椎・胸椎の圧迫骨折、大腿骨頚部骨折)など
2)検査
・血清 Ca、P 濃度は、基準範囲内に保たれる。
・血清アルカリホスファターゼ値は、軽度上昇する。
・X 線検査:骨梁減少、骨皮質菲薄
・骨塩測定:二重 X線吸収測定法(DEXA, dual energy X-ray absorptiometry 法)、超音波骨量測定装
置
DEXA法は、骨に二種類のエネルギーの X線を照射し、X線の骨による吸収の差を利用して骨塩量を
測定
・骨代謝マーカー(わずかな骨代謝回転の異常を検出)
骨吸収マーカー
・破骨細胞産物など破骨細胞の活動性を表す指標
・Ⅰ型コラーゲン N末端架橋テロペプチド(NTX)
・Ⅰ型コラーゲン C末端架橋テロペプチド(NCX)
・酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ(TRACP-5b)
・デオキシピリジノリン(DPD)
骨形成マーカー ・骨型アルカリホスファターゼ(BAP)
・Ⅰ型コラーゲン Nプロペプチド(PINP)
骨マトリックス
関連マーカー
・低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)
・オステオカルシンは、骨芽細胞の最終分化段階で分泌されるたんぱく質で、骨の
非コラーゲンたんぱく質の 10~20%を占めている。
・骨へのカルシウム沈着を抑制する作用がある。骨形成が活発になると血中濃度が
上昇する。
(4)治療
1)食事療法
・十分な Ca(800~900㎎/日)と良質のたんぱく質を含むバランスの良い食事が原則
・高齢者、閉経後女性では Caの吸収が低下しているので、1,500㎎/日を目標(上限 2,500㎎/日)とす
る。
・骨形成に影響する食品
Ca を多く含む食品 乳製品(吸収率 50%)、大豆・大豆製品(吸収率 50%)、野菜(小松菜、ご
ま)(吸収率 50%)、魚(吸収率 30%)、海藻類(吸収率 20%)
ビタミン D 干ししいたけ、いわし、かつお、ぶり、さんま、レバー、バター、卵黄など
ビタミン K わかめ、納豆、あしたば、こまつな、しゅんぎく、キャベツなど
マグネシウム 小えび、梨、バナナ、くるみ、アスパラガス、きゅうりなど
Ca吸収を
抑制する食品
・食物繊維(穀物,海藻など):Ca吸着
・P(インスタント食品など):カルシウム塩形成

臨床病態学 要点整理ノート
105
・蓚酸(ほうれん草,春菊など緑黄色野菜):カルシウム塩形成
・大量のアルコール:肝機能障害により、ビタミン D活性化不足
・油脂:Ca吸収抑制
・低たんぱく食
Ca排泄を
促進する食品
・過剰な食塩:Caの尿中排泄を促進(Naと Ca排泄は比例する)
・P制限:Ca排泄が増加
・過剰なたんぱく質摂取:Ca 吸収の増加、体内の酸の産生増加に伴う骨吸収
の増加、酸の排泄増加による Ca再吸収の抑制により Caの尿中排泄を促進
2)薬物療法
・Ca 製剤、カルシトニン(筋注製剤)、活性型ビタミン D、エストロゲン(閉経後骨粗鬆症)、ビスホ
スホネート、ラロキシフェン
ビスホスホネート
・ピロリン酸と類似の構造を有することから、ヒドロキシアパタイトに強い親
和性を持ち、骨の石灰化面に取り込まれる。
・低用量では、骨吸収を抑制し、高容量では骨の石灰化を抑制する。
・骨組織に沈着し、破骨細胞に貪食され、破骨細胞の活動を抑制することによ
り、骨吸収を抑制する。
・食事と一緒に摂取すると、食事中の Ca と塩を形成し吸収されないので、摂
取後 30 分以上は何も食べないようにする。
ラロキシフェン
・エストロゲン受容体に作用し破骨細胞の活動を抑制する。
・子宮、乳腺ではエストロゲンの作用に拮抗する。
・閉経後骨粗鬆症が適応であるが、更年期障害の症状が強い人は避ける。
3)運動療法
・骨量の増加、運動機能の改善、脊椎運動機能障害による慢性の腰痛の改善が期待される。
・ウォーキング、体操療法(腰痛体操)などを行う。
2.くる病(rachitis, rickets)・骨軟化症(osteomalacia)
(1)病態
・血清 Ca濃度および血清 P濃度の低下による、骨石灰化障害である。
・主な原因は、ビタミン D欠乏による Ca,Pの吸収障害である。
・骨端線閉鎖前の小児に発症した場合をくる病といい、骨端線閉鎖後の成人に発症した場合を骨軟化症
という。
・原因
閉塞性黄疸
膵臓疾患
・脂肪の吸収障害→ビタミン D吸収障害→Caの吸収障害
・腸管内の脂肪が増加すると、Ca不溶性のスープを形成→Caの吸収障害
胃切除後症候群
過剰の制酸剤
・胆嚢・膵機能障害→脂質消化障害→ビタミン D吸収障害→Caの吸収障害
・胃酸不足による Ca溶解性低下→Caの吸収障害
妊娠授乳中 ・Ca、Pの必要量増加
過剰な食物繊維
過剰な P摂取 ・食物中の Caと結合→Caの吸収障害
腎不全 ・ビタミン D活性化不足→Caの吸収障害
・高 P血症,低 Ca血症→Caと Pの不均衡→骨石灰化障害

臨床病態学 要点整理ノート
106
イタイイタイ病
・カドミウム蓄積→尿細管の再吸収障害
・Ca 排泄増加による骨塩の減少と低 P 血症による骨石灰化障害により骨軟化症
が起こる。
(2)診断
1)症状
・低 Ca血症による痙攣(テタニー)
・小児では骨格変形、低身長など、成人では骨痛、筋力低下、歩行障害など
2)検査
・低 Ca血症、低 P血症、アルカリホスファターゼ上昇
・X 線検査:骨陰影低下、骨梁構造不鮮明
(3)治療
・食事療法:Ca、ビタミン Dの十分な摂取
・薬物療法:活性型ビタミン D
3.変形性関節症
(1)病態
・関節面の関節軟骨が薄くなり線維化、断裂などが出現する一方、辺縁の骨や軟骨が不規則に増殖して
骨棘を形成して関節の変形をきたす。
・40~50歳代の女性に多く、膝関節(最も多い)、股関節、肘関節、足関節などに起こる。
・加齢、肥満、O脚などが、危険因子になる。
(2)診断
1)症状
・自覚症状:慢性の関節痛、可動域の制限など
・他覚症状:関節の腫脹、炎症、関節水腫(関節腔に水がたまる)など
2)検査
・関節 X線検査
(3)治療
・関節痛に対しては消炎鎮痛薬やシップ薬を使用する。
・関節を支える筋肉の強化
・体重減少などによる関節への負担の減少
・関節へのヒアルロン酸注入
・手術療法(骨切り術、人工関節置換術)
4.サルコペニア(sarcopenia)
(1)概念
・サルコペニアとは、加齢に伴う筋力の低下、または老化に伴う筋肉量の減少のことをいう。
(2)分類
原発性サルコペニア
・加齢によるもの
・加齢により、損傷を受けた筋肉の再生能力が低下することが筋肉量減少の
要因である。
二次性サルコペニア ・廃用性萎縮によるもの、悪性腫瘍などの疾患に伴うもの、低栄養によるも
のなど

臨床病態学 要点整理ノート
107
(3)診断
・筋肉量の低下が必須であり、これに筋力低下と運動機能の低下が加わることにより診断される。
・筋肉量:二重エネルギーX線吸収測定法、インピーダンス法
・筋力:握力、膝伸展力
・運動機能:歩行速度、Timed Up and Goテスト(椅子に座った状態から立ち上がり、3m先の目印で
ターンをして椅子に座るまでの時間)

臨床病態学 要点整理ノート
108
16.感染症
1.定義(infection)
・感染とは、病原体(微生物)が宿主の体内に侵入して、定着、増殖することである。
・感染により発熱や痛みなど自覚的・他覚的な症状が出現するような病的な状態を感染症(infectious
disease)という。
・感染症を起こす病原体:細菌、ウイルス、クラミジア、リケッチア、マイコプラズマ、真菌、原虫、
寄生虫
・病原体の大きさ:真菌>細菌>リケッチア>クラミジア≒マイコプラズマ>ウイルス
2.要因
病原性 ・体内に侵入した菌量、組織の進入する能力、組織で定着・増殖する能力、毒素
の産生能、抗生物質に対する耐性などの要因が関与する。
宿主の感染防御能
・栄養状態、基礎疾患(悪性腫瘍、AIDS、糖尿病、肝疾患、腎疾患など)、免疫
能(免疫担当細胞の減少や機能異常、免疫抑制薬の使用)などの要因が関与す
る。
衛生環境 ・食物や水の汚染、感染患者との接触、ペットとの接触などの要因が関与する。
3.種類
菌交代現象
(microbial
substitution)
菌交代症
(superinfection)
・病原性の強い細菌感染症を治療するために抗生物質を使用すると、その抗生
物質に感受性がある細菌は減少・消滅するが、感受性のない細菌は逆に増殖
することを菌交代現象という。
・菌交代現象を起こしやすい細菌は一般に病原性が弱く(弱毒菌)ことが多い。
・菌交代現象により感染症が発症することを菌交代症という。
・菌交代症は何らかの理由で感染防御能が低下した患者で、抗生物質による化
学療法を行った場合に起こりやすい。
日和見感染
(opportunistic
infection)
・通常の状態では無害な真菌や弱毒菌であっても、宿主の感染防御能の低下に
より感染症を発症することを日和見感染という。
・真菌、緑膿菌、表皮ブドウ球菌、ニューモシスチス・カリニ、サイトメガリ
ウイルスなど
院内感染症
(nosocomial
infection)
・病院内の感染症である。
・保菌者との接触、針刺し事故、狭い病室の共有、不潔な医療行為などにより
感染する。
・インフルエンザなど感染力の強い病原体ばかりだけでなく、菌交代症や日和
見感染を起こす弱毒菌が原因菌になることもある。
・感染症の管理、感染患者の隔離、病棟の整理・整頓、清掃の徹底、手洗いの
励行など院内感染対策を適切に実施するために、多くの医療機関は院内感染
防止対策委員会を設置し、「院内感染防止マニュアル」などを作成している。
4.院内感染発生の 3大要因と対策
感染源 ・感染源を把握し、隔離する。
伝染経路
・それぞれの感染症に特有な感染経路を把握し、伝染経路を遮断するための適切
な対策を立てる。
・医療従事者に適切な滅菌・消毒の技術を習得・実行させる。
易感受性体
・栄養状態や体力の改善により抵抗力を向上させる。
・抗血清を用いた受動免疫を行う。
・ワクチンを用いた能動免疫を行う。
・感染源から隔離する。(逆隔離)

臨床病態学 要点整理ノート
109
5.再興感染症と新興感染症
再興感染症
・かつて流行していたが、抗生物質の利用や公衆衛生の改善により、発症者の数が一時
期は減少していたが、最近になって再び発症者が増加し、注目されるようになった感
染症の総称である。
・近年注目されている再興感染症としては、結核、マラリア、デング熱、狂犬病、黄色
ブドウ球菌感染症などがある。
新興感染症
・「かつては知られていなかった、この 20 年間に新しく認識された感染症で、局地的
に、あるいは国際的に公衆衛生上の問題となる感染症」である。
・世界保健機関(WHO)が 1990 年に定義したものなので、一般には 1970 年以降に発生
したものが新興感染症として扱われている。
・主に新興感染症には、SARS(重症急性呼吸器症候群)、鳥インフルエンザ、ウエスト
ナイル熱、エボラ出血熱、クリプトスポリジウム症、クリミア・コンゴ出血熱、後天
性免疫不全症候群(HIV)、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、腸管出血性大腸菌感
染症、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)
感染症、マールブルグ病、ラッサ熱などがある。
6.主な感染症
食中毒
・感染型:病原大腸菌、腸炎ビブリオ、セレウス菌(下痢型、生体内毒素型)
・毒素型:黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌(嘔吐型、生体外毒
素型)
後天性免疫不全症候
群
(AIDS, acquired
immunodeficiency
syndrome)
・AIDS は、HIV(human immunodeficiency virus)感染症である。
・HIVは、RNAウイルスである。
・HIVは、外膜にあるたんぱく質 gp120が、T細胞の CD4受容体と結合して、
細胞内に RNA を注入し、大量に複製される。
・AIDS では、血中 CD4陽性リンパ球数が減少する。
7.主な感染症と病原体の組合せ
(1)ウイルス
・麻疹 - 麻疹ウイルス
・風疹、風疹症候群(胎児奇形など) - 風疹ウイルス
・流行性耳下腺炎 - ムンプスウイルス
・日本脳炎 - 日本脳炎ウイルス
・ポリオ - ポリオウイルス
・水痘(初感染)、帯状疱疹(回帰発症) - 水痘・帯状疱疹ウイルス
・口唇ヘルペス - 単純ヘルペスウイルス
・手足口病 - エンテロウイルス、コクサッキーウイルス
・プール熱(咽頭結膜炎)、流行性角結膜炎 - アデノウイルス
・デング熱 - デングウイルス
・黄熱 - 黄熱ウイルス
・ジカ熱 - ジカウイルス
・狂犬病 - 狂犬病ウイルス
・A 型肝炎 - A型肝炎ウイルス
・B 型肝炎 - B型肝炎ウイルス
・C 型肝炎 - C型肝炎ウイルス
・下痢 - ノロウイルス、ロタウイルス、
・インフルエンザ - インフルエンザウイルス
・重症急性呼吸器症候群(SARS) - コロナウイルス
・中等呼吸器症候群(MARS) - コロナウイルス
・エイズ - ヒト免疫不全ウイルス(HIV)

臨床病態学 要点整理ノート
110
・成人 T細胞白血病 - HTLV-I(human T-cell leukemia virus type I)
・子宮頸がん - ヒトパピローマウイルス
(2)細菌
・胃潰瘍、胃がん - ヘリコバクター・ピロリ
・急性糸球体腎炎 - A群β溶血連鎖球菌
・淋病 - 淋菌
・梅毒 - スピロヘータの一種である梅毒トレポネーマ
・結核 - 結核菌
・院内感染 - MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)、バンコマイシン耐性腸球菌
・感染型食中毒 - カンピロバクター、腸炎ビブリオ、緑膿菌感染型、腸管出血性大腸菌 O-157
・毒素型食中毒 - ブドウ球菌、ボツリヌス菌
・コレラ - コレラ菌
・ツツガムシ病 - リケッチア
・発疹チフス - リケッチア
・オウム病 - クラミジア
・マイコプラズマ肺炎 - マイコプラズマ
(3)真菌
・カリニ肺炎 - ニューモシスチス・カリニ
(4)原虫
・マラリア - マラリア原虫

臨床病態学 要点整理ノート
111
17.免疫・アレルギー疾患
1.アレルギー(allergy)
(1)即時型過敏症(immediate hypersensitivity)の発見
・イソギンチャク毒素の研究(Portier(ポワチエ)と Richet(リシュー)、1902)
・毒素に対する免疫の獲得を見ようとして犬に注射すると、1回目の注射では何も起きないが、2回
目の注射直後、嘔吐、下痢、けいれんを起こして死亡したことから、この現象をアナフィラキシ
ー(anaphylaxis、no protection)と名づけた。当初は 1回目の毒素が抵抗力を奪い、2度目に
毒素の効果が現れると考えられた。
・無毒なタンパク質でもアナフィラキシーが起こることを発見。
・アナフィラキシーの性質:抗原特異的に起こることから、過敏症は免疫反応であると考えられた。
allos:異なった+ergon:反応=allergy:アレルギー
・即時型過敏症は受身移入できることから、即時型過敏症を引き起こす因子が血清中にあることが推定
された。
・PK(Prausnitzと Küstner)反応
魚の抽出液を皮内注射 反応
魚アレルギーのない人 変化なし
魚アレルギーのある人 発疹、かゆみ、呼吸困難
アレルギーのない人にアレルギーのある人の血清を皮膚に注射 発疹、かゆみ、呼吸困難
(2)IgE抗体(immunoglobulin E)の発見
・1930 年代~60年代(30 年間)に、IgG、IgM、IgA、IgDが発見
・1960 年代前半、アレルギーを起こす抗体は IgAであると考えられていた。
・しかし、IgA欠損の花粉症患者が見つかったことから、第 5の抗体の存在が推定された。
・1966 年、石坂公成が、アレルギー患者の血清から分離・精製した物質と花粉を皮下に注射して皮膚の
発赤を見ることにより IgEを発見した。
・E は紅斑(eryhtema)と 5番目のアルファベット Eを表す。
・IgEは IgAの 1000 分の 1の濃度である。
(3)即時型過敏症が起こるメカニズム
・アレルゲン(allergen)に初めて暴露して IgE抗体を産生する。この段階では無害。
・繰り返しアレルゲンに暴露することにより血清中 IgE濃度が上昇する。
・IgEが皮膚・粘膜に存在する肥満細胞(好塩基球由来)と結合する。
・肥満細胞に結合した IgE にアレルゲンが結合すると、肥満細胞からヒスタミンなど化学伝達物質が放
出される。
・化学伝達物質は、血管透過性を亢進させ、浮腫、発疹、血圧低下、気管支平滑筋の痙攣、呼吸困難な
どの症状を引き起こす。
(4)IgE産生が増加するメカニズム
・ヘルパーT細胞(Th)の役割:Th1 と Th2の 2種類ある。
・Th1は、細胞性免疫を促進する。
・Th2は、液性免疫(B細胞の活性化、形質細胞への分化、クラススイッチ)を促進する。
・Th2が分泌する IL-4は、IgGから IgEへのクラススイッチを促進するので、Th1/Th2バランスが、Th2
優位になると IgE の産生が増加し、アレルギーを起こしやすくなる。
・遺伝因子(アトピー体質など)、環境因子(ディーゼルエンジンが排出する浮遊粒子物質など大気汚
染など)が、個人の Th1/Th2バランスを決定する要因となる。

臨床病態学 要点整理ノート
112
(5)アレルギーの種類と主なアレルギー疾患
Ⅰ型
・アナフィラキシー型反応(anaphylaxis)
・IgEによる過敏症(Th1細胞<Th2細胞)
・花粉症、アレルギー性鼻炎気管支喘息、蕁麻疹、ペニシリンショック、食物アレルギーな
ど
Ⅱ型
・細胞障害型反応
・細胞や組織に対する抗体産生に補体が関与して細胞障害を起こす。
・自己免疫性溶血性貧血、1型糖尿病(ウイルス感染、食餌抗原)など
Ⅲ型
・アルサス(Arthus)型反応
・抗原-抗体複合体(免疫複合体)が組織傷害を引き起こす。
・血清病、糸球体腎炎、膠原病など
Ⅳ型
・ツベルクリン(tuberculin)型反応(遅延型過敏症)
・ツベルクリン反応:結核菌抽出物の皮下注射⇒発赤、浮腫、かゆみ
36時間から 48 時間でピークに達し、数日続く。
・血清により受身移入できない。リンパ球により受身移入できる(Tリンパ球)
・食物アレルギー、ウイルス脳炎、ウイルス肝炎、接触性皮膚炎、1型糖尿病、膠原病など
Ⅴ型
・抗体の刺激により組織の機能が異常亢進あるいは異常低下するもの
・バセドウ病(甲状腺の TSH受容体に対する抗体により機能亢進)
・重症筋無力症(神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する抗体により機能低下)
2.食物アレルギー(food allergy)
(1)病態
・食品の抗原(アレルゲン)によって誘発されるアレルギー(Ⅰ型、Ⅳ型)である。
・食品の経口摂取により症状が現われることが多いが、皮膚に接触すること、粉末を吸入することによ
っても症状が現われる場合がある。
・乳幼児期・小児期に多く、成長とともに自然寛解することが多い。
・ほとんどすべての食品がアレルゲンになりうる。
動物性食品 卵、牛乳・乳製品、さば・マグロなど魚類、エビ・カニ類、イカ類、貝類、鶏など肉
類、ハム・ベーコンなど肉加工品
植物性食品 大豆・大豆製品、小麦、米、そば、とうもろこし、ピーナツなど豆類、いも類、植物
油
その他 人工着色料、食品添加物などもアレルゲンになることがある。
・3 大アレルゲンは、卵(特に卵白)、牛乳、小麦である。
卵アレルゲン オボアルブミン、オボムコイド、鶏卵リゾチーム、オボトランスフェリンなど
牛乳 αs1-カゼイン、βラクトグロブリンなど
小麦アレルゲン 小麦たんぱく質のグルテニン(弾力)とグリアジン(粘着力)が絡み合って、グルテン
(弾力と粘着力を併せ持つ)ができる。
・複数のアレルゲンに対してアレルギーを起こすことがある。
・一般に、生の方が抗原性強い。
・一般に、調理により抗原性が低下することはあるが、なくならない。
・一般に、動物性タンパク質の方がアレルゲンになりやすい。
・少量でも強い反応を起こすことがある。
・食物依存性運動誘発アナフィラキシー(運動による抗原の吸収量増加が原因)
・食物アレルギーの発症機構
遺伝的
素因
・両親のいずれか、あるいは両方が、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支喘息な
どアレルギー性疾患を有する場合、その子供はアレルギー疾患になる頻度が高い。

臨床病態学 要点整理ノート
113
環境要因
・高エネルギー・高たんぱく質の食生活(母体から胎児への抗原暴露が増加する)
・早期の離乳食(外来たんぱく質、特に卵への早期暴露)
・生後 6ヵ月以内の乳児では、腸管免疫系が未熟なために、アレルゲンが侵入して感作さ
れやすい。
・年齢とともに軽快、消滅することが多いが、この時期に適切な処置をしないと多くの抗
原に感作されることになり、いわゆるアトピー体質になり、その後アトピー性皮膚炎や
気管支喘息を発症する可能性が高くなる。(アレルギーマーチ)
・腸管免疫系の調節機構
・食物に含まれるタンパク質の一部はそのまま吸収される。
・牛乳中の-ラクトグロブリンは摂取した 10万分の 1が血中に出現する。
・下痢、腸炎などはアレルゲンの吸収を促進する。
・腸管を介して大量に入ってくる外来抗原に対するアレルギーを抑制するメカニズム
消化酵素による食品の低アレルゲン化
粘膜による機械的バリア
腸液中の IgAによるアレルゲン凝集によるアレルゲンの吸収抑制
免疫学的抑制機構(経口免疫寛容):腸管を通過するアレルゲンに対する IgE抗体の産生を抑制
(2)診断
1)症状
・皮膚症状(かゆみ、湿疹、蕁麻疹、浮腫)がもっとも多い。
・呼吸器症状(鼻炎、咳、喘鳴、呼吸困難)
・胃腸症状(下痢、嘔吐、腹痛)
・全身症状(血圧低下、ショック)
・通常、アレルゲン摂取後 2時間以内に出現する。
2)抗原診断
・除去試験(疑わしい食品から除去)
・誘発試験(症状消失後,疑わしい食品を投与)
・血清特異的 IgE抗体陽性(Radio-allergo-solvent test,RAST)
・皮膚テスト
皮内テスト
・注射を使い、皮膚の中にアレルゲンを注入
・Ⅰ型の判定は 15〜20 分後
・Ⅳ型の判定は 5〜6 時間後または 24〜48 時間後(ツベルクリン反応は 48 時間後)

臨床病態学 要点整理ノート
114
スクラッチテスト ・皮膚にアレルゲンを付着させ、針で引っ掻く。判定は 15 分後
・Ⅰ型の診断
パッチテスト ・皮膚にアレルゲンを貼り付ける。判定は 1-2 日後
・Ⅳ型の診断
プリックテスト 針で皮膚に穴をあけてアレルゲンを塗布。判定は 15-20 分後
・Ⅰ型の診断
(3)治療
除去食療法
・除去食療法のゴールは、「除去により症状を発現させないで普通の生活を送り、やが
て耐性を獲得して除去を解除すること」にある。
・除去食は誘発される症状の強さにあわせて、必要最小限の除去を行う。(個別対応
が原則)
・完全に除去すべきなのか、加熱すれば食べても良いのか(生卵は不可だがゆで卵は
可など)、部分的には摂取可能か(白身は不可だが黄身は可)を考慮する。
・食物によっては低アレルゲン化米や低アレルゲン化乳などを活用する。
・完全除去食は、アレルギー症状が強く,生命が危険である場合に適応となる。
・一律に完全除去食を投与すべきでない。完全除去食は経口免疫寛容を低下させ、再
投与した際のアレルギー症状が重篤化する可能性がある。
・除去した食品に対し、必ず他の食品(代替食品)で埋め合わせをする。
・除去食の解除
・半年~2年の除去食後、抗原性の低い加工食品を少量投与して、症状を見ながら徐々
に解除する。
・乳児の場合は、消化能力と腸管局所免疫能が十分に発達するまで待つ。
・高熱処理の少量のアレルゲンを含む食品より開始する。
薬物療法
・除去食の補助療法
・症状の緩和、予防療法として、DSCG(Disodium cromoglycate)薬(インタールⓇ)、
抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン等を投与する。
・複数のアレルゲンに感作され、除去食が困難なときも適応となる。
減感作療法 ・症状を誘発する食物アレルゲンの閾値以下を投与することにより、アレルゲンに対
する耐性を獲得する。
アドレナリ
ン注射
・アナフィラキシーショック
3.自己免疫疾患(autoimmune disease)と膠原病(collage disease)
(1)概要
・自己免疫疾患とは自分の組織に対する抗体(自己抗体)が産生されることが原因で起こる疾患である。
・自己免疫疾患には全身性の疾患(膠原病、シェーグレン症候群)と特定の臓器(橋本病、自己免疫性
溶血性貧血、1型糖尿病など)に生じる疾患がある。
・シェーグレン症候群とは、慢性唾液腺炎と乾燥性角結膜炎を主徴とする自己免疫疾患である。
・唾液腺の分泌低下によるドライマウスと涙腺の分泌低下によるドライアイが出現する。
(2)膠原病の特徴
・全身性の炎症疾患であり、発熱や体重減少が生じる。
・多臓器にわたる障害がある。
・慢性に経過し、症状の寛解と再燃を繰り返す。
・種々の自己抗体が出現し、免疫機構の異常が病因として考えられる。
・発症に遺伝的な素因が認められる。

臨床病態学 要点整理ノート
115
(3)主な膠原病の特徴
全身性エリ
テマトー
デス
・SLE, systemic lupus erythematosus
・顔面の紅斑(蝶形紅斑)、口内炎など皮膚症状、光線過敏症、関節炎、腎臓など臓器
病変が出現する。
・抗核抗体、抗 DNA 抗体などの自己抗体と自己抗原の免疫複合体が全身組織に沈着す
る。
・20~40歳代の女性に多い。
・腎臓病変をループス腎炎といい、タンパク尿、血尿、ネフローゼ症候群などが出現す
る。
・末梢血検査で LE細胞(核を貪食した白血球)が出現する。
全身性硬化
症
・PSS, progressive systemic sclerosis
・厚く硬い皮膚とレイノー現象が特徴で、強皮症(scleroderma)とも呼ばれる。
・組織学的には、結合組織の増加による線維化である。
・消化管(特に食道)の線維化により、蠕動運動が低下し、嚥下障害が出現する。
・30~50歳の女性に多い。
・抗核抗体や抗 Scl-70抗体が陽性になる。
多発性筋炎
皮膚筋炎
・PM, polymyositis、DM, dermatomyositis
・横紋筋の炎症性疾患で筋力が低下するものを多発性筋炎といい、このうち皮膚症状を
伴うものを皮膚筋炎という。
・30~40歳代の女性に多い。
・ヘリオトープ疹(heliotrope rash):眼瞼(上眼瞼に多い)の浮腫を伴ったヘリオト
ープ色(薄紫色をした小さな花)の紅斑
・ゴットロン徴候(Gottron sign):手指関節の背面に角化性の紅斑
・逆ゴットロン徴候:手指先端指腹の裂溝を伴う角質化
関節リュウ
マチ
・RA, rheumatic arthritis
・多発性の関節炎による関節の破壊と変形を主病変とする疾患である。
・関節滑膜が増殖してパンヌス(肉芽様の組織)を形成し、やがて軟骨と骨を破壊する。
・パンヌスから分泌される炎症性サイトカインの作用により、破骨細胞が活性化して骨
粗鬆症が出現する。
・関節炎の症状は朝のこわばりが特徴である。
・30~40歳代の女性に多い。
・リウマチ因子、抗環状シトルリン化ペプチド(CCP)が陽性になる。
リウマチ熱
・RF, rheumatic fever
・A 群溶血連鎖球菌の上気道感染に引き続いて心臓、関節、皮膚、中枢神経などに非
化膿性炎症を生じる病態をいう。
・小児学童期に多い。
・心炎、多関節炎、舞踏病、輪郭状紅斑、皮下結節が認められる。
結節性多発
動脈炎
・PN, polyarteritis nodosa
・中小の血管壁に炎症、変性、壊死が起こる疾患である。
・50~60歳代に多い。(男女比は 1:1)
・抗好中球細胞質抗体が陽性になる。
シェーグレ
ン症候群
・Sjögren syndrome
・慢性唾液腺炎と乾燥性角結膜炎を主徴とする自己免疫疾患である。
・唾液腺の分泌低下によるドライマウスと涙腺の分泌低下によるドライアイが出現す
る。
・自己抗体である抗 SS-A抗体と抗 SS-B抗体が陽性になる。(ssは、Sjögren syndrome
の頭文字)

臨床病態学 要点整理ノート
116
(4)血管炎症候群(vasculitis syndrome)
・自己免疫疾患の一群で、主として血管に炎症の主座がある症候群である。
大血管炎 ・大血管を選択的に傷害するものである。
・高安動脈炎(TA)、巨細胞性動脈炎(GCA)など
中血管炎
・中小動脈を傷害するものである。
・結節性多発動脈炎(PAN)、川崎病(KD)、中枢神経限局性血管炎(原発性肉芽腫性中枢
神経系血管炎 PACNS)など
ANCA関連
小血管炎
・抗好中球細胞質抗体(ANCA, antineutrophil cytoplasmic antibody)が検出され
る。
PR3-ANCA(C-ANCA):多発血管炎性肉芽腫症
MPO-ANCA(P-ANCA):顕微鏡的多発血管炎、アレルギー性肉芽腫性血管炎
・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症,(アレルギー性肉芽腫性血管炎,チャーグ・ストラウ
ス症候群;CSS)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA, 旧称ウェゲナー肉芽腫症;WG)、顕微
鏡的多発血管炎(MPA)など
免疫複合体
性小血管
炎
・小動脈、小静脈などの主に小血管の血管壁に免疫グロブリンや補体成分の沈着を伴
う血管炎。
・抗 GBM 抗体関連疾患(Anti-GBM Disease, 旧称 Goodpasture 症候群)、 クリオグロ
ブリン血管炎(CV), IgA血管炎(IgAV)(旧称 Henoch-Schonlein紫斑病), 低補
体蕁麻疹様血管炎(抗 C1q血管炎)がある。

臨床病態学 要点整理ノート
117
18.悪性腫瘍
1.腫瘍(tumor)の定義
・腫瘍とは正常な体を構成する細胞から発生する組織の異常増殖である。
・異常増殖の特徴は周囲の正常な組織との間に調和が保たれないこと(自律性)であり、事情が許す限
り際限なく増殖することである。
・腫瘍は実質(腫瘍細胞)と間質(腫瘍細胞が増殖するのに必要な足場、栄養、酸素などを供給する)
からできている。
・間質は正常な細胞からできていて、腫瘍の増殖は間質を介して宿主に完全に依存している。
2.分類
・一般に「癌」は悪性腫瘍全般を指し、「癌腫(cancer)」は上皮性悪性腫瘍を、「肉腫(sarcoma)」
は非上皮性悪性腫瘍を指す。
・臨床的には予後が良好なものを「良性」、不良なものを「悪性」とする
・病理組織学的には増殖様式により圧排(アッパイ)性増殖のみを示すものを「良性」(benign tumor)、
浸潤性増殖を示すものを「悪性」(malignant tumor)とする。
・悪性であっても圧排性増殖を伴うことがある。
3.転移(metastasis)
・悪性腫瘍は周囲の組織に浸潤して増殖するが、腫瘍細胞が血管内やリンパ管内に浸潤して血液やリン
パ液の流れにのって遠隔臓器に転移することを血行性転移、リンパ行性転移という。
・一般に、癌腫は血行性転移とリンパ行性転移の両方を起こすが、肉腫は血行性転移しやすい。
・悪性腫瘍が胸腔や腹腔などの体腔の表層に達して体腔内に飛び散って癌病巣を作ることを播種という。
4.発生の要因
(1)遺伝要因と環境要因
遺伝要因 ・網膜芽種、ウィルムス腫は常染色体優勢遺伝する癌である。
・家族性大腸ポリポーシスと大腸癌、色素性乾皮症は遺伝性疾患と皮膚癌
環境要因 ・種々の化学物質、食品の加熱産物、食品添加物、大気汚染、排気ガス、タバコ、紫
外線、放射線、ある種のウイルスなど
(2)発癌二段階説
・発癌物質をマウスの皮膚に 1回塗り、その後非発癌物質のクロトン油を繰り返し塗ると腫瘍が発生す
るが、発癌物質単独またはクロトン油単独では、腫瘍は発生しない。
・このことは、発癌の過程には発癌のきっかけを作るイニシエーションの段階と、癌の発生にいたる過
程を促進するプロモーションの段階が必要であることを示している。
(3)癌遺伝子と癌抑制遺伝子
・癌を発生させるウイルスの研究から、癌を発生させる癌遺伝子(src、rasなど)が発見された。
・この癌遺伝子はウイルスの増殖には不必要なものであった。
・多くの癌遺伝子に良く似た遺伝子がヒトの体細胞から分離された。
・これらの遺伝子は細胞の増殖を調節する細胞内シグナル伝達に関わるタンパク質をコードしていた。
・発癌物質は、これらの遺伝子に変異をもたらして癌を発生させることがわかった。
・正常な細胞では増殖を抑制する作用を有する遺伝子が、変異によりその作用が障害されると、増殖を
抑制できなくなる。このような遺伝子を癌抑制遺伝子(p53など)という。

臨床病態学 要点整理ノート
118
(4)ウイルスと発癌
・肝炎ウイルス - 肝細胞癌
・ヒトパピローマウイルス - 子宮頸癌
・EBウイルス - バーキットリンパ腫
・カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス カポジ肉腫
(5)発癌物質と発癌
・アフラトキシン - 肝臓癌
・アニリン - 膀胱癌
・アスベスト - 肺癌、悪性中皮腫
5.治療
・手術療法、放射線療法、化学療法(抗悪性腫瘍薬)の 3種が基本
・食事療法
・抗癌剤の副作用:食欲不振(嘔吐中枢の刺激、消化管粘膜の障害)
・悪液質:炎症性サイトカインによるたんぱく質と脂質の異化亢進 → 体重減少(PEM)
6.主な悪性腫瘍
(1)食道癌
・発生:食道上皮から発生する。扁平上皮癌が 95%を占める。
・病因:喫煙と飲酒が強く関連する。その他、熱いものや辛いものなど
・死亡率:男性 16.2、女性 2.8(人口 10 万人対、平成 21年)
・症状:嚥下困難、胸痛、嗄声など
・診断:食道 X線造影、内視鏡、生検で診断される。
・治療:外科的切除、放射線療法、内視鏡的粘膜切除(早期癌)、化学療法など
(2)胃癌
・発生:胃粘膜上皮から発生する腺癌である。
・病因:食物由来の発癌物質、H.ピロリ感染など
・死亡率:男性 53.4、女性 26.7(人口 10万人対、平成 21年)
・症状:上腹部痛、悪心、嘔吐など上部消化管の症状。
・診断:胃 X線造影、内視鏡、生検で診断される。
・分類
早期胃癌 ・Ⅰ型(隆起型)、Ⅱ型 a(表面隆起型)、Ⅱ型 b(表面平坦型)、Ⅱ型 c(表面
陥凹型、Ⅲ型(陥凹型)
進行胃癌
(ボールマン分類)
・1 型(限局隆起型)粘膜から盛り上がっているもの。比較的予後はよい。
・2 型(限局潰瘍型)進行性胃がんの 25%を占める。肝臓に転移しやすい。
・3 型(浸潤潰瘍型)進行性胃がんの 40%を占める。潰瘍がん。
・4 型(びまん浸潤型)粘膜の下を這うように進行していくがん。スキルス胃が
んとも呼ばれる。
・治療:外科的切除、内視鏡的粘膜切除(早期癌)、化学療法など
(3)結腸癌、直腸癌
・発生:大腸粘膜上皮から発生する。ほとんどが腺癌である。直腸(約 45%)と S状結腸(約 25%)に
発生することが多い。早期癌は S状結腸(60~70%)に多い。
・病因:高脂肪、低線維の食生活が関連している。
・死亡率:男性 37.1、女性 29.5(人口 10万人対、平成 21年)
・症状:貧血、下血、便秘、糞便の細小化など
・診断:大腸 X線造影、内視鏡、生検で診断される。スクリーニング検査として便潜血検査。

臨床病態学 要点整理ノート
119
・治療:外科的切除、内視鏡的粘膜切除(早期癌)、放射線療法、化学療法など
(4)肝臓癌
・発生:肝細胞由来の肝細胞癌(約 90%を占める)と胆管由来の胆管細胞癌がある。
・病因:B型および C型肝炎ウイルスとの関連が強い。その他アフラトキシン
・死亡率:男性 35.3、女性 17.2(人口 10万人対、平成 21年)
・症状:肝腫大、腹部膨満、腹水、黄疸など
・診断:αフェトプロテイン、肝炎ウイルスマーカー、肝機能検査、CT・MRI などの画像診断などによ
り診断する。
・治療:外科的切除、経皮エタノール注入療法、経カテーテル肝動脈塞栓療法、化学療法など
(5)肺癌
・発生:ほとんどが肺、気管支、気管の上皮細胞由来の癌腫である。組織型により腺癌(40%)、扁平
上皮癌(35%)、小細胞癌(15%)、大細胞癌(5%)、その他(5%)などに分類される。
・病因:喫煙がもっとも重要で、その他アスベスト、放射線などが関連する。
・死亡率:男性 79.9、女性 28.8(人口 10万人対、平成 21年)
・症状:咳、痰、血痰、胸痛、呼吸困難など
・診断:胸部 X線・CT・MRI などの画像診断、喀痰細胞診、気管支鏡検査、生検などにより診断する。
・治療:外科的切除、化学療法(小細胞癌)、放射線療法など
(6)子宮頚癌
・発生:子宮頚部に発生する上皮性の悪性腫瘍である。扁平上皮癌(85%)と腺癌(10%)が多い。
・病因:性行為、ヒトパピローマウイルスとの関連が強い。
・死亡率:女性 8.6(人口 10万人対、平成 21年、子宮頸癌+子宮体癌)
・症状:不正性器出血、下腹部痛など
・診断:膣鏡と擦過細胞診で診断される。
・治療:外科的切除、放射線療法、化学療法など
・予防:ヒトパピローマウイルスワクチン(既感染者には無効)
(7)子宮体癌
・発生:子宮内膜から発生する癌である。腺癌が多い。
・病因:ホルモン補充療法などによるエストロゲン暴露、高血圧、糖尿病、肥満、高脂肪食、未経産婦
などと関連する。
・症状:不正性器出血、貧血、月経過多、腹痛など
・診断:内膜細胞診、子宮鏡、超音波エコー・CT・MRIなどの画像検査などにより診断する。
・治療:外科的切除、放射線療法、化学療法など
(8)乳癌
・発生:乳腺の上皮細胞から発生する癌である。
・病因:初産年齢が遅く、出産数の少ないもの、初潮年齢が低く閉経年齢が高いもの、肥満などでリス
クが高い。
・死亡率:男性 0.1、女性 18.5(人口 10 万人対、平成 21年)
・症状:乳房のしこり、乳頭部分のびらんなどで、自分で気づくことが多い。
・診断:視診、触診、X線検査(マンモグラフィー)などにより診断する。
・治療:外科的切除、化学療法、放射線療法、抗エストロゲン薬によるホルモン療法など
(9)前立腺癌
・発生:前立腺に発生する癌である。
・病因:アンドロゲンとの関連が指摘されているが詳細は不明である。
・死亡率:男性 16.4(人口 10万人対、平成 21年)

臨床病態学 要点整理ノート
120
・症状:頻尿、排尿困難、残尿感など
・診断:前立腺特異抗原(PSA)陽性、超音波エコー、針生検などにより診断する。
・治療:外科的切除、放射線療法、抗アンドロゲン薬によるホルモン療法など

臨床病態学 要点整理ノート
121
19.老年症候群
1.褥瘡
(1)概念
・褥瘡(bedsore)とは、身体に加わった外圧により、皮膚および皮下組織に損傷が生じた状態をいう。
・圧迫を受けた組織に血行障害が生じ、組織が虚血状態になって、組織の壊死が起こる。
・創傷の治癒過程は、①出血凝固期、②炎症期、③増殖期、④成熟期の 4期に分類される。
出血凝固期:出血の凝固・止血が起こる。
炎症期:炎症細胞の浸潤、壊死組織の清浄化が起こる。
増殖期:肉芽形成、上皮化、創収縮が起こる。
成熟期:瘢痕形成、瘢痕の成熟が起こる。
(2)好発部位
・仙骨部、踵骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、後頭部、肩甲部、肘頭部など、骨が突出した部位に好
発する。
(3)要因
・内的要因には、栄養状態、循環不全、貧血など全身状態の悪化、糖尿病、加齢などが含まれる。
血清アルブミン値は、栄養状態の指標として用いられる。血清アルブミン値が低下すると、褥瘡が
発生する危険が高くなる。
・外的要因には、圧迫、皮膚湿潤(多汗、尿失禁、便失禁)、摩擦、ずれ、不潔などが含まれる。
・ブレーデンスケールとは、褥瘡発生を予測するスケールである。
「知覚に認知」、「湿潤」、「活動性」、「可動性」、「栄養状態」、「摩擦とずれ」の 6つのカ
テゴリーからできている。合計得点が低いと褥瘡発生のリスクが高い。
(4)重症度分類
・DESIGNツールを用いて判定する。
DESINGツールは、褥瘡の重症度を分類し、治癒過程を数量化するために開発されたスケールである。
項目には、深さ(Depth)、滲出液(Exudate)、大きさ(Size)、炎症・感染(Inflammation/infection)、
肉芽組織(Granuation tissue)、壊死組織(Necrotic tissue)の 6項目があり、それぞれ数値化
されている。
(5)治療
・脱水を予防し、創部の適度な湿潤環境を保つために、適切な水分補給を行う。
創部の乾燥は、治癒を遅延させる。創部の適度な湿潤環境を保つことにより、皮膚の再生を促進す
ることができる。
皮膚の乾燥は、皮膚のバリアー機能を低下させるので、褥瘡の予防にも皮膚の適度な保湿は重要で
ある。
・栄養 エネルギー BMI 18.5以上、たんぱく質 1.2~1.5ℊ/㎏/日、脂質 20~25%
たんぱく質不足は、免疫能の低下、創傷の治癒の遅延をきたすので、褥瘡の予防と治療には、
十分なたんぱく質を投与する。
脂肪エネルギー比を 15%以下の低脂肪食では、適正な体重を維持する十分なエネルギーが確
保できず、必須脂肪酸や脂溶性ビタミンの摂取が不足する可能性がある。脂肪エネルギー比
は 20~25%とする。

臨床病態学 要点整理ノート
122
2.老年症候群
(1)失禁
・失禁の原因は、男性では切迫性尿失禁、女性では腹圧性尿失禁が多い。
・失禁を予防するためは、原因となる要因に応じて、骨盤低筋群の筋力をつける運動療法や薬物療法が
用いられる。
・水分摂取を制限すると脱水になる可能性があるので、水分制限は行わない。
(2)転倒
・転倒の原因には、脳血管障害、パーキンソン病など神経疾患、骨粗鬆症など筋骨格系疾患などの内的
要因と生活環境など外的要因がある。
・転倒を予防するためには、原因となる要因に対する対策と筋力をつけるための運動療法が必要である。
・歩行を禁止すると足の筋力低下につながり、かえって転倒の危険性が高くなる。
(3)誤嚥性肺炎
・誤嚥性肺炎を予防するため、口腔ケアは行う。
口腔内の雑菌を誤嚥することにより、誤嚥性肺炎を起こす可能性があるので、口腔ケアにより口腔
内を清潔に保つことが、誤嚥際肺炎の予防法のひとつになる。
(4)廃用症候群
・廃用症候群とは、安静状態が長期に渡って続く事によって起こる、さまざまな心身の機能低下のこと
である。
・生活不活発病とも呼ばれる。
・筋力低下、関節拘縮、褥瘡など体の一部に起こるものだけでなく、心肺機能の低下、起立性低血圧、
食欲不振など全身症状として出現するもの、うつ状態、知的活動低下など精神や神経の症状として出
現するものがある。
・過度の安静は、かえって廃用症候群を助長する。
(5)フレイルティー(frailty)
・フレイルティー(frailty)とは、虚弱という意味である。
・フレイルティーの定義は、「加齢に伴う種々の機能低下(予備力の低下)を基盤とし、種々の健康障
害に対する脆弱性が増加している状態」で、老年症候群に含まれる。
・フレイルティーの判定基準には、①体重減少、②主観的活力低下、③握力の低下、④歩行速度の低下、
⑤活動度の低下の 5項目があり、このうち 3項目以上当てはまればフレイルティーとされる。
・フレイルティーを予防するためには筋力を向上させる必要があるので、身体活動を制限でず、適切な
強度の運動を推奨する。
Related Documents



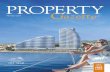



![[XLS] · Web viewイギリス p *16 イタリア ウクライナ オーストリア オランダ ギリシャ スイス スウェーデン スペイン ... 11.00 0.40 17.00 0.40 4281.00](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5b27ff5c7f8b9a8f648b49c3/xls-web-view-p-16-.jpg)



![FdData中間期末:中学社会歴史】 ギリシャ・ローマ【FdData中間期末:中学社会歴史】 [ギリシャ・ローマ ] パソコン・タブレット版へ移動](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5f3036758a66b86a1a21bdff/fddataeoeoeic-ffffff-fddataeoeoeic.jpg)
