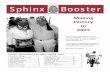平成 22 年度第三回星陵高等学校同窓会文化講座 平成 23 年 2 月 27 日(日) 13:30~15:00 於・星友館 ギザ台地の歴史とスフィンクス信仰 西 村 洋 子 ギザ、おそらく皆さんがエジプトを旅行される時、カイロ空港に着いたら最初に訪問す る観光地でしょう。ギザへはカイロのタハリール広場からバスでわずか 40 分で行くことが 出来、市街地からさほど遠くない砂漠の中にクフ王の大ピラミッドが現れます。 北緯 30 度、東経 31 度 20 分に位置するギザには、クフ王の大ピラミッドの他に、その 東側に広がる王族の共同墓地と西側に広がる高官たちの共同墓地、大ピラミッドの南側に ある船の博物館、そしてクフ王の息子であるカフラー王のピラミッド、カフラー王のピラ ミッドから東へ伸びる参道の先にはいわゆる河岸神殿と大スフィンクスおよびいわゆるス フィンクス神殿、そしてクフ王の孫のメンカウラー王のピラミッドなどがあります。また、 観光旅行では見学することはありませんが、メンカウラー王の河岸神殿の北側にある王妃 ケントカウエスの墓も歴史的かつ建築学的に注目されている遺跡です。 ギザの三大ピラミッドは紀元前 2,600 年から 2,500 年の間に建造されました。古代エジ プトの編年では古王国第四王朝に相当します。古代エジプトは紀元前 3,000 年頃政治的に 統一された王国が出現して以来、アレクサンダー大王がエジプトにやってくる紀元前 332 年まで、 30 の王朝に分けられます。このように分けたのはプトレマイオス時代のエジプト 人神官マネトーで、さらに 1840 年代にカール・リヒャルト・レプシウスによって第三王 朝から第六王朝までが古王国、第十一王朝と第十二王朝が中王国、第十八王朝から第二十 王朝までが新王国にグループ化されました。古王国、中王国、新王国というこの三つの繁 栄期の間は第一中間期および第二中間期と呼ばれ、政治的統一が失われた時代でした。新 王国の後にはリビア人に支配された第三中間期、ヌビア人に支配された第二十五王朝、エ ジプト文化の伝統が復活する第二十六王朝、第一次ペルシア支配時代である第二十七王朝 と続き、ついに世界史の荒波に飲まれてしまいます。 さて、ギザの遺跡群の中で最も注目を集めてきたのがクフ王の大ピラミッドです。現在 の高さ 138.75m、本来の高さ 146.59m、底辺の長さ 230.37m というこの巨大建造物はモ カッタム層の上に建造されています。モカッタム層とは中期始新世、つまり今から 5,200 万年前に形成され、海底に堆積した石灰岩と、石灰堆積層のカルシウム分が海水中でマグ ネシウム化された苦灰石(くかいせき)から成る地層で、ギザ台地の北部と東部に、東西に 約 2.2km、南北に約 1.1km 広がっています。モカッタム層の厚みは 130m ですが、ギザで は約 40m しかありません。モカッタム層の石灰岩は有孔虫の化石を多く含むので、貨幣石 石灰岩と呼ばれます。ギザ台地の南部には泥灰質(でいかいしつ)の石灰岩と砂質の泥灰土 からなるマアディ層がモカッタム層の上におおいかぶさっています。クフ王の大ピラミッ

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
平成 22年度第三回星陵高等学校同窓会文化講座 平成 23年 2月 27日(日) 13:30~15:00 於・星友館
ギザ台地の歴史とスフィンクス信仰
西 村 洋 子 ギザ、おそらく皆さんがエジプトを旅行される時、カイロ空港に着いたら最初に訪問す
る観光地でしょう。ギザへはカイロのタハリール広場からバスでわずか 40分で行くことが出来、市街地からさほど遠くない砂漠の中にクフ王の大ピラミッドが現れます。 北緯 30度、東経 31度 20分に位置するギザには、クフ王の大ピラミッドの他に、その東側に広がる王族の共同墓地と西側に広がる高官たちの共同墓地、大ピラミッドの南側に
ある船の博物館、そしてクフ王の息子であるカフラー王のピラミッド、カフラー王のピラ
ミッドから東へ伸びる参道の先にはいわゆる河岸神殿と大スフィンクスおよびいわゆるス
フィンクス神殿、そしてクフ王の孫のメンカウラー王のピラミッドなどがあります。また、
観光旅行では見学することはありませんが、メンカウラー王の河岸神殿の北側にある王妃
ケントカウエスの墓も歴史的かつ建築学的に注目されている遺跡です。 ギザの三大ピラミッドは紀元前 2,600年から 2,500年の間に建造されました。古代エジプトの編年では古王国第四王朝に相当します。古代エジプトは紀元前 3,000 年頃政治的に統一された王国が出現して以来、アレクサンダー大王がエジプトにやってくる紀元前 332年まで、30の王朝に分けられます。このように分けたのはプトレマイオス時代のエジプト人神官マネトーで、さらに 1840 年代にカール・リヒャルト・レプシウスによって第三王朝から第六王朝までが古王国、第十一王朝と第十二王朝が中王国、第十八王朝から第二十
王朝までが新王国にグループ化されました。古王国、中王国、新王国というこの三つの繁
栄期の間は第一中間期および第二中間期と呼ばれ、政治的統一が失われた時代でした。新
王国の後にはリビア人に支配された第三中間期、ヌビア人に支配された第二十五王朝、エ
ジプト文化の伝統が復活する第二十六王朝、第一次ペルシア支配時代である第二十七王朝
と続き、ついに世界史の荒波に飲まれてしまいます。 さて、ギザの遺跡群の中で最も注目を集めてきたのがクフ王の大ピラミッドです。現在
の高さ 138.75m、本来の高さ 146.59m、底辺の長さ 230.37m というこの巨大建造物はモカッタム層の上に建造されています。モカッタム層とは中期始新世、つまり今から 5,200万年前に形成され、海底に堆積した石灰岩と、石灰堆積層のカルシウム分が海水中でマグ
ネシウム化された苦灰石(くかいせき)から成る地層で、ギザ台地の北部と東部に、東西に約 2.2km、南北に約 1.1km広がっています。モカッタム層の厚みは 130mですが、ギザでは約 40mしかありません。モカッタム層の石灰岩は有孔虫の化石を多く含むので、貨幣石石灰岩と呼ばれます。ギザ台地の南部には泥灰質(でいかいしつ)の石灰岩と砂質の泥灰土からなるマアディ層がモカッタム層の上におおいかぶさっています。クフ王の大ピラミッ
ドよりも早い時代に建造されたサッカラの階段ピラミッドやダハシュールの屈折ピラミッ
ドなどは泥灰土(でいかいど)と粘板岩の比較的柔らかい地層、いわゆるサッカラ層の上に建造されており、あまりにも巨大な建造物は支えきれないという難点がありましたが、ギ
ザ台地のモカッタム層は硬い岩盤であったため、このような巨大ピラミッドの建造を可能
にしたのです。モカッタム層の南東部の丘は大ピラミッド建造のための採石場となり、大
スフィンクスはモカッタム層の岩盤を彫って造られています。 ギザの三大ピラミッドは当時の世界観や来世観を表現した王の墓です。クフ王の大ピラ
ミッドはヘリオポリス神学の宇宙創世を表現していると言われます。すなわち混沌とした
原初の海から現れる原初の丘と太陽の光を象徴しています。カフラー王のピラミッドはク
フ王のピラミッドと大スフィンクスとともに地平線を表すヒエログリフ・サイン(N27)、アケトを表現したのかもしれません。アケトは太陽が昇り、沈む場所です。この場合それは 大スフィンクスが彫刻された理由にもなります。ただし、大スフィンクスの本来の役割は
いまだに不明です。メンカウラー王のピラミッドはおそらくクフ王の大ピラミッドとカフ
ラー王のピラミッドとともにオリオン座の三つ星を表現したのでしょう。古代エジプトで
はオリオン座の三つ星は冥界の支配者オシリス神と同一視されていました。クフ王の埋葬
室に至る通路は上昇するのに対し、メンカウラー王の埋葬室へ至る通路は岩盤に下降して
おり、オシリス神が支配する地下の冥界への旅路を暗示していると考えれば、ピラミッド
はわずか百年の間に太陽神学からオシリス神学へと宗教的意義を変化させたと思われるの
です。 ピラミッドは第四王朝の最後の王の時からギザには建造されなくなりますが、古王国が
終わるまでピラミッド都市に住む人々によって王の葬祭礼拝は続けられました。高官たち
の墓もギザに築かれ続けました。しかし、第一中間期と中王国の間ギザ台地は放棄され、
ピラミッド内部は略奪され、付属する神殿や参道の石材は中王国のピラミッド建造に再利
用されました。王墓としてのピラミッドの建造は王権が弱まった第十三王朝以降途絶え、
ギザの三大ピラミッドも人々から忘れ去られました。 それでも、ギザ台地はギリシア・ローマ時代から観光客の注目を集めました。ヘロドト
スは紀元前 5世紀、すなわち第一次ペルシア支配時代にエジプトを訪れ、三大ピラミッドにまつわる詳細な話を著書『歴史』第二巻 124-135章で述べています。すなわち、クフ王の大ピラミッドに関しては、石材の運搬方法、起重機を使用した階段式のピラミッド構築
法、労働者にタマネギやニンニクを支給するのに要した費用、王が自分の娘を娼家(しょうか)に出して金子(きんす)を稼がせたこと、彼女もまた自分のために大ピラミッドの前の三基の小ピラミッドのうち中央のピラミッドを築いたことが述べられています。紀元前 1世紀にはストラボンが著書『地理書』第十七巻 33-34章で世界七不思議の一つとしてピラミッドに言及しています。他方大スフィンクスについては、彼らのうち誰もそれに言及して
いません。大スフィンクスに言及しているのは紀元後 1世紀のプリニウスの著書『博物誌』第三十七巻 12章だけです。すなわち、ギザの三大ピラミッドの名声が世界中に行き渡り、
下エジプト第二州のブシリス村にはピラミッドに登って観光案内をする人々がいること、
大スフィンクスは地域の住民によって神とみなされていること、ハルマイスという名の王
が大スフィンクスの中に埋葬されていること、大スフィンクスが天然の岩から作られてい
ること、大きさ、顔の赤い着色、売春婦ロドピスによって建てられた小ピラミッドについ
て述べられています。大スフィンクスは後世の発掘によっても明らかになるように、新王
国からプトレマイオス時代まで神として崇拝され続けていたのです。 残念なことに、4 世紀に発布されたテオドシウス帝の勅令によってエジプトで異端の神々の礼拝が禁止されてからは、ギザ台地の遺跡群は砂の下に埋もれました。アラブ時代
ピラミッドは絶え間ない略奪の対象となりました。アイユーブ朝の創始者サラディンは十
字軍の来襲に備えてカイロにシタデル(城塞)と橋を建設する際、ピラミッドや付属神殿の化粧石を再利用しました。マムルーク朝やオスマントルコの権力者たちも財宝を求めて、
ギザの三大ピラミッドに部隊を派遣しました。その他キリスト教の巡礼者たちやヨーロッ
パ諸国の使節団の団長たちもピラミッドに関心を持ちました。アラブの地理学者や旅行家
たちも砂から頭部だけ出している大スフィンクスに言及しています。大スフィンクスの頭
部はアラビア語でアブルホル「恐怖の父」と呼ばれるようになりました。砂漠は悪霊や鬼
が棲むところだからです。大スフィンクスの鼻は 1378 年にムハンマド・サーイム・アッダールというイスラム聖職者によって破壊されたと言われています。現在鼻の跡にはのみ
を打ち込んだ跡が二つ残っています。 ところが、1798-1801 年に行われたナポレオンのエジプト遠征がヨーロッパ中にエジプトブームを巻き起こし、多くの探検家が宝探しにやってきて、エジプト中で発掘を始めま
した。 まず 19・20世紀に大スフィンクスとその周辺で行われた調査について概略します。 19世紀の間大スフィンクスの砂の除去は大変困難で危険な仕事でした。 1817年ジョヴァンニ・カヴィグリアはイギリス領事ヘンリー・ソールトのもとで大スフィンクスの北側の肩の部分に試掘坑を掘り、そこから大スフィンクスの至聖所の床まで達
し、新王国第十八王朝トトメス 4世の石碑と第十九王朝ラムセス 2世の二つの石碑からなる礼拝堂、スフィンクスの額を飾るウラエウスと呼ばれるコブラの頭部、スフィンクスの
付け髭の断片、さらに礼拝堂へ下りるローマ時代の 11段と 30段からなる 2つの前後する階段とその東側にある見晴し台を発見しました。階段と見晴し台はこの区域で発見された
ギリシア語のテクストから 1~2世紀に造られたことが分かりました。参拝者はその階段を下りながら大スフィンクスの眼前に迫る顔の偉大さに圧倒されたことでしょう。 1822年フランソワ・シャンポリオンがヒエログリフの解読に成功しました。 1840-42 年ハワード・ヴァイスは大スフィンクスの頭部の真後ろの背中にある亀裂をドリルと火薬を使って調査しました。このとき大スフィンクスのネメス頭巾のかなりの部分
を吹き飛ばしました。 1842-43 年リヒャルト・レプシウスは、カヴィグリアの調査の後再び砂に埋もれた礼拝
堂から砂を除去しました。このとき礼拝堂の平面図を作成し、トトメス 4世の石碑のコピーを出版しました。 1853 年 9 月 15 日オーギュスト・マリエットは大スフィンクスの発掘を開始しますが、厖大な量の砂に耐えられずに作業を放棄し、代わりにカフラー王の河岸神殿を発見しまし
た。マリエットは 1858 年に大スフィンクスでの作業を再開し、至聖所から砂をすべて除去し、大スフィンクスの胴体の左右に二つずつ直方体の石積みがあるのを発見しました。
さらに大スフィンクスの境内を砂から保護した未焼成レンガの壁の一部と彫像の断片を発
見しました。マリエットはそれらをオシリス柱像とその台座であると結論づけましたが、
彼の推測はまだ証明されていません。マリエットはかつてハワード・ヴァイスが調査した
大スフィンクスの背中の亀裂も調査し、それが大スフィンクスの胴体を貫通する自然の亀
裂であり、古代エジプト人が自然の岩盤から大スフィンクスに似た形を造り出し、胴体に
石積みのおおいを追加して大スフィンクスを完成させたことを悟りました。それからカフ
ラー王の河岸神殿の内部から完全に砂を除去しました。ただし河岸神殿の外壁は砂に埋も
れたままでした。 1880-82年フリンダース・ペトリーが河岸神殿の内部の注意深い測量をしました。 1885-86 年ガストン・マスペロはカヴィグリアとマリエットがすでに掘り出したものから再び砂を除去しましたが、詳細な報告書を残しませんでした。19世紀の発掘調査者たちは砂の侵入を防ぐ壁を築かなかったので、30 年か 40 年の間に大スフィンクスは再び砂に埋もれ、19世紀の発掘調査は無駄骨になりました。 20世紀には大スフィンクス周辺で有益な発掘が行われました。 1902年ガストン・マスペロはギザ台地を 5つの調査区域に分けることを提案し、メンカウラー王のピラミッド複合体はアメリカに、カフラー王のピラミッド複合体はドイツに、
大ピラミッドの西の共同墓地はオーストリアに、大ピラミッドの東の共同墓地はイタリア
に与えられ、大スフィンクス周辺地域はエジプトが管理しました。イタリアの調査区域は
1905年にアメリカに引き継がれました。 1909年ユーフォ・ヘルシャーはカフラー王の河岸神殿でマリエットの作業を続け、参道と河岸神殿とピラミッド神殿の配置を明らかにし、さらに河岸神殿の正面を背にして建つ
第十八王朝アマルナ時代の個人の家の遺構を発見しました。さらにその南側で末期王朝あ
るいはプトレマイオス時代の泥レンガの建築物を発見しました。 1925-36年の 11年間ピエール・ラコーの指揮下にあるエジプト考古局はエミール・バレーズの監督で大スフィンクスの至聖所とスフィンクス神殿から砂を除去しました。バレー
ズは簡単な報告しか残しませんでしたが、彼の残した 226枚の写真と何冊かのノートとスケッチは貴重なアーカイヴとなっています。それらはパリのウラジミール・ゴレニシェフ・
センターが所有しています。バレーズの記録写真に基づいて、11年間に行われた発掘と発見を辿ることは出来ますが、アーカイヴの写真を閲覧させてもらえないと現場の状況が分
かりにくいので、一部だけ触れたいと思います。
1931年エミール・バレーズの砂を除去する作業が大スフィンクスの南かつカフラー王の河岸神殿の西方に達した時、大きな泥レンガの建造物が発見されました。石灰岩の扉の枠
には第十八王朝ツタンカーメン王と王妃アンケセナーメンの名前を捺され、さらにその上
に漆喰が塗られて、第十九王朝ラムセス 2世の名前が上書きされていました。ここからはアメンヘテプ 1世に年代づけられる新王国の碑文も発見されています。この建造物には浴室があり、ツタンカーメン王がギザに短期滞在して、狩りを楽しむためのレストハウスだ
ったのではないかと推測されています。 1932-33 年の冬に、ツタンカーメンのレストハウスの南東角から南方に走る泥レンガの壁を解体したところ、ホルエムアケト神としてのスフィンクスとホルエムアケトという名
前のハヤブサとしてのホルス神に捧げられた多数の石碑、小さな石灰岩製とファイアンス
製のスフィンクス群、小さな青い陶器の耳、多数の土器を発見しました。ピエール・ラコ
ーはこれらが願掛けの奉納物だったと考えました。 セリム・ハッサンは 1936年 10月 4日から 1937年 6月 10日まで大スフィンクスの発掘を引き継ぎました。1936 年 10 月 20 日セリム・ハッサンは大スフィンクスの北東でアメンヘテプ 2世によってフウロン・ホルエムアケト神に捧げられた神殿を発見しました。その神殿の中にはアメンヘテプ 2世の大石碑が今も建っています。神殿の正面は大スフィンクスの頭部の方向に面しています。また 1937年 2月 25日に、大スフィンクスの凹地の北の端に沿って、乱されていない深い砂の層から、願掛けの様々な石碑や小像を発見しま
した。1937 年 3 月 6 日にセリム・ハッサンはアメンヘテプ 2 世の神殿の北東にもう一つの泥レンガの神殿の基礎を発見しました。セリム・ハッサンはこの神殿を何の根拠もなく
トトメス 1 世の神殿であるとみなしました。セリム・ハッサンは 1938 年に河岸神殿の南東にある泥レンガの神殿がオシリス神の神殿だったと言及しますが、この神殿の平面図は
公表されておらず、今日その場所にはその明白な痕跡もありません。 1960年に音と光のショーのための電気システムがスフィンクスの至聖所、アメンヘテプ2世の神殿、スフィンクス神殿のすぐ東側に設置されました。 1965-67 年にヘルベルト・リッケがスフィンクス神殿の大規模な測量と記録を行いました。そして神殿が決して完成されなかったことを認めました。 1978年 2・3月にエジプト考古局とアメリカの研究機関 SRI Internationalが、電気抵抗率の違いで地下構造を推定する電気探査と、音波の伝達速度の違いで地下構造を推定す
る音波探査の二つによって、スフィンクスの至聖所とスフィンクス神殿の地表下の調査を
行いましたが、期待されたような秘密の部屋は見つからず、自然の石灰岩の空洞しか見つ
かりませんでした。また現在エジプト古遺物最高会議議長(通称 SCA)のザヒ・ハワス氏はスフィンクスの至聖所の北東角にある堆積物の山を発掘しました。 1979年からはカイロ・アメリカン・リサーチ・センターのスフィンクス・プロジェクトが開始されました。すなわち、スフィンクスの写真測量とコンピューターグラフィックス
の 3D 画像を駆使したマッピング、地質学的研究、保存の研究が行われました。その研究
成果を受けて、1981年 10月からエジプト考古局はスフィンクスの修復プログラムを開始しました。スフィンクスは地下水面の上昇、風による侵食、環境汚染によって脅かされ、
石材表面の剥離や石材自体の落下が起こっています。スフィンクスの修復と復原は急務の
一つとなっています。 今日約二百年の発掘の後、ようやく比較的満足のいく程度にスフィンクスに関する知識
が得られました。従来ギザの大スフィンクスを知らない人はいませんでしたが、考古学的
にはそれは最近まで最も研究されていない記念碑の一つでした。19世紀の考古学者たちは簡単な報告書しか残さなかったか、あるいは何も残しませんでした。しかし、ギザ台地の
包括的な研究が進むにつれて、エジプト学者たちはスフィンクスがカフラー王の葬祭複合
体の一部であり、その顔がカフラー王のイメージで彫られたことを悟りました。カフラー
王の葬祭神殿と河岸神殿からは様々な大きさの二百体以上の彫像あるいはその断片が発見
されています。1980年代になって初めてマーク・レーナーが紀元前二千年紀の始まりからローマ時代までの歴史とともにエジプトの記念碑の視点から大スフィンクスの分析に着手
しました。現在私たちが持っている大スフィンクスに関する知識の大部分はマーク・レー
ナーの詳細かつ史実に正確な研究に負っています。 マーク・レーナーとは誰か? 彼は若い頃はエドガー・ケイシーに傾倒しており、スフィンクスは今から一万年前に造られ、その右前脚の下にアカシック・レコードと呼ばれる人
類の歴史を記した年代記がある秘密の部屋があると信じていました。彼はその秘密の部屋
を見つけるためにエジプトへやってきて、1975年にカイロ・アメリカン大学を卒業し、13年間エジプトでアメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、エジプトのプロジェクトのため
にフィールド・ワークを行いました。1979年カイロ・アメリカン・リサーチ・センターが後援するスフィンクス・プロジェクトのフィールド・ディレクターに就任。1990年イェール大学で大スフィンクスの研究で博士号を取得。彼は 1985 年にギザ台地マッピング・プロジェクトに資金供給するために設立された古代エジプト調査協会(通称 AERA)のディレクターであり、また 1988 年から現在までギザ台地マッピング・プロジェクトのディレクターでもあります。AERAは現在 4つのプロジェクト、すなわちスフィンクス・プロジェクト、ギザ台地マッピング・プロジェクト、ピラミッド労働者村プロジェクト、ピラミッ
ドの放射性炭素年代測定プロジェクトに取り組んでいます。 それでは、大スフィンクス周辺の地理的状況についてお話しましょう。 古代エジプト人は大スフィンクスの周囲の石灰岩の岩盤に 4つの異なるテラスを造りました。 スフィンクス神殿とカフラー王の河岸神殿がある水平面はテラス I と呼ばれます。テラス I の西側はスフィンクス神殿の西壁によって、大スフィンクスの正面で閉ざされています。北側は高さ 5.25mの岩棚によって閉ざされています。テラス Iは次第に東に傾斜しており、それはスフィンクス神殿のはるか 50m東まで続きます。テラス Iの東の端には河岸神殿の正面に接岸する船のための古代の波止場があったでしょう。テラス I の南限は未調
査のため知られていません。 テラス IIは大スフィンクスの至聖所で、古代エジプト人は自然の岩から U字型の凹みを切り出し、その中央に大スフィンクスの核となる部分を残しました。テラス II とテラス Iの高さの差は約 2.62mです。テラス IIの北東角の真上の岩棚に、すなわちテラス IIIにアメンヘテプ 2世の泥レンガ製の神殿の角があります。床は大スフィンクスの両前脚の間の10×14mの石灰岩の敷石の区画を除いて、天然の岩盤を露出しています。大スフィンクスの至聖所へ下りるローマ時代の階段と見晴し台はエミール・バレーズによって発掘作業中
に取り壊されてしまいましたが、敷石の区画は残されています。また至聖所の北西から南
東にかけて大スフィンクスの胴体全体と床を貫通する大きな亀裂が走っています。亀裂の
深さは 3~4mにも達します。 テラス IIIは大スフィンクスの至聖所とスフィンクス神殿の北の開けた地表で、マーク・レーナーが北の崖と呼ぶもっと高い岩棚によって北側を閉じられています。北の崖の向こ
う側には、大ピラミッドの東側の共同墓地があります。セリム・ハッサンはテラス III の一部で大スフィンクスの背後にある 4.6×9.3mの区域とテラス Iとテラス IIを加えて、大スフィンクス・アンフィシアターと呼びました。テラス III は北西角からスフィンクス神殿の北東角まで 10m以上傾斜しています。 テラス III には新王国の建築物の遺構が 3 つあります。一つはアメンヘテプ 2 世によってフウロン・ホルエムアケト神に捧げられた泥レンガ製の神殿で、テラス III のこの区画は紀元前 1,460 年頃神殿が建てられた時、砂を除去されました。この時の砂の除去は息子のトトメス 4世によって大スフィンクスの胸の台座の上に建てられた花崗岩製の石碑でほのめかされた大スフィンクス発掘の一部だったかもしれません。セリム・ハッサンはアメ
ンヘテプ 2世の神殿と同様な大きさ、方向、平面図を持つ建築物をトトメス 1世の神殿であると言及していますが、もしそれが本当ならば、テラス III はアメンヘテプ 2 世の治世よりももっと早くに砂を除去されたことを示すでしょう。すると、トトメス 4世は父祖たちの治世に始まった大スフィンクスからの砂の除去を自分の功績にしていたかもしれませ
ん。アメンヘテプ 2世の神殿入り口の西方約 60mのところに大スフィンクスの境内を囲む泥レンガの壁の一部が建っています。また、スフィンクス・アンフィシアターの後方の西
の岩棚と垂直に立っているもっと大きな泥レンガの壁があります。厚みが 4.07m、長さ24.79m で、セリム・ハッサンはこれをトトメス 4 世によって建てられた砂の防護壁の一部であると考えました。しかし、この壁がトトメス 4世の治世よりももっと後の時代の遺跡の周壁である可能性もあります。 ちなみに、昨年 10 月にエジプト考古局はトトメス 4 世の治世の大きな泥レンガの壁を新たに発見しました。それは二つの部分からなり、一方はカフラー王の河岸神殿と大スフ
ィンクスの東側に沿って南北に 86m、高さ 75cmあり、もう一方は高さ 90cmで、カフラー王の河岸神殿の北の区域にあります。それは長さ 46mで、河岸神殿の周辺に沿って東西に伸びています。エジプト古遺物最高会議議長のザヒ・ハワス博士は、これがスフィンク
スの北で発見された大きな壁の一部であり、大スフィンクスを砂から守るためにトトメス
4世が建てた周壁であると、解説しています。 テラス IIIとテラス IVを分ける西の岩棚には第二十六王朝の墓が、テラス IIIの北限である北の崖には古王国第五あるいは第六王朝の墓が、いくつかあります。 テラス IVはテラス IIの西の岩棚、カフラー王の参道、クフ王の大ピラミッドの南側を走る現代の道路、カフラー王の葬祭神殿に囲まれた不等辺四角形の地域で、かつて大ピラ
ミッドとカフラー王のピラミッドを建設するために利用された採石場でした。 次に大スフィンクス本体の状態についてお話しします。 ギザ台地を形成するモカッタム層はさらに下から上へメンバーI、II、III と呼ばれる地層に分けられます。大スフィンクスの土台と床はメンバーI すなわち非常に硬い層、胴体はメンバーIIすなわち柔らかい層、頭部はメンバーIIIすなわち中くらいの硬さの層から形成されています。そのため風や砂による侵食は大スフィンクスの胴体によく見られ、石積
みによるおおいを必要としました。今日、石積みの層は南側で胴体の高さの約 3分の 2まで、北側では肩の部分ではその高さの 3分の 1まで、腰の部分では 3分の 2までおおっています。 大スフィンクスの全長は石積みでおおわれた前脚の先端から尻の石積みでおおわれた尻
尾までで 72.55m。前脚の石積みの厚さを 0.15m、尻尾をおおう石積みの厚さを 0.50mと仮定すると、大スフィンクスの核となる部分の全長は 71.90m。幅は尻の部分が最大 19.10m、腰の最も細い部分は石積みの厚みを含めて丁度 10m、前脚の肘から肘までは 18.50m、胸の横幅は 12.70m。大スフィンクスの高さは額のコブラの先端までが約 20.22m、背中の最も高い部分で 12.38mです。 頭部は黒っぽい保護膜(パティナ)におおわれていて、岩盤の表面剥離が少なく、保存状態が良好です。頭部の横幅はネメス頭巾も含めて南北に 10.30m、口の正面からネメス頭巾の後部の折れ目までが 9.78m。ネメス頭巾は顔の両側に約 3m扇形に広がっています。頭部の高さはあごからコブラの残りの先端まで 5.88mです。頭部のてっぺんは平らで、人が中に立てるほどの深さがある穴が開いています。この穴の役割については不明ですが、
王冠あるいは 2本の羽根飾りを差し込むための穴だったのではないかと考える人もいます。 大スフィンクスの額を飾るウラエウスと呼ばれるコブラは、ネメス頭巾のヘッドバンド
の上約 1.50m のところで折れ、1916 年にジョヴァンニ・カヴィグリアによって大スフィンクスの胸の土台で発見されました。このコブラの破片(BM1204)は、付け髭の断片と一緒に、大英博物館に運ばれました。コブラの破片には目の上に赤く着色された下地が、他の
部分に白と黒の斑点が残っています。 頬の両側には古代の赤の着色が残っています。大スフィンクスの鼻はほとんどまったく
失われています。本来の鼻は高さが約 2.20m、最大幅が 1.20mありました。鼻は意図的に長いのみで削り取られました。最初の打撃が鼻柱までつき砕き、2 回目の打撃が北側の鼻腔(びこう)の中と下に入り込んでおり、すばやく南の方へ削り取られています。上唇は鼻
を削り取る破壊によって中央部と南側で損なわれています。 首は大スフィンクスの最も細い部分で、胴体が埋まっている間、風と砂の作用によって
ひどく風化しました。風化によって突出した層とくぼんだ層が交互に重なっているのがよ
く分かります。1925年にエミール・バレーズによって修復され、厚みはセメントカバーを含めて東西に約 7.30m、南北に約 9mです。 胸の横幅は 12.70m。首からあごの下約 6.25m までネメス頭巾の垂れ飾りの位置にわずかな突出部があり、胸の中央部はわずかにくぼんでいます。あごの下約 6.25mのところに目立ったこぶがあります。こぶの高さは丁度 4m、幅 2.30mで、胸から最大 1.25mまで突き出しています。胸は縦の距離 14.30mをおおよそ 57度の角度で両前脚の間の床まで下ります。トトメス 4世の石碑の背後にある石積みが胸と前脚の接合部をわかりにくくしています。 背中の高さは最高 12.38m。最上部の長さは頭部の後部から尻まで 28.85m。幅は頭部の背後で 9.5m、大きな亀裂が大スフィンクスを切断する腰の最も細い部分で幅 3.6m、尻のてっぺんの幅約 8.5m。頭部の大きさと比較すると、かなり細長く見えます。またギザ台地が北西から南東へ傾斜しているため、大スフィンクスを背後から見た時、北から南へ著し
く傾いているように見えます。大きな亀裂が胴体の核となる部分を切断し、頭部の背後
17.5m の背中のてっぺんで口を開いています。これは 1853 年にオーギュスト・マリエットによって初めて発掘され、葬祭用の縦穴ではなく、大スフィンクスの胴体を貫通して床
の下まで走る自然の亀裂であることが分かりました。背中の亀裂の幅は 2m 以上あり、エミール・バレーズによって鉄の棒と石灰岩の破片や灰色のセメントで屋根のようにおおわ
れました。大スフィンクスの背中にはもう二つ亀裂があります。一つは首の後ろから約 40~50cm の背中を横切って切断しています。もう一つは背中を横切ってさらに西へ 9.3~9.5mまで切断しています。ハワード・ヴァイスは 1837年にこの亀裂にドリルで穴を開け、1840~42年に火薬を使ってボーリング・ロッドを抜こうとしましたが、ボーリング・ロッドは抜けず、ネメス頭巾のかなりの部分を吹き飛ばしました。 胴体の北脇腹には二つの亀裂が見られます。一つは胴体の中央を貫通し、もう一つは腰
を貫通しています。南脇腹には三つの亀裂が見られます。一つは頭部の真後ろに、二つ目
は胴体の中央に、三つ目は腰に見られます。これらの亀裂による胴体の分離を防止するた
め脇腹は石積みにおおわれています。 尻は胸や両脇腹よりもひどく風化しており、その高さの 3分の 2まで石積みでおおわれています。 両前脚の幅は 5.74~5.76m、長さは 17.05~17.40m、高さは胸の方で 3.37~3.50m、指先で 2.30~2.40mです。1983年末から 1984年初めにかけて石積みのおおいが取り替えられた時、岩盤には赤い着色が見られました。両前脚にはライオンの筋肉組織の様式化され
た彫刻表現が見られます。 1981 年に高さ 1.80~1.96m、長さ 2.75m の石積みの化粧石の一区画が北側の後ろ脚の
側面から落ちたことから、1981-82 年から北側の後ろ脚の上の石積みのおおいの大部分が新しい石材と取り替えられました。このとき三つの亀裂が見つかりました。後ろ脚の指先
には爪の彫刻表現が見られました。 尻尾は胴体の脇腹から約 2m 突き出しており、彫刻ではなく、石積みで形作られていました。 大スフィンクスの最も重要な部分は両前脚の間にある礼拝堂です。 1817年ジョヴァンニ・カヴィグリアが大スフィンクスの発掘を始めた時、両前脚の間に礼拝堂を発見しました。その礼拝堂の中心となるのは第十八王朝トトメス 4世が治世 1年増水季第三月 19日、すなわち紀元前 1,400年の 10月初めに建立した高さ 3.5mの花崗岩の石碑です。それは今日まで、元の場所に建っています。礼拝堂の前の両前脚の間の床は
10×14mの石灰岩の敷石の区画で、その東方には大スフィンクスの至聖所へ下りるローマ時代の階段と見晴し台がありました。敷石はひどく風化していました。両前脚の両内側の
指の間には二つの石灰岩の壁があり、両前脚の区域を閉ざしていました。その壁のそばか
ら頭を振り向け、両前脚を交差させたライオンの彫像が発見されており、壁の上には一対
のライオン像が置かれていたのではないかと推測されています。二つの石灰岩の壁には開
口部があり、その東側直前に花崗岩の祭壇(土台は現在も元の位置にあり、上部は大英博物館が所蔵)が建っていました。祭壇は 0.87m四方で、その高さは 1.17mでした。祭壇には供物を燃やした跡と思われる火の跡が残っていました。ここでどんな儀式が行われたのか
は分かりません。礼拝堂の入り口にも両前脚の内側から突き出す短い二つの壁があり、そ
の間に小さなライオン像が大スフィンクスの方を向いて座っていました。礼拝堂の大きさ
は 3.05m×1.52m、西の壁はトトメス 4 世の石碑で、両前脚の内側に北壁と南壁が建てられていましたが、北壁の上半分はひっくり返っていました。そして北壁と南壁の上にラム
セス 2世の石碑が一つずつ置かれましたが、北側の石碑は礼拝堂内に倒れていました。ラムセス 2世の二つの石碑はルーヴル美術館が所蔵しています(南側の石碑が B18、北側の石碑が B19)。ラムセス 2世の石碑は石灰岩製ですが、トトメス 4世の花崗岩製の石碑と調和させるために赤く着色されています。塩分によって石碑の表面の一部が剥がれ落ち、その
部分はレリーフの曖昧な輪郭しか残っていません。イギリス領事ヘンリー・ソールトはラ
ムセス 2世の石碑だけではなく、敷石も壁もライオンの彫像もすべて赤く塗られていたと書き残しています。ラムセス 2世の石碑では大スフィンクスは高い台座の上に安置され、東の方を向いています。南の石碑ではラムセス 2世は大スフィンクスに香炉と供物を差し出し、北の石碑では右手を大スフィンクスの方へ上げ、左腕を身体に沿って下に伸ばし、
左手に香炉を持っています。ラムセス 2世の石碑は北壁と南壁の上に置かれて、ラムセス2世の図像がトトメス 4世の図像と同じ高さになるように配慮されていました。 ヘンリー・ソールトは大スフィンクスの付け髭の 4つの断片を図示しています。それらには付け髭の編み込み模様とネメス頭巾を着用し、ひざまづいて大スフィンクスに襟飾り
を差し出す王の彫刻があります。このうちDの断片(BM58)が大英博物館に送られました。
それは長さが 78.7cm あります。付け髭の断片は他にもあり、それらは大英博物館とカイロのエジプト博物館に収蔵されています。発見された付け髭は神々の付け髭のように先端
が丸くなったものであり、大スフィンクスが作られた時代のものではなく、新王国の修復
作業時に新たに作られたものと考えられています。 トトメス 4世の石碑が古王国の石材の再利用であることはずっと以前から知られてきましたが、マーク・レーナーによってカフラー王の葬祭神殿の、参道からの入口にある扉の
まぐさを再利用したものであるとつきとめられました。 そしてスフィンクスの胸の下の土台から礼拝堂にかけての石積みは、新王国にありふれ
ていた青いフリット(粉末ガラス)が発見されていることから、トトメス 4 世の治世に造られたことを示唆しています。すなわち、大スフィンクスが大修復を受けたのは主にトトメ
ス 4世の治世であり、礼拝堂の多少の変更がラムセス 2世時代やローマ時代に行われたと考えられます。 ところで、大スフィンクスは古代エジプトでは何と呼ばれていたのでしょうか? 「スフィンクス」という呼称はギリシア語からの借用語で、本来オイディプスの伝説に登場する
怪物を指していました。それは翼を持ち、女性の頭部と乳房とライオンの身体を持ちまし
た。古代エジプト語の「生ける像」を意味するシェセプ・アンクがスフィンクスの語源で
あるという説もありますが、残念ながらそれはあらゆる種類の彫像を意味します。シェセ
プ・アンクはスフィンクス全体の呼称でもギザの大スフィンクスの名前でもありません。
実は大スフィンクスが建造された第四王朝の碑文にも第五・第六王朝の碑文にも大スフィ
ンクスへの言及はありません。どこにも見つかっていないのです。だから、大スフィンク
スがカフラー王を表現する彫像だったと多くのエジプト学者たちが考えているにもかかわ
らず、大スフィンクスが古王国に何と呼ばれていたのかも、その役割も明らかではないの
です。 大スフィンクスの東側に建設された未完成の神殿、いわゆるスフィンクス神殿の役割も
不明です。発掘者のヘルベルト・リッケは 1970 年の報告書でこの神殿を「カフラー王のハルマキス神殿」と呼びました。ハルマキスは太陽神ホルエムアケトのギリシア語読みで
す。ヘルベルト・リッケはこの神殿が太陽神礼拝のために建設され、大スフィンクスを太
陽神とみなしたのです。しかし、古王国にはホルエムアケトという名前は知られていませ
ん。神殿の中心軸も大スフィンクスの中心軸から 6.4m 以上南へずれています。従って、大スフィンクスと神殿との関係は考え直されなければなりません。 ヘルベルト・リッケの説に対して 1971 年に提出されたルドルフ・アンテスの説は大変興味深いです。ルドルフ・アンテスは、いわゆるスフィンクス神殿は太陽神ラーに捧げら
れた初めての神殿であり、大スフィンクスはその神殿で捧げられる供物を太陽神ラーに差
し出す王の象徴である、と主張しました。ルドルフ・アンテスによれば、大スフィンクス
とスフィンクス神殿の建設は王=ホルス神という王権の教義に太陽信仰を組み込む試みでした。「太陽神ラーの息子」の称号の登場と太陽神ラー・ホルアクティーという複合名の登
場はその試みと関連づけられます。このルドルフ・アンテスの説は非常に説得力があるよ
うに思われますが、にもかかわらず、碑文のない建造物のいかなる解釈も証明することは
出来ないので、仮説や推測に過ぎないということを忘れてはなりません。 しかし、新王国以降大スフィンクスは神として礼拝されていたことが明らかです。最初
は太陽神ホルエムアケトとして、次にフウロン・ホルエムアケト神として、新王国以後ロ
ーマ時代までは「ローセタウの支配者であるオシリス神の息子、ホルス神」として礼拝さ
れました。ローセタウとは冥界への入口であり、ギザ台地を指しています。 ホルエムアケトという名前は第十八王朝初めのアメンヘテプ 1世の治世に初めて知られます。大スフィンクスは王、王族、高官達から平民まで参拝や巡礼の対象となりました。
古王国崩壊後六百年も経過してから、なぜ突然そうなったのかについては分かりません。
アメンヘテプ 1世がメンフィスおよびその周辺地域でどんな活動をしたのかは知られていません。しかし、彼の父イアフメス 1世が異民族の支配者達ヒクソスを国外に追放した後、古都メンフィスに再びエジプト人が定住したので、その時にギザの三大ピラミッドが古代
の祖先達の遺跡として注目され、大スフィンクスがメンフィスの墓地の守護神として崇拝
されるようになったのかもしれません。とにかく、ホルエムアケトは大スフィンクスだけ
の呼称でした。ホルエムアケトとは「地平線のホルス神」という意味であり、新王国のエ
ジプト人は大スフィンクスをホルス神の姿であると理解したことを示しています。「地平線
の」という形容詞句は、クフ王のピラミッドの名前で「クフの地平線」を意味するアケト
クフに由来したと思われます。そして東を向き、二つのピラミッドを背景にしてそびえ立
つ大スフィンクスはまさにアケトのサインだったのです。 大スフィンクスは太陽神ラー・ホルアクティーとすぐに同化し、トトメス 4世の石碑ではホルエムアケト・ケプリ・ラー・アトゥム神と呼ばれます。ケプリとは朝日、ラーは日
中の太陽、アトゥムは夕日を指します。これは新王国に新たに発展した太陽神学の教義を
示しています。太陽は朝生まれ、昼に成人になり、夕方には老人になり、夜には死者にな
って冥界を旅し、そして翌朝再び幼児の姿で生まれるのです。大スフィンクスは新しい太
陽神学との結合によって、太陽神となったのです。さらにまたアトゥム神はヘリオポリス
神学ではライオンの姿で原初の海から現れ、宇宙を創造した原初の神です。それは大スフ
ィンクスが自然の岩盤から彫刻されたという事実に一致しました。このようにして、大ス
フィンクスは新王国の神学活動によってさまざまな神々と結びつけられました。ただし、
第四王朝のエジプト人が大スフィンクスを単なる王像としてではなく、そのような認識を
持って造ったかどうかは不明です。 さて、カイロ博物館には指をくわえてしゃがんでいる幼児姿のラムセス 2世を背後から守護するハヤブサの神の彫像(CG64735)があります。タニスから出土したこの彫像は本来アメンヘテプ 2世がギザに建てたフウロン・ホルエムアケト神の神殿に置かれたものでした。台座にはラムセス 2世の太陽神ラーの息子名に続けて「フウロン神に愛される者」と彫られています。ギザで初めてフウロン神が登場するのはおそらくトトメス 3世か息子の
アメンヘテプ 2世の治世で、バール神、レーシェフ神、アスタルテ女神という他のシリア・パレスティナの神々と一緒に現れました。トトメス 3 世はシリア・パレスティナに 17 回軍事遠征をし、エジプトの領土を最大にしたことから、「エジプトのナポレオン」と呼ばれ
ています。息子のアメンヘテプ 2世もシリア・パレスティナに 3回軍事遠征をしました。この結果大勢の戦争捕虜がメンフィスへ連行され、シリア・パレスティナの神々の信仰も
エジプトに定着しました。ただなぜフウロン神が大スフィンクスと結合させられたのかに
ついては不明です。私達はフウロン神について不十分な知識しか持ちません。もしかした
らホルス神とフウロン神が共に H 音と r 音を持ち、音声上似ているからかもしれません。ともかく、エジプト人は大スフィンクスをフウロン神と呼び、フウロン神をホルス神と同
様ハヤブサの姿で表現しました。 大スフィンクスの周辺からはアメンヘテプ 3世の名前を持つワイン壷の栓やツタンカーメン王のレストハウスも見つかっています。ラムセス 2世は礼拝堂に二つの石碑を建て、アメンヘテプ 2世の神殿にフウロン神に守護された彫像を置き、ツタンカーメン王のレストハウスを再利用しました。大スフィンクスを訪ねた王たちについては、社会思想社現代
教養文庫 1065 セリム・ハッサン著『スフィンクスの秘密』(1982 年)の最後の章で述べられています。大スフィンクスに参拝した人々は王と王族だけではありませんでした。大ス
フィンクスは、神殿の奥深くにある至聖所にいる他の神々と違って、誰でも近づいて、拝
むことが出来ました。第十九王朝に頂点に達する歴史ブームはギザに出張したり、メンフ
ィス周辺で勤務する人々を旧所名跡に向かわせました。例えば、高官、書記官、軍事指揮
官、建築士、彫刻師などです。彼らはギザの大スフィンクスを参拝し、石碑やライオンあ
るいはハヤブサの彫像などを奉納しました。それらについては、Christiane Zivie-Coche, Giza au deuxième millénaire, Le Caire, 1976で見ることが出来ます。あいにく今回この本を入手できませんでしたので、みなさんには詳しく説明出来ませんが、いくつかはセリ
ム・ハッサンの『スフィンクスの秘密』で見ることが出来ますので、そちらをご覧下さい。 新王国以後の大スフィンクスの信仰に大きな変化をもたらしたのは、ギザでのイシス女
神信仰です。ギザでのイシス女神の信仰はアメンヘテプ 2世の時代から証明されています。クフ王の妃の一人ヘヌートセンのピラミッドに付属する葬祭礼拝堂は、紀元前 1,000 年頃第二十一王朝のプスセンネス 1世とアメンエムイペト王の治世に、イシス女神の礼拝堂に造り変えられました。そしてそれ以来イシス女神は「ピラミッド群の女主人」と呼ばれる
ようになりました。ヘヌートセンの葬祭礼拝堂は第二十六王朝とプトレマイオス時代にも
再建と増改築が行われました。ヘヌートセンのピラミッドはクフ王のピラミッドの東側に
並ぶ三つのピラミッドのうちの一番南側のピラミッドですが、なぜヘヌートセンの葬祭礼
拝堂がイシス女神の礼拝堂に造り変えられたのかは不明です。 1858年イシス女神の礼拝堂からオーギュスト・マリエットによって「クフ王の娘の石碑」(JE2091)が発見されました。それは高さ 76.2cm、幅 38cm、花崗岩製の四角い石碑です。石碑にはクフ王への言及がありますが、制作年代は第二十六王朝と思われます。ここにギ
ザで礼拝されていた神々の目録が記されています。周囲の枠の碑文には「ホルス・メジェ
ド、上・下エジプトの王、クフ、生命を与えられし者が生きますように。彼はローセタウ
の支配者、オシリス神の家の北西に、ハウルン神の家のそばに、ピラミッド群の女主人イ
シス女神の家を見つけた。彼はこの女神の神殿のそばに彼のピラミッドを建設し、この神
殿のそばに王の娘ヘヌートセンのピラミッドを建設した。彼は彼の母、神の母、イシス女
神と天空の女主人ハトホル女神のために石碑に彫られた目録を作った。彼は彼女のために
神の供物を復活させ、石で彼女の神殿を建設した。その結果彼が廃墟の中に発見したもの
が再建され、神々が彼らの場所にいる。」と記されています。石碑は四段に分けられ、一番
上の段にはミン神、ウプワウト神、ホルス神、トート神、二段目にはイシス女神の聖船、
イシス女神、ハトホル女神、ネフテュス女神、イシス・メスケテト女神、サソリの姿のイ
シス女神、三段目には父の復讐者としてのホルス神、子供としてのホルス神、プタハ神、
セクメト女神、オシリス神、イシス女神、誕生殿のイシス女神、四段目にはアピス牛、ネ
フェルテム神、レネヌーテト女神、大スフィンクスの図像が彫られています。大スフィン
クスの前には「フウロン・ホルエムアケトの境内はピラミッド群の女主人イシス女神の神
殿領の南、ローセタウの支配者オシリス神の北にある。以下云々。」という碑文が彫られて
います。この記述から、イシス女神の礼拝堂としてのヘヌートセンの葬祭礼拝堂、オシリ
ス神とイシス女神の息子のホルス神としての大スフィンクス、さらに南東の耕地と砂漠が
出会うところにオシリス神殿があったことが分かります。 イシス女神は冥界の支配者オシリス神の配偶神であり、ホルス神の母でした。つまり、
新王国以降大スフィンクスはギザにおいてこれら三柱神の一柱として、古都メンフィスの
神々とともに信仰されていたのです。さらに、第二十六王朝プサンメティコス 1世から第二十七王朝クセルクセス王の治世まで続いた神官達の一族は、「ローセタウの秘密の長官」
とイシス女神の神官の称号だけではなく、ホルエムアケト神の神官の称号、さらにクフ王、
ジェドエフラー王、カフラー王、メンカウラー王の神官の称号も保有することがありまし
た。第四王朝の諸王の葬祭礼拝が復活したわけではありませんが、それらの王の神官の称
号は遠い昔に忘れさられた王達の名前に再び栄光を与えました。その結果ギザ台地全体が
聖地となったのです。それと同時に第二十六王朝からプトレマイオス時代まで再びギザ台
地の墓地としての利用が盛んに行われました。古王国に築かれた墓からこの時代の人々の
ミイラや土器が大量に見つかるのはこのためです。 このように、過去二百年間の発掘調査によって、新王国以降スフィンクス信仰によって
ギザ台地が有名な聖地かつ観光地になったことが明らかになりました。しかし、大スフィ
ンクスが造られた第四王朝当時のついてはまだまだ不明な点がたくさんあります。今後の
調査研究によってそれらは次第に明らかにされていくでしょう。 ご清聴ありがとうございました。
★参考文献★
Christiane Zivie-Coche, Sphinx ; History of a Monument, Ithaca, Cornell U. P., 2002.
Christiane Zivie-Coche, Giza au Premier Millénaire. Autour du Temple d’Isis, Dame des
Pyramides, Museum of Fine Arts, Boston, 1991.
Christiane Zivie-Coche, Giza au Deuxième Millénaire, Institut Français d'Archéologie Orientale, Le
Caire, 1976. (未入手)
Mark Lehner, Archaeology of an Image : The Great Sphinx of Giza, UMI, 1991.
Related Documents