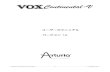労働災害の原因のひとつに「知識不足」や「技能未熟」と いうのがあります。初めての現場に入るときは誰しも不安が あります。現場の状況がわからないし、元請や他職の人たち に顔見知りがいなかったりします。現場特有のルールがあっ たりします。安全作業を行うためには事前に「知らないこと」 を教えてもらうことは重要です。 朝礼にも参加せず、新規入場者教育も受けずに勝手に現場 に入り、開口部から墜落して死亡した例もあります。 「大切な自分の命」と「大切な家族」を守るためにも新規 入場者教育を受けてください。 本冊子は、新規入場者教育とはどんなもので、何を学べば よいのか? という疑問にこたえるものです。様々な場面で 使っていただき、新規入場者による労災事故を防ぎましょう。 はじめに 目 次 はじめに 1 新規入場者は災害にあいやすい!… ……………………………………… 2 2 送り出し教育とは? 新規入場者教育とどう違うの?… ……………… 3 3 新規入場者教育とは?… …………………………………………………… 4 4 教育内容… …………………………………………………………………… 6 1安全施工サイクル…/2作業を行う上でのルール…/ 3現場内設備の使用取り決め…/4危険箇所、立入禁止箇所…/ 5危険予知(KY)の具体的な実施…/ 6正しい服装・安全帯・保護具…/7指差呼称…/ 8墜落・転落災害…/9電動工具・脚立…/… 5S と安全通路…/ 熱中症の予防、健康の保持 コラム「現地 KY で、現場の危険に敏感になろう」 … ………………………… 28 5 産業廃棄物の処分ルール… ……………………………………………… 29 6 作業に必要な資格… ……………………………………………………… 30 コラム「資格はなぜ必要なの? それは、あなたの命を守るため!」 … ……… 32

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

労働災害の原因のひとつに「知識不足」や「技能未熟」と
いうのがあります。初めての現場に入るときは誰しも不安が
あります。現場の状況がわからないし、元請や他職の人たち
に顔見知りがいなかったりします。現場特有のルールがあっ
たりします。安全作業を行うためには事前に「知らないこと」
を教えてもらうことは重要です。
朝礼にも参加せず、新規入場者教育も受けずに勝手に現場
に入り、開口部から墜落して死亡した例もあります。
「大切な自分の命」と「大切な家族」を守るためにも新規
入場者教育を受けてください。
本冊子は、新規入場者教育とはどんなもので、何を学べば
よいのか? という疑問にこたえるものです。様々な場面で
使っていただき、新規入場者による労災事故を防ぎましょう。
はじめに
目 次
はじめに1 新規入場者は災害にあいやすい!………………………………………… 22 送り出し教育とは? 新規入場者教育とどう違うの?………………… 33 新規入場者教育とは?……………………………………………………… 44 教育内容……………………………………………………………………… 6
1安全施工サイクル…/2作業を行う上でのルール…/3現場内設備の使用取り決め…/4危険箇所、立入禁止箇所…/5危険予知(KY)の具体的な実施…/6正しい服装・安全帯・保護具…/7指差呼称…/8墜落・転落災害…/9電動工具・脚立…/…� 5S と安全通路…/�熱中症の予防、健康の保持
コラム「現地KYで、現場の危険に敏感になろう」…………………………… 285 産業廃棄物の処分ルール………………………………………………… 296 作業に必要な資格………………………………………………………… 30コラム「資格はなぜ必要なの? それは、あなたの命を守るため!」… ……… 32

2
新規入場者は災害にあいやすい!
1
「工事現場で起こる災害にあいやすい人には、共通点があります!」
このようにお話すると、驚くかもしれません。しかし、共通点はあるのです。
それは「新規入場者」であることです。
◉新規入場者とは
新規入場者とは、工事現場に入場して間もない人のことです。実は、災害に
あった人の約70%は、新規入場してから7日以内に被災しているのです。
国土交通省の直轄工事では、事故の3分の1は新規入場後7日以内に発生し
ているとのデータがあります。
0
5
10
15
20
25(人)
入場日数(日)
■ 死傷者数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出所:国土交通省「安全啓発リーフレット(平成30年度版)―直轄工事における事故発生状況」より
◉なぜ、新規入場者の災害が多いのか
新規入場者の災害が多い、その大きな理由としては、「現場特性をよく知ら
ない」からです。現場のルールや危険
箇所は現場ごとに異なりますよね。入っ
たばかりの時期は、それらがよくわか
らず、災害にあってしまうケースが多
いようです。
最初の7日は災害の可能性が大きいと知ろう!
特に初日に多い!

3
送り出し教育とは?新規入場者教育とどう違うの?
2
「新規入場者教育」と似たものとして、「送り出し教育」があります。この
2つの教育の違いは、どのようなものでしょうか?
先に答えを言うと、実施する時期と場所が異なります。新規入場者教育は、
工事現場に入場した日の朝(朝礼後)に現場事務所等で行うのに対して、送り
出し教育は入場の前日までに、各事業所(会社事務所)で行います。
内容の違いは、新規入場者教育では、当現場のルール等を学ぶ事に対し、送
り出し教育では、仕事を行う上で必要な安全衛生の基本を学びます。○新規入場者教育と送り出し教育の違い
新規入場者教育 送り出し教育
実 施 者 協力会社の職長・安責者 協力会社の安全衛生担当または職長・安責者
実施期間 工事現場入場日の朝(主に朝礼後)
工事入場日の前日以前または定期実施
目 的 現場のルールを理解する 安全衛生の基本的知識を理解する
教育内容現場の危険箇所、他業者との関係事項、連絡体制等のルールや規則
安全衛生の基本方針、作業手順等または次に入場する現場のルールや特徴等
送り出し教育は、作業員の安全衛生の基礎力向上のために行います!

4
新規入場者教育とは?3
新規入場後の最初の7日間は、最も災害にあいやすい時期です。元請会社も
協力会社も、この期間の災害防止には注意を払っています。
(1)入場前の確認
協力会社の職長・安全衛生責任者は、事前に元請会社に対して、必要事項を
書類で提出します。書類については、元請会社によって異なりますが、一般的
には次のような内容が含まれます。元請会社には次の書類を提出します。
・作業員名簿・所有資格一覧・健康診断実施記録(過去1年以内)・高年齢者・年少者就労届・送り出し教育記録・その他(使用車両届、使用機械届、作業手順書等)
(2)新規入場者教育の進め方
実際の教育の進め方は、一般的に次のように進めます。
① 職場体操・安全朝礼終了後に、現場事務所会議室や打ち合わせ室などに集合させる。②� 新規入場者アンケート用紙に、氏名、生年月日などの必要事項を入場者本人が記入する。
③ DVDや教育テキスト、資料を使って、新規入場者教育実施内容を教える。④ 新規入場者アンケート用紙に記載事項を確認後、署名させて終了する。
新規入場者教育は、送り出し教育と共通した内容も含みますが、現場特有の
注意事項も多く含みます。しっかりと理解し、現場作業に取り掛かりましょう。

5
(3)新規入場者教育の内容
新規入場者教育は、朝礼やKY、作業前点検の後に行うことが多いようです。
場所は、現場事務所や休憩所が使われます。送り出し教育で、実施内容の一部
を教育していた場合は、その項目は省略されます。
・労働者が混在して作業を行う場所の状況・労働者に危険を生ずる箇所の状況・混在作業場所において行われる作業相互の関係・退避の方法・指揮命令系統・担当する作業内容と労働災害防止対策・安全衛生に関する規定・建設現場の安全衛生管理計画の内容
出所:「元方事業者による建設現場 安全管理指針のポイント」より(厚生労働省)
「労働者が混在して作業を行う場所の状況」例 「労働者に危険を生ずる箇所の状況」例
新規入場者は必ず、教育後に作業に取り掛かろう!

6
教育内容4安全施工サイクル1
工事現場には、全作業員が災害にあわないようにするためのルールが必要で
す。作業の進め方のルールの代表が、安全施工サイクルです。
朝礼の掲示板に描かれているので見た経験はありますよね。
安全朝礼
毎日のサイクル
所長巡視
使用開始時点検
終業時の確認
持ち場後片付け
安全工程打合せ
安全ミーティング
新規入場者教育
作業中の指導監督
安全施工サイクルとは、現場で元請業者から作業員までが一体となって、工
事施工と安全衛生管理を一体的に進めていく手法のことです。
このサイクルでは月・週・日等の周期の中で、「誰が」「いつ」「何を」行う
かを定めています。
このサイクルに従い、「今は何をすればよいか」を自分で判断し、毎日、毎週、
毎月の単位で、きちんと回していくことで、現場のリズムを作り、安全衛生管
理の徹底を図ることができるのです。
Related Documents